中学2年生になると数学の学習範囲が一気に広がり、「文字式」や「方程式」の考え方をより深く学ぶことになります。
その中でも特に大きな山場となるのが「連立方程式」です。
多くの学生さんが最初に「難しそう」「どうやって解くのかわからない」と感じやすい単元ですが、実は基本を丁寧に押さえれば確実に得点源になる分野です。
このページでは、連立方程式の基本から代表的な解き方(解法)までを体系的に解説していきます。
単なる公式や操作の暗記ではなく、「なぜその方法で解けるのか」という背景を理解することで、問題を応用する力も自然と身につけることができます。
また、連立方程式は中学数学だけでなく、高校数学や社会での問題解決、さらに将来の進学試験でも頻出する内容です。
したがって今のうちにしっかり理解しておくことは、将来にわたってしっかりと活用できる知識になっていきます。
それではまず、連立方程式とはどのようなものかを整理したうえで、実際の基本的な解法へと進んでいきましょう。
連立方程式とは何か

中学1年で学んだ一次方程式は、未知数(通常は$x$)を1つ含む方程式でした。
例えば、
$2x+3=7$
のような形です。
これを解けば、$x=2$という解を1つ求めることができます。
ところが、現実の問題では「未知の数が1つ」では解決できない場合も多く存在します。
たとえば、次のような状況を考えてみましょう。
- ノート1冊とペン1本を買ったら合計で500円になった。
- ノート2冊とペン3本を買ったら合計で1,300円になった。
このとき、「ノート1冊の値段」と「ペン1本の値段」の両方を求めたい、という問題が出てきます。
このように「未知数が2つあり、それらを同時に決定しなければならない」場面で使うのが連立方程式です。
つまり、2つ以上の一次方程式を同時に満たす解を見つけることが連立方程式を解くということなのです。
連立方程式を解く意味と重要性

連立方程式を解くことは、単なる計算練習にとどまらず、論理的に問題を整理し、複数の条件を満たす解を導く力を養います。
これは数学の基本的な力であると同時に、社会生活や理系・文系を問わない多くの分野で必要とされる思考法でもあります。
日常生活における応用例
例えば次のような場面で、連立方程式の考え方が応用できます。
- 買い物の合計金額から商品の単価を推測する
- 家庭でのレシピ計算(材料の量を2つの条件から調整する)
- 仕事のシフト調整(人数と時間数の2つの条件を満たすように割り当てる)
中学生の段階では「連立方程式は実生活にどう関係するの?」と感じることがあるかもしれません。
しかし、社会に出ると「条件が2つ以上ある問題」を解決する機会は多くあり、そのときに数学的な考え方が役立つのです。
学習上の意義
学習面においても、連立方程式の理解は非常に重要です。
- 高校数学の「二次関数」や「図形と方程式」では、連立方程式を使って交点を求めます。
- 物理では「運動方程式」を複数立てて解くときに連立方程式の知識を活用します。
- 統計や経済学では「需要と供給」の関係を式に表すときに連立方程式が登場します。
このように、連立方程式の解き方をしっかりマスターすることは、数学を得意科目にするうえで避けて通れない基礎なのです。
連立方程式の基本的な解法の種類

連立方程式を解くにはいくつかの方法があり、それぞれに特徴があります。
中学2年で主に学ぶのは次の2つです。
- 代入法
- 加減法
ここからは、それぞれの解法を順に見ていきましょう。
代入法とは
代入法は、1つの式からある文字を他の文字で表し、それをもう一方の式に代入して解く方法です。
例えば、次の連立方程式を考えます。
$\begin{eqnarray}
\left\{
\begin{array}{l}
x+y=5 \\
2x+y=1
\end{array}
\right.
\end{eqnarray}$
1つ目の式から$y=5-x$と変形できます。
これを2つ目の式に代入すると、
$2x−(5−x)=1$
となり、これを解けば$x$の値が求められます。
その後、再び$y$を計算することで答えが出ます。
代入法のメリットは、論理の流れが明確で、初学者にも理解しやすい点です。
デメリットは、代入後の式が複雑になる場合があることです。
加減法とは
加減法は、2つの式を足したり引いたりして、どちらかの文字を消去して解く方法です。
例として、次の連立方程式を考えましょう。
$\begin{eqnarray}
\left\{
\begin{array}{l}
2x+y=8 \\
3x−y=7
\end{array}
\right.
\end{eqnarray}$
この2つの式を足し合わせると、
$(2x+y)+(3x−y)=8+7$
$5x=15$
となり、簡単に$x=3$を得られます。
その後、どちらかの式に代入して$y=2$と求められます。
加減法のメリットは、計算の効率がよく、式がきれいにまとまる点です。
デメリットは、式をうまく揃えないと計算がやや複雑になることです。
代入法の詳しい解き方

ここまでの説明では、連立方程式の基本的な考え方と、代表的な解法である「代入法」「加減法」について概要を確認しました。
ここからは、実際にどのような手順で問題を解いていくのかを、具体的な例題を用いながら解説していきます。
中学2年生が学習する段階では、ただ公式を当てはめるだけではなく「なぜこの操作をするのか」を理解することが大切です。
操作の意味をしっかり理解しておけば、テストで少しひねった応用問題が出題されても、冷静に対応できるようになります。
それでは、ここから具体的に代入法・加減法の順に実践的な解き方を見ていきましょう。
代入法は、連立方程式の中で最も「論理の流れがはっきりしている」解法です。
まずはこの方法から、例題を通じて手順を確認していきましょう。
基本手順
代入法の解き方は次のステップに分かれます。
- どちらかの式から、1つの文字を他の文字で表す。
- その式をもう一方の式に代入する。
- 代入した式を解き、1つの文字の値を求める。
- 求めた値を使って、もう1つの文字を計算する。
例題で確認
次の連立方程式を代入法で解いてみましょう。
$\begin{eqnarray}
\left\{
\begin{array}{l}
x+y=8 \\
2x−y=4
\end{array}
\right.
\end{eqnarray}$
ステップ1:1つの式を変形する
1つ目の式から$y=8−x$と変形します。
ステップ2:代入する
これを2つ目の式に代入すると、
$2x−(8−x)=4$
$3x=12$
となります。
ステップ3:解を求める
$3x=12$
$x=4$
ステップ4:もう一方の文字を求める
これを$y=8−x$に代入すると、
$y=8-4=4$
よって解は$(x,y)=(4,4)$です。
ポイントと注意点
代入法を行っていく際のポイントと注意点は下記のとおりです。
- 変形しやすい式を選ぶ:できるだけ文字の係数が1になっている式を選ぶと計算がスムーズになります。
- 符号の処理に注意:特に「-」を代入するときにミスが多いので注意しましょう。
- 代入後の式が複雑になりやすい:計算を整理しながら進めることが大切です。
加減法の詳しい解き方

続いて、加減法を見ていきましょう。
加減法は、2つの式を足したり引いたりして、どちらかの文字を消去する方法です。
特に係数がそろっているときに非常に有効です。
基本手順
加減法の解き方は以下のように進めます。
- 2つの式の文字の係数をそろえる。
- 文字を消去するために、2つの式を足したり引いたりする。
- 残った文字を解く。
- その解をもとに、もう一方の文字を求める。
例題で確認
次の連立方程式を加減法で解いてみます。
$\begin{eqnarray}
\left\{
\begin{array}{l}
2x+3y=11 \\
3x−2y=4
\end{array}
\right.
\end{eqnarray}$
ステップ1:係数をそろえる
1つ目の式を2倍すると、
$4x+6y=22$
2つ目の式を3倍すると、
$9x−6y=12$
となります。
ステップ2:足す(加法)
これらを足し合わせると、
$(4x+6y)+(9x−6y)=22+12$
$13x=34$
ステップ3:解を求める
$x=\frac{34}{13}$
ステップ4:もう一方の文字を求める
この値を最初の式に代入します。
$2⋅\frac{34}{13}+3y=11$
$\frac{68}{13}+3y=11$
$3y=\frac{143-68}{13}$
$3y=\frac{75}{13}$
$y=\frac{25}{13}$
したがって解は$(x,y)=(\frac{34}{13},\frac{25}{13})$です。
ポイントと注意点
加減法のポイントと注意点は下記のとおりです。
- 係数をそろえるときの工夫:最小公倍数を考えると計算がスムーズになります。
- 引き算のときに符号ミスが出やすい:必ず丁寧に計算するようにしましょう。
- 整数の答えが出るとは限らない:分数で答えを表す場合もあります。
2つの解法の比較

ここまでで、代入法・加減法を利用する方法という2種類の解法を学びました。
改めてそれぞれの特徴を整理してみましょう。
解法の特徴まとめ
| 解法 | メリット | デメリット | 向いている場面 |
|---|---|---|---|
| 代入法 | 論理の流れがわかりやすい | 式が複雑になりやすい | 片方の式が変形しやすいとき |
| 加減法 | 計算がスムーズに進みやすい | 符号ミスに注意が必要 | 係数がそろえやすいとき |
このように、それぞれの解法には得意・不得意があります。
テストや入試で効率よく問題を解くためには、状況に応じて最適な方法を選べるようになることが重要です。
入試やテストでよく出る連立方程式の問題

ここまでの説明で「連立方程式とは何か」と「基本的な解法の種類」について整理し、さらに「代入法・加減法」を具体的に学びました。
ここからは、さらに一歩進んで実践的な問題への応用、入試やテストでの解法の選び方、そして学習法の工夫 を解説していきます。
連立方程式の解き方を正しく理解していても、実際の試験問題では「文章題」や「複雑な設定」を伴うことが多く、そのままでは解きにくいと感じることもあります。
そこで重要になるのが、どの解法を選ぶべきかを見極める力と、計算を効率よく進める工夫です。
さらに、連立方程式は数学の知識にとどまらず、実社会や将来の学問にもつながる重要な基礎です。
ここからは「数学を学ぶ意味」や「将来への応用」にも触れながら、学習を深めていきましょう。
中学生が連立方程式を学ぶ大きな目的のひとつは、定期テストや高校入試で得点できる力を身につけることです。
ここではよく出題されるパターンを確認しておきましょう。
単純な計算問題
もっとも基本的な問題は、すでに学んだように「連立方程式を解け」というものです。
この場合は、代入法・加減法を正しく使い分けられるかがポイントになります。
- 片方の式が変形しやすければ「代入法」
- 係数をそろえやすければ「加減法」
この判断を瞬時にできるように、普段から練習しておくことが大切です。
文章題
次に重要なのが文章題です。
文章題では、状況を式に置き換える力が試されます。
「ノートを2冊とペンを3本買ったら合計で850円。ノートを1冊、ペンを4本買ったら合計で1,000円になった。ノート1冊とペン1本の値段を求めよ。」
この場合、
- ノート1冊の値段を$x$円
- ペン1本の値段を$y$円
とすると、
$\begin{eqnarray}
\left\{
\begin{array}{l}
2x+3y=850 \\
x+4y=1000
\end{array}
\right.
\end{eqnarray}$
となります。
あとは代入法または加減法で解くだけです。
文章題では「どのように式を立てるか」が最大のポイントであり、解法の選び方よりも前の段階の整理力が求められます。
応用問題(速さ・割合・図形)
さらに発展的な応用問題では、「速さ・時間・距離の関係」や「食塩水の濃度」「図形の面積」などと組み合わせて出題されます。
例えば、速さの問題では
この場合、距離 = 速さ × 時間の式を利用し、徒歩と走る場合でそれぞれ方程式を立てると、2つの式が得られます。
このように応用問題では、「数学の知識+現実の公式や性質」を組み合わせる力が問われます。
どの解法を選ぶべきか

実際に問題を解くときには、常に「代入法・加減法」のどれを使うべきかを判断する必要があります。
代入法を選ぶ場合
- 片方の式が「$y=…$」や「$x=…$」の形にすぐ直せるとき
- 文章題で、自然に「○○は△△を使って表す」という関係が出てくるとき
加減法を選ぶ場合
- 2つの式の係数が揃いやすいとき
- 計算をスピーディーに進めたいとき
特に入試では加減法を使ったほうが計算量を減らせることが多く、効率的です。
学習を深めるための工夫

連立方程式を得意にするためには、単に練習量をこなすだけでなく、効果的な学習方法を工夫することが大切です。
解法を自分の言葉で説明する
「なぜその操作をするのか」を言葉にして説明できるようになると、理解が一気に深まります。
友達や家族に「代入法ってどうやって解くの?」と聞かれたときに説明できるレベルを目指すと良いでしょう。
解法の比較練習
同じ問題を「代入法」「加減法」の2通りで解いてみると、それぞれの長所と短所が実感できます。
テストや入試で瞬時に選べる力は、このような比較練習から養われます。
ケアレスミスを防ぐ習慣
連立方程式では符号の見落としや計算の途中の省略がミスにつながりやすいです。
- 式を丁寧に書く
- 計算のステップを飛ばさない
- 最後に「元の式に代入して確認する」
この習慣を徹底すると、確実に点数を安定させられます。
連立方程式の発展と将来へのつながり

中学数学で学ぶのは「二元一次連立方程式」が中心ですが、数学の世界にはさらに発展した連立方程式が数多く存在します。
高校数学へのつながり
- 二次関数との交点問題:二次関数と一次関数の交点を求めるときは、必ず連立方程式を立てます。
- 三元連立方程式:未知数が3つになる場合もあり、加減法を発展させて解きます。
大学や社会での活用
- 物理学:力のつり合いや運動方程式を同時に解く場面で利用します。
- 経済学:需要と供給を数式化したモデルを解くときに連立方程式が登場します。
- プログラミング:複数の条件を同時に処理するアルゴリズムの考え方に応用されます。
このように、連立方程式は数学だけでなく幅広い分野で応用されているのです。
まとめ
このページでは連立方程式の解き方に焦点を当てて解説を行ってきました。
連立方程式にの学習は前回の二元一次方程式との関連性から始まり、解法まで丁寧に学習を行っていくことから、非常に重要な学習単元であることは間違いありません。
また、最後に少し紹介しましたが、連立方程式の解き方については、今後の学習や将来にもつながる大事な知識です。
ここで紹介した2つの解法のメリットとデメリット、実際の解き方の手順をしっかりと身につけて、連立方程式の計算やこれからの学習に最大限活かしていきましょう。







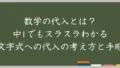
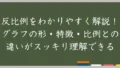
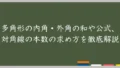
コメント