中学校で学ぶ数学の中でも、最初につまずきやすい単元のひとつが「文字式」です。
小学校までは、問題に出てくるのは具体的な数字だけでした。
しかし中学生になると、$x$や$y$といった「文字」を使って式を表現する学習が始まります。
「数字で計算できるのに、なぜわざわざ文字を使うのか?」
「文字式で考えるとはどういうことなのか?」
「文字を使って説明することにはどんな意味があるのか?」
こうした疑問を持つのは自然なことです。
なので、このページでは、それらの疑問に答えながら、数学を学ぶうえで文字式が持つ本当の意味と役割を解説していきます。
数字だけではなく文字を使う理由

では、まず先に数学で文字を使う理由から復習していきます。
このことについては、中学1年の文字式の学習のところでも解説があった部分なので、思い出しながら見ていきましょう。
数字のままでは不便になる場面
小学校の算数では、具体的な数を使って計算問題を解いてきました。
たとえば、ノート1冊120円なら、2冊で240円、3冊で360円と求めることができます。
しかし、「何冊買った場合の代金も考えたい」となると、どうでしょうか。
2冊、3冊、4冊…とその都度計算しなければなりません。計算自体は簡単でも、冊数が変わるたびに計算し直すのは効率が悪いのです。
文字を使うとどうなるか
ここで「文字」を使います。
ノートの値段を120円、冊数を$x$冊とすると、代金は「$120x$」と表すことができます。
この式があることで、$x$に好きな数を代入すればすぐに答えが出せます。
- $x=2$ → $120×2=240$円
- $x=3$ → $120×3=360$円
- $x=10$ → $120×10=1200$円
つまり、文字を使うことで「すべてのパターンを一つの式で表現できる」ようになるのです。
数字と文字の大きな違い
数字は「その場の答え」を求めるには便利ですが、一般的な関係を表すことはできません。
一方、文字は「変わるもの」「未知のもの」を代わりに置くことで、幅広いケースをまとめて考えることができます。
数学が具体的な計算から一歩進んで、普遍的な考え方や関係を扱えるようになるのは、この「文字式」があるからなのです。
文字式で考えるとはどういうことか

数学で文字を使って考える理由については、今見てきたとおりです。
では、ここから中学2年生の「文字式で考えること」について考えていきましょう。
「考える」とは「しくみを理解する」こと
「文字式で考える」とは、単に式を作ることではありません。
結論から述べると、ここでいう「考える」とは、「ものごとのしくみやルールを理解すること」です。
たとえば友だちとお菓子を分ける場面を考えてみましょう。
- 1人に$a$個ずつ配る
- $b$人に配る
このとき必要なお菓子の数は「$a×b$」個です。
もし $a=3$,$b=4$と具体的に数字がわかっていれば$3×4=12$と計算できます。
しかしあえて文字のまま考えることで、「1人に$a$個、$b$人に配ると$a×b$」という場面のルールそのものを理解できるのです。
文字式で考えることのメリット
このように考えていくと、文字式で考えるメリットは下記のようなものがあることが分かります。
- 具体的な数値が決まっていなくても状況を表せる
- いろいろな数値を代入してすぐに結果を出せる
- 場面を一般化して理解できる
つまり「文字式で考える」とは、物事を個別の数字でなく、関係やしくみとして理解するということなのです。
文字を使って説明するとはどういうことか

では、もう1つの学習内容である、「文字を使って説明する」ということについても考えていきます。
式で理由を伝える力
ここも最初に結論を述べると、「文字を使って説明する」とは、単に答えを出すことではなく、「なぜそうなるのか」を式を用いて順序立てて示すことです。
たとえば、リンゴ1個を$x$円で買うとき、3個買うといくらになるかを考えます。
- 1個が$x$円
- 3個なら$x+x+x$
- まとめて$3x$
このように、計算の過程を式で示すことで「どうして$3x$になるのか」が相手に伝わります。
説明することの意味
このように文字を使って説明をすることで、次のような力が身につきます。
- 自分の理解を整理できる
- 他人にわかりやすく伝えられる
- 数学的に正確な表現を使える
これは数学の学習に限らず、社会に出てから必要になる「論理的に説明する力」に直結します。
文字式は「計算の道具」から「考える道具」へ

ここまで見てきたことはこれまで学習してきた算数や中学1年の数学とは少し意味合いが異なると感じたでしょうか?
数学を「考える学び」に変える
どういった点で意味合いが異なるのかというと、上記のように文字式を使うと、数学は「ただ計算する教科」から「考えを整理して表す教科」へと変わります。
複雑な問題に出会っても、文字式で関係を整理すれば落ち着いて解けるようになります。
また、自分の考えを式で表して説明することで、相手にも理解してもらえるようになります。
文字式は、計算だけでなく「思考を形にする力」を育てるのです。
実際の生活に役立つ文字式の考え方

ここまでは学習内容として、文字式で考えることや文字式を使って説明することを解説してきました。
これらの内容については、数学の学習だけでも身についていくものでありますが、日常生活に落とし込んで考えられるようになると、より知識の定着が早かったりします。
なので、ここでは日常生活の中で役立つ文字式の考え方を紹介していきます。
コンビニでの買い物
文字式が役立つ場面は、学校のテストだけではありません。
身近な生活の中でも、文字を使って考えると便利になる場面があります。
たとえば、コンビニで次のような買い物をしたとします。
- おにぎりを1個 $x$円
- ジュースを1本$y$円
- それぞれ2つずつ買う
このときの合計金額は「$2x+2y$」と表すことができます。
実際に金額が決まっていれば計算は簡単ですが、文字を使えば「おにぎりとジュースを2つずつ買う」というルール自体を表現できます。
後から「もしおにぎりが150円でジュースが120円なら?」と聞かれても、式に代入すればすぐに答えが出せます。
これは「文字式で考える」力の実生活での活用例です。
家族でのお出かけ
別の例を考えてみましょう。
家族旅行に出かける場合、交通費や食事代が人数に応じて変わります。
- 電車代:1人あたり$a$円
- 食事代:1人あたり$b$円
- 人数:$n$人
このとき、全体の費用は「$n(a+b)$」と表せます。
人数が3人なら$3(a+b)$、4人なら$4(a+b)$と簡単に計算できます。
このように文字式を使えば、「人数が変わっても考え方は同じ」ということが一目でわかります。
割引やポイントの計算
さらに文字式は、買い物のお得さを比べるときにも役立ちます。
- 商品1つの値段:$p$円
- 個数:$n$個
- 割引率:10%
割引後の合計金額は「$0.9pn$」で表せます。
さらに、ポイント還元が5%あれば、「$0.95×0.9pn$」で計算できます。
このように文字式を使えば、複雑に見える条件も整理して考えられるようになります。
学校以外で文字式を使う意味

上記で見てきたように日常生活の中でも、様々なシーンで文字式を使っていくことができ、どういった条件でも文字式で対応することが分かりました。
では、学校の勉強以外で文字式を使う意味とは何なのか?
ここでは、その意味について考えていきます。
スポーツやゲームに応用
スポーツやゲームでも、文字を使った考え方は役立ちます。
たとえばバスケットボールで、シュート1本が2点、フリースローが1点だとします。
- 2点シュートの成功数:$x$本
- フリースローの成功数:$y$本
合計点数は「$2x+y$」です。
実際の試合では得点がその都度変わりますが、この式を知っていれば「得点のしくみ」を整理できます。
また、ゲームのスコア計算やポイント換算も同じように文字式で表せます。
アルバイトや将来のお金の計算
中学生のうちはまだ実感がないかもしれませんが、高校生や大学生になるとアルバイトを始める人も増えます。
そのときに役立つのが文字式です。
- 時給:$w$円
- 勤務時間:$h$時間
- 日数:$d$日
アルバイト代は「$whd$」で計算できます。
さらに交通費が1日あたり$t$円かかるなら、差し引いた金額は「$whd-td$」になります。
こうして式で表すと、「働く日数を増やせば収入が増える」「交通費が高いと手取りが減る」といった関係もすぐに理解できます。
つまり、文字式を使う意味は「複雑な条件を文字の数式で簡略化して表現し、様々な状況に応じて対応しながら考えていく道具」となります。
文字式を使って「説明する」力の実例

では、実際に文字式を使って自分でも説明できるかを考えていきます。
ですが、いざやってみようとすると、何についてすればいいのか分からないということもあると思うので、ここではいくつか実例を紹介します。
友だちに教えるとき
「なぜそうなるのか」を説明するときに、文字式はとても役立ちます。
たとえば、次のような会話を考えてみましょう。
友だち:「どうして$a(b+c)=ab+ac$になるの?」
自分:「$b+c$は2つのまとまり。そこに$a$をかけるっていうのは、$a×b$と$a×c$を足すのと同じだよ。」
さらに図や表を使いながら説明すると、よりわかりやすくなります。
式を使って順序立てて伝えることで、自分の理解も深まります。
レポートやプレゼンでも活きる
学校の授業や部活動で、レポートを書いたり発表をしたりすることがあります。
そのときに「文字を使って説明する」力があると、論理的でわかりやすい内容にできます。
たとえば、文化祭で模擬店を出す場合、仕入れ値や販売数を文字で表して利益を計算できます。
これをプレゼンで説明すれば、聞いている人に「なるほど」と思ってもらいやすくなります。
将来の仕事で活かされる文字式

ここまでの説明で、文字式を考えることや文字式を使って説明することの重要性の理解は深まってきていると思います。
では、これらの重要なことが将来にどう活かされるのかも紹介しておきます。
設計や建築の仕事
設計図や建築では、長さ・面積・体積を文字で表して計算することが欠かせません。
部材の長さを$x$、幅を$y$とすると面積は$xy$です。
高さを$z$とすれば、体積は$xyz$になります。
このように文字を使うことで、多くのパターンを一度に扱えます。
プログラミング
プログラミングでは「変数」と呼ばれる考え方を使います。
変数はまさに文字式そのもので、$x$や$y$に値を入れて計算したり処理をしたりします。
たとえば「商品の値段×数量」をプログラムで書くと、
price * quantity
という式になります。
これは数学の文字式そのものです。
データ分析や経済分野
データを扱う仕事では、数式を使って関係を表します。
たとえば、売上高を「価格 $p$×数量$q$」とすれば、売上の変化を文字式で分析できます。
経済や経営の世界でも、文字式で考える力は欠かせません。
学校の学習と実生活をつなげる「文字式の考え方」

ここまで見てきたように、日常生活の中や将来でも文字式の考え方を活かすことが分かりました。
では、学校で学ぶ知識と実生活への応用をどう結び付けていけばいいのでしょうか?
その方法や考え方をいくつか紹介していきます。
①計画を立てるときに役立つ
貯金計画や勉強時間のスケジュールを考えるときも、文字を使って表すと整理がしやすくなります。
例えば「毎月1万円を$n$か月貯めると合計金額はいくらか?」を$10000n$円と表せば、将来の見通しを立てられます。
②未知の数量を考える力を養う
文字式は「まだ決まっていない数を扱う」ためのものです。
この発想は、将来プログラミングや経済学、統計学などを学ぶ際にも重要になります。
未知の要素を変数として扱い、式で関係を表す思考はあらゆる学問の基盤となるからです。
③問題解決力を高める
数学は「答えを出すこと」よりも「筋道を立てて考えること」が大切だとよく言われます。
文字式を使えば、「もしこうなったらどうなるか?」を試しながら論理的に解決策を導く力がつきます。
これは将来の仕事や日常の問題解決にもつながります。
このように方法や考え方は挙げればきりがありません。
ですが、意外に自分が学習内容と日常生活の事象を結び付けられれば、何でもいいことが分かります。
なので、積極的に学んだことを日常生活に活かしていきましょう。
将来につながる「文字式で考える力」

では最後に、文字式を使う力がどう将来につながるのかを簡単に紹介だけしておきます。
①高校・大学での発展
高校では二次方程式、関数、微分・積分など、すべてが「文字を使った表現」に基づいています。
大学に進めば、理系はもちろん文系でも統計学や経済学で文字式を扱います。
②仕事での活用
建築や設計では、建物の強度や面積を文字で表して計算します。
また、情報技術やプログラミングでは、変数を使って処理を記述します。
加えて、どのようなビジネスでも、利益やコストの計算を「売上=単価×数量」といった式で整理します。
③人生設計での活用
人生の大きな選択でも「条件を文字に置き換える」ことで見通しが立ちます。
例えば「毎月の支出を$x$円、収入を$y$円」とすれば、「$y-x$」が黒字か赤字かを示します。
まとめ
このページでは、「文字を用いた式で捉えること」と「文字を用いた式で説明すること」について解説してきました。
数学の学習で文字を使うのは、ただむずかしくするためではありません。
文字を使うことで、より多くの場面に対応できたり、自分の考えをしっかり説明できたりするようになります。
イメージを掴むのが難しい、わからないときは、まず身の回りの例で考えてみましょう。
そして、そのしくみを式で表せるようになれば、それが「式で捉える力」、それを使って人に説明できれば「式で説明する力」になります。
文字式は「数字を扱うための単なる記号」ではなく、考えを整理し、未知の状況を理解するための強力な道具です。
- 学校で学ぶ基礎(文字式のルールや計算方法)
- 日常生活での応用(買い物、料理、計画立てなど)
- 将来の学問や仕事での発展的な活用
これらを結びつけて考えると、「文字式で考える」とは、単に問題を解く力を育てるのではなく、論理的に未来を見通す力を育てることだとわかります。
これから文字式を学ぶみなさんも、「ただの計算」だと思わず、「自分の生活や将来につながる力を育てている」と意識して学んでみてください。







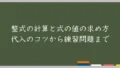

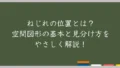
コメント