確率について学習を進めて中で、「多数の観察」や「多数回の試行」という言葉を一度は耳にしたことがあるでしょう。
上記のような固い言い方ではなかったかもしれませんが、同じような意味で、「繰り返し行う」や「〇日間観察を続ける」などの文言が確率の問題に入っているものもあったかと思います。
これから様々な確率の学習を行っていきますが、その中でも1つ重要になってくる確率の学習として、「多数の観察や多数回の試行よって得られる確率」があります。
このページでは、「多数の観察や多数回の試行よって得られる確率」について、どういったことが多数の観察や多数回の試行になるのか、逆にどういったことが該当しないのか、多数の観察や多数回の試行で得られる確率とはどういったものなのか、などを解説していきます。
試行回数とは何か

まずは、確率の問題で目にする、「試行回数」という言葉から見ていきます。
試行という言葉の意味
「試行」とは、ある出来事や実験を繰り返すことを指します。
例えば、コインを投げて「表」か「裏」が出るかを調べることや、サイコロを振って出た目を記録することが典型的な「試行」です。
ここで重要なのは、「試行」とは必ずしも一度で終わるものではなく、何度も繰り返すことを前提にした行為であるという点です。
コインを一度投げるのも試行ですが、それを100回、1,000回と続けて行えば「試行回数が100回」「試行回数が1,000回」と表現します。
試行回数の重要性
試行回数は確率を考える上で非常に大切な要素です。
なぜなら、試行の回数が少なければ少ないほど、偶然による偏りが強く出てしまうからです。
例えばサイコロを1回だけ振って「6」が出たとき、「サイコロはいつも6が出る」とは言えません。
2回、3回程度でも同じです。
しかし100回、1,000回と回数を重ねていけば、「各目が大体同じくらいの割合で出る」という傾向が見えてきます。
この「回数が増えることで偶然の影響が平均化される」ことこそ、確率学習における基盤となる考え方です。
多数回の試行とは何か

上記で試行という言葉の定義を確認したところで、ここで学習していく「多数回の試行」とはどういうことかを見ていきましょう。
「多数回」の意味
では、「多数回の試行」とは具体的にどのようなものを指すのでしょうか。
一般的に「多数回」とは明確に「〇回以上」という基準が決まっているわけではありません。
しかし、1回や2回、10回程度ではなく、できるだけ大きな回数を繰り返すことを意味します。
例えば、サイコロを100回振る、コインを1,000回投げる、天気を30日間毎日記録する、などが「多数回の試行」にあたります。
少数回との違い
少数回の試行と多数回の試行の違いを具体的に考えてみましょう。
- 少数回の試行
サイコロを10回振ってみると、「2」が3回出たのに「5」が1回も出ない、という結果になることがあります。
この場合、「サイコロは2がよく出て、5は出にくいのではないか」と誤解してしまうかもしれません。 - 多数回の試行
サイコロを100回、1,000回と振っていくと、各目はほぼ均等に出るようになり、理論的に考えられる「$\frac{1}{6}$」という確率に近づいていきます。
つまり、「多数回の試行」を行うことで、初めて「理論的な確率」に近い傾向を観察できるのです。
経験的な確率とは何か

多数回の試行の定義とその重要性は上記で説明した通りです。
では、次にもう1つの学習内容である「経験的な確率」とは何かを見ていきます。
定義と意味
「経験的な確率」とは、実際に行った多数回の試行や観察の結果から求められる確率のことです。
その求め方はとてもシンプルで、次の式で表されます。
経験的な確率$=\frac{ある事柄が起こった回数}{試行回数}$
例えばコインを100回投げて「表」が48回出た場合、
表が出る確率$≒\frac{48}{100}=0.48$
と表されます。
理論的な確率は0.5(50%)ですが、実際の試行では偶然の影響により少しずれることがあります。
それでも多数回を行えば行うほど、経験的な確率は理論的な確率に近づいていきます。
理論的な確率との関係
- 理論的な確率:数学的な計算から導かれる理想的な値(例:サイコロの目は$\frac{1}{6}$ずつ出る)。
- 経験的な確率:実際に試行して得られた値。
両者は完全に一致するとは限りませんが、試行回数を増やすことで両者の差は小さくなります。
この性質は「大数の法則」と呼ばれ、確率論の基本原理の1つです。
サイコロを用いた具体例

実際にサイコロを振る試行を例にして、経験的な確率の考え方を確認してみましょう。
10回振った場合
ある人が10回サイコロを振って出た目が次のようになったとします。
1, 2, 2, 3, 6, 6, 4, 3, 2, 1
この結果では「2」が3回出ており、「5」が1回も出ていません。
これだけを見ると「2は出やすく、5は出にくい」と思えてしまいます。
100回振った場合
次に100回サイコロを振ったときの結果を記録すると、例えば次のようになったとします。
- 1の目:18回
- 2の目:16回
- 3の目:19回
- 4の目:17回
- 5の目:14回
- 6の目:16回
ここでは、各目が大体15回から20回程度ずつ出ており、理論的な確率$\frac{1}{6}$(約16.7%)に近づいていることがわかります。
このように、回数を増やすことの大切さが実感できます。
日常生活で見られる多数回の観察

確率の学習は教科書や問題集の中だけのものではなく、私たちの身近な生活の中でも役立っています。
特に「多数回の観察」や「多数回の試行」に基づいたデータは、社会で幅広く利用されています。
天気予報の例
ニュースやスマホアプリでよく見る「降水確率40%」という情報は、多数の観測データから導かれています。
気象庁や気象会社は過去の似たような気象条件を膨大に集め、そのときの降水状況を分析して確率を出しています。
つまり、降水確率40%とは「過去に同じ条件のとき、10回のうち4回は雨が降った」という統計に基づくものなのです。
アンケート調査の例
世論調査や市場調査で「〇%の人がこの商品を利用している」という結果が出るのも、多数の回答を集めたからこそわかることです。
例えば1,000人にアンケートをとり、そのうち800人が「利用している」と答えれば「利用率80%」という経験的な確率が求められます。
少数回の試行ではなぜ不十分なのか

では、なぜ確率の問題を考えていく際に、多数回の試行でなければいけないのでしょうか?
理論的な確率を知っているのであれば、その値を軸に考えていくのが効率的だと考える人も少なくないでしょう。
ここでは、多数回の試行の重要性について深掘りしていきたいと思います。
偶然の偏りが強く出る
試行回数が少ないと、偶然の結果に大きく左右されます。
例えばサイコロを5回振ったときに「6」が3回出ることは珍しくありません。
しかしこの結果だけを見て「サイコロは6が出やすい」と考えるのは誤りです。
確率は「長期的に見ればどうなるか」を扱うものであり、少数回ではその傾向を正しくつかむことができません。
実験データの例
- コインを10回投げる実験
ある人は10回投げて「表」が7回出ました。
その結果から「表が出る確率は70%」と考えてしまうと、実際の確率50%とは大きくずれてしまいます。 - コインを100回投げる実験
同じ人が100回投げたら「表」が49回でした。
このときの経験的な確率は49%であり、理論的な確率50%にかなり近い結果となりました。
この比較からもわかるように、試行回数が少ないと偏りが強く、試行回数を増やすと確率は安定していきます。
大数の法則とは何か

ここまで多数回の試行を中心に解説を進めてきました。
ここからは上記の説明の中で登場した「大数の法則」について簡単に解説していきます。
法則の概要
「大数の法則」とは、多数回の試行を行うと経験的な確率が理論的な確率に近づいていくという法則です。
数学的には、試行回数を無限に大きくすると両者は一致する、と説明されます。
日常生活でのイメージ
例えばサイコロを1,000回振れば、各目は大体160~170回程度ずつ出て、理論的な$\frac{1}{6}$に近い割合になります。
1万回振ればさらに精度が上がり、ほとんど誤差が見えなくなります。
つまり、試行回数が大きければ大きいほど、確率は「理論通り」に落ち着いていくのです。
重要なポイント
- 少数回では「偏りのあるデータ」が得られることが多い
- 多数回では「理論的な確率に近いデータ」が得られる
- 完全に一致するわけではないが、差はどんどん小さくなる
この考え方は、確率論だけでなく、統計学やデータ分析の基礎にもつながります。
サイコロとコインで見る大数の法則

大数の法則の概要は解説した通りです。
この法則について、サイコロとコインを使って実際に考えてみましょう。
サイコロの実験
あるクラスでサイコロを振る実験を行いました。
- 10回の平均 → 「1」が出る割合は 22%
- 100回の平均 → 「1」が出る割合は 16%
- 1,000回の平均 → 「1」が出る割合は 16.6%
このように、回数を増やすほど「1の目は$\frac{1}{6}$」という理論値に近づくことが確認されました。
コインの実験
別の実験ではコインを投げて「表」の出る回数を調べました。
- 20回投げた → 表は14回(70%)
- 200回投げた → 表は96回(48%)
- 2,000回投げた → 表は1,002回(50.1%)
こちらも、回数が増えるごとに「50%」に近づいていくことがわかります。
少数回に惑わされないために

ここまで解説してきた内容の理解が進んでいれば、確率の問題を考えるときは試行回数が重要だと感じてもらえていると思います。
では、実生活の中でも様々な確率の値と向き合うことがあると思います。
その時に、どうその数値と向き合うのがいいかを見ていきましょう。
偏りのある結果をどう捉えるか
例えば、ある商品を買った人10人にアンケートを取ったところ、7人が「満足」と答えました。
ここで「満足度70%」と結論づけてしまうのは危険です。
なぜなら10人というサンプル数が少なすぎるからです。
もし1,000人に聞けば「満足度55%」というように、全体の傾向が見えてくるかもしれません。
試行回数を増やす工夫
- 短時間でできる簡単な試行を繰り返す(例:サイコロ、コイン)
- グループで分担してデータを集める
- 過去のデータを活用する(気象観測や統計調査など)
このようにして試行回数を増やすことで、より信頼できる確率を導くことができます。
身近な応用例

数学の学習的な解説は今まで行ってきた内容ですが、実生活の中で実際に使われている多数回の試行や大数の法則をいくつか紹介していきます。
天気予報
天気予報で「降水確率60%」と表示されたとき、それは多数の観測データに基づいています。
過去に似た条件の気象状況が100回あった場合、そのうち60回は雨が降った、という経験的な確率が利用されているのです。
スポーツ
野球選手の打率は「ヒットの回数 ÷ 打席数」で求められます。
打席数が10回しかなければ大きな偏りが出ますが、シーズンを通して500打席もあれば、その選手の本来の打率がはっきりと見えてきます。
健康や医療
医学の臨床試験では、多数の患者に対して薬を投与し、効果や副作用を調べます。
試行人数が多いほど、得られる確率は信頼できるものになります。
将来の仕事で活かされる例

日常生活の次に紹介する例として、将来の仕事の中で活かせる例も見ていきましょう。
ビジネスにおける活用
現代社会では、データ分析に経験的な確率の考え方が欠かせません。
- 広告効果の測定
1,000人に広告を見せて、そのうち50人が購入した → 購入率5% - 顧客満足度
500人にアンケートして400人が「満足」と答えた → 満足度80% - 商品の不良率
1万個の製品を調べて不良が120個 → 不良率1.2%
これらの確率は「将来の予測」にもつながります。
たとえば「次に商品を出荷したとき、不良が出る確率は1%程度」と考えられるのです。
医学・健康分野での応用
医学研究でも、多数のデータから経験的な確率を導きます。
- 薬の効果
1,000人に薬を投与して600人に効果があった → 効果の確率は60% - 副作用の確率
2,000人中40人に副作用が見られた → 副作用発生確率は2%
このように多数のデータを集めて確率を求めることで、安全性や有効性を客観的に判断できるのです。
経験的な確率を考える際の注意点

最後に、経験的な確率は直感的に使える値であるからこそ気をつけてもらいたい点を3つ提示しておきます。
注意1:少数回では正しい結論を出せない
試行回数が10回や20回では、偶然の要素に左右されやすく、信頼性が低い結果になります。
なるべく回数を多くすることが重要です。
注意2:確率は必ず誤差を含む
多数回の試行をしても「完全に理論通り」にはなりません。
サイコロを600回振っても「各目が100回ずつ出る」とは限らず、95回や107回といった誤差が出ます。
注意3:未来を「予言」するものではない
確率は「次に必ずこうなる」というものではなく、「長期的にこうなる可能性が高い」という考え方です。
例えば降水確率60%でも雨が降らない日もあるし、40%でも降ることがあります。
まとめ
このページでは、多数の観察や多数回の試行によって得られる確率について解説をしてきました。
確率の学習の中でも、「多数の観察」や「多数回の試行」によって得られる確率は、非常に大切な考え方です。
1回だけの結果にとらわれず、くり返し調べることで、本当の傾向や確率が見えてくることがわかったと思います。
この考え方は勉強だけでなく、ニュースを読むときや日常の判断をするときにも役立ちます。
確率の考え方を通して、「物ごとを正しく見る力」も少しずつ養っていきましょう。










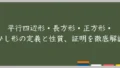
コメント