前回までで整式の計算、具体的には単項式と多項式の計算を学んできました。
唐突ですが、ここで整式の計算を学習した目的を考えてみましょう。
いろいろな考えが思いつくと思いますが、筆者は整式の計算を学習した目的を「整式をまとめること(コンパクトにすること)で、その後の計算処理を簡単にするため」だと思っています。
どういうことかというと、中学数学からは文字を使った計算が中心になっていますが、実際の計算では、数を文字に入れて(代入して)計算を進めていきます。
ですが、項がたくさんある式に1つ1つわざわざ文字に数を代入していっては、計算が多くなりミスが発生する原因になります。
そこで、整式を整理したうえで、最後に文字に数を代入することで、数の計算をできる限り減らしてミスをなくすのが目的になっていると考えます。
なので、今回このページで学習する式の値は、整式の計算処理が理解できている前提で進めていったほうが、理解が早いと筆者は考えます。
もし、整式の計算がまだあいまいな学生さんは、以下のページに振り返ってから式の値の学習に移っていきましょう。
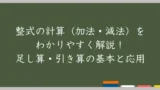
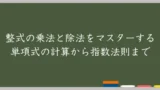
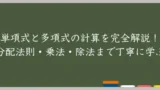
整式の計算を学ぶ目的とは?
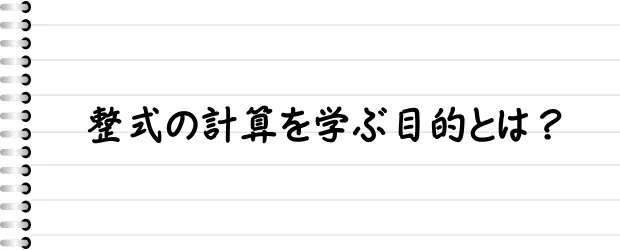
まず整理しておきたいのが、「なぜ整式の計算を学ぶのか?」という点です。
中学数学では文字を使った計算が中心ですが、最終的には文字に数を代入して計算する場面がほとんどです。
もし整式を整理しないまま代入すれば、次のような問題が起こります。
- 代入する回数が多くなり、計算量が増える
- 複雑になりすぎて途中でミスが増える
- 最後まで解き切れずに時間切れになる
例えば次の例を見てみましょう。
例:整式を整理せずに代入する場合
式
$2x+x+3x+5$
に$x=2$を代入するケースを考えます。
整理しないまま代入すると、
$2×2+2+3×2+5$
$=4+2+6+5=17$
一応答えは出ますが、4回も代入していて無駄が多いです。
例:整式を整理してから代入する場合
では、上記のような大変な計算をしないために式を整理したうえで計算するとどうでしょう。
まず同類項をまとめます。
$2x+x+3x+5=6x+5$
次に$x=2$を代入します。
$6×2+5$
$=12+5$
$=17$
代入回数は1回で済み、計算が圧倒的にスムーズになります。
つまり、整式の計算は代入後の計算を楽にするための準備なのです。
代入の基本ルールをおさらい
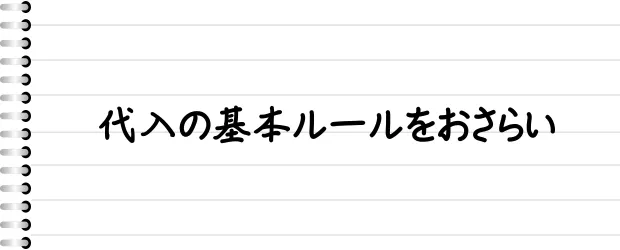
次に「代入」とは何かを1年生で学んだ範囲から復習します。
基本の流れ
- 文字のところに指定された数を入れる
- 四則演算(× ÷ + −)の順序を守って計算する
これだけですが、実際にやると計算ミスが起きやすいので注意が必要です。
下記のいくつかの例題を通して、代入計算を簡単に復習しておきましょう。
例題1
式
$2x+3$
に$x=3$を代入します。
代入すると
$2×3+3$
$=6+3$
$=9$
答えは9です。
例題2
式
$3x−2y$
に$x=2$,$y=4$を代入します。
代入すると
$3×2−2×4$
$=6−8$
$=−2$
答えは−2です。
このように、文字が複数ある場合でも、1つずつ代入してから計算すればOKです。
代入でよくあるミスとその防ぎ方
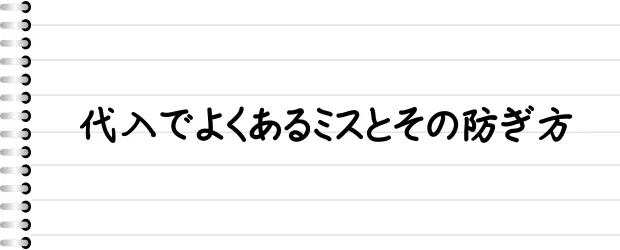
代入計算について簡単に振り返りましたが、上記でもお話した通り、「代入」は一見シンプルですが、実際にはミスが起きやすいです。
どんなミスが起こりがちかも確認しておきます。
ミス①:負の数をそのまま代入してミス
例
$ab−2b$
に$a=−1$,$b=4$を代入します。
ここで「−1×4」を正しく書けずにミスすることがあります。
ポイントは「負の数を代入するときは必ずカッコでくくる」こと。
ミス②:計算順序を無視してしまう
例えば
$2+3x^2$
に$x=2$を代入します。
間違いの例のようにしないためにも、指数(べき乗)の計算を忘れずに先に行うこと。
ミス③:代入する文字を取り違える
式に複数の文字がある場合、$x$と$y$を入れ間違えることがあります。
こうった文字の取り違えを福ぐために、代入する前に文字の上に小さく代入値を書き込むことをおすすめします。
例
$2x+3y$
$x=2$,$y=5$の場合、式に「$x=2$,$y=5$」と上書きしておくとミスが激減します。
代入の練習問題(基本)
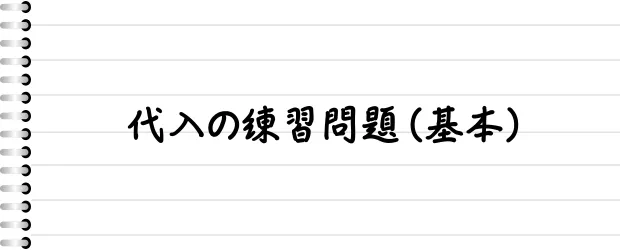
では、ここまでの流れを確認するために、基本的な問題を解いてみましょう。
問題1
次の式に$x=3$を代入したときの値を求めよ。
$5x−2$
解答
$5×3−2$
$=15−2$
$=13$
答えは13
問題2
次の式に$x=2$,$y=5$を代入したときの値を求めよ。
$2x+3y$
解答
$2×2+3×5$
$=4+15$
$=19$
答えは19
問題3
次の式に$a=−1$,$b=4$を代入したときの値を求めよ。
$ab−2b$
解答
$(−1)×4−2×4$
$=−4−8$
$=−12$
答えは−12
問題4
次の式に$x=0$を代入したときの値を求めよ。
$7x+5$
解答
$7×0+5$
$=0+5$
$=5$
答えは5
複雑な整式の代入
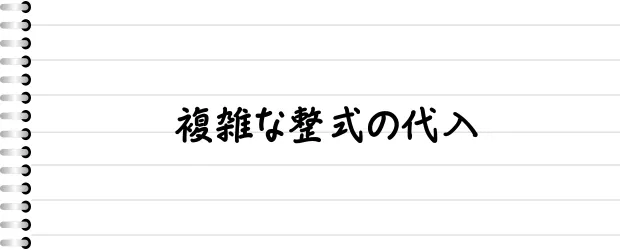
ここまでの説明では、整式の整理と代入の基本ルール、そしてミスを防ぐコツを確認しました。
ここからは、さらに複雑な整式や文章題の中で使われる式の値に焦点をあて、実際のテストや入試で得点できる力を養っていきます。
まずは「同類項が複数」「文字が3種類以上ある」といった式を扱ってみましょう。
例題1(文字が3種類以上の場合)
次の式に$x=2$,$y=−1$,$z=3$を代入して値を求めよ。
$2x^2−3y+4z$
解答
$2×2^2−3×(−1)+4×3$
$=2×4+3+12$
$=8+15$
$=23$
答えは23
例題2(少し複雑)
次の式に$a=1$,$b=−2$を代入して値を求めよ。
$3a^2b−2ab^2+b^3$
解答
$3×1^2×(ー2)−2×1×(ー2)^2+(ー2)^3$
$=3×1×(ー2)ー2×1×4ー8$
$=ー6ー8ー8$
$=ー22$
答えは−22
文字が分母にある場合の注意
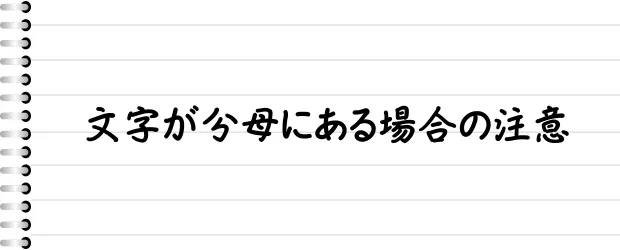
ここまでの計算は係数や代入する数が整数の場合の計算を見ていきました。
ですが、いつもそういった数しか取り扱わないというわけではありません。
係数や代入する数が分数であり、分母に文字が含まれる場合、代入によって分母が0にならないかを確認することが重要です。
ここからは分数を含む計算を見ていきます。
例題3
$\frac{2x+3}{x-1}$
に$x=1$を代入してみましょう。
代入すると
$\frac{2×1+3}{1-1}$
$=\frac{5}{0}$
この場合、分母が0になってしまうので、値は存在しない(定義できない)という結論になります。
ポイント
分数の形で出題された場合は、上記の例で見たような解も存在するため、分数の形で出題された際は、下記のポイントを必ず押さえるようにしましょう。
- 代入前に分母が0になる値が含まれていないかチェック
- 分母が0になる場合は「定義されない」と答える
これは高校数学以降でも頻出の確認事項です。
多項式を整理してから代入
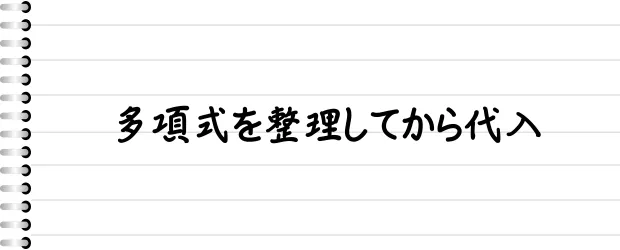
では、中学2年で学習をする多項式への代入も見ていきましょう。
複雑な代入を楽にするコツは冒頭でもお話した通り、「先に整理」です。
例題4
次の式に$x=2$を代入。
$2x+3x^2−4+x^2$
まず整理します。
$2x+3x^2−4+x^2$
$=2x+4x^2-4$
次に代入していきます。
$2×2+4×2^2-4$
$=4+16ー4$
$=16$
答えは16
文章題における「式の値」
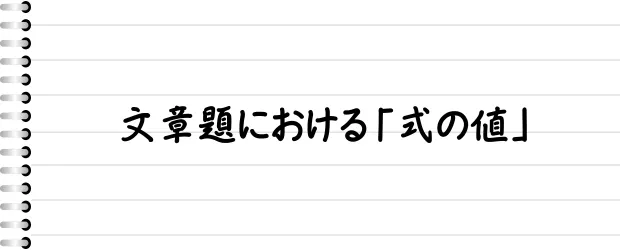
このような計算問題が整式の整理や代入の問題ではよく出題されます。
加えて、出題頻度は少ないですが、文章問題でも出題されることがあります。
なので、ここからは、数学の文章題で「式の値」がどう使われるかを見ていきましょう。
例題5(長方形の面積)
縦を$x$、横を$y$とする長方形の面積は$xy$で表されます。
縦が3cm、横が5cmのときの面積を求めよ。
解答
$xy=3×5=15$
答えは$15cm^2$
このように、文章題では「状況を式で表してから代入」する流れになります。
例題6(料金の計算)
ある遊園地では、入場料を$x$円、乗り物代を1回$y$円とする。
大人2人と子供3人が入場し、さらに乗り物に5回乗ったときの合計料金を求めよ。
ただし入場料は1人あたりで同じ金額で800円とし、乗り物代は200円とする。
式の立て方
$2x+3x+5y$
$=5x+5y$
入場料が800円、乗り物代が200円なので
$5×800+5×200$
$=4000+1000$
$=5000$
答えは5,000円
実戦形式で練習問題
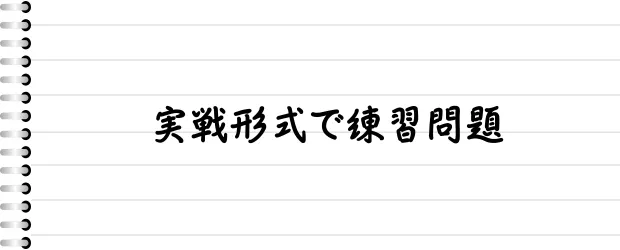
ここまでの内容を確認するために実践問題に近い形の練習問題を行ってみましょう。
問題1
次の式に$x=3$,$y=−2$を代入せよ。
$2x^2y−3xy+y^2$
問題2
次の式に$a=−1$,$b=2$を代入せよ。
$ab^2−3a^2b+b^3$
問題3
$\frac{x^2-1}{x-1}$
に$x=3$を代入して値を求めよ。
問題4
兄の年齢を$x$、弟の年齢を$y$とするとき、次の式は兄が弟より何歳年上かを表す。
$x-y$
兄が15歳、弟が12歳のとき、この式の値を求めよ。
問題5
1辺が$x$cm の正方形の面積は$x^2$で表される。
$x=7$のとき、面積を求めよ。
解答
1.
$2x^2y−3xy+y^2$
$=2×3^2×(-2)-3×3×(-2)+(-2)^2$
$=2×9×(-2)-3×3×(-2)+4$
$=-36+18+4$
$=-14$
2.
$ab^2−3a^2b+b^3$
$=(-1)×2^2-3×(-1)^2×2+2^3$
$=(-1)×4-3×1×2+8$
$=-4-6+8$
$=-2$
3.
$\frac{x^2-1}{x-1}$
$=\frac{3^2-1}{3-1}$
$=\frac{9-1}{2}$
$=\frac{8}{2}$
$=4$
4.
$x-y$
$=15-12$
$=3$
3歳
5.
$x^2$
$=7^2$
$=49$
$49cm^2$
典型ミスと対策
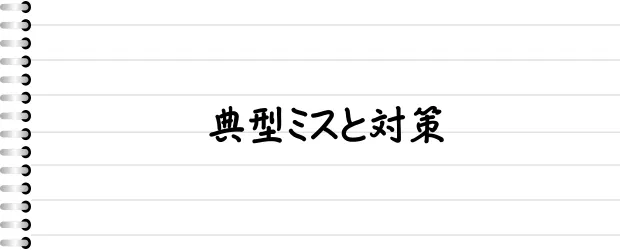
ここまでで「解ける」ようになった人も、テストでは次のようなミスが多発します。
最後に典型的なミスとその対策を見ておきましょう。
- 符号ミス:「-(-3)」を計算して-3 にしてしまう(正しくは+3)
- 代入の順序ミス:整理せず代入して計算が煩雑になる
- 分母の確認漏れ:分母が0になる場合を見逃す
これを防ぐには途中式を必ず書くことdです。
計算用紙に大きめに書いて確認しながら進めましょう。
まとめ
今回のページでは、式に数を代入して「式の値」を求める方法について学びました。
中学1年生で習った「代入」の考え方をふり返りながら、実際の計算方法、よくあるミス、そして練習問題に取り組むことで、基本をしっかりと確認できたと思います。
ここで学習したことは、あまり多くなかったと感じたかもしれませんが、そのように感じることが多かった学生さんほど、丁寧に計算していくという意識を高く持つことをおすすめします。
簡単な分野こそ、ちょっとしたミスで足元をすくわれることもあるので、何回もお話してきましたが、丁寧に計算することを意識して、この範囲の学習をしていくようにしましょう。
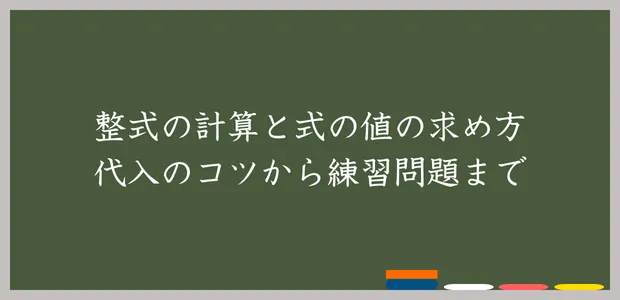








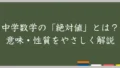
コメント