前回のねじれの位置から中学数学の空間図形の学習が本格的に始まりますが、図形の位置関係以外にも、空間図形を中心に、様々な図形の計量を行っていきます。
この分野は公式を覚えたうえで実際に計算していくことが多いですが、公式を覚えることに苦労してしまう学生さんも多いです。
なので、このページでは空間図形の種類やそれぞれの図形の公式を中心に解説をしていきます。
- 空間図形って何?
- 空間図形を学ぶ意味って?実生活や入試との関係
- 中学数学で登場する代表的な空間図形の種類と特徴
- 図形の特徴を理解するコツは「展開図」と「対応する辺・面・点」
- 正多角形を底面に持つ図形と名称のルール
- 多面体ってどんな図形?定義と空間図形との関係
- 多面体の構成要素:面・辺・頂点の意味とは?
- 多面体の分類:正多面体とそれ以外の多面体
- 正多面体の種類と特徴
- 正多面体の構成数を求める公式(辺・面・頂点)
- 多面体を身近に感じる!図形のイメージと活用例
- 多面体の学習でつまずきやすいポイントと対策
- 空間図形の公式まとめ|体積・表面積の一覧で確認しよう
- 空間図形の問題を解くための視点:展開図のコツとよく出る形
- よく出る!空間図形の入試問題タイプと解き方のポイント
- まとめ
空間図形って何?
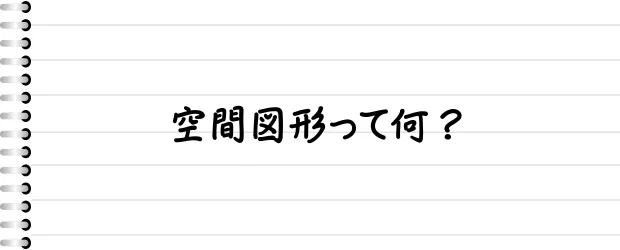
空間図形の種類や公式の解説を行っていく前に、根本的な空間図形とは何かを説明していきます。
数学で出てくる「図形」には、大きく分けて平面図形と空間図形の2種類があります。
「空間図形とは?」という疑問に答えるには、まずこの違いを理解することが大切です。
平面図形は、紙の上や黒板の上など、1枚の平面の中だけで表現される図形です。
三角形、四角形、円などがその代表です。
長さや面積などを測る対象です。
一方、空間図形は、縦・横だけでなく奥行き(高さ)を持った立体です。
たとえば、ジュースの缶、ティッシュの箱、アイスのコーンなど、実際に手で持てるような形が空間図形にあたります。
このように、空間図形は立体的に存在する形を表しており、これからの学習内容はその特徴や体積・表面積を求める計算が重要になってきます。
空間図形を学ぶ意味って?実生活や入試との関係
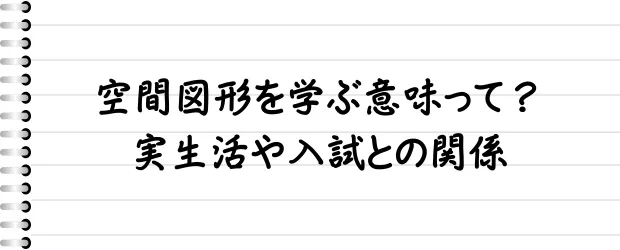
では、空間図形の学習をしていく目的や理由はどういったことがあるのでしょうか?
「空間図形なんて日常で使う?」と疑問に思うかもしれません。
でも、実は空間図形の考え方は平面図形以上に身近な生活の中にたくさん潜んでいるのです。
たとえば、
- 宅配便の荷物の体積や大きさを測るとき
- 部屋の家具のレイアウトを考えるとき
- 建物や製品の設計図を見るとき
すべて空間図形の理解が役立っています。
さらに日常生活以外にも、中学数学の定期テストや高校入試でも空間図形の問題は定番です。
特に「体積・表面積」「展開図」「多面体の特徴」「断面図」などが頻出分野となっています。
こうした背景からも、「空間図形の基本を理解すること」は中学生にとってとても大事な学びなのです。
中学数学で登場する代表的な空間図形の種類と特徴
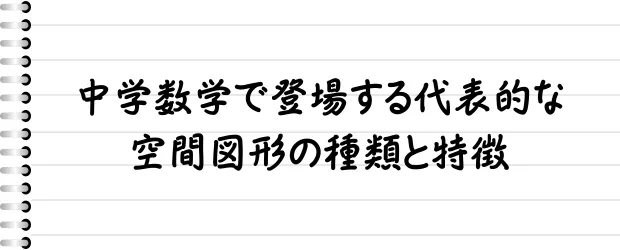
空間図形の定義と学ぶ意義を明確にしたところで、早速空間図形の種類を紹介していきます。
ここでは、特に中学数学で登場する主要な空間図形をわかりやすく紹介します。
それぞれの構造・形の特徴をしっかり把握しておくことが、問題を解くうえでの大きなヒントになります。
説明の中で表面積や体積の公式も紹介していきますが、その部分についてはご自身の学習の進度に合わせて確認をするようにしてください。
円柱
まず1つ目は円柱です。
円柱の特徴は下記のようなものがあります。
特徴
- 上下の底面が同じ大きさの円
- 側面は曲がった面(展開すると長方形)
- 円の半径と高さで体積や表面積が決まる
公式
- 体積:$\pi r^2 h$
- 表面積:$2\pi rh+2\pi r^2$
日常例:缶ジュース、ペットボトルの胴体部分
円錐
次に2つ目は円錐です。
円錐の特徴は下記のようなものがあります。
特徴
- 底面が円、上部に頂点
- 側面はなめらかな曲面
- 「母線」という斜めの線で頂点と円の端が結ばれている
公式
- 体積:$\frac{1}{3}\pi r^2 h$
- 表面積:$\pi rl++\pi r^2$($l$は母線の長さ)
日常例:アイスクリームのコーン、三角コーン
三角柱
次に3つ目は三角柱です。
三角柱の特徴は下記のようなものがあります。
特徴
- 底面と上面が三角形で、向かい合って平行
- 側面は長方形が3枚
- 高さは底面から上面までの垂直距離
公式
- 体積:底面積×高さ
- 表面積:三角形2枚 + 長方形3枚の合計面積
日常例:木材の三角の角材、プリズムの模型
四角柱
続いて4つ目は四角柱です。
四角柱の特徴は下記のようなものがあります。
特徴:
- 底面と上面が四角形(正方形・長方形)
- 側面は長方形が4枚
- 高さは上下の四角形の距離
公式
- 体積:底面積 × 高さ
- 表面積:四角形2枚 + 長方形4枚の合計面積
日常例:ティッシュ箱、ビルの形状
三角錐
続いて5つ目は三角錐です。
三角錐の特徴は下記のようなものがあります。
特徴
- 底面が三角形
- 頂点から底面の各辺に向かって三角形の側面が広がる
- 側面は三角形3枚
公式
- 体積:$\frac{1}{3}×底面積×高さ$
日常例:テント、屋根の模型
四角錐
最後は四角錐です。
四角錐の特徴は下記のようなものがあります。
特徴
- 底面が四角形
- 頂点から底面の各辺に向かって側面が広がる
- 側面は三角形4枚
公式
- 体積:$\frac{1}{3}×底面積×高さ$
日常例:ピラミッド、折り紙の山型構造
以上で見てきた図形を図示すると下記のとおりです。
| 形 | 名称 |
 |
円柱 |
 |
円錐 |
 |
三角柱 |
 |
三角錐 |
 |
四角柱 |
 |
四角錐 |
それぞれの特徴と図形をしっかりと結びつけて、どういった特徴を持っている図形がどの図形なのかをしっかりと区別できるようにしておきましょう。
併せて、空間図形を構成する要素についても図示しておきます。

これらの名称についてもしっかりと押さえておくようにしましょう。
図形の特徴を理解するコツは「展開図」と「対応する辺・面・点」
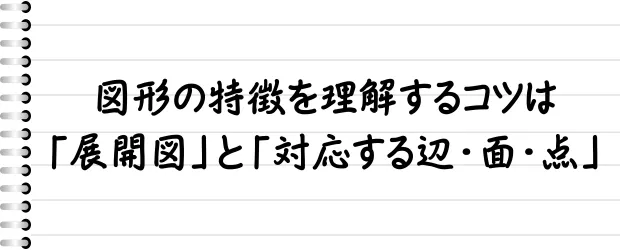
上記で空間図形の種類を紹介してきました。
これぐらいに数が多いと正直特徴を覚えるのすら大変に感じることもあると思います。
そこで、空間図形を理解するには、展開図を使って立体を広げてみると非常に効果的です。
展開図を描くことで、それぞれの面の関係性や形のつながりが見えやすくなります。
また、円柱・三角柱など「柱体」は上下に対応する面があり、側面はすべて長方形になります。
それに対して錐体は頂点から底面に向けた構造になっており、側面はすべて三角形です。
この「柱体と錐体」の視点を持つと、複雑な図形も整理しやすくなります。
正多角形を底面に持つ図形と名称のルール
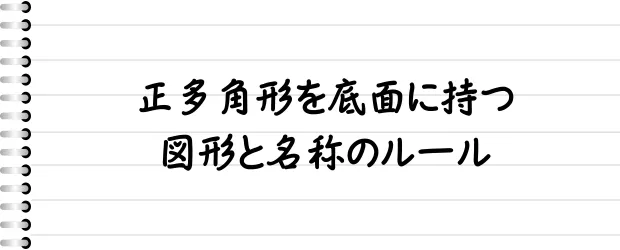
ここで、紹介した6つの図形をさらに細かく分類していきます。
空間図形の名前には、底面の形が関係しているものもあります。
特に、底面が正三角形や正方形などの正多角形である場合には、名前にも「正」が付きます。
その例を下記のように示します。
| 底面の形 | 柱体 | 錐体 |
|---|---|---|
| 正三角形 | 正三角柱 | 正三角錐 |
| 正方形 | 正四角柱 | 正四角錐 |
このように、底面が正多角形=名前に「正」が付くというルールを知っておくと、図形の種類をスムーズに判別できます。
多面体ってどんな図形?定義と空間図形との関係
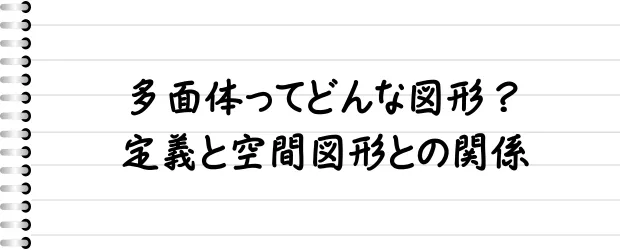
ここまでの内容は空間図形の主な分類になります。
覚えることが多いように感じるかもしれませんが、ここでまた別の図形を紹介しておきます。
中学数学では「空間図形」の中でも特に重要なグループに「多面体」があります。
暗記が大変になりますが、もう少し頑張っていきましょう。
●多面体の定義(中学数学の範囲)
まず、多面体の定義から触れていきます。
中学生の数学において、多面体とは
すべての面が平面でできた立体の図形
というのが基本的な定義です。
つまり、曲がった面(円柱や円錐の側面など)は含まれません。
例えば次のような図形は「多面体」に該当します。
- 正四面体(すべての面が正三角形)
- 立方体(正六面体)
- 三角柱や四角柱
- 三角錐や四角錐
一方で、円柱・円錐・球などの「曲面」を持つ立体は多面体ではない点に注意してください。
多面体の構成要素:面・辺・頂点の意味とは?
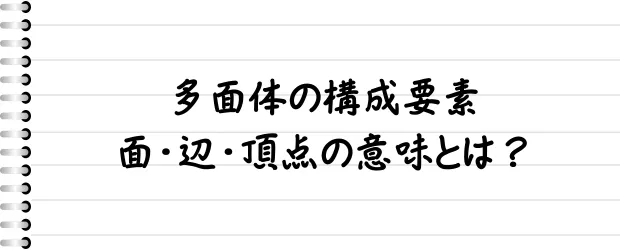
多面体を理解するうえで、3つの重要な要素があります。
それが、「面」「辺」「頂点」の3つです。
それぞれどういうものかを解説していきます。
●面
まず、「面」からです。
面とは、多面体を形作っている平らな板の部分のことです。
たとえば、立方体なら正方形が6枚あります。
面の形は三角形や四角形、五角形などさまざまです。
●辺
次に「辺」です。
辺とは、面と面がぶつかる「線の部分」です。
1つの辺は必ず2つの面にまたがって存在しています。
●頂点
最後に「頂点」です。
頂点とは、辺と辺が交わる角の点です。
多面体の形を決定づけるポイントになります。
これらは以下のような関係で結ばれています
- 辺は2つの面の交わり
- 頂点は2つ以上の辺の交わり
この関係はしっかりと押さえておくようにしましょう。
多面体の分類:正多面体とそれ以外の多面体
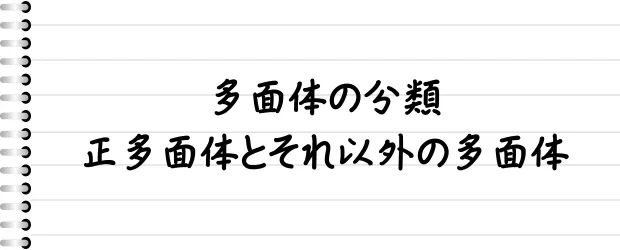
ここまでの説明で、覚えることが多いと感じているかもしれません。
ですが、安心してください。
中学数学では、多面体の中でも特に対称性が高い「正多面体」だけ見ていきます。
●正多面体とは?
正多面体とは、次の条件をすべて満たす多面体のことです。
- すべての面が同じ形の正多角形
- 各頂点に集まる面の数も等しい
この条件を満たす立体は、実は5種類しか存在しません。
5種類の正多面体については、下記で見ていきます。
正多面体の種類と特徴
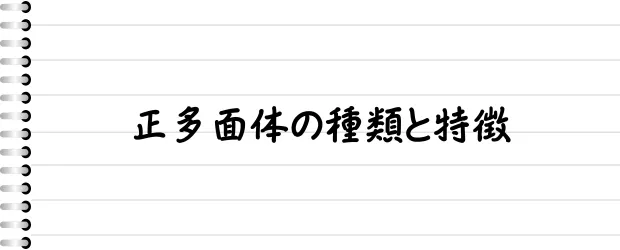
では、中学の数学で学ぶ5つの正多面体について見ていきます。
以下の表に、正多面体の種類とその構成要素をまとめました。
個別に覚えるのが苦手な学生さんはこの表を覚えられるように頑張ってみましょう。
| 名称 | 面の形 | 面の数 | 辺の数 | 頂点の数 |
|---|---|---|---|---|
| 正四面体 | 正三角形 | 4 | 6 | 4 |
| 正六面体(立方体) | 正方形 | 6 | 12 | 8 |
| 正八面体 | 正三角形 | 8 | 12 | 6 |
| 正十二面体 | 正五角形 | 12 | 30 | 20 |
| 正二十面体 | 正三角形 | 20 | 30 | 12 |
すべての正多面体に共通するのは、「面の形がすべて同じ正多角形であること」です。
正多面体の構成数を求める公式(辺・面・頂点)
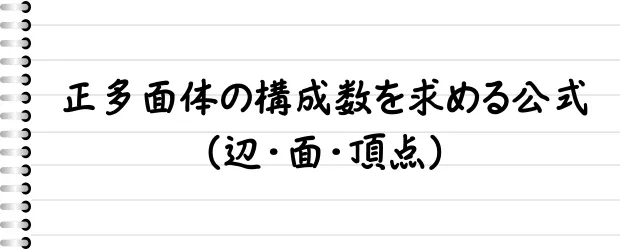
上記の表の要素を覚えていくことは必要になりますが、これらの計算式で算出することができます。
それぞれ具体的に見ていきます。
●面の数 → 名前そのまま
まずは面の数ですが、面の数は正〇面体の名称のままです。
- 正四面体 → 面が4つ
- 正十二面体 → 面が12個
名前と一致しているので、まずはここから押さえましょう。
●辺の数の求め方
次に辺の数です。
辺の数は公式で算出することになります。
辺の数=$\frac{面の1つの辺の数×面の数}{2}$
このような公式があります。
この式の中で、2で割る理由は、1つの辺は2つの面にまたがってカウントされるからです。
例:正十二面体(正五角形が12面)
$\frac{5×12}{2}=\frac{60}{2}=30$本
●頂点の数の求め方(オイラーの定理)
最後は頂点の数です。
頂点の数についても下記の公式で求めることができます。
頂点の数=辺の数-面の数+2
これは「オイラーの多面体定理」と呼ばれる、空間図形の構造に関する有名な法則です。
例:正十二面体
- 面の数:12
- 辺の数:30
頂点数=30-12+2=20
中学数学では暗記までは求められませんが、公式の成り立ちと意味を理解しておくと、難関問題でも対応しやすくなります。
多面体を身近に感じる!図形のイメージと活用例
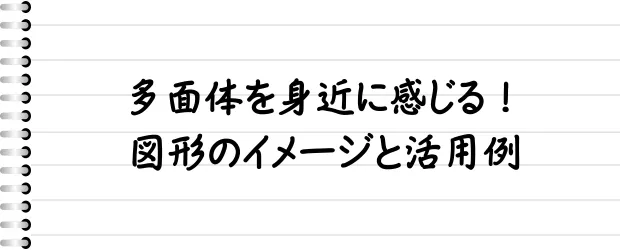
多面体は知識を増やしていくことがメインになって大変に思うかもしれません。
ですが、多面体は日常生活の中で実に多く見られる図形でもあります。
その例を下記で見ていきたいと思います。
●身近な多面体の例
身の回りにある多面体の例は下記のようなものがあります。
- サイコロ → 正六面体(立方体)
- ピラミッド → 四角錐(正四角錐)
- サッカーボール → 正五角形と六角形で構成(正多面体ではないが近い構造)
こうしてみると、「あれもそうかも!」と思えるようなものも思いつくかもしれません。
●理科・工学・建築でも使われる
また、高校生以上になって学習する分野でも多面体は見られます。
- 原子や分子の結晶構造
- 建築物のドーム設計(ジオデシック構造)
- 宇宙構造物や人工衛星の設計
このように、図形の構造理解は理系科目全般に関わる重要な力です。
多面体の学習でつまずきやすいポイントと対策
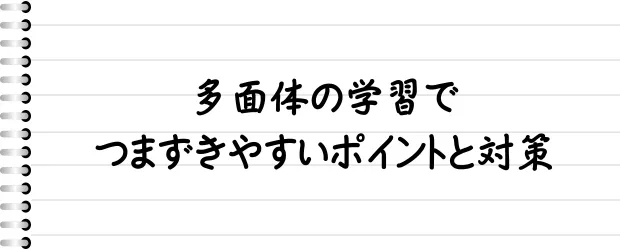
このようにしてみると、多面体の知識は今の学習においても、これからの学習においても非常に重要になってくることが分かります。
だからこそ、今の段階でしっかりと知識をつけておく必要があります。
そこで、ここでは中学生が多面体を学ぶとき、よくあるつまずきを確認しておきます。
よくあるつまずきは次の3点です。
| よくあるつまずき | 理由 | 解決法 |
|---|---|---|
| 辺の数がわからなくなる | 1本の辺を2回数えてしまう | 公式で割る:÷2の意味を理解 |
| 展開図で面の数が混乱する | 平面に広げると立体のイメージが難しい | 模型を作る、図を描いて確認 |
| 名前と図形が一致しない | 正〇面体の「正」が何を意味するかわからない | 面がすべて同じ正多角形と理解 |
このようなつまずきをなくすために、学習の際は、図や模型を使って視覚的に理解することがとても効果的です。
空間図形の公式まとめ|体積・表面積の一覧で確認しよう
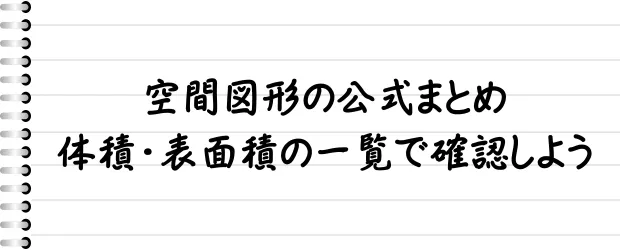
ここまで様々な公式を紹介してきました。
空間図形の学習で最もよく使われるのが、「体積」と「表面積」の公式です。
ここでは中学数学で習う代表的な立体の公式をまとめます。
ここの内容も学習の進度に合わせて読み進めるようにしてください。
●柱体(円柱・三角柱・四角柱など)の公式
| 図形 | 体積 | 表面積の求め方 |
|---|---|---|
| 円柱 | 底面積 × 高さ($\pi r^2 h$) | 側面積:$2\pi r h$ 全体:$2\pi r^2 + 2\pi r h$ |
| 三角柱 | 底面積 × 高さ($\frac{1}{2}×底辺×底面の高さ×高さ$) | 底面×2 + 側面積(展開図で確認) |
| 四角柱 | 底面積 × 高さ(縦×横×高さ) | 底面×2 + 側面(長方形4つ分) |
●錐体(円錐・三角錐・四角錐)の公式
| 図形 | 体積 | 表面積の求め方 |
|---|---|---|
| 円錐 | $\frac{1}{3}$ × 底面積 × 高さ($\frac{1}{3} \pi r^2 h$) | 底面積 + 側面積($\pi r l$:$l$は母線) |
| 三角錐 | $\frac{1}{3}$ × 底面積 × 高さ | 底面+側面3つの三角形 |
| 四角錐 | $\frac{1}{3}$ × 底面積 × 高さ | 底面+側面4つの三角形 |
空間図形の問題を解くための視点:展開図のコツとよく出る形
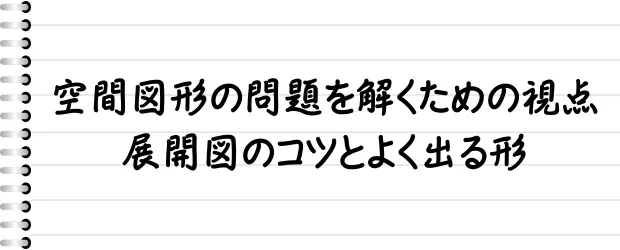
公式を改めて確認してきたところで、空間図形の問題を解くために活用する展開図のコツに触れておきます。
展開図は中学数学の定番テーマです。
ここで展開図の基本も含めてしっかりと見ていきます。
●展開図の基本
展開図を考えるときは下記のポイントを意識しながら考えていくようにしましょう。
- 面の数と位置を正確に把握する必要あり
- 特に「隣り合う面がどこか」「どこが底面か」を意識する
●よくある展開図の問題
実際に展開図が問題として出題されるときは、下記のような問題が出されます。
- 「この展開図はどの立体を作るか?」
- 「立体を展開したときの面の形と位置は?」
- 「展開図を折りたたんだとき、どの面がどこに来るか?」
問題で出題されたときに、手元と図形を作ることはできないので、問題の図形の面を塗りつぶすなどして、展開図を考えやすくするようにしましょう。
よく出る!空間図形の入試問題タイプと解き方のポイント
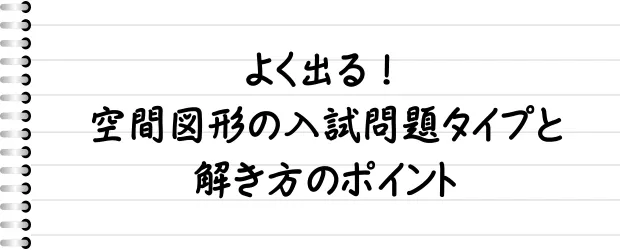
ここまで何度もお話してきたように、高校入試や定期テストで空間図形の問題は非常によく出題されます。
ここでは代表的なパターンと解き方を紹介します。
●立体の体積や表面積の応用問題
まずは立体の体積や表面積の問題を紹介していきます。
これらのテーマの問題は下記のような問題がよく出題されます。
- 「一部がくり抜かれている」
- 「2つの立体を組み合わせている」
- 「部分的に塗られている」など
解き方のコツ
このような問題を解き進めるコツは下記のように進めるといいでしょう。
- まず全体を求める
- くり抜き部分は引き算
- 複合立体は1つずつ分解して計算
●水を入れる・傾ける系の図形問題
次に紹介するのは、空間図形の物体に水を入れたり、水を入れた状態の中身について考える問題です。
具体的には「容器に水を入れてどの高さになるか?」「容器を傾けたときの水面の面積は?」という問題なります。
解き方のコツ
このような問題を解き進めるときは、実際にどうなるかを想像しながら下記のポイントに注意しながら解き進めます。
- 図を2Dにして考える(断面図にする)
- 水は常に水平になることを意識
- 三角形や台形の面積と高さから計算
まとめ
このページでは、空間図形の名称と、その特徴について解説していきました。
中学数学で学習する空間図形は、このようにしてみると思っていた以上に多い印象があるかもしれません。
ですが、どれも特徴がしっかりとある図形であり、そして考え方を変えればこれだけ特徴のある空間図形はないので、覚えやすいとも言えます。
数学は暗記自体は少ないものの、こういった内容はどうしても暗記しなければいけない内容が多く出てくるものでもあるので、時間がかかっても丁寧に知識を定着させていくことをおすすめします。
焦らずにコツコツと自身の知識を積み重ねていき、得点が取れる分野にしていけるように頑張っていきましょう。
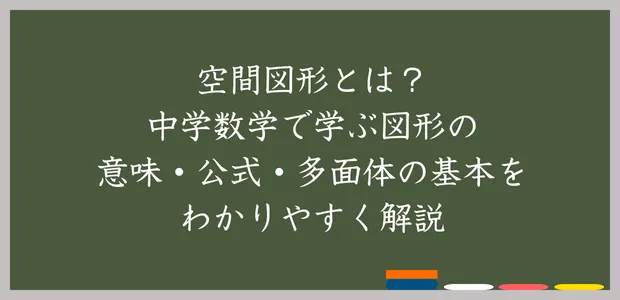








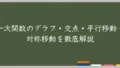
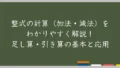
コメント