平面図形の学習を終えると次に空間図形の学習が始まりますが、空間図形の問題については、算数の時から苦手と感じる学生さんも少なくなかったのではないでしょうか?
数学の空間図形は、算数の時の空間図形よりも知識も多くなり、より苦手に感じる学生さんも増えるものと思われます。
このページでは、空間図形で苦手意識を持たないように、空間図形の基本である平面や直線の位置関係と中学数学で初めて学ぶ「ねじれの位置」について説明していきます。
空間図形が苦手に感じるのはなぜ?
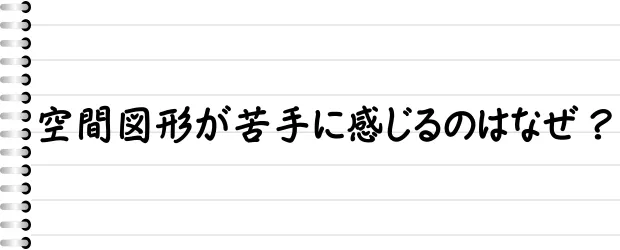
算数から数学へと内容が高度になってから、少しずつ数学の難しさを実感する学生さんが増えてきていると思います。
文字式でもかなり抽象度の高い内容であったにもかかわらず、図形の単元になるとよりそれを強く感じ、苦手になる学生さんもいるようです。
その中でも「空間図形」は、多くの学生さんが苦手に感じる分野のひとつです。
特に、「ねじれの位置」については、「イメージができないし、正確に説明もできない」という人も多いのではないでしょうか?
空間図形では、平面や直線、点の位置関係を立体の中で考える必要があります。
平面図形と違って、紙に描かれた2次元の世界ではなく、縦・横・高さのある3次元空間で考えるため、どうしてもイメージしにくくなるのです。
ですが、ポイントを押さえて順序立てて学べば、空間図形の理解は確実に深まり、「ねじれの位置」も簡単に見分けられるようになります。
平面図形から空間図形へ
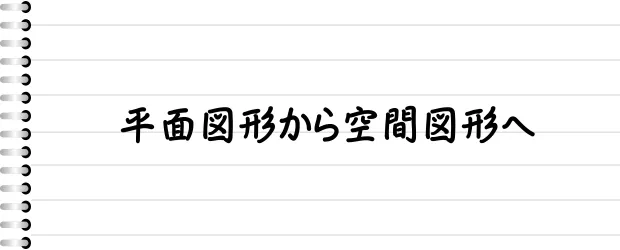
空間図形の学習を進めていく前に、まずは、「空間図形」とはどのようなものか、基本から確認しておきましょう。
空間図形とは?
「空間図形」とは、縦・横・高さの3つの方向を持った立体的な図形のことです。
身の回りのものの多くは空間図形です。
例えば、
- 箱(直方体)
- 筒(円柱)
- サッカーボール(球)
- ピラミッド(四角錐)
などはすべて空間図形です。
なぜ空間図形はわかりにくいのか?
平面図形は紙の上に描けますが、空間図形は「頭の中」で立体的にイメージする力(空間認識力)が必要です。
この力はすぐには身につきませんが、図や模型を使いながら練習していくことで、確実に伸びていきます。
点と平面の関係を理解しよう
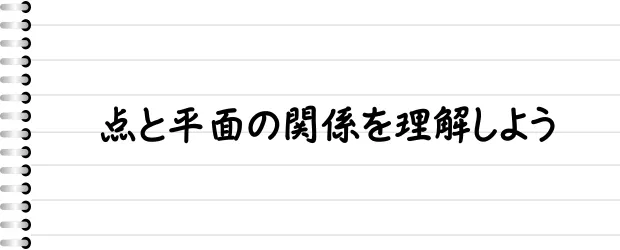
空間図形というものがどういうものかをお話したところで、早速空間図形の学習を進めていきます。
空間図形を理解するうえで、まず大切なのが「点・直線・平面」の関係性です。
平面とは?
ここで、平面の定義を明確にしておきます。
平面とは、「端のない広がった面」のことを指します。
具体的には、「3つの点を通る面」で、この3点が一直線上にないことが条件です。
たとえば、教室の机の天板やホワイトボードなどがイメージしやすいでしょう。
今ここでイメージができなくても後述するので焦らなくてももんだいありません。
点と平面の関係は2つ
では、点と平面の関係性を見ていきます。
点と平面の関係性は下記の2つの関係性があります。
- 点が平面上にある(平面に含まれる)
→ ペンが机の上に置かれている状態。 - 点が平面外にある(平面から浮いている)
→ ペンが机の上に浮かんでいるような状態。
この2つの位置関係はイメージしやすいものなので明確に理解しておきましょう。
点の数によって平面はどう決まる?
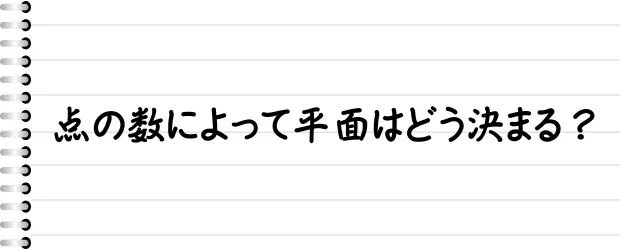
点と平面の関係性のイメージがついたところで、もう少し点と平面の関係性を深く見ていきます。
平面は、通る点の数とその配置によって、その存在の仕方が変わります。
これは空間図形において非常に重要な性質なので、しっかり確認しておきましょう。
1点がある場合
まず空間上に1点のみ存在する場合です。
空間上に1点だけがあるとき、その点を通る平面は無数に存在します。
ちょうど、空中に1点ピンで刺したような状態だと思ってください。
その点を通るような「紙(平面)」は、向きを変えていくらでも存在します。
イメージは下記の図のようになります。

かなりごちゃごちゃして分かりにくいかもしれませんが、青い点が空間に1個だけの時は、その1点だけ通れば、無数に平面が存在できることがイメージできれば問題ありません。
2点がある場合
次に空間上に2点ある場合を見ていきます。
2つの点があれば、その点を結ぶ直線ができます。
そして、この直線を含む平面もまた、無数に考えられるのです。
例えば、針金のような棒を手で持って、回転させながら紙を通すイメージです。
このときも、点が1つのときよりは範囲が制限されますが、やはり平面は1つには決まりません。
イメージ図は下記のようなものになります。

青い点2つを結ぶ赤い直線がありますが、この直線上にあれば、平面は無数に存在できることがイメージできるでしょうか?
ただし、1点の時に比べて、平面が存在できる範囲は限定されています。
3点がある場合(ただし一直線上でない)
最後に空間上に3点ある場合を見ていきます。
そして、これが最も重要です。
一直線上にない3点が与えられると、それらを通る平面はただ1つに決まります。
これは、「平面を一意に定める条件」と呼ばれ、空間図形の基礎中の基礎です。
例えば、三脚を床に置いたとき、3本の足が床に接していれば、その3点によって床(=平面)の位置が1つに決まるのと同じです。
イメージは下記のような図になります。

イメージすると上記の図のようになります。
このように平面を通る点が、空間上にいくつの点が存在するかによって、存在できる平面の数は変わってくることは重要な基礎知識になるので、しっかりと覚えておくようにしてください。
空間図形における「ねじれの位置」とは?
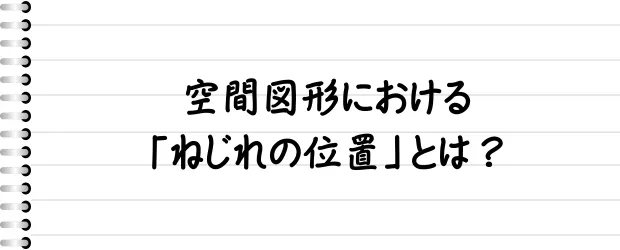
点と平面の関係の次に学んでいく内容は、中学の空間図形の知識でつまずく学生さんが多発する「ねじれの位置」についてです。
ねじれの位置の問題は中学数学でもよく出題され、理解が難しいにもかかわらず、正確な理解が必要とされる単元です。
では、ねじれの位置について、解説を進めていきます。
ねじれの位置とは?簡単に言うと…
結論からお話すると、「ねじれの位置」とは、2本の直線が、平行でもなく、交わってもいない関係のことです。
つまり、「ある直線と、別の平面の上にある直線」が、「同じ面にないので交わらず、方向もずれている」関係を言います。
この定義を聞いてもイメージが難しいかもしれませんが、この後、図を用いて説明するので安心して読み進めてください。
ねじれの位置になる3つの条件
もう少しねじれの位置について深堀していきます。
以下の3つの条件をすべて満たすと、「ねじれの位置」と判断されます。
- 交わらないこと
→ 図形の中で交点がないこと。 - 平行でないこと
→ 向きが一致せず、一定の距離を保ってもいないこと。 - 同一平面上にないこと
→ この条件が見落とされやすい。どんなに交わらず、平行でなくても、同じ面にあると「ねじれ」ではない。
この条件を踏まえて、実際の図形の中に見えるねじれの位置の例を見ていきます。

上記の図では、直線$l$と直方体があります。
ここで、直線$l$と各辺の位置関係を見ていくと
- $AB、BC、DA、AE、BF$は交わっている(上図の緑の辺)
- $CD、EF、GH$は交わらない(平行であるため、上図の紫の辺)
- $FG、HE、CG、DH$は交わらない(ねじれの位置であるため、上図の赤の辺)
ということになります。
この図を参考にしながら3つの条件をしっかりと押さえておきましょう。
よくある間違いに注意!
ここで、ねじれの位置について、よく見る間違いを紹介しておきます。
間違いというより勘違いに近いものですが、誤解しがちな内容なので、こういった間違いをしないように意識付けするようにしましょう。
- 「交わらなければねじれ」は間違いです。
- 「平行でないからねじれ」も不十分です。
- 最も大切なのは「異なる平面にあること」なのです。
ねじれの位置を見つけるコツ
ねじれの位置について、間違えずに見つける方法も一緒に紹介しておきます。
ポイントは下記の3つのステップで判断していくことです。
- 交わっている? → NO
- 平行? → NO
- 同じ平面にある? → NO
→ この3つすべてが「NO」なら、それは「ねじれの位置」!
この三段階で判断すれば、迷うことがぐっと減ります。
平面と直線の関係を正しく理解しよう
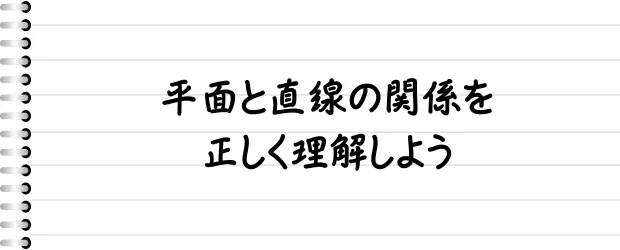
上記では点と平面の位置関係とねじれの位置について解説を行ってきました。
「ねじれの位置」が登場する場面では、上記の解説内容とあわせて、平面と直線の位置関係や平面どうしの関係についても正しく理解しておくことが重要です。
ここでは、それぞれの関係性を丁寧に確認していきましょう。
平面と直線の位置関係は3種類だけ
まずは平面と直線の位置関係から見ていきます。
平面と直線の関係性も点と平面の関係性と同じく3パターンあります。
この3つをしっかり覚えておけば、「ねじれ」かどうかも判断しやすくなります。
それぞれ見ていきます。
①直線が平面上にある
1つ目は直線がそのまま平面に含まれている関係です。
たとえば、机の上に置いた定規は、その面と一体になっているようなイメージです。
イメージ図は下記のようなものです。

このイメージでは直線$l$と平面$P$は無数の点で交わっています。
②直線が平面と交わる
2つ目は直線が平面を1点で貫く状態です。
空中から針を机に刺したようなイメージが近いです。
このとき、交わる点は必ず1つで、直線と平面は「交差している」と言えます。
イメージ図は下記のようなものです。

特に、平面と直線が垂直に交わるときは
$P \perp l$
と表現できます。
③直線と平面が平行で交わらない
3つ目は直線が平面に近づくことなく、ずっと同じ方向に離れて存在する場合です。
このときは「直線と平面が平行」と判断します。
イメージ図は下記のようなものです。

平行の場合は、
$P /\!/ l$
と表現できます。
この3つのパターンも点と平面の関係性と同じく、空間図形の基礎知識になるので、しっかりとイメージしながら覚えるようにしていきましょう。
平面どうしの位置関係も2パターンだけ
最後に確認するのは、「平面と平面」の関係です。
これは難しくはなく、次の2つに分類できます。
それぞれ見ていきます。
①平面と平面が交わる
1つ目は2つの平面が交差する場合、それは「1本の直線として交わる」と表現します。
例えば、教室の壁と床を考えてください。
どちらも面ですが、それが交わる部分は壁と床の隅のように「直線」になります。
イメージは下記の図のようになります。

特に、平面と平面が垂直に交わるときは
$P \perp Q$
と表現できます。
②平面と平面が平行
2つ目は紙を上下に重ねて浮かせたような状態を思い浮かべてください。
どちらの平面も交わらず、常に一定の距離を保っています。
このように、2つの平面がどこまでも交わらないときは「平行」と呼びます。
イメージは下記の図のようになります。

平行の場合は、
$P /\!/ Q$
と表現できます。
特に平面同士の位置関係は2つしかないので、暗記が苦手な学生さんは、平面同士の関係から覚えていくことをおすすめします。
「ねじれの位置」とはどう違うの?
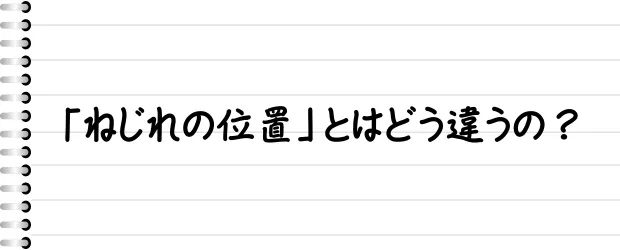
ここまで直線と平面の位置関係について見ていきました。
ここで、改めて「ねじれの位置」と比較して整理しておきましょう。
| 関係 | 交わる? | 平行? | 同一平面? | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 直線と直線A | はい | ― | はい | 交わる |
| 直線と直線B | いいえ | はい | はい | 平行 |
| 直線と直線C | いいえ | いいえ | いいえ | ねじれの位置 |
| 直線と平面 | はい | ― | ― | 交点が1つ |
| 平面と平面 | いいえ | はい | ― | 平行 |
このように、「ねじれの位置」は唯一、交わらず、平行でもなく、同じ平面にもないという、特殊な関係です。
ここまで解説した内容を1つ1つ覚えるのが難しいと感じる場合は、この表だけ覚えるということに注力してもいいかもしれません。
見分け方のコツ:図形を分解して考える
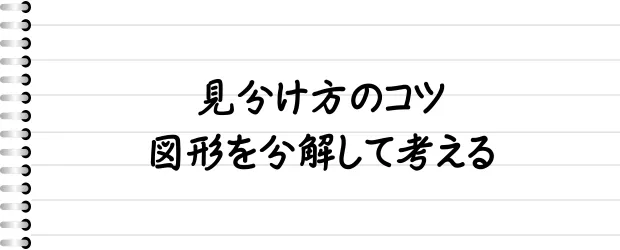
ここまでは点と直線と平面の位置関係について解説してきました。
そして、このような知識は「ねじれの位置」を中心に、直方体や三角柱などの立体でよく出題されます。
しかし、全体を見ようとすると混乱してしまう人が多いので、特にねじれの位置を考えるうえでのコツを紹介します。
ステップ①:対象となる2直線を見つける
まず、どの2つの辺や直線の関係を調べるのかをはっきりさせましょう。
ステップ②:同じ平面上にあるかを確認
「ねじれ」かどうかは、「同一平面にあるかどうか」が最大の判断ポイントです。
まずは、2直線を含む四角形や三角形が作れるかを考えてみてください。
作れれば同じ平面にある可能性が高いです。
ステップ③:交点の有無・平行かどうかを確認
- 交点がある → ねじれではない
- 向きが完全に一致(平行)している → ねじれではない
ステップ④:3条件すべてをチェック
- 交わらない
- 平行でない
- 同じ平面上にない
この3条件がそろえば、それは確実に「ねじれの位置」です。
よくあるミスとその対策
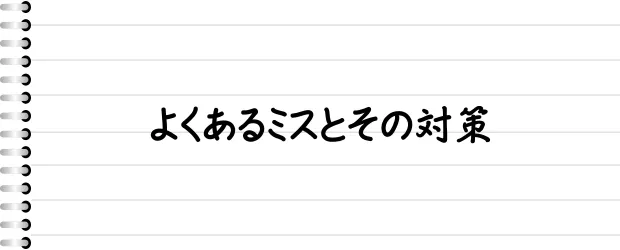
ここまでの解説した内容を押さえたうえで、ねじれの位置にに関する典型的な誤答を見ていきます。
よく見かける間違いには次のようなものがあります。
ミス①:平行じゃないから、ねじれ!
→ 平行じゃなくても、同じ平面にあれば「ねじれ」ではありません。
例:正方形の対角線同士は交わらないけど、同じ平面上にあるのでねじれではありません。
ミス②:交わらない=ねじれ!
→ これも間違いです。
単に交わらないだけでは「平行」や「離れているだけ」の可能性もあります。
対策
これらのミスをしないようにも、下記のような対策をしっかりと行いながら問題を進めていくようにしましょう。
- 必ず「同一平面上かどうか」をチェックする
- 「ねじれ=特殊な空間関係」であると意識する
入試によく出る「ねじれの位置」パターンとは?
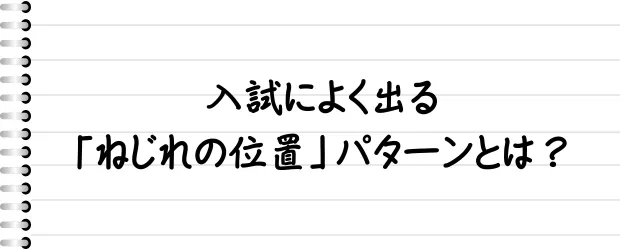
ここまでで、点と直線と平面の位置関係の基礎知識を解説してきました。
ここからはこれらの知識を使って、実際の問題を使って知識を固めてきたいと思います。
高校入試では、特にねじれの位置の典型問題が繰り返し出題されています。
特に、次の2つのパターンは非常によく登場するので、確実に押さえておきましょう。
パターン①:直方体や立方体の対角線の組み合わせ
よく見る問題の代表例は、直方体や立方体の対角線や辺の組み合わせの問題です。
例:直方体の中で、ねじれの位置にある辺の組を選ぶ問題
例えば、「辺ABと辺CGはねじれの位置か?」という問題です。
このような問題では、聞かれている2つの辺がそれぞれどこに位置していて、その2辺がねじれの位置の条件を満たしているかを見ていくようにします。
パターン②:三角柱や四角柱の辺の組み合わせ
また、ねじれの位置の問題は、三角柱などの図形でもよく出題されます。
柱体は、底面と上面、そして側面で構成されているため、さまざまな「ねじれの位置」が潜んでいます。
例:四角柱の底辺と上面の対角線を比較
このような問題でも考え方は同じです。
聞かれている辺はどこに位置していて、2つの辺の関係において、ねじれの位置の条件を満たしているかを考えていくようにします。
よくある引っかけ問題の対策
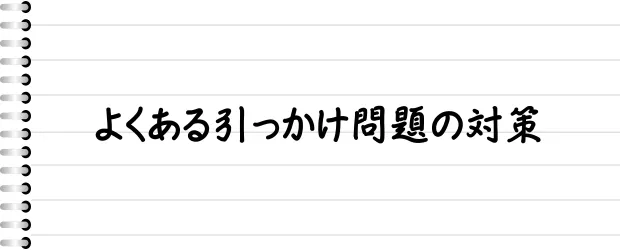
頻出問題は上記のような問題ですが、ねじれの位置に限らず、空間図形は引っかけ問題がよく見受けられます。
そのパターンと対策も併せて紹介していきます。
引っかけ①:「図を見ると交わっていそうに見える」
図はあくまでも平面の投影です。
斜めに描かれている線は交わって見えても、実際には空間で離れていることがあります。
こういった問題の対策は「平面を特定する→含まれるかを確認する」の手順を使って、見た目に惑わされないようにしていきます。
引っかけ②:「交わらない直線=ねじれ」だと思ってしまう
交わらず、平行でもなければねじれ…と早合点してしまうケースがあります。
しかし、同一平面にあればそれは「交わらない平行な直線」です。
このような問題の対策は3つの条件(交わらない・平行でない・同一平面にない)を毎回確認しながら解き進めるようにしましょう。
引っかけ③:「平行だと思ったら実は同一面にいない」
一見すると平行なように見える直線でも、位置がずれていて、実は異なる平面上にある=ねじれというパターンもあります。
このような問題の対策は「同じ平面の中で平行かどうか」を確認します。
もし、そうでなければ平行とは言えません。
効率的な覚え方・暗記法のコツ
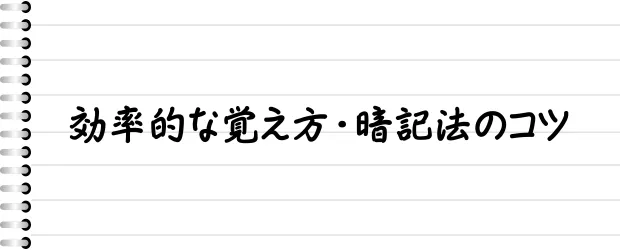
このページで解説している内容については、数学の計算の方法よりも暗記事項が多いという点で、苦手な学生さんも多くなっています。
特に空間認識に苦手意識を持つ学生さんは多く、特に「ねじれの位置」はイメージしにくいと感じることがあります。
そんなときは、以下のような視覚+ストーリー暗記法が効果的です。
覚え方①:「お互いすれ違ってばかりの2本の線」
ねじれの位置にある2本の線は、交わることなく、決して出会うことはありません。
同じ平面にもいない、方向も違う、永遠に交わらない…そんな「すれ違いの線」だと覚えましょう。
覚え方②:直方体の「前と後ろ、上と下」に注目
ねじれの位置については、2本の辺の位置関係を実物の空間図形で考えてみるのも効果的です。
例えば、ティッシュの箱を直方体としてとらえて、
- 前面の辺ABと、背面の辺CG → 交わらない、平行でない、同じ面にない
→ ねじれの位置
こうした組み合わせを目で覚えて体で理解するのが最も効果的です。
まとめ
このページでは、空間図形の基礎の平面や直線の位置関係について解説していきました。
まだ計算問題なども出てきていないため、暗記しなければいけない公式などもありませんが、位置関係の問題の中でも「ねじれの位置」については、入試でも頻繁に出題される問題であります。
改めて、このページで解説したねじれの位置の成立条件を記しておきます。
- 交わらない
- 平行でない
- 同一平面に含まれない
この3つすべてを満たした直線の関係だけが「ねじれの位置」です。
暗記が得意な学生さんには簡単だと思いますし、そうでない学生さんも覚えてしまえば簡単な分野になると思います。
ですが、簡単な分野だからこそ、しっかりと知識を定着させることで、ケアレスミスやもったいない失点を減らせることができるので、この分野の学習については漏れがないように勉強をしていきましょう。
特にねじれの位置については、中学生の空間図形で初めて出てきた知識なので、身の回りの空間図形を用いて、視覚的に理解を深めていく工夫はするようにしてみましょう。
こういった学習の工夫の積み重ねが、確実な知識の定着に繋がっていくので、頑張っていきましょう。
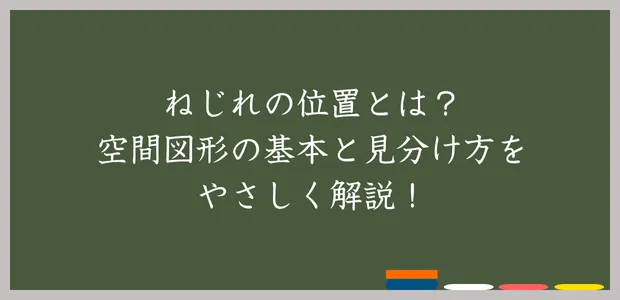







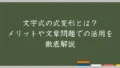


コメント