中学数学の図形の基本として、もう1つ、ここで学習する「図形の移動」というものがあります。
この学習分野は覚えることも少なく、ほとんど躓くことはない分野ではありますが、だからこそ基本をしっかりとマスターして、まずは平面図形の基本を身につけていってもらいたいところになります。
図形の移動は全部で3種類あるので、それを1つずつ解説していきます。
図形の移動はなぜ重要なのか?
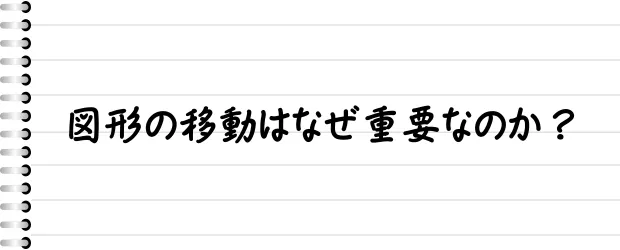
図形の移動の解説を行っていく前に、まず図形の移動を学習する理由をお話していきます。
中学数学の図形分野において、最も基本的でありながら今後の学習にも大きく関わる単元が「図形の移動」です。
「図形を動かすって、そんなに大事なことなの?」
そう思うかもしれません。
しかしこの分野では、図形の性質を守ったまま位置や向きを変える方法を学び、図形全体の本質的な理解につなげていくことが求められます。
しかも、「覚える公式が少なく、感覚的に理解できる」ため、苦手意識を持ちにくく、数学が得意になるきっかけとしても最適です。
そのため、特に数学の図形の分野が苦手な学生さんは、この図形の移動の分野から学習を進めていくことがおすすめですし、特に苦手意識がない学生さんにおいてはしっかりと点数を取れる分野にしていくようにしましょう。
図形の移動には「3種類」ある
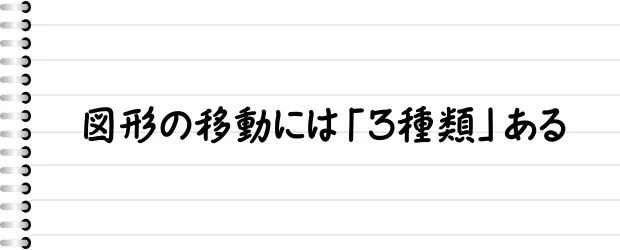
図形の移動を学ぶ理由をお話したところで、早速解説に入っていきます。
図形の移動の分野で、まず最初に押さえておきたいのは、図形の移動には明確に3種類あるという点です。
それぞれ下記の3つになります。
- 平行移動(translation)
図形全体をまっすぐスライドする操作。形や大きさ、向きは変わらない。 - 回転移動(rotation)
ある点を中心として、図形をくるっと回す操作。形や大きさは変わらず、向きが変わる。 - 対称移動(reflection)
ある直線を軸にして、図形を鏡に映したように折り返す操作。向きが反転する。
上記3種類については、詳しく見ていきますが、ここでは、ざっくりとそれぞれ特徴があることを認識しておきましょう。
また、英単語も記載しておきましたが、特に覚える必要はないので、それぞれの違いをイメージする程度に見ておいてください。
どの移動も共通して、図形の「形」「大きさ」は絶対に変化しないことがポイントです。
したがって、たとえ位置や向きが変わったとしても、元の図形と移動後の図形は形も大きさも同じになります。
この基本をおさえたうえで、1つずつ詳しく見ていきましょう。
平行移動とは何か? ─ まっすぐ同じ方向にスライド
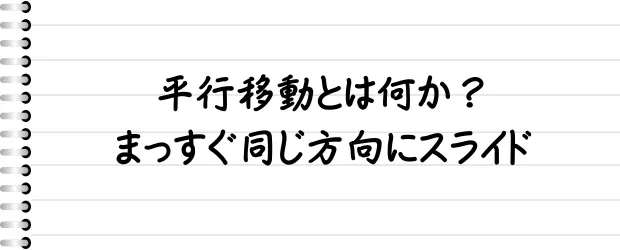
では、1つ目の移動から見ていきます。
図形の移動の中で最もわかりやすいのが平行移動です。
平行移動は、図形をある方向に一定の距離だけ、まっすぐ移動させる操作のことを指します。
たとえば、紙の上に描かれた三角形を、その形のまま右に5cmスライドさせる。
このような操作が平行移動です。
数学的には、すべての点が同じ方向・同じ長さだけ動くというのが定義になります。
平行移動のイメージは下記の図のとおりです。

この図中の赤い矢印を見てわかるように、三角形の各頂点が同じ長さ、同じ角度で移動していることが分かります。
平行移動の3つの特徴
平行移動のイメージができたところで、平行移動についての3つの特徴を見ていきます。
平行移動の特徴は下記のとおりです。
- 図形の形や大きさが変わらない
三角形でも四角形でも、スライドするだけなので変形しません。つまり、辺の長さや角度も変化なしです。 - 向きが変わらない
右を向いていた矢印が、移動後も右を向いたままになります。 - どの方向にも自由に移動できる
上下左右、あるいは斜めでも、平行移動は可能です。数学の問題では「$x$方向に+3、$y$方向に−2」などと表現されることもあります。
この特徴はしっかりと押さえておきましょう。
身の回りにある平行移動の例
では、平行移動は身の回りではどのように活かされているのでしょうか?
日常生活に見られる平行移動の例をいくつか紹介します。
- 机の上のノートを横にスライドする
力を加えても、ノートの形は一切変わりません。同じ方向に動いているだけなので、平行移動そのものです。 - キャスター付きの椅子で真横に移動する
椅子に座ったまま横滑りするとき、椅子も自分も同じ方向・同じスピードで動いています。これも平行移動です。 - スマホ画面上のアイコンの移動
アプリのアイコンを長押しして動かすとき、上下左右にそのままスライドさせることができます。これもまさに平行移動です。 - プリンターが紙を送り出す動作
用紙がまっすぐ前に送り出される動きも、平行移動に該当します。
このようにしてみると、日常生活の中で見られるものの移動の多くが、平行移動になると考えることができます。
図形における平行移動の例
続いて、実際の数学の問題ではどのような問題で平行移動が出題されるのでしょうか?
中学数学でよく出てくる平行移動の問題は、以下のような問題です。
例題
三角形ABCを右に4cm、上に3cmだけ平行移動させたとき、新しい三角形A′B′C′の座標を求めよ。
このような問題では、各頂点の座標にそれぞれ$x$方向に+4、$y$方向に+3を加えることで、新しい頂点の位置を求めます。
このような問題を通して、平行移動は各点の座標に対して一定の加減算をする操作であることがわかります。
回転移動とは何か? ─ 中心を基準にくるっと回す動き
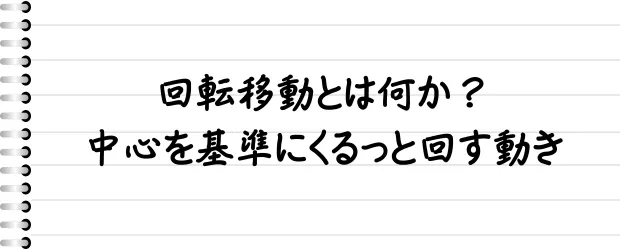
続いて2つ目の移動の回転移動を見ていきます。
回転移動は、図形をある1点(回転の中心)を軸として、一定の角度だけ回す操作のことを指します。
数学の中での定義としては、以下のようになります。
回転移動は、ある点を中心にして、図形全体を指定した角度だけ回す操作。
図形の形・大きさは変わらず、向きだけが変化する。
イメージとしては「扇風機の羽」や「時計の針」が近い例です。
これらは、中心を軸に一定方向に回る動きをしていますよね。
回転移動の基本的な構成要素
回転移動は平行移動と違い、回転移動をするための「要素」が必要になります。
その「要素」は下記の3つのものになるので、それぞれ押さえておきましょう。
- 回転の中心(固定された点)
図形が回るときの軸となる点。原点や特定の頂点が使われることが多い。 - 回転角度
図形がどのくらい回転するかを表す角度。例:90度、180度、270度など。 - 回転の方向
・時計回り(右回り)
・反時計回り(左回り)
これらが揃うことで、正確な回転移動が可能になります。
上記の内容を踏まえて、実際の回転移動の参考の図を見てみます。

この図のように、図中の赤い点を回転の中心とし、各頂点が90°ずつ右に回転していることが分かります。
回転移動の3つの特徴
回転移動のイメージができたところで、回転移動に見られる3つの特徴を見ていきます。
回転移動では下記の3つの特徴を有しています。
- 回転中心からの距離は変わらない
元の図形の各点と回転中心との距離は、移動後も変わりません。 - 形・大きさはそのまま
長さ・角度は一切変化せず、図形自体の構造は変わりません。 - 向きが変わる
図形は回転角度に応じて方向が変わります。向きの変化が最大の特徴です。
特に1つ目の特徴は大事な特徴なので、しっかりと押さえておきましょう。
日常で見かける回転移動の例
回転移動は、平行移動と同様に、生活の中でも非常によく見かけます。
以下に代表的な例をいくつか紹介します。
- 時計の針が進む動き
中心を軸にして、短針・長針が時計回りに進むのは、まさに回転移動の代表例です。 - 扇風機の羽根が回る
電源を入れると、一定の中心を軸にして羽根が均等に回転します。 - ドアノブの動作
手でドアノブを回すときも、軸を中心にした回転です。 - 自転車の車輪
車輪が一定の点を軸として滑らかに回転している状態です。 - 回転寿司の皿の動き
ベルトコンベアで動くお皿も、円を描くように一定の中心に沿って回転しています。
こうした身近な動作が「数学的に回転移動と捉えられる」ことを知ることで、学習に対する親しみやすさが増します。
図形での回転移動の例題と考え方
日常生活に見られる回転移動の例を見ていったところで、次は数学の問題でよく出る問題を見ていきます。
回転移動の問題は以下のような問題が頻出です。
例題
点A(2, 1)を原点を中心として90度反時計回りに回転したときの座標を求めよ。
このような問題では、以下の変換ルールを覚えておくと便利です(すべて原点中心の場合)。
| 回転方向 | 角度 | 座標の変換 |
|---|---|---|
| 反時計回り | 90度 | $(x, y) → (−y, x)$ |
| 反時計回り | 180度 | $(x, y) → (−x, −y)$ |
| 反時計回り | 270度 | $(x, y) → (y, −x)$ |
| 時計回り | 90度 | $(x, y) → (y, −x)$ |
この法則に当てはめるだけで解答でき、さらに計算も不要ということで、間違えずに座標を求めることができます。
実生活で図形の回転が使われている場面(応用編)
回転移動については、日常生活の中でも実用品に応用されている例が多かったことから、実際の社会活動の中でも活かせることがあります。
その例についてもここで簡単に紹介しておきます。
建築・設計分野
- 建物のパーツやデザイン要素を配置するとき、回転して配置のバランスをとる場面があります。
- CAD(設計ソフト)では、図形の回転機能が頻繁に使われます。
デザイン・アート
- ロゴやパターンデザインでは、特定の図形を回転させてバランスよく並べることが基本テクニックとなります。
プログラミング・ゲーム開発
- ゲーム内のキャラクターやオブジェクトの回転処理には、数学の回転移動の原理が使われています。
- 座標系と回転行列の計算も、回転移動の応用です。
こうした具体例を通じて、回転移動を学んだ先にはこういった応用があるという学習した先の目的が明確になります。
なので、ぜひ自分の身の回りにあるもので、回転移動の例を探してみてください。
補足:回転移動と回転対称性の違い
ここで、1点補足をしておきたいと思います。
数学の学習で、似た言葉に回転対称性がありますが、これは図形を回転したときに見た目が変わらない性質のことです。
- 正三角形 → 120度回転ごとに見た目が同じ
- 正方形 → 90度回転ごとに見た目が同じ
これは「回転移動によって図形が自分自身と一致する」ことを意味します。
回転移動を理解していないと、このような対称性の理解も不十分になります。
今ここで、回転対称性については理解しなくてもいいですが、こういったことを今後学習することがあるんだということは、頭の隅に置いておくといいかもしれません。
対称移動とは何か? ─ 鏡のように映して図形を移動
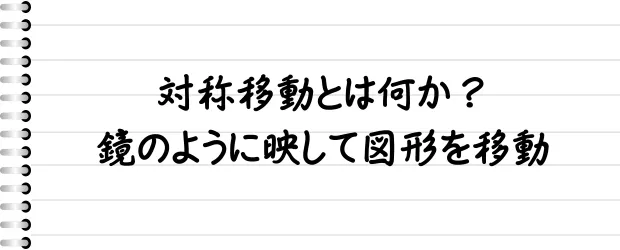
では、いよいよ3つ目の移動の対称移動を見ていきます。
対称移動は、図形をある直線(対称の軸)をはさんで、鏡のように映した位置に移す操作のことです。
たとえば、紙の上に図形を描き、その上に鏡を置いて映すと、鏡の中に反転した図形が見えますよね?
この反転して向きが逆になる移動が、まさに対称移動です。
対称移動の定義と特徴
対称移動については、少し難しく感じるかもしれませんが、もう少し頑張りましょう。
ここで数学的な定義を見ていきます。
数学的には、対称移動は以下のように定義されます。
対称移動はある直線(対称の軸)に対して、図形を折り返したときの位置に移動する操作。
移動後の各点は、元の点と対称の軸をはさんで同じ距離だけ反対側にある。
となっています。
対称移動の3つの特徴
対称移動についても、他の2つの移動と同じように特徴があるので見ていきましょう。
対称移動も下記の3つの特徴があります。
- 形・大きさは変わらない
辺の長さや角度はそのままなので、合同な図形になります。 - 向きが反転する
これは平行移動・回転移動との大きな違いです。図形の「向き」が逆になります。 - 対称の軸との距離が等しい
元の点と移動後の点は、常に対称の軸から等距離にあります。
特に3つ目については、対称移動の大きな特徴であり、対称移動になる場合は、必ず「対称の軸」というものがありますが、この軸から各点の距離は等しくなるので、対称移動の作図をする際の目安になります。
これらの特徴を踏まえたうえで、実際に対称移動の参考の図を見ていきましょう。

この図では、赤の線が対称移動の軸になっています。
この軸を境にして各頂点が鏡写しのように移動していることが分かります。
実生活で見られる対称移動の例
対称移動についてのイメージが出来上がったところで、実生活に見られる対称移動の例も併せてみていきましょう。
対称移動も、意識してみると身の回りに多く存在します。
以下はその例です。
- 鏡に映った自分の姿
鏡の面が対称の軸。鏡の中の姿は左右反転していて、まさに対称移動の結果です。 - 左右対称のデザイン(ロゴ・模様など)
車のエンブレムや企業ロゴには、対称性を活かしたデザインが数多くあります。 - 蝶の羽や人間の顔
自然界の多くの生き物は、体の左右が対称になっています。これも対称性の一例です。 - 折り紙の折り線
中心で折ると、左右がピッタリ重なります。これはまさに「対称軸」をはさんだ対称移動の典型例です。
特に鏡の例については、毎日見るものであるので、とても身近に感じるものであります。
なので、「対称移動=鏡」ぐらいで知識を紐づけてもいいかもしれません。
数学の問題における対称移動の扱い方
対称移動の定義や特徴、実生活の例も見てきたところで、他の移動でも見た実際の問題例も見ていきます。
対称移動は、中学の図形問題において頻繁に出題されます。
以下のようなパターンが多いです。
例題
点P(3, 2)を$x$軸に関して対称移動したときの座標を求めよ。
この場合、対称軸が$x$軸なので、$y$座標の符号が反転します。
よって答えは (3, −2) です。
ポイント:軸による変化
対称移動の問題を考えていく際にポイントになるのが、「軸による変化」です。
どういうことかというと、「何を対象の軸にして」移動させるということです。
代表的な対称の軸を下記の表にまとめてみました。
| 対称の軸 | 移動後の座標の変化例 |
|---|---|
| $x$軸 | $(x, y) → (x, −y)$ |
| $y$軸 | $(x, y) → (−x, y)$ |
| $y=x$ | $(x, y) → (y, x)$ |
| $y=−x$ | $(x, y) → (−y, −x)$ |
特に下の2つは比例のグラフであります。
なので、先々の話になりますが、対称移動の問題については、特に比例の問題との融合問題も出題されることがあるので、対称移動については早めにイメージを固めておくことをおすすめします。
【比較表】図形の移動3種類の違いと共通点
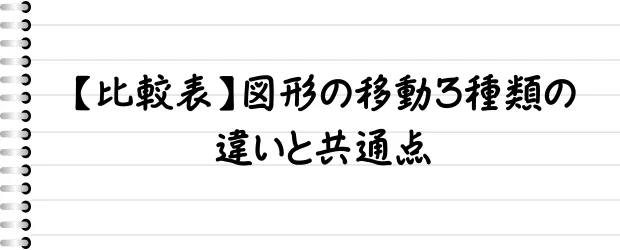
ここまでで3つの図形の移動を見てきましたが、実際の移動や特徴など多くのポイントがありました。
それらの特徴を一覧表で比較して、理解を深めましょう。
| 項目 | 平行移動 | 回転移動 | 対称移動 |
|---|---|---|---|
| 形・大きさ | 変わらない | 変わらない | 変わらない |
| 向き | 変わらない | 回転方向に応じて変わる | 反転(左右逆) |
| 使うもの | 移動する距離・方向 | 中心・角度・回転方向 | 対称軸(直線) |
| 合同になるか | 常に合同 | 常に合同 | 常に合同 |
| 身近な例 | ノートをずらす | 時計の針 | 鏡に映った姿 |
このようにしてみると、3種類とも「図形の形・大きさが変わらない」という共通点がありつつ、それぞれに向きや移動方法が異なるという違いがあります。
この表はこの後の学習を進める前に、しっかりと覚えるようにしてください。
図形の移動を日常・学習に活かすコツ
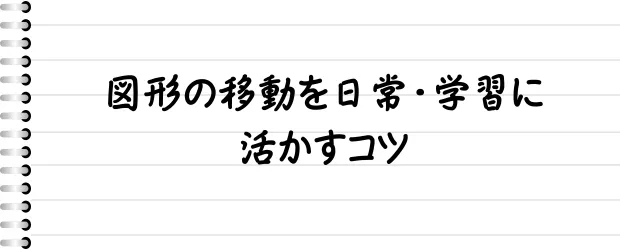
図形の移動の説明をしていく中で、それぞれの移動が日常生活の中にあふれていることが分かったと思います。
その例も一部を紹介しただけで、よく探してみると本当に多くの移動の例があります。
なので、図形の移動については、机の上での勉強に限らず、身の回りの物を「見る」というだけでも学習になります。
それだけでは少々物足りない、理解が難しいという学生さんは、実際に作図してみたり、今の時代はアプリなどでもイメージできるので、参考に使ってみるのもおすすめです。
視覚的な理解を重視しよう
では、身の回りの物を見るだけではイメージが難しいという場合、具体的に図形の移動を学ぶときはどのような学習がいいのでしょうか?
結論からお話すると、図形の移動を学ぶときは、まず重要なのは目で見て理解することです。
たとえば以下のような方法を活用しましょう。
- ノートに図形を描いて、透明シートを使って実際に動かしてみる
- 無料アプリ「GeoGebra」などを使って、図形を動かして学習
視覚を通した学習は、記憶にも残りやすく、アプリを使えば実際に移動しているところも見れるので、試験本番でも図形を頭の中で動かす力になります。
ぜひ参考にしてみてください。
まとめ
このページでは、3種類の図形の移動についてそれぞれの特徴や日常生活の中で使われている例を見ていきました。
図形の移動は、一見シンプルに見えるかもしれませんが、視点を変えたり動かしたりする柔軟な思考力を養う非常に重要なテーマです。
改めてこのページでは、以下のことを学びました。
- 図形の移動には 平行移動・回転移動・対称移動 の3種類がある
- すべての移動において、形・大きさは変わらず、同じ形になる
- 各移動の特徴や、日常での具体例
- 作図・座標・応用の考え方
- 各移動の違いと共通点の整理
図形を自由に動かす力は、単なる試験対策にとどまりません。
将来の設計・建築・デザイン・プログラミングなど、さまざまな分野への入り口となる知識でもありました。
ぜひ、この知識を土台に、図形の分野の問題をもっと深く、そして楽しみながら勉強を進めていきましょう。
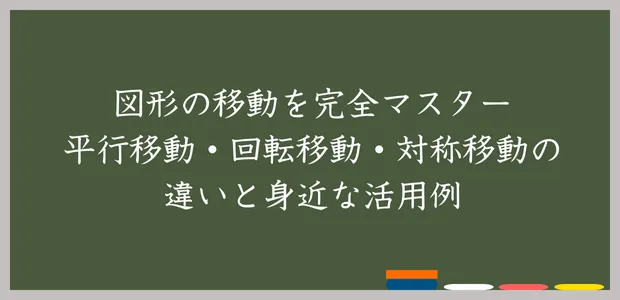





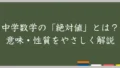
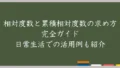

コメント