「比例」とは、2つの数が一定の割合で変わる関係のことです。
中学1年で最初に学ぶ関数の基本ですが、「式やグラフが難しそう」と感じる人も多いでしょう。
実は比例は、買い物の値段や距離と時間など、身の回りの出来事の中にもある考え方です。
このページでは、「比例とは何か」から始めて、式$y=ax$の意味、比例定数と傾きの違い、グラフの読み取り方までをやさしく解説します。
グラフや式の動きをイメージしながら読み進めることで、数学の基礎がしっかり身につきます。
| 中学生のおすすめ学習塾3選 | |||
|---|---|---|---|
横浜予備校 |
WAM |
明光義塾 |
|
| 対象 | 中学生 | 中学生 高校生 |
中学生 高校生 |
| 授業料 (税込) |
29,700円~ (月額) |
7,600円~ (週1回) |
15,400円~ (週1回) |
| 入塾金 | 0円 | 16,500円~ | 11,000円 |
| 指導形式 | 学習塾 | 学習塾 (個別指導) |
学習塾 (個別指導) |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | |
比例とは?中1で学ぶ「比例関係」をわかりやすく解説
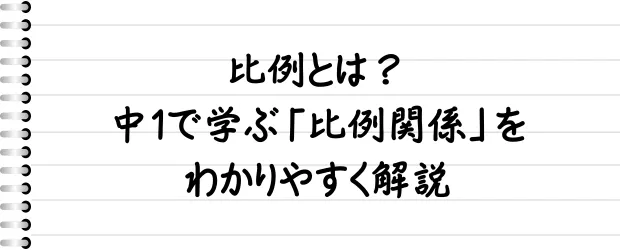
中学1年で最初に本格的に扱う関数のテーマが「比例」です。
数学では式やグラフが登場するため、最初はむずかしく感じるかもしれません。
しかし、比例は買い物や移動の距離など、日常の中で自然に使っている考え方です。
ここでは、まず比例関係の直感的な意味をつかみ、そこから式「$y=ax$」につながる考え方、さらに混同しやすい「反比例」との違いまで理解できるように丁寧に解説していきます。
比例をしっかり理解できると、中学数学だけでなく高校数学の関数の学習にもスムーズに進めるようになります。
「比例関係」とは?2つの数の変わり方に注目しよう
比例とは、一方の数が変わると、それに合わせてもう一方の数も「同じ割合」で変わる関係のことです。
数学的な言い方をすると「1つの数が増えると、もう1つの数も同じ割合で増える、または減る関係」といえます。
まずはこの「同じ割合で変わる」というイメージをつかむことが大切です。
身近な例を見てみましょう。
たとえば、りんご1個100円のお店があるとします。
- 1個 → 100円
- 2個 → 200円
- 3個 → 300円
個数が2倍になれば値段も2倍、3倍なら3倍。これはまさに比例の典型例です。
また、「一定の速さで進むときの時間と距離」も比例関係になります。
時速5kmで歩いている場合、1時間で5km、2時間で10km、3時間で15kmと増えていきます。
時間が2倍・3倍になると、距離も2倍・3倍になります。
このように、「変化の仕方」がそろっているとき、数学では
「$y$は$x$に比例する」
と表現します。
そして、この関係は式
$y=ax$
で表されます。
比例のグラフは原点(0,0)を通るまっすぐな線になるという特徴があり、後のグラフ学習につながる重要なポイントです。
比例の式を見てみよう|y=ax の形になる理由
ここでは、比例の式「$y=ax$」の意味をもう少し具体的に見ていきます。
この式が常にこの形になる理由を理解すると、比例の本質がより深くわかります。
まず、式の中にある文字の役割を確認しましょう。
- $x$:変える数(入力する数)
- $y$:$x$に合わせて決まる数(結果の数)
- $a$:$x$と$y$がどの割合で対応するかを示す数(のちに「比例定数」と呼ばれる)
身近な具体例で見てみましょう。
みかん1個100円のとき、個数を$x$、値段を$y$とすると
$y=100x$
となります。
この式の100が比例定数$a$に当たります。
では、なぜ比例は必ず$y=ax$の形になるのでしょうか?
たとえば、$x=1$のときの$y$の値を$a$とします。
すると、$x=2$のときは$a$の2倍で$2a$、$x=3$のときは$3a$です。
$x$が増えるにつれて「倍の関係」がそのまま$y$に伝わるため、どんな$x$の値に対しても
$y=a×x$
の形で表すことができます。
また、この一定の割合で増える関係性があるため、グラフがまっすぐな直線になる、という性質も自然に説明できます。
グラフの詳細は後述しますが、比例の式とグラフが密接に結びついていることをここで意識しておくと理解が深まります。
比例と反比例の違いを知っておこう
比例とよくセットで登場するのが「反比例」です。
名前が似ているため混同しやすいのですが、関係の性質は大きく異なります。
ここでは反比例についての詳しい解説はしませんが、下記にて両者の違いをしっかり理解しておきましょう。
反比例とは「$x$が大きくなると$y$が小さくなる関係」のことです。
式では
$y=\frac{a}{x}$
で表され、比例の「一直線」とは違い、グラフは双曲線になります。
比例と反比例を一覧で比べると次のようになります。
| 項目 | 比例 | 反比例 |
|---|---|---|
| 式の形 | $y=ax$ | $y=\frac{a}{x}$ |
| 関係の向き | $x$が増えると$y$も増える | $x$が増えると$y$が減る |
| グラフ | 原点を通る直線 | 双曲線 |
具体例で考えると理解しやすくなります。
比例の例は「買い物の個数と値段」「一定の速さでの時間と距離」などです。
一方、反比例の典型例は「作業人数と作業時間」です。
人数が増えるほど作業時間は短くなります。
たとえば、1人で3時間かかる作業も、3人で行えば1時間で終わる、というように、増え方と減り方が反対になります。
まとめると、
- 比例:同じ方向に変わる関係
- 反比例:逆の方向に変わる関係
と覚えておくと、問題の見分けが簡単になります。
比例グラフの特徴をつかもう|なぜ直線になるの?
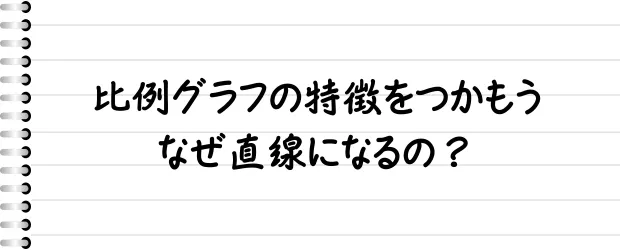
上記では、比例とは「一方が2倍になると、もう一方も2倍になる関係」であり、式では$y=ax$と表されることを学びました。
では、この比例の式をグラフにするとどんな形になるのでしょうか。
中学1年で最初に扱う本格的なグラフが「比例のグラフ」です。
比例を理解するうえで、グラフの形・直線になる理由・グラフから読み取れる情報の3つは欠かせません。
ここでは、比例グラフの基本的特徴、直線になる理由、さらに比例定数や傾きをグラフから読み取る方法まで、順を追って丁寧に解説していきます。
比例のグラフはどんな形?原点を通るまっすぐな線
比例のグラフは、見た目にもはっきりした特徴があります。
まず押さえておきたいのは、比例のグラフは必ず原点(0,0)を通る直線になるということです。
これは、比例の式$y=ax$に$x=0$を代入すると$y$も0になるため、「$x$も$y$も0になる点」である原点が必ず含まれるからです。
具体例で確認してみましょう。
たとえば$y=2x$のとき、
- $x=1$ → $y=2$
- $x=2$ → $y=4$
このように、点(1,2)、(2,4)…が得られるので、これらを結ぶと原点を通る右上がりの直線になります。
比例定数$a$の性質によって、直線の向きも決まります。
- $a$が正のとき:右上がりの直線
- $a$が負のとき:右下がりの直線
たとえば$y=−2x$の場合は、
- $x$が1 → $y=−2$、
- $x$が2 → $y=−4$
となり、点(1,−2)、(2,−4)…が一直線に並び、右下がりの直線になります。
比例のグラフに共通して言えるのは、$x$と$y$が常に同じ割合で増減するため、どの点も一直線上に並ぶということです。
座標平面に原点から伸びるまっすぐな線——これが比例グラフの基本的な形です。
頭の中では、定規を使ってスッと引いたような線をイメージするとよいでしょう。
どうして比例グラフは直線になるの?
では、なぜ比例のグラフは必ず直線になるのでしょうか。
この理由を理解しておくと、比例という関係の本質がより深くつかめます。
比例の式は$y=ax$の形です。
この式は、$x$が1増えると$y$は常に$a$だけ増えるという意味を持っています。
いわば「増え方がずっと一定」だと言えます。
たとえば$a=2$のときは、$x$が1増えるごとに$y$が2増えるという関係がずっと続きます。
ここでグラフの見方を少しだけ取り入れてみます。
任意の2つの点をとって、傾きを比べてみると、(1,$a$) と (2,$2a$) の間では
- $x$の増加量:1
- $y$の増加量:$a$
(2,$2a$) と (3,$3a$) の間でも、増え方は同じです。
つまり、どの部分を切り取っても「増え方の割合」が変わらないため、グラフを結ぶと常にまっすぐな線になります。
まとめると、
「比例グラフが直線になるのは、変化の割合(比例定数)が常に一定だから」
という一言に集約できます。
グラフから比例定数や傾きを読み取ってみよう
比例のグラフを見たとき、そこから式の情報を読み取ることができるようになると、数学の理解が大きく深まります。
ここでは、グラフから比例定数(=傾き)を読み取る方法を解説します。
比例定数$a$は、$x$が1増えたとき、$y$がどれだけ増えるか を表す数です。
これはグラフ上では「傾き」に相当します。
たとえば、グラフに点(1,2) と (2,4) が描かれている場合、
- $x$の増加量=1
- $y$の増加量=2
となるので、比例定数$a=2$とわかります。
式は$y=2x$です。
また、グラフの傾きが大きければ大きいほど線が「急」になり、$a$が小さいほどなだらかな線になります。
さらに、線が右上がりなら$a$は正、右下がりなら$a$は負です。
これは比例のグラフが持つ非常に重要な特徴です。
グラフを見た瞬間に「この点が(3,6)なら$a=6÷3=2$だな」と読めるようになると、比例の式を素早く判断できるようになります。
これはテストや文章問題で大きな武器になる力です。
| 中学生のおすすめオンライン塾・家庭教師3選 | |||
|---|---|---|---|
ウィズスタディ |
家庭教師の銀河 |
WAM |
|
| 対象 | 中学生 高校生 |
中学生 | 中学生 高校生 |
| 授業料 (税込) |
9,800円~ (1科目) |
2,750円~ (1コマ) |
7,600円~ (週1回) |
| 入会金 | 27,500円~ | 22,000円 | 16,500円~ |
| 指導形式 | 学習塾 (オンライン) |
家庭教師 | 学習塾 (オンライン) |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | |
比例定数とは?グラフの傾きとの違いをやさしく説明
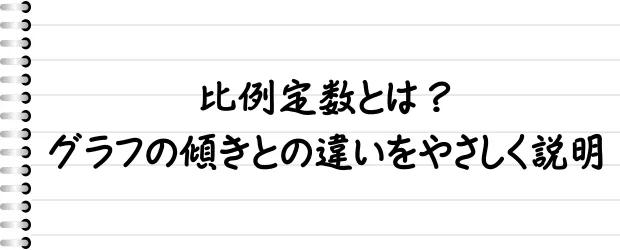
ここまでは比例の基本的な式や、変化の様子が一定になるという特徴を学びました。
ここでは、その中でも特に重要な役割をもつ「比例定数」と、グラフを読むときに欠かせない「傾き」について、具体例を使いながら丁寧に確認していきます。
名前が似ているため混乱しやすい2つですが、それぞれの役割や見える世界が異なります。
ここでしっかり整理し、比例の理解をワンランク深めていきましょう。
比例定数とは?変化のきまりを表す大切な数
「比例定数」とは、比例の式$y=ax$の中に出てくる「$a$」のことです。
この$a$は、$x$が1のときの$y$の値を表していて、$x$と$y$の関係をつなぐ「変化のきまり」を示しています。
つまり、どれだけ$x$が増えたら、どれだけ$y$が増えるかという「ルール」を決める役割をもつ、とても重要な数です。
比例では、$x$が変わると$y$も同じ割合で増減します。
たとえば$x$が2倍になると$y$も2倍、$x$が3倍になると$y$も3倍というように、変化のしかたが常に一定です。
この「一定の変化の割合」が比例定数$a$にあたります。
身近な例で比例定数をつかむ
比例定数を理解するときは、生活の中の例を使うとイメージしやすくなります。
例1
りんご1個100円。
りんご$x$個の値段$y$は
$y=100x$
となります。
1個あたり100円なので、比例定数$a=100$。
2個なら200円、3個なら300円。
増え方が常に一定です。
例2
時速60kmで走る車。
走った時間を$x$(時間)、進んだ道のりを$y$(km)とすると
$y=60x$
1時間に60km進むので、比例定数$a=60$。
2時間なら120km、3時間なら180kmと、やはり増え方は一定です。
このように比例定数がわかると、「1増えたらどれだけ増えるのか」をすぐにつかむことができ、式の意味もぐっと理解しやすくなります。
また、比例定数の大きさによって、あとで学ぶグラフの傾きが変わります。
- $a$が大きい → 傾きが急な線になる
- $a$が小さい → 傾きがゆるやかな線になる
このつながりが、次の「傾き」の理解へとつながります。
傾きとは?グラフの「上がり方・下がり方」を表すもの
「傾き」とは、グラフで直線を見るときの「上がり方・下がり方」を表す数のことです。
もっと具体的に言うと、$x$が1増えたときに、$y$がどれだけ増えるか(または減るか)を示します。
たとえば、点 (1,2) と (2,4) がある場合、
- $x$は1→2で 1増加
- $y$は2→4で 2増加
よって傾きは2となります。
グラフの見た目とのつながり
傾きは、直線の見た目にも大きく関係します。
- 傾きが大きい(例:3、5、10など)
→ 線が急に上がっていく(「立っている」イメージ) - 傾きが小さい(例:0.5、0.2など)
→ 線がゆるやかに上がる(「寝ている」イメージ)
さらに、傾きの正負にも意味があります。
- 傾きが正(+)のとき:右上がりの直線
- 傾きが負(−)のとき:右下がりの直線
坂道に例えると、とてもイメージしやすくなります。
急な坂なら傾きが大きい、なだらかなら傾きが小さい。
つまり傾きとは、直線がどれくらい「傾いているか」を表す値なのです。
比例定数と傾きの違いを比較してみよう
ここまで見ると、「比例定数」と「傾き」はとてもよく似た考え方だと感じるはずです。
実際に比例のグラフでは、比例定数=傾き となり、同じ数値を表します。
しかし、使われる場面や考え方に少し違いがあります。
共通点
- どちらも 「変化の割合」 を表す
- 比例のグラフでは 必ず一致する
違い
| 項目 | 比例定数 | 傾き |
|---|---|---|
| 登場する場所 | 式$y=ax$の中 | グラフ上の線の角度 |
| 意味 | $x$と$y$の関係を決めるルール | $x$が1変わったときの$y$の変化量 |
| 表し方 | 数値として示す | 線の見た目(右上がり・右下がり)としても理解 |
| 比例での関係 | $a$=傾き | 傾き=$a$ |
具体例で確認
$y=2x$
- 比例定数$a=2$
- 傾きも2 → 右上がりでやや急な直線
$y=−3x$
- $a=−3$
- 傾きも−3 → 右下がりで急な直線
注意点
傾きという概念は、比例以外の直線($y=ax+b$のように切片がある場合)でも使われます。
しかし比例は必ず原点を通るので、式が$y=ax$の形になります。
そのため比例では、比例定数と傾きが常に同じ値になります。
比例のグラフで考える!比例定数と傾きの関係を確認しよう
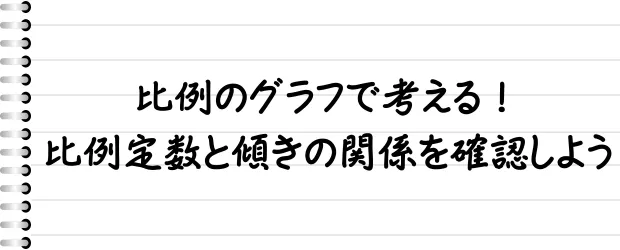
上記では、比例定数と傾きの意味や違いについて学びました。
ここからは、さらに一歩進んで「グラフの見た目」と「比例定数$a$」がどのようにつながっているのかをくわしく確認していきます。
文章だけではイメージしにくい部分も、グラフを思い浮かべながら読むことで理解がぐっと深まります。
比例のグラフはすべて原点を通る直線です。
だからこそ、比例定数$a$の値が変わると線の向きや立ち方が大きく変わるのです。
ここでは、比例定数の大きさ・符号・意味を、グラフの特徴と結びつけながらしっかり整理していきましょう。
比例定数が変わるとグラフはどうなる?
前の内容でも触れたように、比例定数$a$は「$x$が1増えたときに$y$がどれだけ増えるか」を表す、大変重要な数です。
比例そのものの「変化のきまり」を決めていると言えます。
では、この$a$の値が変化すると、比例のグラフはどのように変わるのでしょうか?
まず、比例の式$y = ax$を考えると、$a$の値が大きいほど「1増えるごとの$y$の増え方が大きい」ということになります。
つまり、
- $a$が大きい → グラフが急に上がる(傾きが大きい)
- $a$が小さい → グラフがなだらかになる(傾きが小さい)
具体的に、以下の3つを同じ座標平面に描いた様子を想像してみましょう。
- $y=x$
- $y=2x$
- $y=3x$
たとえば$x=1,2,3$を代入したときの$y$の値を比べると、増え方がどれだけ違うかがよくわかります。
| $x$ | $y=x$ | $y=2x$ | $y=3x$ |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | 2 | 4 | 6 |
| 3 | 3 | 6 | 9 |
同じ$x$の増加に対して、$y$の増える量が比例定数に合わせて大きくなっていることがわかります。
グラフのイメージでは、$a$の値が大きくなるほど、直線が原点を中心に「回転して立ち上がる」ような感じになります。
実生活でもこのイメージは役立ちます。
たとえば、
- りんご1個100円 → $y=100x$(比例定数100)
- りんご1個200円 → $y=200x$(比例定数200)
1個100円より1個200円の方が、購入個数が増えたときの金額の伸び方が大きいので、グラフもより急に上がります。
傾きと比例定数の関係をグラフで見てみよう
では、比例定数と傾きの関係をさらにくわしく見ていきましょう。
比例の式$y=ax$をグラフで考えると、「$x$を1増やしたときに$y$が$a$増える」という関係がそのまま「傾き」になります。
たとえば$y=2x$の場合、点 (1,2) と (2,4) を比べると、
- $x$の増加量:1
- $y$の増加量:2
→ 傾き=2
これはそのまま比例定数$a=2$と一致します。
同じように$y=0.5x$なら、
- $x$の増加量:1
- $y$の増加量:0.5
→ 傾き=0.5
こちらも比例定数と完全に一致しています。
また、グラフから数を読み取る逆方向の考え方もできます。
たとえば、2点 (2,4) と (4,8) を結ぶ直線について考えると、
傾き$=\frac{8-4}{4-2}=2$
→ したがって比例定数$a$も2。
このように、比例では「比例定数$a=傾き」という関係が常に成立します。
グラフを見れば線の角度、式を見れば$a$の数字で「変化の割合」がわかるので「見た目と数が一致する」というのが、比例の非常にわかりやすいポイントです。
比例定数の符号でグラフの向きが変わる!
比例定数の大きさは傾きの急さを表しますが、比例定数の「符号(+か−か)」はグラフの「向き」を決めます。
aが正のとき
- $xが増えると$y$も増える
- グラフは右上がり
例:$y=2x$
原点を通り、右へ行くほど上へ伸びていく線になります。
aが負のとき
- $x$が増えると$y$は減る
- グラフは右下がり
例:$y=−2x$
原点から右へ進むほど下へ向かう線になります。
さらに、$a$が2と−2のように絶対値が同じ場合でも、符号が異なるだけでグラフは「鏡に映したように」逆向きになります。
日常的なイメージでは、
- $a>0$は「増えると増える関係」
- $a<0$は「増えると減る関係」
と覚えると理解しやすくなります。
| 中学生のおすすめ学習塾3選 | |||
|---|---|---|---|
横浜予備校 |
WAM |
明光義塾 |
|
| 対象 | 中学生 | 中学生 高校生 |
中学生 高校生 |
| 授業料 (税込) |
29,700円~ (月額) |
7,600円~ (週1回) |
15,400円~ (週1回) |
| 入塾金 | 0円 | 16,500円~ | 11,000円 |
| 指導形式 | 学習塾 | 学習塾 (個別指導) |
学習塾 (個別指導) |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | |
比例の式を理解しよう|y=axの意味と読み取り方
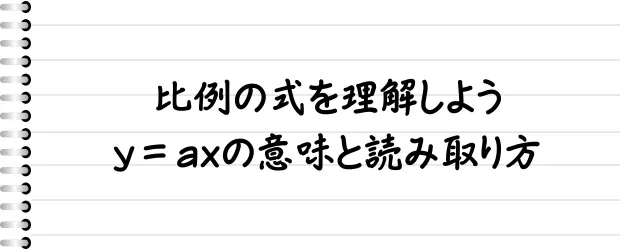
ここまでは、比例のグラフや比例定数の役割について学びました。
ここでは、比例を表す最も基本的な式 「$y=ax$」 がどんな意味をもち、どのように読み取ればよいのかをくわしく確認していきます。
比例は中学数学の中でも特に重要な分野で、関数の学習や高校数学の土台になる内容です。
「式の形がこうなっている理由」や「数字を代入すると何が起こるのか」を理解できると、グラフの読み取りだけでなく実際の計算問題にも強くなります。
ここからは、式の構造 → 比例定数の役割 → 数で読み取る練習、という順に理解を深めていきましょう。
比例の式「y=ax」は何を表しているの?
これまでの学習でも登場した「比例」という言葉ですが、改めて式の形に注目してみましょう。
比例の基本式$y=ax$は、「$x$に$a$をかけると$y$が決まる」という関係を表しています。
つまり、
- $x$の値を決めると、$y$の値も自動的に決まる
- $x$と$y$が「セットで動く」関係
という状態を式にしたものです。
式に出てくる文字の意味を整理すると次のようになります。
- $x$:変化させる数(入力・元になる量)
- $y$:$x$に対応して変わる数(結果・出力)
- $a$:$x$と$y$の関係を決めるルールとなる数(比例定数)
たとえば$y=2x$を考えると、$x$に2をかけたものが常に$y$になります。
- $x=1$ → $y=2$
- $x=2$ → $y=4$
- $x=3$ → $y=6$
このように、$x$が増えると$y$も同じ割合で増えることがわかります。
表にすると関係がより見えやすくなります。
また、比例の式をグラフに表すと、必ず原点(0,0)を通る直線になります。
これは「$x$に0を入れると$y$も0になる」という式の特徴がそのままグラフに表れているのです。
「$x$と$y$が連動して増減する関係を式で表したもの」
それが比例の基本式$y=ax$の正体です。
aの正体は?比例定数の役割を式で考えよう
では、式の中にある$a$(比例定数)はどんな役割を持っているのでしょうか。
比例定数$a$の意味は次のようにまとめられます。
- $x$が1のときの$y$の値を表す数
- $x$が1増えるとき、$y$がどれだけ増えるかを示す数
つまり$x$と$y$の「変化の割合」そのものです。
具体的に例を見ると理解しやすくなります。
$y=3x$
- $x$が1増えると、$y$は3増える → $a=3$
- グラフは急な右上がり
$y=0.5x$
- $x$が1増えると、$y$は 0.5 増える → $a=0.5$
- グラフはゆるやかな右上がり
さらに、$a$の「符号」も重要なポイントです。
- $a>0$ → $x$と$y$は同じ向きに増減 → 右上がりの直線
- $a<0$ → $x$が増えると$y$は減る → 右下がりの直線
比例定数$a$は、グラフの「傾き」や「向き」を決定する重要な役割を持っています。
言いかえると、$a$は「$x$と$y$の増え方をつなぐルール」であり、比例関係の中心的な要素と言えます。
xとyの変化を読み取ろう|数の関係を表で確認!
ここまで学んだ内容を、表を使って具体的に確認していきましょう。
比例の式は数字を並べると規則性が非常にわかりやすくなります。
たとえば$y=2x$の場合、次のようになります。
| $x$ | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| $y$ | 2 | 4 | 6 | 8 |
この表から読み取れるのは、
- $x$が1増えるごとに、$y$は2増えている
- 増え方が常に一定である
ということです。
別の式とも比較してみましょう。
| $x$ | $y=2x$ | $y=3x$ | $y=0.5x$ |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 0.5 |
| 2 | 4 | 6 | 1 |
| 3 | 6 | 9 | 1.5 |
比例定数$a$の値が変わると、$y$の増え方も変わっていることが表からよくわかります。
この「増え方がいつも一定で続く」という規則性こそが、比例関係の本質です。
また、表の値をグラフにプロットすると、どの式も原点を通る直線になります。
表 → グラフ → 式 がつながっていることを意識すると、比例の理解がしっかり深まります。
まとめ
比例は中学数学の中でも特に重要なテーマであり、「変化の割合」を理解する出発点です。
比例関係とは、1つの量が変わると、それに合わせてもう1つの量も一定の割合で変わる関係のことです。
式$y=ax$の形で表され、比例定数$a$がその変化のきまりを決めています。
グラフにすると常に原点を通る直線になり、この直線の傾きが比例定数そのものです。
比例の意味をしっかり理解することで、反比例や1次関数、高校数学の関数分野にもスムーズに進めるようになります。
ぜひ、式とグラフのつながりを意識して学んでみましょう。
| 中学生のおすすめオンライン塾・家庭教師3選 | |||
|---|---|---|---|
ウィズスタディ |
家庭教師の銀河 |
WAM |
|
| 対象 | 中学生 高校生 |
中学生 | 中学生 高校生 |
| 授業料 (税込) |
9,800円~ (1科目) |
2,750円~ (1コマ) |
7,600円~ (週1回) |
| 入会金 | 27,500円~ | 22,000円 | 16,500円~ |
| 指導形式 | 学習塾 (オンライン) |
家庭教師 | 学習塾 (オンライン) |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | |
練習問題
問1
次の比例式の比例定数$a$を求めなさい。
$y=7x$
問2
次のときの$y$の値を求めなさい。
$y=−3x$,$x=4$
問3
比例$y=ax$において、$x=5$のとき$y=20$となる。このとき比例定数$a$を求めなさい。
問4
比例$y=ax$において、$a=−2$,$y=14$のとき、$x$の値を求めなさい。
問5
ある比例のグラフが点(3,9) を通るとき、次の問いに答えなさい。
(1) 比例式を求めなさい。
(2) この比例のとき、$x=−2$のときの$y$の値を求めなさい。
問6
ある一定の速さで歩くと、歩く距離$y$(m)は歩いた時間$x$(分)に比例し、$y=ax$で表される。
(1)3分歩くと 180m 進む。比例定数$a$を求めなさい。
(2)比例式を使って、10分で進む距離を求めなさい。
(3)この人が 150m 進むのに必要な時間$x$を求めなさい。
解答
問1
$y=7x$の比例定数$a$は:$a=7$
問2
$y=-3x$,$x=4$のときの$y$は?
計算: $y=−3×4=−12
問3
比例$y=ax$で$x=5$のとき$y=20$。$a$は?
計算: $a=\frac{y}{x}=\frac{20}{5}=4$
問4
比例$y=ax$で$a=−2$,$y=14$。$x$は?
計算:$x=\frac{y}{a}=\frac{14}{-2}=-7$
問5
ある比例のグラフが点 (3,9) を通るとき、
(1) 比例式は?
(2) $x=−2$のときの$y$は?
(1) 計算: $a=\frac{9}{3}=3$。よって、$y=3x$。
(2) 計算: $y=3×(−2)=−6$。
問6
歩く距離$y(m)=ax$($x$は分)
(1) 3分で180m → $a=\frac{180}{3}=60$(単位:m/分)
(2) 10分での距離: y=60×10=600(m)
(3) 150m進むのに要する時間$x:\frac{150}{60}=2.5$=2分30秒
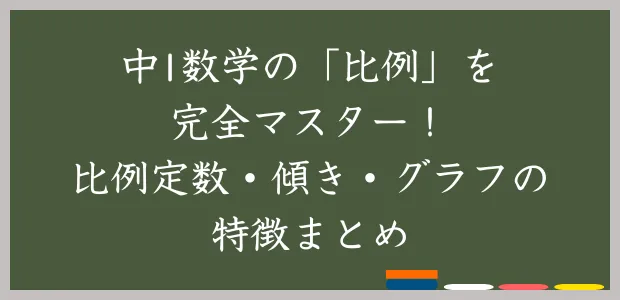

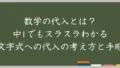
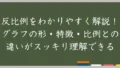
コメント