中学1年生にとって「不等式」は数学の新しい重要な概念です。
このページでは、不等式の基本的な意味や不等号の種類、等式との違いを初歩からわかりやすく解説します。
数の大小関係を式で表す方法や、日常生活に身近な例を使って理解を深め、さらには不等式の性質や計算のポイントも押さえます。
図や表を豊富に使い、理系が苦手な中学生でもスッと理解できるよう工夫しています。
不等式の基礎を固め、数学の自信につなげましょう。
| 中学生のおすすめ学習塾3選 | |||
|---|---|---|---|
横浜予備校 |
WAM |
明光義塾 |
|
| 対象 | 中学生 | 中学生 高校生 |
中学生 高校生 |
| 授業料 (税込) |
29,700円~ (月額) |
7,600円~ (週1回) |
15,400円~ (週1回) |
| 入塾金 | 0円 | 16,500円~ | 11,000円 |
| 指導形式 | 学習塾 | 学習塾 (個別指導) |
学習塾 (個別指導) |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | |
不等式とは?基本の意味から押さえよう
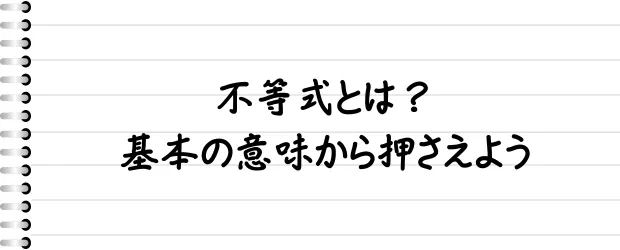
ここでは、数値の大小関係を数学で表すための「不等式」について詳しく学んでいきます。
不等式は中学数学で新しく登場する概念ですが、実は日常の中で自然と使っている考え方が詰まった便利な道具です。
まずは基本の意味からしっかり押さえましょう。
不等式とは?2つの数量の大小関係を表す式
不等式とは、2つの数量(数や量)の大小関係を不等号(<、>、≦、≧)を使って表した式のことです。
たとえば
- 3<5(3は5より小さい)
- 8>2(8は2より大きい)
のように、数と数の比較がそのまま式になっています。
等式(=)が「AとBはまったく同じ値」と示すのに対し、不等式は「AがBより小さい」「AがB以上」など、等しくない関係を表現する式です。
中学1年ではまず、この「大小比較を式で書く」ことが中心となります。
不等号には次の4種類があります。
- <:より小さい
- >:より大きい
- ≦:以下(小さいか等しい)
- ≧:以上(大きいか等しい)
さらに理解を深めるために、等式との違いを以下の表で整理してみましょう。
| 種類 | 記号 | 意味 | 例 |
|---|---|---|---|
| 等式 | = | 値が等しい | 4=4 |
| 不等式 | < | 左が右より小さい | 3<5 |
| 不等式 | > | 左が右より大きい | 7>2 |
| 不等式 | ≦ | 左が右以下 | $x$≦5 |
| 不等式 | ≧ | 左が右以上 | $x$≧7 |
また、文章を不等式に直す表現も重要です。
例えば 「りんご3個はみかん5個より少ない」→ 3<5 のように、日本語がそのまま数学の式に置き換わります。
不等式とはイメージで捉えよう!身長比較でわかる
不等式は数字だけで考えるより、身近な例でイメージすると一気に理解しやすくなります。
たとえば身長を比べてみましょう。
弟:140cm 兄:160cm
この関係を不等式で書くと、140<160(弟の身長<兄の身長)となります。
ほかにも、日常の中で不等式は自然と使われています。
- お小遣い100円<お菓子120円(買えない)
- 70点>60点(テストで勝った)
- 中1の年齢13歳≦高校生の16歳
- 35kg<40kg(体重比較)
- 家から学校までの距離1.2km<2.0km
また、よく使われる覚え方として「<や>はワニの口で、大きい方を食べる向きに開く」という比喩もあります。
例:8>3 → ワニは8の方を向く=8の方が大きい。
もし「等式」と比べると、次の違いもイメージしやすくなります。
- 等式=同じ身長の双子がピッタリ並ぶ
- 不等式=兄弟のようにどちらかが高い・低い
この違いを理解することで、不等式の役割がさらにクリアになります。
不等式の左辺・右辺の役割を知ろう
不等式は基本的に 「左辺(左の式) 不等号 右辺(右の式)」 の形で表します。
例:$x$<10
→ 左辺:$x$(調べたい値)
→ 右辺:10(比べる基準)
このように、不等号は左右の値の大小を決める「比較の司令塔」のような働きをします。
さらに例を見てみましょう。
- $x$<5($x$は5より小さい)
- 5>$x$(5が$x$より大きい=$x$<5と同じ意味)
左右を入れ替えると、不等号の向きも反転することがわかります。
次の表も確認してみましょう。
| 左辺 | 不等号 | 右辺 | 意味 |
|---|---|---|---|
| $x$ | < | 5 | $x$は5より小さい |
| 5 | > | $x$ | 5は$x$より大きい(=$x$<5) |
| $x$ | ≧ | 10 | $x$は10以上 |
| 3 | ≦ | $y$ | 3は$y$以下(=$y$≧3) |
中1では、未知の数量を$x$などの文字で表すことが増えます。
不等号は常に「左→右へ読む」ことで意味を正しくとりやすくなります。
不等号の意味と種類を口の向きで覚える
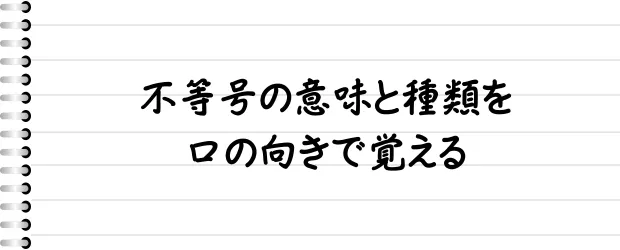
上記では「不等式そのものの考え方」を学び、数の大小関係を式で表せるようになりました。
ここでは、その不等式の中心となる記号——不等号に焦点を当てて学んでいきます。
不等号は見た目の形から混乱しやすい記号ですが、覚え方のコツをつかめば確実に使いこなせるようになります。
まずは意味と種類を整理し、最後に「向き」で覚える方法を確認しましょう。
不等号とは?大小関係を示す記号の基本意味
不等号とは、2つの数や式の大小関係をはっきり示すための記号です。
たとえば次のように使います。
- 3<5(3は5より小さい)
- 7>4(7は4より大きい)
等号(=)が「左右がまったく同じ値」を示すのに対し、不等号は左右が等しくない関係を表す記号です。
数学では値の大小の違いを正確に伝えることが大事なので、不等号は非常に重要な存在になります。
さらに、不等号は「どちらが大きいか」を直感的に理解しやすくする役割もあります。
同じ数を使っていても、書く順番や不等号の向きが違うと意味がまったく変わるため、不等号の読み方と形の理解が欠かせません。
例
- 3<5(3が小さい)
- 5>3(5が大きい)
同じ大小関係でも、不等号の向きによって読み方が変わる点に注意しましょう。
不等号の種類と読み方「<」「>」「≦」「≧」の区別
不等号には4つの種類があり、それぞれに明確な意味があります。
初めて学ぶときは、この4種類をしっかり区別することが第一歩です。
| 記号 | 読み方 | 意味 |
|---|---|---|
| < | 小なり | 左側が右側より小さい |
| > | 大なり | 左側が右側より大きい |
| ≦ | 小なりイコール 以下 |
左側が右側より小さいか等しい |
| ≧ | 大なりイコール 以上 |
左側が右側より大きいか等しい |
読み方の例を挙げると次のようになります。
- $a$<$b$:$a$は$b$より小さい
- $a$>$b$:$a$は$b$より大きい
- $a$≦$b$:$a$は$b$以下
- $a$≧$b$:$a$は$b$以上
特に、≦ と ≧ は「= を含む」ことが重要です。
つまり、大小に加えて等しい場合も含めるという意味が入っています。
学習初期では、まず形と意味のセットで覚えることが大切です。
「尖っている方が小さい」「広がっている方が大きい」というようなイメージとして捉えると記憶が定着しやすくなります。
口の向きでわかる!不等号の覚え方のポイント
不等号が苦手な中学生の多くがつまずくポイントは、「どちらが大きい?どちらが小さい?」を判断する際に向きを混乱してしまうことです。
ここで大活躍するのが、「口の向き」で覚える方法です。
不等号の「く」の字に見える部分(口のように開いている部分)は、大きい数の側に向くというルールがあります。
例
- 3<5
→ 開いている口は 5 の方を向く
→ 5 が大きい - 7>4
→ 開いている口は 7 の方に向く
→ 7 が大きい
つまり
- 口が開いている側が大きい
- とがっている側が小さい
この2点を押さえると、不等号の向きは一気に理解しやすくなります。
さらに、よく使われる例えとして「ワニの口」があります。
ワニは大きい数字を食べたがる
だからワニの口(不等号の開いている側)は大きい数に向く
このイメージを持つだけで、多くの学生さんが不等号の向きミスを減らしています。
もう一つ大事なポイントは、不等号の向きを間違えると意味が正反対になってしまうことです。
- 3<5(正しい)
- 3>5(意味が逆になるので誤り)
このように誤読・誤記は計算結果や文章題の解釈に直結します。
だからこそ、初学者は絵や図で視覚的に覚える方法が効果的です。
ワニの口の図を手帳に書いておくなど、日常的に確認できる工夫をすると理解が定着します。
| 中学生のおすすめオンライン塾・家庭教師3選 | |||
|---|---|---|---|
ウィズスタディ |
家庭教師の銀河 |
WAM |
|
| 対象 | 中学生 高校生 |
中学生 | 中学生 高校生 |
| 授業料 (税込) |
9,800円~ (1科目) |
2,750円~ (1コマ) |
7,600円~ (週1回) |
| 入会金 | 27,500円~ | 22,000円 | 16,500円~ |
| 指導形式 | 学習塾 (オンライン) |
家庭教師 | 学習塾 (オンライン) |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | |
等式と不等式の違いを表でスッキリ比較
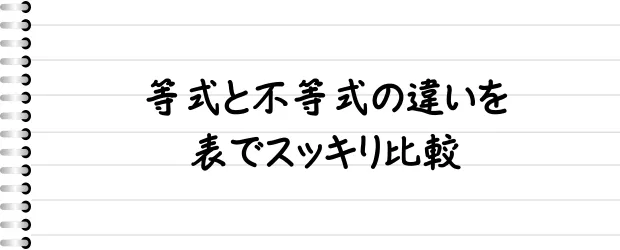
ここまでは、不等式の基本的な意味や不等号の向きについて学びました。
ここでは、その不等式とよく比較される「等式」との違いを、表を使って整理していきます。
等式と不等式は記号の形も意味も大きく異なり、学習が進むほど使い分けが重要になります。
中学数学の基礎として、2つの考え方をしっかり区別しておきましょう。
等式と不等式の記号を表で比較
まずは、それぞれで使われる“記号”の違いをまとめた表を見てみましょう。
| 項目 | 等式 | 不等式 |
|---|---|---|
| 記号 | = | <、>、≦、≧ |
| 見た目の特徴 | 横線1本で「等しい」をシンプルに表す | 口の開きで大小関係を視覚化(開く方が大きい) |
| 例 | 5=5 | 3<5、7>4、2≦3、4≧1 |
等式の「=」は、左右が完全に同じことを強調するため、シンプルな横線が2本並んだ形です。
一方、不等式は「く」のように口が開く形になっていて、開いた側がどちらかによって大小が決まります。
中学1年で初めて学ぶ不等号は次の4種類です。
- <:より小さい
- >:より大きい
- ≦:以下
- ≧:以上
「= はピッタリ一致」「不等号はハングリー(食べる方向が大きい数)」という覚え方をすると記憶しやすくなります。
等式と不等式の意味を表で整理
次は、記号が表す「意味そのもの」の違いを整理しましょう。
| 項目 | 等式 | 不等式 |
|---|---|---|
| 意味 | 左右の値が完全に等しい | 左右の値に大小関係がある |
| 関係性の例 | A=B(同じ値) | A<B(AがBより小さい) |
| 日常例 | 双子の身長が同じ | 弟より兄の方が背が高い |
等式は「A=B」のように、左右がまったく同じ値であることを断言する関係式です。
たとえば「10=10」「3+2=5」など、数も式も完全一致する場面で使います。
一方、不等式は「左右が等しくない」ことを前提とし、どちらが大きい・小さいかを比較するための式です。
日常の中でも次のような例が不等式になります。
- 兄の身長160cm > 弟の身長140cm
- 所持金500円 < 商品価格700円
- テストの点数80点 ≧ 合格ライン70点
「等式=平等」
「不等式=優劣」
というキーワードで覚えると、2つの区別が一気に明確になります。
等式と不等式の解の範囲を表でチェック
最後に、数学で重要なポイントである「解の範囲」の違いを見てみましょう。
これは特に後半の学習で差が大きくなる部分です。
| 項目 | 等式 | 不等式 |
|---|---|---|
| 解の形 | 1つの値(ピンポイント) | 範囲(広がった区間) |
| 例 | $x$=3(3だけが正解) | $x$<5(5より小さいすべての数が正解) |
等式の解はたった1つの値しかありません。
例えば、$x$=3なら「3」の1点だけが解です。
一方、不等式は値の範囲を表すことができます。
$x$<5は「5より小さいすべての数」が解になります。
このように点ではなく広がりを持つのが特徴です。
さらに、不等式では次のような範囲表現もよくあります。
- $x$≥0:0以上の数(右向きに広がる)
- $x$≤0:0以下の数(左向きに広がる)
- 1<$x$≦5:1より大きく5以下の数(両側で条件が異なる)
このように、等式=点、不等式=広がった範囲という違いを押さえることが、今後の方程式・関数の学習にも役立ちます。
不等式とは具体的にどんな式?立て方のコツ
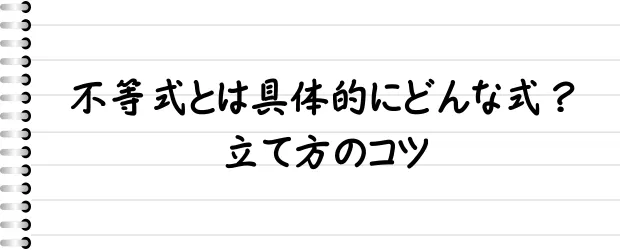
上記で、不等式が数量を比較するための式であることを確認しました。
では実際に文章題を読んだとき、どのように不等式を立てればよいのでしょうか。
ここでは、数量の関係を読み取るためのキーワード、文字を使って不等式を組み立てる手順、さらに間違えやすいポイントを例題とともに整理していきます。
文章題では、言葉の意味を正しく理解できるかどうかが結果を大きく左右します。
ここで紹介するコツを身につけることで、不等式の作り方がぐっとスムーズになります。
意味を見極めよう!数量の関係を読み取るコツ
文章題で最も重要なのは、数量の関係を示す言葉(キーワード)を見つけることです。
不等式はどちらが大きいか・小さいかを表す式なので、文章の中にある比較の言葉を探せば、どんな不等式になるかが自然と見えてきます。
まずは代表的なキーワードと不等号の対応を確認しましょう。
- 「より」:厳密な大小比較(例:Aより大きい→A<B、Aより小さい→A>B)
- 「以下/以上」:等号を含む比較(例:100円以下→値段≦100)
- 「同じ」:=(等式だが比較判断で触れることがある)
次に、文章を読み取る際のポイントをまとめます。
- 「より」の向きは必ず主語側を確認する
- 「以下/以上」は等しい場合も含むことを忘れない
- 人物や物の数量には、1つの数量に1つの文字を割り当てる
- 数量の比較が複数ある場合は、主語を正確に追う
- 「少ない=小さい」と判断し、大小の向きを逆にしない
また、視覚的に整理すると理解しやすくなるため、以下のような表にまとめるのも有効です。
| 文章例 | 関係キーワード | 不等号 |
|---|---|---|
| 弟より兄が背が高い | より | 弟<兄 |
| 点数80以上で合格 | 以上 | 点数≧80 |
日常生活から例を取るとさらに理解が深まります。
お小遣い、所要時間、走った距離、持ち物の数など、普段の生活でも「どちらが多い/少ない」は頻繁に出てくる比較です。
文章題でつまずいたときは、身近な例に置き換えて考えると、大きさ関係が掴みやすくなります。
文字を使った不等式の立て方基本ステップ
数量を読み取ったら、次は実際に不等式を作ります。
ここでは初学者でも迷わず作れるように、4つのステップに分けて整理します。
①数量を文字に置き換える
例:太郎のりんごの数を$t$、妹のりんごの数を$m$とする。
(1つの数量につき1つの文字を必ず割り当てる)
②関係キーワードを探す
例:「太郎の方が2個少ない」→「少ない」は小さいなので
$t$<$m$
③数値や条件を追加して式を整える
例:妹が10個持っている → $m$=10
→ $t$< 10
差の場合:「2個少ない」→ $t$+2=$m$と関連式を作るのも有効。
④できた式を文章に戻して確認する
例:$t$< 10
→「太郎のりんごは10個未満」
この読み上げ確認がとても重要で、向きの誤りを防げます。
より複雑な例も見てみましょう。
文章例:「花子の本は3冊で、浩太はそれより多い」
- $h$=3(花子の冊数)
- $k$=浩太の冊数
- 「より多い」→ $k$>$h$
よって$k$>3
よくある例題で学ぶ不等式の作り方と注意点
ここからは例題を通して、不等式をどう立てればよいか、またどこで間違いやすいかを確認します。
例題1:「体重50kgの母より父が重い」
- 母:50
- 父:$f$
→ $f$>50
(重い=数量が大きい)
例題2:「テスト60点以上で合格」
点数:$x$
→ $x≧60
(「以上」は60も含む)
例題3:「お菓子5個を分け、兄が妹より1個多い」
- 兄:$a$
- 妹:$b$
→ $a=b+1$
(ここは差分の式が必要)
よくあるミスをリストで整理します。
- 不等号の向きを逆にしてしまう
- 単位をそろえず比較する(cmとmの混在など)
- 「同じ」が入るときに等式を忘れる
- 同じ文字を複数の数量に使う
ここまで見てきたように、キーワードの把握、文字の割り当て、式の確認という手順を守ることで、不等式は正しく立てられます。
文章題での不等式は「言葉の意味を式に変える作業」と理解すれば、確実に得点源になります。
| 中学生のおすすめ学習塾3選 | |||
|---|---|---|---|
横浜予備校 |
WAM |
明光義塾 |
|
| 対象 | 中学生 | 中学生 高校生 |
中学生 高校生 |
| 授業料 (税込) |
29,700円~ (月額) |
7,600円~ (週1回) |
15,400円~ (週1回) |
| 入塾金 | 0円 | 16,500円~ | 11,000円 |
| 指導形式 | 学習塾 | 学習塾 (個別指導) |
学習塾 (個別指導) |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | |
不等式の基本性質を知って計算の第一歩
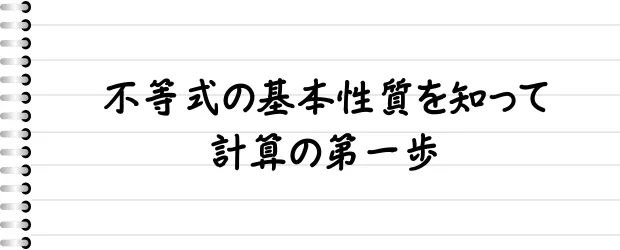
ここまでは、不等式が数量を比較する式であることを学びました。
ここでは、その不等式がどのような性質をもつのかを整理し、計算や文章題に自信をもって取り組むための基礎を固めていきます。
不等式は単なる「大きい・小さい」の比較ではなく、数直線上での位置関係や値の広がりを表すものです。
その性質を理解しておくと、複雑な文章題でも「どの値がどこに位置するか」を自然に扱えるようになります。
特に中学数学では、この段階で不等式のルールをしっかり押さえられるかどうかが、その後の計算問題の理解に直結します。
不等式の推移律:A<B<CならA<C
不等式がもつ重要な性質の一つに推移律(すいいりつ)があります。
これは「AがBより小さく、さらにBがCより小さいなら、自動的にAもCより小さい」というつながりの法則です。
間にある値を飛ばしても、大きさの流れがそのまま続くイメージです。
日常に近い例で見てみましょう。
| 関係 | 例(身長) | 結果 |
|---|---|---|
| A<B<C | 小学生<中学生<高校生 | 小学生<高校生 |
| 数値例 | 3<5<8 | 3<8 |
このように、大きさが段階的に並んでいれば、端と端の関係も自然に決まります。
「階段を上る」イメージで、1段目<2段目<3段目であれば、当然「1段目が一番下」です。
お菓子の個数でも、弟3個<兄5個<父8個と並べば、弟<父は明らかです。
推移律は不等式を連続して使うときの基盤です。
たとえば文章で「AさんはBさんより遅く、BさんはCさんより遅い」と書かれていれば、A<B<C の流れから A<C が成立します。
なお、逆の関係も同様で、A>B>C なら A>C となります。
不等式は「範囲」を表す性質
不等式の大きな特徴は、「1つの点」ではなく広がり(範囲)を表すことです。
等式では$x$=3のように、ただ1つの値だけが解になります。
しかし不等式では、$x$<5と書かれた瞬間に「5より小さいすべての数」が解になります。
このように、不等式は 「どこからどこまでが可能なのか」 を示す道具です。
日常の例を挙げると、
- 「100円以上ならOK」→お金の量≥100(100円〜いくらでも)
- 「合格は60点超」→点数>60(61点から上すべて)
と、幅を持つ情報であることが分かります。
また、不等式には次の4種類があり、向きと含む値に注意が必要です。
- $x$<$a$:$a$より左の範囲
- $x$>$a$:$a$より右の範囲
- $x$≦$a$:$a$を含んで左側
- $x$≧$a$:$a$を含んで右側
矢印の方向を意識すると、範囲を間違えにくくなります。
不等式の大小が保たれる基本ルール
不等式が扱いやすい理由の1つが、「一度決まった大小関係は、簡単には崩れない」という性質です。
数の世界では、小さいものはずっと小さいまま、大きいものは大きいままという安定した順序が成り立ちます。
この性質のおかげで、推移律や範囲の考え方が確かなものになります。
主なルールを表にまとめると次の通りです。
| ルール名 | 内容 | 例 |
|---|---|---|
| 推移安定 | A<B<CならA<Cが永続 | 身長などの連鎖関係 |
| 範囲安定 | $x$<5の解はいつでも5未満 | 範囲が変わらない |
| 比較一貫 | 3<5はいつでも真 | 順序は崩れない |
このように、数の大小は自然の順序のように安定しており、「急に逆転する」ことはありません。たとえば、
- 年齢
- 持ち物の数
- 距離
- 点数
いずれも大きい・小さいは常に同じ関係のまま保たれます。
不等式の大小関係は固定されているため、計算や文章題で「どちらが大きいか」を比較するときに迷いが少なくなります。
この安定性が、不等式の学習を進める上で大きな支えとなります。
まとめ
不等式は、2つの数量の大小関係を表す便利な数学の道具です。
不等号には「<」「>」「≦」「≧」の4種類があり、口の向きでどちらが大きいかを覚えることがポイントです。
等式との違いを理解し、解の範囲が点ではなく区間であることも押さえておくと、数学の応用へつながります。
また、不等式の推移律と安定性の性質を知ることで、大小関係が自然と保たれ、文章題や計算問題への対応がしやすくなります。
この基本を丁寧に学ぶことで、中学数学の大きな土台が築けるでしょう。
| 中学生のおすすめオンライン塾・家庭教師3選 | |||
|---|---|---|---|
ウィズスタディ |
家庭教師の銀河 |
WAM |
|
| 対象 | 中学生 高校生 |
中学生 | 中学生 高校生 |
| 授業料 (税込) |
9,800円~ (1科目) |
2,750円~ (1コマ) |
7,600円~ (週1回) |
| 入会金 | 27,500円~ | 22,000円 | 16,500円~ |
| 指導形式 | 学習塾 (オンライン) |
家庭教師 | 学習塾 (オンライン) |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | |
練習問題
問1
次の不等式のうち、推移律を正しく使って導けるものをすべて選びなさい。
(1) 2<5<9 → 2<9
(2) 3<7<6 → 3<6
(3) 8>4>1 → 8>1
(4) 1<4>2 → 1<2
問2
次の不等式の「表す範囲」を、言葉を使って説明しなさい。
(1) $x$<6
(2) $x$≧−2
問3
次の不等式の大小関係が正しく保たれるかどうか「◯/✕」で答えなさい。
(1) 4<9<12 より 4<12
(2) 5>1>3 より 5>3
(3) 7<10 だから 10<7
(4) 0≦3 だから 3≧0
問4
以下の文章を読み、それぞれ不等式を立てなさい。
(1)花子さんの持っているお金$x$円は、500円より少ない。
(2)テストで合格するには、点数が60点以上である必要がある。点数を$y$点とすると、不等式で表しなさい。(3)ある公園の入場料は「12歳未満の人の料金は$a$円より安い」と言われている。12歳未満の人の料金を$p$円として、不等式で表しなさい。
解答
問1
(1) ○ 推移律で 2<9 が導ける
(2) ✕ 7<6 は成り立たないため推移不可
(3) ○ 8>1 が導ける
(4) ✕ 1<4>2 は連鎖ではないため推移律は使えない
問2
(1)$x$は6より小さいすべての数。
(2)$x$は−2を含んで、それより大きいすべての数。
問3
(1) ○
(2) ✕ 1>3 が成り立たないため
(3) ✕ 大小が逆転している
(4) ○
問4
(1) $x$<500
(2) $y$≧60
(3) $p$<$a$
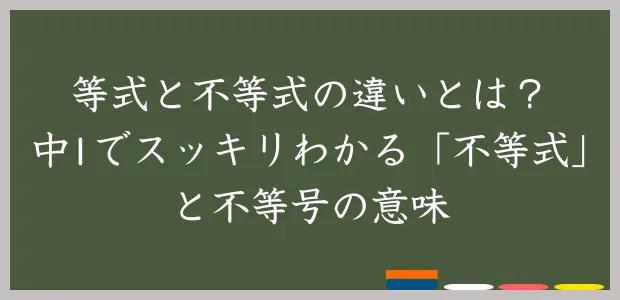
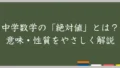

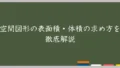
コメント