中学1年生で学ぶ「文字式」は、数学の基礎でありながら、初めて見るルールや書き方に戸惑うことも多い単元です。
このページでは、「かけ算の×を省略する理由」「数字と文字の並べ方の基本」「符号の使い方と累乗の表し方」といった文字式の書き方に関する重要なルールをわかりやすく解説します。
さらに、正しい書き方をマスターすることで、テストで高得点を狙えるように導きます。
| 中学生のおすすめ学習塾3選 | |||
|---|---|---|---|
横浜予備校 |
WAM |
明光義塾 |
|
| 対象 | 中学生 | 中学生 高校生 |
中学生 高校生 |
| 授業料 (税込) |
29,700円~ (月額) |
7,600円~ (週1回) |
15,400円~ (週1回) |
| 入塾金 | 0円 | 16,500円~ | 11,000円 |
| 指導形式 | 学習塾 | 学習塾 (個別指導) |
学習塾 (個別指導) |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | |
文字式って何?中1数学で最初におさえたい基本ルール
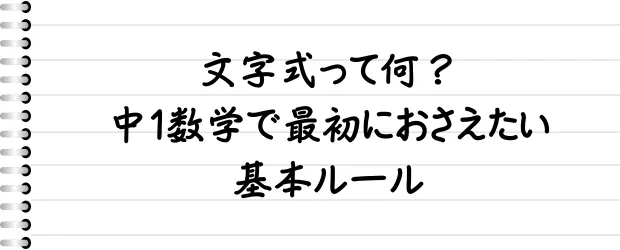
中学1年生で初めて登場する「文字式」は、数学の世界を一気に広げてくれる大切な考え方です。
計算のルールが数字だけでなく「文字」にも広がることで、具体的な数が決まっていない場面でも式を使って数量を整理したり、法則を見つけたりできるようになります。
ここでは、文字式とは何か、その役割、そして実際の例を通して中1数学の土台になる基本ルールを丁寧に解説します。
文字式の基本定義
文字式とは、数字と文字(例:$a$,$x$,$y$)を組み合わせて作られた式のことです。
中学1年生の数学で最初に学ぶ「代数の入口」といえる内容で、具体的な数値ではなく「未知の量」や「変わる数量」を文字で表現します。
たとえば、
- 10+$a$ …「10と$a$を足す」
- $3x$ …「3×$x$」
のように、数字と文字を組み合わせた表現を文字式と呼びます。
文字式の大きな特徴は、かけ算の記号(×)を省略する点です。
例えば$3×x$と書かずに$3x$と書きます。
これは文字式の書き方の基本ルールであり、式をコンパクトかつ読みやすくするために広く使われます。
逆に、足し算や引き算は省略しません。
さらに、$1×a$は「$a$」と書くのが一般的で、同じ文字が続く場合は指数を使い、$xxx$は$x³$と表します。
このように文字式は、計算そのものよりも「数量をどう表すか」が大切なポイントです。
数字では表せない状況を扱えるようになるため、数学の考え方の幅がぐっと広がります。
なぜ文字式を使うの?
文字式を使う最大の理由は、1つの式でさまざまな状況を表現できるからです。
具体的な数字を決めなくても、式を使えば「どんな場合にも共通のルール」を表せます。
たとえば、1個180円のケーキを$x$個買い、箱代50円が必要な場合、
$180x+50$
と書くことで「総額」を表せます。
$x=2$なら 410円、$x=5$なら 950円…というように、状況ごとに数字を代入して計算できます。
日常生活でも文字式の考え方は自然に登場します。
お菓子1個120円を$y$個買い、友達に50円分を渡したとすると、
$120y−50$
で「自分が払う金額」を表すことができます。
$y=3$を代入すると、120×3−50=310円となり、実際の計算にも結びつきます。
さらに、文字式は図形にも使われます。
長方形の面積が「縦の長さ$l$」「横の長さ$w$」なら、面積は$lw$です。
数字を入れなくても、どの長方形にも共通する法則を式で表せるわけです。
このように文字式は
- 数量の変化を扱える
- 公式を見つけやすい
- さまざまな問題を一つの式で整理できる
などのメリットがあり、中学以降に学ぶ方程式・比例と反比例・関数へとつながる重要な基礎となります。
文字式の簡単な例
ここでは、中1数学でよく登場する文字式の基本例を確認しておきましょう。
まずは足し算・引き算の例です。
- $5+b$:5と$b$を足す
- $c$−2:$c$から2を引く
次に掛け算の例です。
文字式では掛け算の記号を省略することが基本です。
- $4a$:4×$a$
- $xy$:$x$×$y$
このとき、数字は文字の前に書くことが決まりです。
また、$1a$は$a$と書き、「1」は省略されます。
複数の文字を含む式では、$a$ → $b$ → $c$のようにアルファベット順で並べることが推奨されます。
例:$2ab+3c$
「同じ文字が続く場合」は指数表記を使うため、
$xxx$ → $x³$
と書きます。
割り算が入る場合は、
$a÷b$ → $\frac{a}{b}$(分数)
のように書き換えるのが一般的です。
また、符号がつく場合は、
$-3d$
と書き負の数量を表します。
文字式は見慣れると非常にシンプルで、数字の計算と同じ感覚で扱えるようになります。
「数字と文字をどう組み合わせるか」をおさえることで、中1数学の基礎がしっかり固まり、これ以降の単元の理解も大きくスムーズになります。
数学で使われる文字:アルファベットとギリシャ文字
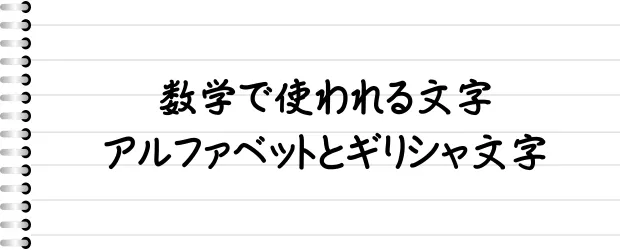
文字式の基本的なルールについても解説したところで、数学で使われる文字を簡単に触れておきたいと思います。
数学では、様々な文字が使われますが、主にアルファベットとギリシャ文字が用いられます。
これらの文字は、数量や関係性を表すために使用されます。
アルファベット
数学で使用される代表的なアルファベットは以下の通りです。
| $a, b, c$ | 一般的な定数や係数を表すのによく使われます。 |
| $x, y, z$ | 未知数や変数を表すのによく使われます。 |
| $n, m$ | 整数や要素の数を表すのによく使われます。 |
| $f, g, h$ | 関数を表すのによく使われます。 |
| $i, j, k$ | 添え字や整数を表すのによく使われます。 |
| $l$ | 長さを表すのによく使われます。 |
| $p, q$ | 確率や比率を表すのによく使われます。 |
| $r$ | 半径を表すのによく使われます。 |
| $s$ | 弧の長さや表面積を表すのによく使われます。 |
| $t$ | 時間を表すのによく使われます。 |
| $u, v, w$ | ベクトルや速度を表すのによく使われます。 |
上記の表の中には、よく分からない言葉もあるかもしれません。
ですが、この段階で分からないからと調べる必要は特にありません。
学年が上がったり、高校生になったら学習するものなので、今はこういうものに使われるのかぁぐらいの認識で全く問題ありません。
ギリシャ文字
ギリシャ文字は全て覚える必要はありませんが、数学で使用される機会も多いので、一覧にして紹介します。
| $α$ (アルファ) |
$β$ (ベータ) |
$γ$ (ガンマ) |
$δ$ (デルタ) |
| $ε$ (イプシロン) |
$ζ$ (ゼータ) |
$η$ (イータ) |
$θ$ (シータ) |
| $ι$ (イオタ) |
$κ$ (カッパ) |
$λ$ (ラムダ) |
$μ$ (ミュー) |
| $ν$ (ニュー) |
$ξ$ (クサイ) |
$ο$ (オミクロン) |
$π$ (パイ) |
| $ρ$ (ロー) |
$σ$ (シグマ) |
$τ$ (タウ) |
$υ$ (ウプシロン) |
| $φ$ (ファイ) |
$χ$ (カイ) |
$ψ$ (プサイ) |
$ω$ (オメガ) |
これらの文字は、数学の様々な分野で使用されますが、中学1年生の段階では、主にアルファベットの小文字を使用することが多いです。特に、$x, y, z$などの文字が未知数や変数として頻繁に登場します。
文字の選び方のポイント
文字を使うときには、単にアルファベットを並べるのではなく、状況に合った文字、理解しやすい文字を選ぶことが重要です。
頭文字に合わせると覚えやすい
- 人数:$n$(number)
- 時間:$t$(time)
- 速さ:$v$(velocity)
- 距離:$d$(distance)
このように、意味とつながる文字を選ぶと、式にしたときに読み解きやすく、問題文との対応も自然になります。
小文字を優先し、アルファベット順で整理
同じ式で $a$,$b$,$c$を使う場合は、
- りんご:$a$
- バナナ:$b$
- みかん:$c$
のように、アルファベット順に並べると無理がありません。
また、同じ文字を二重に使わないことも重要です。
意味が混在すると式が読めなくなってしまいます。
数字と混同しないこと
- $l$(エル)は 1 と区別がつきにくい
- $o$(オー)は 0(ゼロ)に似ている
- $x$ は × と混乱しないよう注意
特に手書きのテストでは読み間違いによる失点もあるため、正確に書き分ける習慣が大切です。
実生活でも自然に登場
例えば、自転車で
速さ:v
時間:t
進んだ距離:d
とすると、
$d=vt$
が成立し、文字式の考え方が身近な現象を整理するのに役立つことが実感できます。
| 中学生のおすすめオンライン塾・家庭教師3選 | |||
|---|---|---|---|
ウィズスタディ |
家庭教師の銀河 |
WAM |
|
| 対象 | 中学生 高校生 |
中学生 | 中学生 高校生 |
| 授業料 (税込) |
9,800円~ (1科目) |
2,750円~ (1コマ) |
7,600円~ (週1回) |
| 入会金 | 27,500円~ | 22,000円 | 16,500円~ |
| 指導形式 | 学習塾 (オンライン) |
家庭教師 | 学習塾 (オンライン) |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | |
中1数学の文字式の書き方|×を省略する・順番・記号のルール

上記では、文字や記号そのものの種類について学びました。
ここからは、実際に文字式を書くときに必ず守るべき書き方のルール をまとめていきます。
中学1年生の文字式では、書き方が整っているかどうかが成績に直結します。
特に、かけ算記号「×」の省略、数字と文字の順番、符号のつけ方と累乗(2乗・3乗)の扱いは、テストでも頻出ポイントです。
どれも「正しく書けているか」を見られるため、ここで一度しっかり整理しておきましょう。
「×」を省略して書く理由とポイント
文字式では、文字が含まれるかけ算では必ず「×」を省略します。
これは中学数学で統一された表記法であり、式を簡潔に、読みやすくする目的があります。
たとえば、
- $3×a$ → $3a$
- $a×b$ → $ab$
- $2×a×b$ → $2ab$
のように書き換えます。
「×」が残っていると計算途中の式のように見えるため、テストでは減点対象になることが多いです。
「×」省略のポイントまとめ
数字×文字 → 数字を前に書き、×を省略($4×x$ → $4x$)
文字×文字 → そのまま並べて書く($y×z$ → $yz$)
数字×文字×文字 → $2ab$のように一列にまとめる
例外はなく、文字を含むかけ算では必ず省略します。
数字同士だけ(2×3=6)の場合は「×」を使いますが、文字が混ざった瞬間に省略するというのがルールです。
実際の場面で考えると、例えば「りんごを$a$個、みかんを$b$個買い、その合計を2倍する」という状況は
$2×(a+b)$ → $2a+2b$
となり、さらに「$2×a$→$2a$」「$2×b$→$2b$」の × が省略されるため、式がスッキリして読みやすくなります。
数字と文字の順番ルール:数字は先、文字はアルファベット順に
次に重要なのが、数字・文字の並び順のルール です。
基本ルール
- 数字を前に書く
- 複数の文字はアルファベット順に並べる
これは、式の統一感を保ち、読み間違いを防ぐためのルールです。
具体例
- $x×3$ → $3x$(数字が先)
- $a×4$ → $4a$
- $b×a$ → $ab$($a$が先なので並べ替える)
- $2×c×a$ → $2ac$($a$→$c$の順)
- $d×b×3×a$ → $3abd$(数字→$a$→$b$→$d$)
誤った例として
$5b×a$ → $5ba$(誤り) → $5ab$(正しい)
順番を統一することで、例えば$ab+2cd$のように、多項式でも見やすさが格段に向上します。
文字式は「どれだけ簡潔に、正しく整理できているか」が評価されるため、この順番は必須知識です。
符号と累乗の使い方:マイナスと同じ文字の掛け算の表し方
最後に、符号(+/−)と累乗(2乗・3乗)の扱いです。
特に マイナスの付け方と、同じ文字が重なるときの表し方 はテストでも間違えやすい部分です。
マイナスを含む場合
- $(-3)×a$ → $-3a$
- $a×(-1)$ → $-a$(-1 を省略)
- $1×m$ → $m$
- $(-1)×n$ → $-n$
係数(数字)が1、あるいは-1の場合は 1や-1を省略し、文字だけを残します。
ただし、0.5a のような小数は省略しません。
同じ文字のかけ算=累乗
- $x×x$ → $x²$
- $y×y×y$ → $y³$
- $(-2)×x×x$ → $-2x²$
累乗を使うことで、式が短く、理解しやすい形になります。
分数との組み合わせ
$\frac{-a}{b}$ → -$\frac{a}{b}$
同じ文字が並んだまま($xx$)や、「-$a$」を「-$1a$」のまま書いてしまうのは典型的なミスなので注意しましょう。
「文字式の順番ルール」を攻略!符号・数字・文字の並べ方の基本

ここまででは、文字式を書くときの「×を省略する」という基本ルールを学びました。
しかし、文字式を正しく読みやすく書くためには、「順番のルール」を押さえることが欠かせません。
特に、符号の位置、数字(係数)と文字の並べ方、文字同士の順番は、中学1年生の文字式で最も重要なポイントです。
これらを正しく使いこなすことで、式が整い、計算ミスも大幅に減らせます。
ここでは、数学で統一されている順番のルールを詳しく整理し、どのように式を書き換えれば良いかを理解していきましょう。
符号の位置:マイナス記号は項の先頭に
文字式で最も基本となるのが マイナス記号(−)の書き方 です。
マイナスは、常に各項の先頭に置くという統一ルールがあります。
これは、項全体の符号を明確にし、式の見間違いを防ぐために非常に重要です。
例えば
- $(-3)×b$ → $-3b$
- $a×(-2)$ → $-2a$
のように書き換えます。
詳しいルール
項全体が負の場合
$−(3a+b)$ → $-3a-b$
(展開後、各項の先頭にマイナスを付ける)
係数−1 の場合
$-1×x$ → $-x$(1 を省略)
分数のマイナス
$a÷(−b)$ → −$\frac{a}{b}$
(マイナスは分母の外に出す)
符号は項ごとに独立
$-a+b$はそのまま
$5a-(-b)$は二重マイナスで$5a+b$
実生活の例では、「借金100円(−100)と収入$x$円 → $x-100$」のように、マイナスは項の前にあると状況が分かりやすくなります。
符号の位置をいつもチェックする習慣をつけることで、テストでの符号ミスが大きく減らせます。
数字と文字の並べ方:数字を前に置く基本
数字(係数)と文字の積は、必ず数字を先頭に置きます。
これにより、式が整理され、係数がひと目で分かる形になり、後の因数分解や整理もスムーズになります。
基本例
- $x×5$ → $5x$
- $3×y×2$ → 数字同士を先に計算して$6y$
- $a×4×b$ → $4ab$
小数や分数も同様で
- $0.5p$ → $0.5p%(省略なし)
- $\frac{1}{2}×q$ → $\frac{q}{2}$
ただし、文字→数字の順は絶対に書かないよう注意しましょう。
$a3$ (誤り)→ $3a$(正しい)
よくある間違い例
- $p×2.5$ → $p2.5$(誤)→ $2.5p$(正)
- $r×(-3)×s×1$ → $-3rs$(1は省略)
生活場面では、「時給800円 × 時間$t$ → $800t$」のように、数字が前にあると意味がとても分かりやすくなります。
このルールは例外がなく、どの問題でも共通して使われるため、確実に身につけておく必要があります。
文字同士の順番:アルファベット順でスッキリ整理
複数の文字を並べるときは、アルファベット順($a$→$b$→$c$→ … →$z$)に並べるのが数学での標準ルールです。
これにより式が整理され、誰が見ても同じ形になるため、テストの採点もスムーズになります。
並べ替え例
- $b×a×z$ → $abz$
- $x×c×y$ → $cxy$
同じ文字が複数ある場合は 累乗にまとめてから順番に並べます。
$m×n×m$ → $m×m×n$ → $m²n$
数字が混ざる場合は
$2×d×b×a$ → $2abd$
のように、数字→アルファベット順 の流れになります。
ギリシャ文字は中1ではほとんど使いませんが、$\pi r²$のように、$\pi$(パイ)が$r$より前に置かれる形になる点は知っておくと役立ちます。
よくある間違い
$q×v$ → $vq$(誤)→ $qv$(正)
($q$はアルファベット17番目、$v$は22番目)
実生活でも、「商品$a$個 × 価格$b$円 × 税率$c$」→ $abc$のように考えると、順番がスッと理解できます。
最後に、並べ替えのチェックリストとして「①並び替え→②数字先→③×省略→④累乗へ」の順に確認すると間違いを防げます。
| 中学生のおすすめ学習塾3選 | |||
|---|---|---|---|
横浜予備校 |
WAM |
明光義塾 |
|
| 対象 | 中学生 | 中学生 高校生 |
中学生 高校生 |
| 授業料 (税込) |
29,700円~ (月額) |
7,600円~ (週1回) |
15,400円~ (週1回) |
| 入塾金 | 0円 | 16,500円~ | 11,000円 |
| 指導形式 | 学習塾 | 学習塾 (個別指導) |
学習塾 (個別指導) |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | |
よくあるミスと対処法
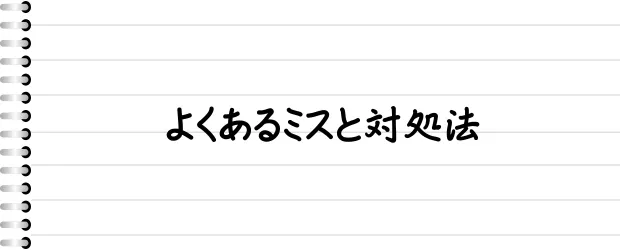
ここまでは、文字式の順番ルールや符号・数字・文字の並べ方を整理して学びました。
しかし、そのルールを知っていても、実際の計算でミスが起こるのが中学1年生の文字式です。
ここでは、特に頻度の高い「符号のミス」「カッコの外し方の誤り」「累乗の書き忘れ」という3つの代表的な間違いに焦点を当てて、どこでつまずきやすいのか、どうすれば防げるのかを具体例とともに解説します。
ここで紹介するコツを普段の問題演習に取り入れることで、ケアレスミスを大きく減らすことができ、テストでも安定して得点できるようになります。
符号ミスを防ぐコツと注意ポイント
文字式の計算で最も多いミスが「符号ミス」です。
特に、カッコを外すときや、マイナス×マイナスで符号が変化する場面での見落としが原因になります。
例えば、
- -($a+b$) を -$a+b$と書いてしまう
- $a−(b−c)$ の$−(−c)$を見落として、$a−b−c$としてしまう
といった間違いは非常によく見られます。
コツ1:マイナス符号を丸で囲む
計算に入る前に式の中のマイナスに○や□を書いて目立たせる方法です。
例: $−(3x+2y)$
→ ○−($3x+2y$) と印をつけておくと、展開時に$−3x−2y$と正しく符号を反転できます。
コツ2:項ごとに符号を明記してから整理
式を「+項」「−項」のまとまりとして見る練習をすると、符号の確認が楽になります。
例: $2a−(b−c)$
→ $2a−b+c$
内側の$−c$に対する$−×−=+$を見落とさないためにも有効です。
注意したいポイント
- 二重マイナスはプラス(-$-a$ → $+a$)
- 全体にマイナスがつくと、すべての項の符号が反転
符号だけを声に出して確認しながら計算する学生さんは、符号ミスが大幅に減少します。
カッコの外し方で間違えやすい例と正解パターン
カッコを外すときに必要なルールは「前の符号を内側すべての項に適用する」という一点です。
しかし、実際には多くの学生さんが、後半の項だけ符号が変わらない、あるいは部分的に反転してしまうなどのミスをします。
よくある誤りと正しい形を整理すると次のようになります。
| 式 | 間違えやすい書き方 | 正解 |
|---|---|---|
| $a−(b+c)$ | $a−b+c$ | $a−b−c$ |
| $4a−(b+2c)$ | $4a−b+2c$ | $4a−b−2c$ |
正しいカッコ外しの手順
- カッコの前の符号を確認(+ならそのまま、−なら全項を反転)
- 反転後に数字→文字の順に整理
- 同類項をまとめる前にもう一度符号を確認
計算そのものよりも、符号を確実に処理することを優先するとミスが減ります。
同じ文字の掛け算で累乗を使い忘れないために
中学1年生がよくするミスに「$x×x$を$xx$と書いてしまう」「$3y×y$を$3yy$と書く」など、累乗の使い忘れがあります。
指数の意味を理解していないまま計算をしていると起こりやすいミスです。
ミス例
$x×x×2x$
間違い:$2xxx$
正解:$2x³$
$3y×y×(−y)$
間違い:$−3yyy$
正解:$−3y³$
防ぐコツ
同じ文字を見つけたら先に個数を数えて累乗にまとめる
係数(数字の部分)は先に計算してしまう
→ $4m×2m×m=8m³$
最後に「指数の合計は合っているか?」をチェックする習慣をつくる
累乗を確実に書けるようになると、今後学習する式の計算や因数分解で大きな強みになります。
まとめ
文字式を書くときには「×を省略する」「数字は文字の前に書く」「複数の文字はアルファベット順に並べる」「マイナス符号は項の先頭につける」「同じ文字のかけ算は累乗を使う」といった基本ルールを押さえることが大切です。
これらのルールを守ることで、式が整い、計算ミスを減らし、数学をスムーズに理解できます。
普段の練習で意識的にルール通りに書く習慣を身につけましょう。
| 中学生のおすすめオンライン塾・家庭教師3選 | |||
|---|---|---|---|
ウィズスタディ |
家庭教師の銀河 |
WAM |
|
| 対象 | 中学生 高校生 |
中学生 | 中学生 高校生 |
| 授業料 (税込) |
9,800円~ (1科目) |
2,750円~ (1コマ) |
7,600円~ (週1回) |
| 入会金 | 27,500円~ | 22,000円 | 16,500円~ |
| 指導形式 | 学習塾 (オンライン) |
家庭教師 | 学習塾 (オンライン) |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | |
練習問題
問1
次の式を正しく計算して、できるだけ簡単にしなさい。
(1) $-(3x−5)$
(2) $2a−(b−3a)$
(3) $5−2y−(3−y)$
問2
次の式を展開し、同類項をまとめて簡単にしなさい。
(1) $(4m−n)−(m+2n)$
(2) $3x−(2x−5)$
(3) $−(a+b+c)+2a$
問3
次の式を、数字→文字の順に並べ替え、累乗を使って簡単に書きなさい。
(1) $x×x×3x$
(2) $4y×(−2y)×y$
(3) $2m×m×m×(−3)$
問4
ある文房具屋では、ノート1冊を$x$円、鉛筆1本を$y$円で売っています。
次の問いに答えなさい。
(1) ノート2冊と鉛筆3本を買ったときの代金を文字式で表しなさい。
(2) さらに「50円割引券」を使いました。割引後の金額を文字式で表しなさい。
(3) $x$=120、$y$=40 のとき、実際の支払金額を求めなさい。
解答
問1
(1) $−3x+5$
(2) $5a−b$
(3) $2−y$
問2
(1) $3m−3n$
(2) $x+5$
(3) $a−b−c$
問3
(1) $3x^3$
(2) $−8y^3$
(3) $−6m^3$
問4
ノート$x$円、鉛筆$y$円
(1) $2x+3y$
(2) $2x+3y−50$
(3) 2×120+3×40−50=240+120−50=310(円)
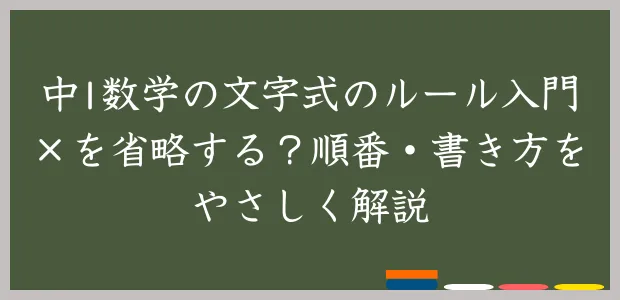
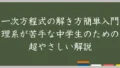

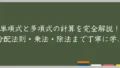
コメント