中学1年生の数学の最初のテーマである「正の数・負の数」は、数の世界の広がりを体感できる重要な単元です。
これまで「自然数」だけを扱っていた小学校の算数とは異なり、中学数学では0を中心に数直線の左右へ世界を広げ、負の数という新しい概念を学びます。
このページでは、正の数と負の数の定義や関係、さらに正の整数や自然数との違いまでを体系的に整理し、数のしくみを論理的に理解できるように解説します。
| 中学生のおすすめ学習塾3選 | |||
|---|---|---|---|
横浜予備校 |
WAM |
明光義塾 |
|
| 対象 | 中学生 | 中学生 高校生 |
中学生 高校生 |
| 授業料 (税込) |
29,700円~ (月額) |
7,600円~ (週1回) |
15,400円~ (週1回) |
| 入塾金 | 0円 | 16,500円~ | 11,000円 |
| 指導形式 | 学習塾 | 学習塾 (個別指導) |
学習塾 (個別指導) |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | |
数の世界を広げよう:正の数と負の数の導入
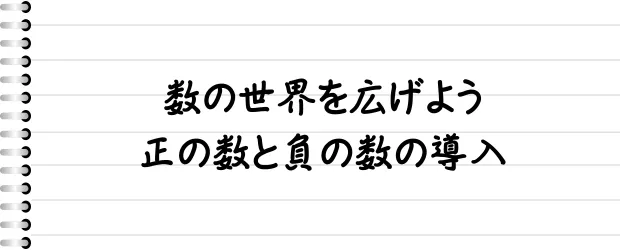
中学数学の最初に学ぶ大きなテーマが、「正の数・負の数」という新しい数の考え方です。
これまで小学校で扱ってきた数は、主に物の個数を数えるためのものでした。
しかし、中学生になると、もっと幅広い場面を数学で扱えるようにするために、数の世界そのものを大きく広げる必要があります。
ここでは、その入口となる「自然数のふり返り」から始め、「0の役割」そして「負の数」という新しい数がどのようにして誕生したのかを順に理解していきましょう。
これまで学んだ数(自然数)をふり返ろう
ここまで小学校で扱ってきた数は、主に「自然数」と呼ばれるものでした。
自然数とは、1、2、3、… のように、物の個数を表すために使われる数のことです。
たとえば、「りんごが3個ある」や「鉛筆を5本買った」といったように、実際に数えられる物を扱う場面では自然数が役立ちました。
しかし、自然数には一つ大きな弱点があります。
それは、0や負の数が含まれないという点です。
自然数の世界では、数が減っていく場面や、ある量を基準にして「どれだけ変化したか」を表す状況を扱うことが難しくなります。
「差がどれくらいあるか」を表したい場面でも、自然数だけでは考え方を整理しきれないのです。
このような不足を補うために、数学では新たに「数の世界」を広げていく必要がありました。
これこそが、中学数学で本格的に始まる「新しい数の考え方」への第一歩です。
0の登場と数の範囲の広がり
自然数をふり返ったうえで、次に登場するのが0という新しい数です。
0は「何もない量」を表す数として位置づけられますが、小学校では「数としての0」を学んだだけで、その数学的な役割まで深く触れる機会は多くありませんでした。
中学数学では、この0がとても重要になります。
0が加わることで、数は単なる「個数」ではなく、「位置」として考えられるようになるからです。
たとえば、数直線を思い浮かべてみると、0は真ん中に置かれ、その右側が大きい数、左側が小さい数という形で数が並びます。
このとき、0は単なる数字ではなく、右と左を分ける基準点として新しい役割を果たします。
この「0を基準にする」という考え方こそが、これから学ぶ正の数・負の数の全ての出発点になります。
0が登場したことで、数は物を数えるだけではなく、「位置」や「量の変化」を表現できるようになったのです。
0より小さい数を考える:負の数の出発点
0が「基準」になると、次の疑問が自然と生まれます。
それは、「0より小さい値を表すにはどうするのか?」ということです。
自然数にも0にも含まれない「0より小さい量」を表現するために、数学では新しい数が導入されました。
それが負の数です。
負の数は数直線の左側にあり、−(マイナス)という符号をつけて表します。
例えば、−1、−2、−3… のように並びます。
正の数が0より大きい数を表すのに対し、負の数は0より小さい値を表す役割を担っています。
0をはさんで、正の数と負の数は互いに対称的に並ぶという性質も、中学で大切になるポイントです。
負の数が導入されたことで、数学はさらに表現の幅を広げることが可能になりました。
特に、「差」や「変化量」を扱うとき、負の数はなくてはならない存在です。
具体例にはまだ触れませんが、この「変化を表せる」という性質によって、数学で表現できる範囲が大きく広がったことがわかります。
正の数とは何か:0より大きい数の定義
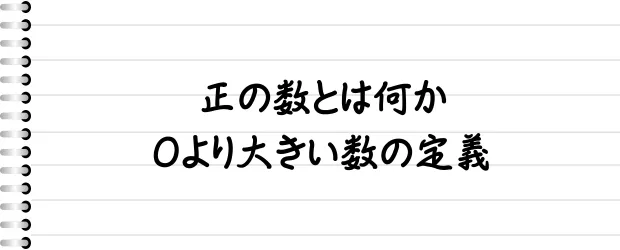
ここまでは、0を基準として数の世界が右にも左にも広がることを確認しました。
ここからは、そのうちの「0より大きい側」にある数、つまり正の数について詳しく学んでいきます。
正の数は小学校でも自然に扱っていましたが、中学数学ではより厳密に「定義としての正の数」を理解することが重要です。
正の数の考え方をしっかり押さえることで、今後学ぶ負の数や数直線、整数・有理数の扱いがよりスムーズになります。
ここでは、正の数の基本的な意味、数直線での位置、そして正の数に含まれる種類について整理していきましょう。
0より大きい数としての正の数
数学では、0より大きいすべての数のことを正の数と呼びます。
数を表すときにつける符号「+」は、この正の数を示すための記号です。
たとえば、+3と書かれていれば「0より大きい3」であることを明示していることになります。
ただし、一般的には符号の「+」は省略され、単に3と書いても正の数として扱われます。
これは、数学で数を書き表すとき、何も符号がついていなければ正の数を表すという約束事があるためです。
正の数には、整数だけでなく、小数や分数も含まれます。
つまり、1、2、3 といった自然数だけではなく、0.5や1.2、$\frac{1}{3}$や$\frac{5}{4}$といった数もすべて正の数です。
数学的に表すと、正の数は$x$>0を満たすすべての数と定義できます。
この定義を理解しておくと、今後の学習で扱う負の数との比較や、式の変形などがぐっと分かりやすくなります。
正の数を理解する際に大切なのは、「0を基準としたときに右側にある数すべてが正の数である」という見方です。
0より大きいという条件は、数の種類に関係なく共通する特徴であり、正の数の本質そのものです。
数直線上での正の数の位置
正の数のイメージをさらに深めるために役立つのが、数直線です。
数直線は、数を位置として表す図で、数の大小を視覚的に理解することができます。
数直線上では、中央に0が置かれ、その右側に正の数が並びます。
1、2、3、4… といった整数はもちろん、0.5や2.3のような小数も、$\frac{1}{2}$や$\frac{3}{4}$のような分数も、すべて0より右に位置します。
数直線で重要なのは、右に行くほど数が大きくなるという法則です。
これは整数でも小数でも分数でも変わりません。
たとえば、数直線上では3よりも5が右にあり、0.7よりも1.2が右にあります。
この「右側にあるほど大きい」という視覚的な理解が、正の数の大小比較を行う際の大きな助けになります。
また、正の数は0から右方向に無限に続いている点も押さえておきましょう。
整数の並びは 1、2、3、… と終わりなく続きますし、小数や分数を考えれば、二つの数の間にも必ず他の正の数が存在します。
このように、正の数の世界は非常に広く、どこまでも続いていることがわかります。
正の整数・正の分数・正の小数の整理
正の数と一口に言っても、その中にはいくつかの種類があります。
ここでは、主に扱う三つの分類について整理し、正の数の構造を理解しやすくしていきます。
まず正の整数は、1、2、3、4… といった自然数を指します。
いずれも0より大きく、小数点も分数の形も持たない数です。
小学校で最も多く触れてきた数であり、正の数の基本的な例でもあります。
次に正の分数です。
分数は「分子 ÷ 分母」の形で表されますが、正の分数は分子・分母がどちらも正の数になっているものを指します。
たとえば、$\frac{1}{2}$や$\frac{3}{4}$、$\frac{5}{3}$などが正の分数です。
これらは整数と整数の間にも存在し、正の数の世界をより細かく埋める役割を持っています。
そして正の小数は、0.3や2.5、1.75のように、小数点以下を持つ正の数です。
分数よりも視覚的にイメージしやすい場合が多く、整数と分数の中間のような役割を果たします。
重要なのは、これらすべてが「0より大きい」という共通点をもつ同じグループ(正の数)であるという点です。
正の整数は正の数の一部であり、正の分数や正の小数も同じ仲間です。
数学では、このような分類を意識しておくと、数の構造が整理され、計算や比較が理解しやすくなります。
| 中学生のおすすめオンライン塾・家庭教師3選 | |||
|---|---|---|---|
ウィズスタディ |
家庭教師の銀河 |
WAM |
|
| 対象 | 中学生 高校生 |
中学生 | 中学生 高校生 |
| 授業料 (税込) |
9,800円~ (1科目) |
2,750円~ (1コマ) |
7,600円~ (週1回) |
| 入会金 | 27,500円~ | 22,000円 | 16,500円~ |
| 指導形式 | 学習塾 (オンライン) |
家庭教師 | 学習塾 (オンライン) |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | |
負の数とは何か:0より小さい数の考え方
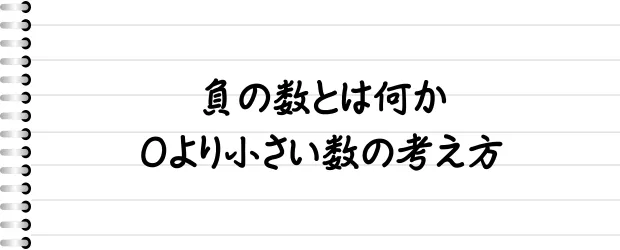
ここまでは、0より大きい数である正の数について学びました。
そこで扱ったように、数直線上では0を基準に右側へと数が広がっていました。
しかし、0を基準にして数を考えるとき、右側だけでは表しきれない値が存在することが分かります。
たとえば「0より小さい値」を扱いたい場面が出てくると、正の数だけでは表現ができません。
そこで数学では、0より小さい範囲の数を新しく考える必要がありました。
このときに導入されたのが負の数です。
ここでは、負の数の定義、数直線での位置、正の数との対応関係を整理し、0を基準に広がる数の世界の見方をさらに深めていきます。
0より小さい数としての負の数
負の数とは、「0より小さいすべての数」のことを指します。
数学的には$x$<0を満たす数すべてが負の数です。
この負の数には、必ず符号として 「−」 がつきます。
正の数と違い、負の数では符号を省略することはありません。
「−」がついていることで、「この数は正ではなく、0より小さい側にある」という意味を正確に表せるからです。
たとえば、−1、−2、−3 といった数は、0より小さい順に並んでいます。
正の数では符号(+)を省略できますが、負の数の場合は符号を省略すると意味が正の数と区別できなくなってしまうため、必ず「−」を明示して表記します。
重要なのは、符号「−」は「正の値ではない」という性質を示すために導入された記号だということです。
つまり、−3は単に「3とは別の記号がついている数」ではなく、「0より小さい位置にある」という全く異なる性質をもった数です。
0より小さい値を表すために負の数が必要であり、符号によって正と負が区別されるという仕組みが数学では重要になります。
数直線上での負の数の位置
負の数がどのような位置にあるかを理解するには、数直線を用いると非常にわかりやすくなります。
数直線では、中央に0を置き、右側には正の数が並びます。
そして、0の左側に新しく広がる領域が負の数の範囲です。
数直線の左側では、−1、−2、−3… のように並び、左へ進むほど値は小さくなります。
「小さい」というのは、正の数のときと同じで、数直線上の位置が左にあるほど数としての大きさが小さいということです。
たとえば、−3は−1よりも左側にあるため、−3の方が小さい数となります。
負の数同士を比べるとき、「右にある方が大きい」という点は正の数と同じです。
また、負の数も正の数と同じく、無限に広がっているという特徴を持っています。
−1の左には−2があり、−2の左には−3があり…と、どこまでいっても負の数は続きます。
このように、数直線を使うことで、正の数と負の数は0を中心に左右へ広がる形で対称的に存在していることが視覚的に理解できます。
正の数との対応関係を考えよう
負の数をより深く理解するためには、正の数との関係性を整理して考えることが効果的です。
正の数と負の数は、0をはさんで対称的な構造をもっています。
たとえば、1は−1に対応し、2は−2に対応するように、数直線上で0から同じ距離にありながら、反対側に位置します。
このように、大きさが等しく符号が逆の数どうしの関係を、数学では「絶対値が同じ」と表現します。
この対応関係を理解すると、「数は左右両方向に無限に広がる」という数学の世界の構造が見えてきます。
正の数が右に増えていくように、負の数は左に向かって無限に続きます。
そして、それぞれの正の数には対応する負の数が存在し、ちょうど鏡に映したような対称の関係を作っています。
このような対称性を押さえることで、数の大小の比較や、今後学ぶ整数・有理数の扱いがよりスムーズになります。
また、符号が変わることで数の性質が大きく変化する理由も理解しやすくなります。
正の数と負の数の関係:数直線で比較してみよう
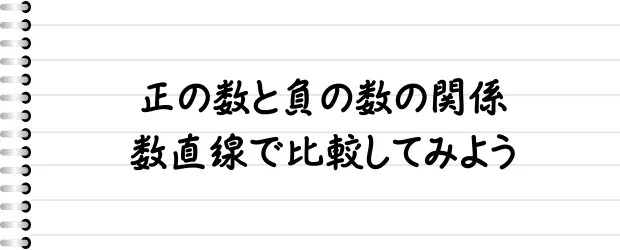
ここまでは、正の数や負の数がどのような場面で使われるのかを確認しました。
ここではその理解をさらに深めるために、正負の数を「数直線」という図を使って整理していきます。
数直線は、数の並び方や大小関係を視覚的に確かめられるとても便利な道具です。
「どの数が大きいか」「符号がつくとどのように意味が変わるのか」といった疑問も、数直線を使うと一気に整理できます。
ここでは、数直線の見方、正負の大小比較、符号の意味について詳しく説明していきましょう。
数直線の見方と0を基準にした位置関係
数直線とは、数を「位置」で表すための一本のまっすぐな線です。
線上には目盛りが一定間隔で打たれており、左から右へといくほど数の値が大きくなるというルールで並んでいます。
この並び方を理解しておくと、数の大小を直感的につかめるようになります。
まず、数直線の中心には必ず「0」が置かれます。
0は正の数でも負の数でもない「中立の数」であり、数直線を見るときの重要な基準点です。
0を境にして、右側には+1、+2、+3といった正の数が並びます。
右にいくほど数の値が大きくなるため、+3は+1より右側にあり、より大きい数です。
一方、0の左側には−1、−2、−3といった負の数が位置します。
負の数は「0より小さい数」であり、左に行くほど数は小さくなります。
例えば、−3は−1より左側にあるため、−3のほうがより小さい数であることがわかります。
正の数と負の数は、0を真ん中にして配置されているため、それぞれが対称的な関係にあります。
たとえば、+2と−2は数直線上で0をはさんで同じ距離に位置しています。
この対称性を理解しておくと、正負の性質をより深く理解できるようになります。
正の数・負の数の大小関係を読み取ろう
正負の数を比べるときには、「数直線上で右にある数ほど大きい」というルールを使います。
このルールさえ押さえておけば、どんな数どうしでも大小関係を判断できるようになります。
まず、正の数はどれも0より右側にあるため、必ず0より大きい数です。
一方、負の数はどれも0より左側にあるため、必ず0より小さい数です。
このことから、どんな正の数でも、どんな負の数より必ず大きくなります。
例えば、+1と−100を比べると、値だけを見ると100と1なので−100のほうが大きい気がするかもしれません。
しかし、数直線上では+1は右側、−100は左側にあるため、+1の方がはるかに大きい数です。
次に、負の数どうしを比べる場合を考えてみましょう。
負の数は左側に並んでいるため、「右側にある方が大きい」というルールは同じように働きます。
たとえば、−2と−5を比べると、−2の方が0に近い右側にあります。
そのため、−2のほうが−5より大きいという判断になります。
「−2と−5、どちらが大きい?」と聞かれると戸惑う人も多いですが、数直線で位置を確認すれば迷うことはありません。
大小比較をするときは、符号だけで判断するのではなく、必ず数直線上での位置をイメージすることが大切です。
これにより、数の関係がより確実に理解できるようになります。
符号と数の関係を整理しよう
正負の数を扱う上で欠かせないのが、数につく「+」「−」という符号の意味を理解することです。
符号は数の性質を示す大切な記号であり、これを正しく読み取れるかどうかが、中学数学以降の学習に大きく影響します。
まず、「+」の符号は「0より大きいこと」を表します。
ただし、+1を1と書いても同じ意味になるため、数学では+の符号は省略して表すのが一般的です。
このため、特に理由がない場合は正の数は符号をつけずに書きます。
一方、「−」の符号は「0より小さいこと」を表します。
−の符号は省略できないため、負の数には必ず−がつきます。
また、符号は単に「大きい・小さい」を表すだけではなく、0から見てどちらの方向に位置しているかを示す役割もあります。
0を境にして符号が変わることで、数の世界「一方向に大きくなる自然数の世界」から「正負の両側に広がる世界」へと発展しました。
この符号の概念を理解することは、数学の基礎を築くうえで非常に重要です。
| 中学生のおすすめ学習塾3選 | |||
|---|---|---|---|
横浜予備校 |
WAM |
明光義塾 |
|
| 対象 | 中学生 | 中学生 高校生 |
中学生 高校生 |
| 授業料 (税込) |
29,700円~ (月額) |
7,600円~ (週1回) |
15,400円~ (週1回) |
| 入塾金 | 0円 | 16,500円~ | 11,000円 |
| 指導形式 | 学習塾 | 学習塾 (個別指導) |
学習塾 (個別指導) |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | |
正の数・正の整数・自然数の違いを整理しよう

上記では、数直線を使って正の数と負の数の関係を確認しました。
ここからさらに数の理解を深めるために、「正の数」「正の整数」「自然数」という、よく似ていて混同しやすい言葉の違いを丁寧に整理していきます。
これらを正確に区別しておくことは、数学の基礎をしっかり固めるうえで非常に大切です。
同じ「正の数」という表現でも、その中に含まれる範囲は用語によって大きく変わります。
ここでは、まず数の種類を広い視点でとらえ、そのうえで正の数・正の整数・自然数の関係を順を追って整理してみましょう。
自然数・整数・分数など数の分類を確認しよう
数学で扱う「数」には、実はさまざまな種類があります。
日常生活では1、2、3といった数や、−1や0などの整数を中心に使いますが、数学ではさらに細かい値を表すために分数や小数も用いられます。
まずは、数の分類を大きな枠組みとして理解しておくことが重要です。
最初に出てくるのは「自然数」です。
自然数とは、ものの個数を数えるときに使う数で、1、2、3、4…と続く、最も基本的な数の集まりです。
中学数学では通常0は自然数に含めません。
自然数は数の世界の出発点とも言える存在で、ここからさらに数の範囲は広がっていきます。
次が「整数」です。
整数には、…−3、−2、−1、0、1、2、3…のように、負の数・0・正の数がすべて含まれます。
自然数に比べて、整数は0を含み、さらに負の領域まで広がった範囲といえます。
「自然数は整数に含まれる」という関係がここで成り立ちます。
さらに数の範囲を広げると、「分数」や「小数」が登場します。
これは整数と整数の間を細かく埋める数で、例えば$\frac{1}{2}$や0.3などがその例です。
これらの数を使うことで、より細かい量や変化を表せるようになります。
このように、自然数から始まり、整数、分数・小数へと数の世界は徐々に広がっていきます。
この広がりが数学の数体系を築き、今後扱うさまざまな内容の基礎となります。
正の数・正の整数・自然数の定義を比べよう
ここからは、本題である「正の数」「正の整数」「自然数」の違いを具体的に確認していきます。
どれも「0より大きい数」を含んでいるため、一見すると同じ意味のように感じますが、それぞれが示す範囲は異なっています。
正確な定義を理解すると、問題を解く際の迷いがなくなり、数学の世界をより明確にとらえられるようになります。
まず「正の数」とは、0より大きいすべての数を指します。
ここには整数だけでなく、小数や分数も含まれます。
たとえば、1、2、10といった数はもちろん、$\frac{1}{2}$や0.3なども正の数に含まれます。
正の数は最も広い概念であり、「正である」という性質だけに注目した集まりと言えます。
次に「正の整数」です。
これは整数の中で0より大きい数、つまり1、2、3、4…と続く数のことです。
どの数も整数であることが条件となるため、$\frac{1}{2}$や0.7のような分数・小数は含まれません。
そして「自然数」です。
自然数は1、2、3…のように、物の個数を数えるときに使う数です。
中学数学では0を含めないのが一般的で、この場合「正の整数」と自然数は同じ範囲になります。
ただし、高校数学や大学数学では自然数に0を含める場合もあり、文脈によって異なることがあるため注意が必要です。
これらの関係をまとめると、
「自然数は正の整数に含まれていて、正の整数は正の数に含まれている」
という包含関係が成り立ちます。
つまり、自然数はより大きな集合である正の数の中に含まれているという構造になっています。
図で見るそれぞれの数のつながり
用語の違いを言葉で整理できたら、図として関係性を整理しておくと理解がさらに深まります。

まず、一番中心となる小さな集合が「自然数」です。
これは1、2、3…と続く数の集まりで、最も基本的な範囲です。
その外側には自然数とほぼ同じ意味を持つ「正の整数」が重なります。
さらにその外側にあるのが「正の数」です。
正の数には正の整数に加えて、正の分数や正の小数といった幅広い数が含まれます。
そのため、「自然数は正の整数に含まれていて、正の整数は正の数に含まれている」という同心円のような図を思い浮かべると関係がつかみやすくなります。
整数全体まで広げると、中央に0があり、その右側に正の領域、左側に負の領域が広がる形になります。
数の分類を図で整理しておくと、学習が進んだときにも迷いにくくなるため非常に有効です。
まとめ
中学数学で学ぶ「正の数・負の数」は、数の範囲を広げる大切な第一歩です。
0を基準にして右側(正の数)と左側(負の数)が対称的に広がる構造を理解すると、数のしくみが明確になります。
また、「正の数」「正の整数」「自然数」は似た言葉でも指す範囲が異なるため、定義を整理しておくことが重要です。
数直線を通してそれぞれの関係をつかむことで、今後学ぶ整数や有理数の基礎がよりしっかりと身につくでしょう。
| 中学生のおすすめオンライン塾・家庭教師3選 | |||
|---|---|---|---|
ウィズスタディ |
家庭教師の銀河 |
WAM |
|
| 対象 | 中学生 高校生 |
中学生 | 中学生 高校生 |
| 授業料 (税込) |
9,800円~ (1科目) |
2,750円~ (1コマ) |
7,600円~ (週1回) |
| 入会金 | 27,500円~ | 22,000円 | 16,500円~ |
| 指導形式 | 学習塾 (オンライン) |
家庭教師 | 学習塾 (オンライン) |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | |
練習問題
問1
次の数を 小さい順 に並べかえましょう。
3, −2, 0, 5, −4
問2
次の大小関係が成り立つように、□に「>」または「<」を入れましょう。
1.
−3 □ −1
2.
2 □ −5
3.
−4 □ 0
問3
次のうち、正の数 に当てはまるものをすべて選びましょう。
−3, 0, $\frac{1}{2}$, 4, −1.2
問4
次のうち、自然数ではあるが正の数のうち整数に限定したときでも同じ範囲に含まれるもの(=正の整数) をすべて選びましょう。
1, 0, 5, 2.5, −3
問5
次の数を「自然数」「正の整数」「正の数」のどれに分類できるか考え、それぞれグループ分けをしましょう。(複数にまたがる場合あり)
3, $\frac{3}{4}$, −2, 0
問6
あるクラスで、温度の変化を調べる実験を行いました。午前9時の時点で気温は2℃でした。その後、
① 正午に気温が0℃になった
② 午後3時には−3℃になった
これについて、以下の問いに答えましょう。
(1)
午前9時から正午にかけて、気温は「正の変化」でしょうか、「負の変化」でしょうか?
(2)
正午の0℃から午後3時の−3℃は、数直線上でどちらの方向に変化したといえますか?
(3)
午前9時の2℃と午後3時の−3℃では、どちらが大きいですか?
数直線の位置関係を使って説明しましょう。
解答
問1
小さい順:
−4, −2, 0, 3, 5
解説:数直線で左から右へならべた順(左ほど小さい)。
問2
1.
<
2.
>
3.
<
問3
正の数に当てはまるもの:
$\frac{1}{2}$, 4
解説:正の数は「0より大きいすべての数」。−3は負、0は正でない(中立)、−1.2は負。
問4
正の整数(=自然数)に当てはまるもの:
1, 5
解説:正の整数は1,2,3,…。0は含めない(中学数学の扱い)、2.5は小数、−3は負。
問5
各数が該当するグループ(該当するものすべて):
3:自然数、正の整数、正の数
$\frac{3}{4}$:正の数(ただし自然数・正の整数ではない)
−2:(どれにも該当しない)※負の整数であり「正」の集合には入らない
0:(どれにも該当しない)※中学扱いでは自然数・正の整数・正の数のいずれでもない
解説:自然数=1,2,3…、正の整数は同じ範囲(中学では同義)、正の数は整数・分数・小数を含む広い数。0と負の数は「正」には含まれない。
問6
(1)
負の変化(気温が下がった)。
解説:午前9時が2℃で正午が0℃へ。0℃の方が小さいので値は減っており、変化は負(減少)。
(2)
数直線で左方向に変化した(0→−3 は 0 の左へ進む)。
解説:0から−3へは負の方向(左)への移動。値は小さくなっている。
(3)
午前9時の2℃のほうが大きい。
解説:数直線上で 2(右側)は−3(左側)より右にあるため、2℃>−3℃。また一般にどんな正の数でもどんな負の数より大きい。

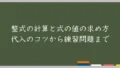
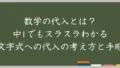

コメント