突然ですが、学生の皆さんは、試験直前期はどのような勉強をしているでしょうか?
1人ひとり勉強の仕方や内容は違うと思いますし、どんな教科であっても試験直前の勉強は大切になりますが、理系科目に限って言えば、その重要性はさらに高いと言えます。
数学や理科の問題は、基本を押さえていれば得点できる問題も多い反面、理解が不十分だと一気に点数を落としてしまうという特徴があります。
そういった特徴があるがゆえ、特に
- 「範囲が広すぎてどこから手をつければいいかわからない」
- 「今さら新しい内容をやっても間に合わないのでは?」
- 「公式は覚えているのに、実際の問題になると解けない」
このような不安や悩みを持つ学生さんは少なくありません。
だからこそ、試験直前の戦略的な学習が点数を左右します。
直前1週間の使い方次第で、実力を「点数として見える形」にできるのが理系科目の特徴です。
このページでは、
- 試験1週間前〜3日前までの勉強内容
- 試験3日前〜前日までのやるべきこと
- 理系科目に特化した具体的な勉強法
について、順序立てて丁寧に解説していきます。
理系科目の直前期に必要な3つの考え方
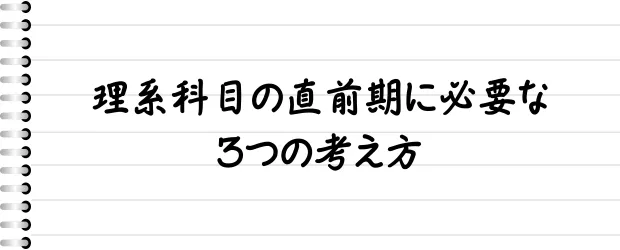
本題の直前期の勉強法や勉強内容を解説していく前に、まずは試験直前の「考え方」に焦点を当てて話を進めていきます。
「考え方」に焦点を置く理由は、「考え方」を整えることが、試験直前の学習で最も重要だと筆者は考えているからです。
考え方を理解すると、効率的な勉強ができるようになるため、効率のよい学習を実現するためには、以下の3つの考え方を押さえておく必要があります。
①全範囲をカバーしようとしない
1つ目は試験範囲の全体をカバーする勉強はしないということです。
理系科目は内容量が多く、すべてを完璧に網羅しようとすると、かえって知識が中途半端になってしまいます。
重点分野を決めて「捨てる勇気」も持つことが重要です。
ただし、学校の定期テストなどの場合は、範囲が狭い時もあるので、そういったときはしっかりと範囲内の知識を振り返っておくことも重要です。
そのため、ケースバイケースで調整していけるようにしましょう。
②基礎・基本に戻る
2つ目は基本を重要視することです。
直前期ほど「応用よりも基本」が大切です。
公式や定義、基本問題を確実に得点できるようにするだけで、試験全体の6〜7割はカバーできます。
「確実に取れる問題」を落とさないことが第一優先です。
③弱点補強よりも「できることを確実にする」
3つ目はできる部分に時間を割くということです。
時間がない中で苦手を克服しようとしても、うまくいかないことが多いです。
そのため直前期は「得意な単元を伸ばす」か「あと少しで点になる分野に絞る」のが賢明な判断です。
試験1週間前から3日前までの過ごし方:理系は「絞って」復習する
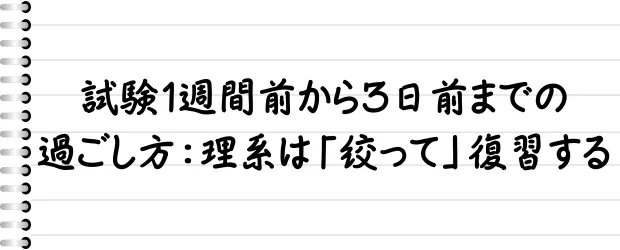
上記の説明で、試験直前期の考え方をお伝えしたところで、早速試験直前の過ごし方を見ていきます。
この時期は、まだ少し余裕がある時期でもあります。
焦って手当たり次第に勉強するのではなく、「今の自分にとって必要な範囲」に集中しましょう。
数学と理科科目のそれぞれのこの時期の取り組む内容を見ていきましょう。
数学:苦手単元の見直しと「基礎問題」の徹底演習
数学は、直前で伸びやすい科目でもあります。
なぜなら、試験に出やすい「基本問題」や「典型問題」が多いからです。
次のステップを参考にして学習を進めましょう。
ステップ1:苦手単元の洗い出し
自分のこれまでのミスや不安な分野をリストアップから始めましょう。
リストアップをする際は、模試・問題集・ノートの見直しが有効です。
ステップ2:基本問題だけを解き直す
この時期はまだ応用問題は一旦脇に置き、公式の使い方が問われる基本問題を繰り返すことで「知識を使える形」に変えていきます。
ステップ3:典型的な出題パターンを整理
例えば、連立方程式や因数分解など、「問題を見た瞬間にやるべき解法がわかる」状態を目指して、ノートなどにパターンをまとめていくと、記憶にも定着しやすくなります。
この際のポイントは、解けなかった問題は「なぜ間違えたのか」「次はどうすればいいか」を必ず書き残すことです。
理科科目:重要事項の再確認と「基本知識の応用力」を鍛える
理科科目は知識量が多く、「暗記だけで乗り切ろうとする」と失敗します。
そのため重要なのは、知識をどう使うかです。
知識の使い方を身につける学習ステップを見ていきましょう。
ステップ1:教科書・資料集で知識の穴を埋める
理解が不十分な用語・公式・グラフなどを教科書を中心に「見て→読んで→書いて」覚えることから始めましょう。
特に定期テスト範囲で明記されている単元は、「出る前提」で対策を進めましょう。
ステップ2:基本問題集やプリントを再活用
数学と同じく、この時期に使うべき教材応用問題などが掲載されているものではなく、「基本問題集」と「学校配布プリント」です。
特に以下のような問題を重点的に復習しましょう。
- 計算問題(物理・化学)
- 用語の正誤(生物・地学)
- 実験手順とグラフ解釈
ステップ3:解き直しノートをつくる
理科科目では、「間違えた問題」と「その理由」を1冊にまとめておくと、短時間で効率よく復習できます。
まとめておいたのーとそ使って学習する際、最も効果が出るのは「なぜその答えになるか?」を自分の言葉で説明できるようにすることです。
学習効率を高める3つの生活習慣
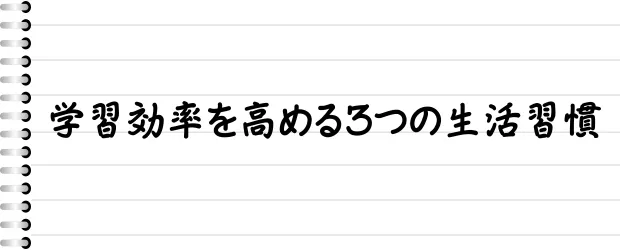
ここまでで、1週間前から3日前までの期間の勉強方法を紹介してきました。
ですが、どれだけ良い学習法を実践しても、集中力・記憶力が低下していれば学習の質は下がります。
そのため、理系科目に取り組むときほど、生活リズムも意識しましょう。
①睡眠時間の確保
まず最も重要なことは睡眠時間です。
理想は7〜8時間と言われていますが、ここは人によって違いがある部分なので、日中すっきりと頭を回せるぐらいの時間を必ず確保するようにしましょう。
また、徹夜は絶対にNGです。
記憶の定着や思考力を高めるには、睡眠の質と量が不可欠です。
②バランスの良い食事
次に、食事のバランスです。
特に、炭水化物を抜くダイエットや、偏った食事は集中力を低下させます。
上記を踏まえたうえで、試験1週間前はエネルギーをしっかり摂取することが学習の基本です。
③適度な運動やストレッチ
3つ目は適度な運動をすることです。
1日5分の軽いストレッチや散歩でもOKです。
気分転換にもなりますし、理系科目は頭を使うため、脳に酸素が届く状態を保つことが大切にもなります。
試験直前3日前からの学習は“仕上げ”のフェーズへ
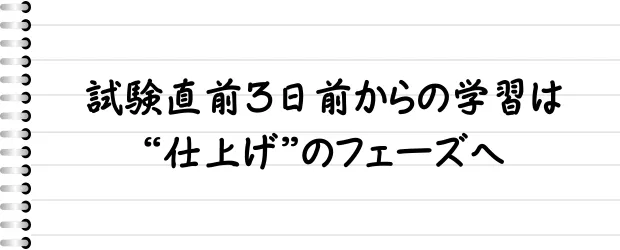
話を直前期の学習方法に戻します。
1週間前から取り組んできた基礎固めや苦手克服が一通り終わったら、試験3日前からはいよいよ総仕上げに移行する段階です。
この時期は、これまでにインプットしてきた知識や解法を「正確にアウトプットできるか」を確認することが最大の目的になります。
新しいことに取り組むのではなく、「わかることを確実に得点に変える」ための作業に集中しましょう。
試験3日前:知識と解法の定着を徹底する
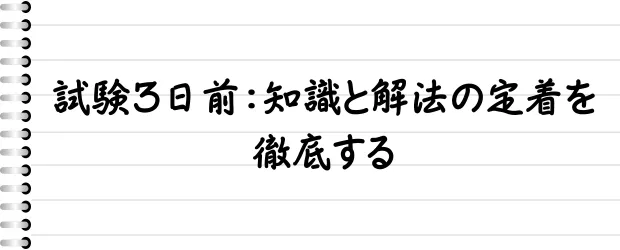
では、3日前からの勉強方法について見ていきます。
数学:反復練習で“解法の自動化”を目指す
この段階での数学の勉強は、「時間内に正確に解けるか」を意識して進めていきましょう。
これまでに取り組んだ問題の中から、解き方に不安が残るもの、間違えたもの、時間がかかったものをピックアップし、再度解いてみることが有効です。
具体的な学習方法
- 公式集や自分でまとめたノートをざっと見返し、公式の意味・使い方を整理
- 過去問・模試の見直しに重点を置き、「自分が解けなかった問題だけ」を集中的に解き直す
- 解法パターンを音読しながらノートに整理し直す
この時期の注意点
この時期の取り組みについては、応用問題にこだわりすぎず、「出るパターンをいかに確実に得点できるか」にフついて焦点を当てることを重視してください。
理科科目:科目ごとの特性に合わせた総復習を
理科科目は、物理・化学のように論理的思考や計算が必要なものと、生物・地学のように知識の正確な暗記が必要なもので、最終確認の方法が異なります。
物理・化学(論理・計算型)
- 公式一覧表を見ながら、「どんな問題でその公式が使われるのか」までイメージを持つ
- グラフ問題や単位換算など、うっかりミスをしやすいところを重点的に演習
- 間違えた問題は「なぜ間違えたのか」を紙に書き出す(公式の誤用/思い込み/計算ミスなど)
生物・地学(暗記型)
- 教科書やノートをパラパラと見返しながら、図や表を使って頭の中を整理
- 一問一答形式で知識を確認し、「あいまいな用語」や「よく出る例外事項」を潰していく
- 実験や観察に関する内容も、手順・結果・理由の3点セットで確認する
それぞれの科目の特徴を把握したうえで、自分の苦手なところに重点を置きながら学習を進めていくのもポイントになります。
試験2日前:ミスを最小限にする確認作業を徹底
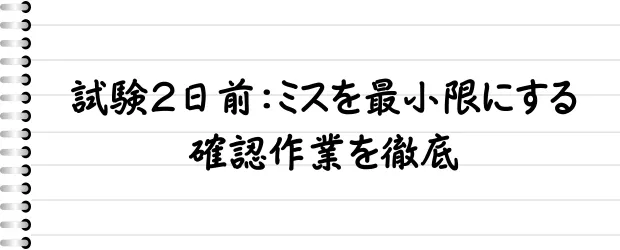
知識や解法がある程度定着してきたら、次にすべきことは「ミスをしない仕組み作り」です。
特に理系科目は、うっかりした計算ミスや単位の見落としが失点に直結するため、この時期にそれらを減らす工夫をしておきましょう。
数学:公式や典型パターンを最終確認
数学は、前日に焦って詰め込むのではなく、2日前のうちに重要公式や頻出問題のパターンを最終確認しておくのがおすすめです。
ポイント
- 公式は「覚えているか」だけでなく、「どの場面で使うか」まで明確に
- 教科書レベルの典型問題を“解法の手順”ごと声に出して説明する練習も効果的
- 実際の試験時間を想定して、過去問の1セットを時間を計って解いてみるのもおすすめ
理科科目:グラフ・実験・典型問題の再演習
理科科目では、知識確認に加えて、「資料の読み取り能力」も問われる問題が増えています。
実験の手順やグラフ問題を通じて、知識と応用力の接続を意識しましょう。
やっておくべきこと
- 実験内容の再確認(手順/目的/結果/考察)
- よく出る実験問題を何題か時間を計って演習
- 公式の変形・単位換算問題の確認で、計算に慣れておく
この時期は「これまで何度も出てきた問題」を考えなくてもすぐに手が動く状態にしておくと、試験本番で大きな安心感につながります。
試験前日:新しいことはやらない!「できる」を固めて安心を得る
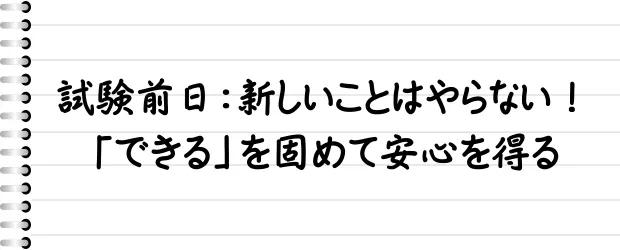
試験前日はつい不安になって、新しい問題や難しい問題に手を出したくなるかもしれませんが、それは逆効果です。
新しい知識の定着には時間がかかるため、直前に詰め込んでもほとんど効果がありません。
むしろ、今まで勉強してきた内容を整理し、頭の中をスッキリさせておくことが、試験当日にベストなパフォーマンスを発揮するために重要です。
数学:公式の“使い方”をイメージできるかが鍵
数学は公式だけ覚えていても、本番で使えなければ意味がありません。
前日は、「この公式はどういう問題で出るか」「どこでミスをしやすいか」をイメージしながら確認していきましょう。
前日にやるべきこと
- 公式の使いどころを「例題」とセットで思い出す
- 過去問から「基本問題だけ」を抜き出して演習(難問はスルーでOK)
- 試験時間と同じ時間で軽く1セット解いて、時間感覚を確認
理科科目:実験と公式の整理で「最後の仕上げ」
理科科目では、出題されやすい「図表」「グラフ」「公式」について、目と頭を使って整理しておくことが大切です。
おすすめの学習法
- 公式一覧を10分程度見返す→その場で例題を1〜2問解いて、記憶を呼び起こす
- 教科書に掲載されている実験の図を見て、「どういう流れで結果が得られたか」を思い出す
- 一問一答や用語カードをサラッと確認して、「覚えきれてない単語」をその場で暗記
次はいよいよ試験当日。心身のコンディションも整える段階へ
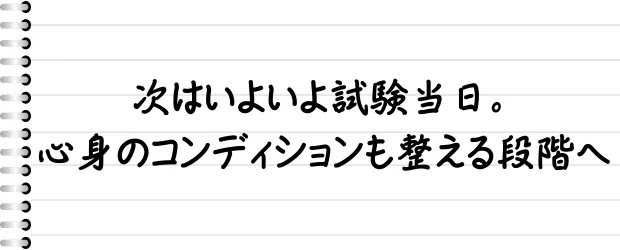
ここまでくれば、学習の準備はほぼ完了です。
次に意識すべきは「本番で自分の力を出し切るための環境づくり」です。
どれだけ勉強しても、体調不良や緊張で力が出せなければ意味がありません。
ここからは、試験当日の心構えと、実際のスケジュール例について詳しく紹介していきます。
知識の完成度だけでなく、当日の“整え方”が得点力を左右する
ここまで、理系科目の試験直前1週間にどのような勉強を行うべきかを時系列で確認してきました。
1週間前〜3日前の基礎固め、そして3日前〜前日までの総仕上げを終えたら、いよいよ迎えるのが試験本番当日です。
この日は、単に知識や公式を覚えているかどうか以上に、「これまでの学びをいかに安定して発揮できるか」が問われる日です。
つまり、試験当日の朝からの過ごし方や心の持ち方が、学力と同じくらい大切になってきます。
試験当日の朝の行動:脳と身体を“本番モード”に整える準備
まずは試験当日の朝の行動から見ていきます。
前日までの復習が終わったら、当日は「心身の調整」に集中しよう
試験当日の朝は、前日の勉強の延長として何かを詰め込もうとするのではなく、脳と体を正常に起動させることを最優先に考えるのが鉄則です。
十分な睡眠が最強の準備:記憶も集中も“寝た者勝ち”
よく「直前まで粘って勉強したい」と思いがちですが、睡眠不足は思考力や注意力、判断力に明らかな悪影響を及ぼします。
上述もしましたが、日中に頭が回転するぐらいの睡眠時間は確保し、脳が冴えた状態で試験に臨むことが、何よりの武器になります。
朝食は必須。脳のエネルギー源を切らさないために
また、試験当日の朝は必ず朝食を摂るようにしましょう。
朝食をとらないと血糖値が不安定になり、試験中に頭がぼんやりしたり、集中できなくなったりする恐れがあります。
おすすめの朝食内容は以下のとおりです。
- ごはん/パン(主食でエネルギー供給)
- 卵/納豆/ヨーグルト(脳の働きを支えるタンパク質)
- バナナやフルーツ(即効性のある糖分とビタミン)
ここで注意点ですが、普段コーヒーなどのカフェインが含まれているものを摂取しない人は可能なら避けるのが無難です。
カフェインは、普段から摂取している人のみ推奨します。
慣れていない人は不安感やトイレが近くなる原因にもなります。
試験前のストレッチで緊張を緩める
起床後に軽くストレッチや深呼吸を行うことで血行が良くなり、脳の働きが活発になります。
身体と心を落ち着いた緊張感に整える効果もあるので、リズムをつける意味でもぜひ試してみてください。
試験直前:最後の1時間は「安心の確認」で整える時間
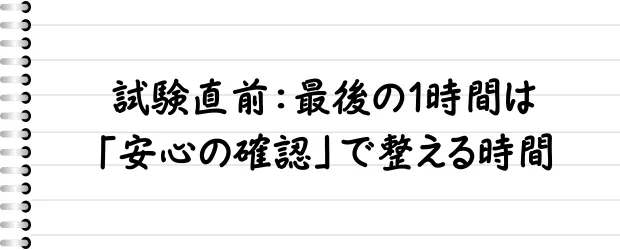
当日の朝は上記のように過ごすのがおすすめです。
そして、試験開始までの時間も有効に使うようにしましょう。
勉強の追い込みはしない。「確認の時間」と割り切る
試験会場に着いてからの時間も重要です。
ここで焦ってあれもこれもと復習しようとすると、「できていないところ」が気になり始め、自信が削がれてしまうことがよくあります。
なので、会場についてからは今まで学習してきたことを確認する時間と割り切って振り返りを行うようにしましょう。
直前には「できる問題だけ」を見返そう
振り返りを行うこの時間におすすめなのは、「自分が確実に解ける」問題やノートを見ることです。
例えば、
- 過去問で解けた問題の解答を見直す
- 公式まとめや自作の解法ノートを見て、自信を再確認する
などが効果的です。
自分にとっての安心材料を確認する時間として使いましょう。
試験前の心の整え方:不安を「なくす」のではなく「扱う」
理系科目では計算や時間管理のプレッシャーがかかりやすく、誰でも緊張します。
そのとき、「不安をなくそう」とするのではなく、「不安はあって当然」と受け入れたうえで行動することが大切です。
こうした気持ちを持ったうえで、リラックスして臨むようにしましょう。
リラックスするためのコツは例えば下記のようなものがあります。
- ゆっくりと深呼吸を3回行う
- 手をギュッと握って離す(緊張と弛緩を意識する)
- 呼吸とともに「できることに集中しよう」と自分に声をかける
自分が最もリラックスできる方法を探ってみて、実践してみてください。
試験中の時間配分戦略:理系科目の“計算ミス”を減らすコツ
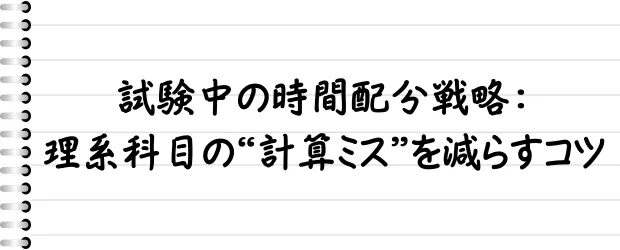
ここまでは、試験前までの準備や気持ちの作り方を紹介してきました。
ですが、ここまでの準備を発揮するのは試験の本番の取り組み次第です。
最後に試験本番の取り組み方を見ていきます。
解ける問題から解く。「満点」ではなく「高得点」を狙う
試験が始まったら、まずはざっと全体を見渡し、自分が確実に解けそうな問題を先に片づけるようにしましょう。
理系科目では、1問に固執して時間を浪費すると、解けるはずだった他の問題まで落としてしまう可能性があります。
時間配分の目安を持っておくと安心
また、時間配分をあらかじめ決めておくのも効果的です。
例えば、50分で5問なら1問あたり10分が基準になります。
ですが、以下のような方針をもっておくと、現実的に動きやすくなります。
- 5分以内で解けそうなものは即答
- 難しい問題は「飛ばしてマークだけ」しておく
- 試験終了10分前は「見直しタイム」として確保する
ケアレスミス防止も「戦略」の一つ
そして、必ず見直しをする時間を設けるようにしてください。
最後の5分〜10分での見直しが、計算ミスや単位ミスを減らします。
特に理系科目では、「途中式の見直し」や「単位の再確認」が点数に直結するため、あらかじめ時間を残すつもりで臨むのがおすすめです。
まとめ
このページでは理系科目の試験直前期の勉強方法やその内容、試験当日から本番中の向き合い方まで解説してきました。
改めてもう一度、大切なポイントを振り返ってみましょう。
試験直前期〜当日で特に意識したいポイントは下記の通りでした。
| タイミング | 意識すべきこと |
|---|---|
| 1週間前〜3日前 | 基礎と苦手克服、基本問題の徹底演習 |
| 3日前〜前日 | 解法パターンと公式の整理・暗記 |
| 当日朝 | 睡眠・朝食・ストレッチで脳と体の準備 |
| 試験直前 | 自信のある内容の確認で心を整える |
| 試験中 | 時間配分と戦略的な解答順で得点最大化 |
理系科目が苦手な人も、得意な人も、「本番で自分の力を出し切れるかどうか」は準備の質と当日の過ごし方次第です。
焦るのではなく、丁寧に・冷静に・計画的に進めることが、最も確実な成功の道です。
自分がこれまで積み重ねてきた努力は、必ず形になります。
ぜひ今回紹介した方法を実践し、自信を持って試験に臨んでください。
自分に合った試験直前期の準備ができるようになっていれば、必ず結果はついてくるようになります。
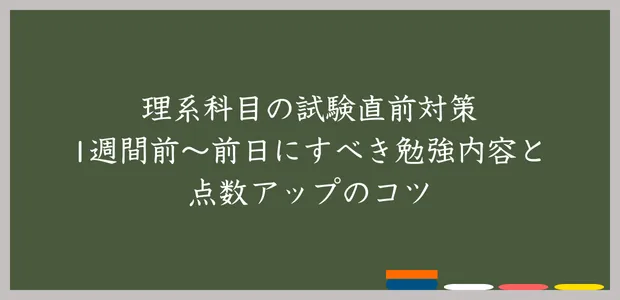








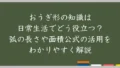
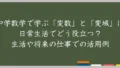
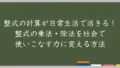
コメント