数学が苦手…「どうして自分だけできないんだろう?」と悩んでいる中学生・高校生は、決して少数派ではありません。
その理由は能力不足ではなく、実は勉強の方法や心の持ち方に大きく左右されています。
このページでは、数学が苦手・嫌いになる原因から、具体的な克服のコツ、今日からできる小さな一歩まで、等身大の悩みに寄り添いながら解説します。
誰でも始められる工夫や成功例を交え、「数学が苦手」「数学できない」「数学が嫌い」を乗り越えたい学生さんを力強くサポートします。
“できない”を“できる”に変えるヒントを、一緒に見つけていきましょう。
| 中学生のおすすめ学習塾3選 | |||
|---|---|---|---|
横浜予備校 |
WAM |
明光義塾 |
|
| 対象 | 中学生 | 中学生 高校生 |
中学生 高校生 |
| 授業料 (税込) |
29,700円~ (月額) |
7,600円~ (週1回) |
15,400円~ (週1回) |
| 入塾金 | 0円 | 16,500円~ | 11,000円 |
| 指導形式 | 学習塾 | 学習塾 (個別指導) |
学習塾 (個別指導) |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | |
なぜ「数学が苦手」と感じるのか?中高生に多い3つの理由
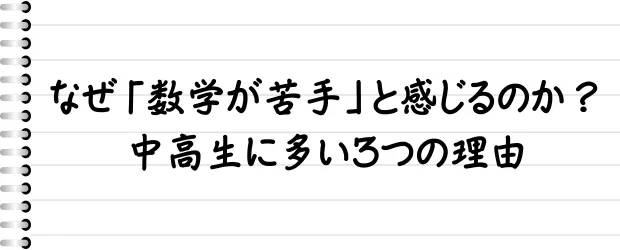
数学に苦手意識を持つ中学生・高校生はとても多く、「自分だけできない」と悩んでしまう人も少なくありません。
しかし実際には、数学が苦手になる理由の多くは「勉強の仕方」や「心の持ち方」にあります。
ここでは、数学嫌いが生まれる代表的な原因を5つの視点から見ていきましょう。
どれも決して「能力の差」ではなく、誰にでも起こりうるものです。
計算ミスや理解不足が重なって「数学ができない」と思い込む
多くの学生さんが、「計算ミス=自分の能力が低い」と感じてしまいます。
しかし、計算ミスの多くは焦りや確認不足、あるいは単純に基礎練習量が少ないことが原因です。
特にテスト中は時間に追われて焦ってしまうため、普段はできる問題でもミスをしてしまうことがあります。
一度の失敗をきっかけに「やっぱり自分はダメなんだ」と自己否定してしまう心理もよく見られます。
こうした思い込みが積み重なると、「数学=苦手」という固定観念が生まれてしまうのです。
このような固定観念への対処法としては、ミス分析ノートを作るのがおすすめです。
どんな問題で、どんなミスをしたのかを書き出して整理することで、同じ失敗を防ぎやすくなります。
また、間違い直しを習慣化することで、ただ解くだけの勉強から「できるようにする勉強」に変わります。
覚えておいてほしいのは、間違いの数よりも修正力の方が大切ということです。
教科書の説明が難しく感じてしまい、数学が嫌いになる瞬間
次に多いのが、「教科書の説明が難しすぎてわからない」というケースです。
数学の教科書は、言葉が抽象的で説明の省略も多く、初めて学ぶ人には理解しづらい構成になっています。
さらに、授業でも「途中の説明を飛ばして進める先生」も多いため、ついていけないと感じる学生さんが出てきます。
このような事態に直面した時、「わからない」と思った多くの人は、恥ずかしさから質問できずにそのままにしてしまうということも少なくありません。
この経験が積み重なると、いつの間にか「数学=苦手科目」という印象が固定されてしまいます。
そんなときは、わかりやすい市販教材や動画解説を活用するのがおすすめです。
最近では、例題ごとに丁寧に解説してくれるYouTubeや学習アプリも多くあります。
また、学校の先生や塾の講師に個別に質問するだけでも理解がぐっと深まります。
大切なのは、「説明がわからない=頭が悪い」ではないということです。
説明の仕方があなたに合っていないだけです。
公式の丸暗記に頼りすぎて応用ができなくなる理由
「公式を覚えたのにテストでは解けない」と感じたことはありませんか?
これは、「覚える=理解している」と勘違いしてしまう勉強法によく見られるパターンです。
公式を丸暗記しても、問題の出方が少し変わるだけで対応できなくなるのは、「なぜその公式が成り立つのか」を理解していないためです。
たとえば二次方程式の解の公式を、自分で導き出せるように練習すると、「公式の意味」が自然と理解できます。
図を描く習慣をつけたり、自分の言葉で説明してみる練習も効果的です。
暗記は必要なステップですが、それだけで終わらせないことが大切です。
理解する力こそが応用力の土台になります。
テストで結果が出ずに「自分は数学が苦手」と決めつけてしまう
「テストの点数が悪い=自分はダメだ」と思ってしまう学生さんも多いでしょう。
しかし、テストの点数は必ずしも実力を正確に表していません。
理解不足ではなく、時間配分のミスや焦り、ケアレスミスが原因のことも多いのです。
1回のテスト結果で「自分は数学ができない」と決めつけてしまうと、次の勉強への意欲まで下がってしまいます。
これは「固定観念化」と呼ばれる心理的な罠です。
点数を見るときは、「どこでつまずいたか」を分析する視点を持つことが大切です。
間違い分析ノートを活用し、「次のテストでは1つだけ改善する」など小さな目標を立ててみましょう。
努力の方向が明確になると、自然と結果もついてきます。
成功体験の少なさが「数学の苦手意識」を深めてしまう
最後に、数学が苦手な学生さんに共通するのが「成功体験の少なさ」です。
数学は答えが一つであり、正解できないと成果を感じにくい教科です。
そのため、「努力しても結果が出ない」「頑張っても意味がない」という無力感を抱きやすくなります。
しかし、小さな成功が自信を育てることを忘れてはいけません。
たとえ1問でも「できた!」という感覚を積み重ねることが、苦手意識をやわらげる第一歩になります。
効果的なのは、小目標の設定です。
「今日は計算ミスを1つ減らす」「この単元の基本問題を完璧にする」など、達成しやすい目標を立てると自信が少しずつ戻ってきます。
さらに、先生や親御さんがその努力を認めてあげると、学習意欲は大きく高まります。
「できた」という実感こそが、“嫌い”を“できる”に変える出発点です。
「数学ができない」と思い込んでしまう心理とは
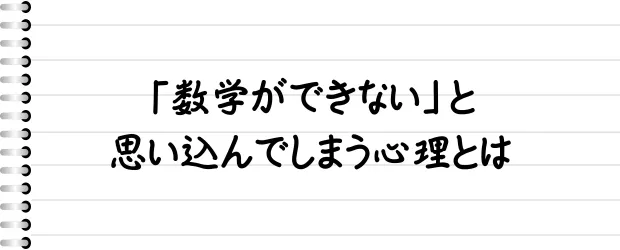
では、数学が苦手な学生さんは、なぜ「数学ができない」と思い込んでしまうのでしょうか?
数学を苦手に感じている人の多くは、「できない」という“現実”ではなく、「自分には向いていない」という“思い込み”にとらわれています。
実際、成績や理解度の差は能力の差ではなく、学び方や考え方の違いに由来することがほとんどです。
ここでは、数学に対して「自分はできない」と思い込んでしまう心理的な要因を5つの側面から整理し、その背景にある“心のクセ”を見ていきましょう。
「自分は文系だから」と思い込む固定観念のワナ
「文系だから数学は苦手」「理系の人だけが数学に強い」――こうした言葉を一度は耳にしたことがあるでしょう。
けれども、実際には「文系・理系」という区分は高校以降の教科選択のための便宜的な分類にすぎません。
にもかかわらず、中学生の段階から「自分は文系」と思い込んでしまうことで、学ぶ意欲を自ら狭めてしまうケースが多いのです。
思い込みが強いと、「どうせできない」と努力する前に諦めてしまい、結果として成長のチャンスを逃してしまいます。
しかし、成績を左右するのは「得意・不得意」ではなく、“やり方”と“継続”の差です。
たとえば、スポーツやゲームも最初から得意な人はいません。
最初は失敗ばかりでも、練習を重ねるうちにコツをつかみ、できるようになるのです。
そういう意味では数学もまったく同じです。
「文系だからできない」は根拠のない思い込みです。
正しい方向に努力を続ければ、誰でも必ず伸ばせます。
失敗の経験が「数学ができない」というレッテルを強化する
また、過去のテストで思うような点数が取れなかったり、苦手な単元でつまずいた経験があると、その「失敗の記憶」が心に残ってしまいます。
そして、その記憶が「やっぱり自分はダメなんだ」という自己イメージを作り上げてしまうのです。
心理学ではこれを「自己効力感の低下」と呼びます。
一度の失敗を過大に受け止めてしまうと、「挑戦しても無駄」と思い込み、次の学びへの意欲が失われてしまうのです。
ですが、数学は知識を積み重ねていく教科です。
つまり、一度のつまずきがその後の単元にも影響を与えやすいという特徴があります。
しかし、それは「失敗が致命的」という意味ではありません。
むしろ、人は失敗こそが上達の材料になります。
プロのスポーツ選手も、自分のミスを分析して次の試合に活かしています。
数学も同じで、失敗を「成長途中のデータ」として見直せば、それは貴重な学びになります。
過去の結果は未来の可能性を狭めるものではありません。
他人との比較が苦手意識を深めてしまう理由
では、「友達の方が点数が高かった」「あの子は理解が早い」――そんな風に他人と比べて落ち込んだ経験はありませんか?
SNSや学校の成績表など、周囲との比較が簡単にできてしまう現代では、「自分は劣っている」と感じやすい環境が整っています。
しかし、他人との比較は焦りや劣等感を生み出すだけで、学習モチベーションを下げてしまうことが多いのです。
人それぞれ理解のスピードも違えば、得意分野も違います。
大切なのは、「他人と比べる」のではなく「過去の自分と比べる」ことです。
たとえば、「昨日より理解できた」「前回より計算ミスが減った」といった小さな変化を記録する学習ノートをつけると、成長を実感しやすくなります。
「あの子より点数が低い」ではなく、「前よりできた」を喜べるようになれば、勉強のモチベーションは自然と高まります。
努力しても成果が出ないと感じる“学習の誤解”
「こんなに頑張っているのに、全然成果が出ない」――このように感じたことがある人も多いでしょう。
しかし残念ながら数学では、「たくさんやった=できるようになる」とは限りません。
もし間違った勉強法を続けていれば、努力の量に比例して成果が出ないこともあるのです。
たとえば、答えを見ながら丸写ししたり、公式を暗記するだけの勉強では、応用力が育ちません。
重要なのは、「努力=量」ではなく、「努力=正しい方向と継続」という考え方です。
問題を自分の言葉で説明してみたり、間違えた箇所を繰り返し復習するなど、理解中心の勉強に変えるだけで結果は変わります。
「わからない=自分が悪い」と思ってしまう自己否定の思考
最後に、「理解できない自分」を責めてしまう人も多いです。
「頭が悪い」「センスがない」と思い込んでしまうのは、非常に危険なサインです。
実際には、理解できない原因の多くは外的要因にあります。
説明の仕方が合っていない、学ぶタイミングが悪かった、教材のレベルが適切でない――そういった要素が重なって理解を妨げていることが多いのです。
もし「わからない」と感じたら、それは自分のせいではなく、学び方を変えるチャンスです。
質問したり、別の参考書を試したり、先生や友達に説明してもらうだけで理解が一気に深まることもあります。
数学が嫌いになるきっかけ|多くの中高生がつまずく場面
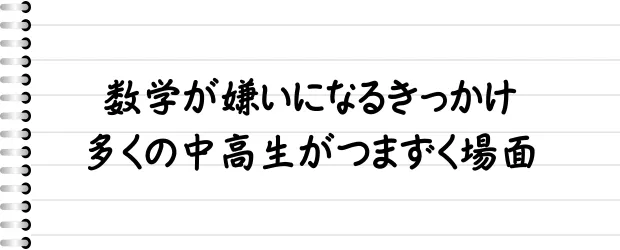
ここまで、数学が苦手になる理由などを見ていきましたが、多くの中高生が「数学が嫌い」と感じるようになる瞬間には、共通する“きっかけ”があります。
それは、能力の問題ではなく、「環境の変化」「評価の仕方」「心理的なプレッシャー」などが重なって生まれるものです。
誰でも一度は「もうわからない」「自分には無理かも」と感じたことがあるはずです。
そのため、数学が嫌いになるのは決して特別なことではありません。
ここでは、そんな“嫌いになってしまう理由”を具体的な場面ごとにひも解き、数学が苦手な学生さんが「自分だけじゃない」と感じられるように解説していきます。
中学から高校への難易度アップで「急に数学がわからない」と感じる瞬間
中学から高校へ進学すると、多くの学生さんがまず感じるのが「急に難しくなった」という壁です。
中学数学では計算練習が中心でしたが、高校では一気に抽象的で理論的な内容が増えます。
方程式を“解く”だけでなく、「なぜそうなるのか」「一般的にどう証明できるのか」を考えるようになるため、思考の方向がガラッと変わるのです。
この切り替えに戸惑い、「中学まではできたのに、急にわからなくなった」と感じる学生さんが多くいます。
しかし、これは能力が落ちたわけではなく、学びが発展段階に入った証拠です。
高校数学は中学内容の基礎の上に積み上がる構造なので、過去に理解があいまいだった部分が再び表面化することもあります。
そのため焦る必要はありません。
中学内容を復習しながら、「なぜそうなるのか」と自分に問いかける習慣をつけることで、理解は確実に深まります。
途中式が多くて面倒に感じ、「数学が嫌い」と思うようになる
数学の問題は一度で答えが出るものではなく、途中式をいくつも積み重ねて答えにたどり着きます。
この「途中式を書く」という作業を、多くの学生さんが“面倒”と感じるようになります。
「答えだけ書ければいいのに」「こんなに式を書かなくてもわかってる」と思ってしまう瞬間が、数学へのモチベーションを下げるきっかけになるのです。
しかし、途中式は単なる手順ではありません。
自分の考えを見える化する大切な記録です。
途中式を書くことで、自分がどこで間違えたのか、どんな考え方をしているのかを整理できます。
つまり、「面倒だな」と思う作業こそが、理解を深めるための練習なのです。
きれいに書こうとするより、「自分が後で読み返して理解できるメモ」として活用することで、数学の見方が変わっていきます。
正解が一つしかないプレッシャーが苦手意識を生む
国語や社会では「部分点」や「表現の工夫」で評価されることがありますが、数学では正解・不正解がはっきりしています。
そのため、「間違えたらダメ」「完璧にできなきゃ意味がない」というプレッシャーを感じやすいのです。
特に真面目な学生さんほど“完璧主義”に陥りやすく、ミスを極端に恐れてしまいます。
テストでちょっとした計算ミスをしただけで、「自分はやっぱり向いてない」と落ち込んでしまうこともあるでしょう。
でも、本当は間違えることこそが学びのスタートです。
正解しか見ない勉強よりも、「なぜ間違えたのか」を考える時間の方が成長につながります。
テストの点数で評価されることが“数学嫌い”を決定づける
数学に限らず、学校ではテストの結果が点数として明確に表れます。
そのため、良い点を取れなかったときの落ち込みが強く、「努力が無駄だった」と感じやすい傾向があります。
さらに、点数中心の評価制度では、「前回より理解できた」「考える力がついた」といった目に見えない成長が見逃されがちです。
親御さんや先生から「点数が悪い=努力不足」と決めつけられると、「どうせやっても無駄」と感じてしまうこともあるでしょう。
しかし、点数は努力のすべてを映すわけではありません。
問題を理解するスピードが上がったり、計算ミスが減ったりするのも立派な成長です。
「前より1問多く正解した」「解けなかった問題が解けるようになった」――そんな小さな変化を見つけていくことで、学ぶことへの前向きな気持ちは戻ってきます。
点数は結果の一部でしかありません。
努力は確実に積み上がっているという視点を忘れないことが大切です。
「自分にはセンスがない」と思ってしまう思考の落とし穴
最後に、多くの中高生が口にするのが「自分には数学のセンスがない」という言葉です。
しかし、数学にセンスはほとんど関係ありません。
必要なのは才能ではなく、慣れと手順の積み上げです。
たとえば、スポーツでも最初は上手くいかないのが当たり前です。
練習を重ねてコツをつかむうちに、自然と体が覚えていきます。
数学も同じで、「わからない」と感じるのは“まだ慣れていないだけ”の状態です。
「センスがない」と思い込むと、努力する前にあきらめてしまい、成長の機会を自ら閉ざしてしまいます。
大切なのは、「自分にはセンスがない」ではなく、「まだ経験が足りない」と考えることです。
理解する力は、練習によって必ず育ちます。
| 中学生のおすすめオンライン塾・家庭教師3選 | |||
|---|---|---|---|
ウィズスタディ |
家庭教師の銀河 |
WAM |
|
| 対象 | 中学生 高校生 |
中学生 | 中学生 高校生 |
| 授業料 (税込) |
9,800円~ (1科目) |
2,750円~ (1コマ) |
7,600円~ (週1回) |
| 入会金 | 27,500円~ | 22,000円 | 16,500円~ |
| 指導形式 | 学習塾 (オンライン) |
家庭教師 | 学習塾 (オンライン) |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | |
数学嫌いの根本原因を知ることが克服の第一歩
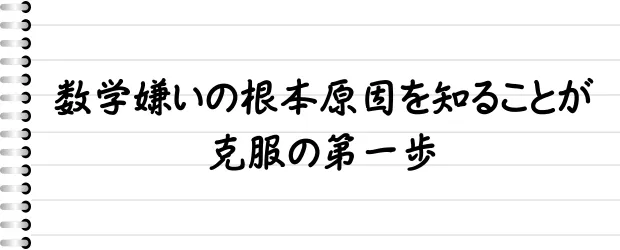
数学が嫌い――そう感じてしまう学生さんの多くは、実は「能力がない」わけではありません。
その背景には、ここまでお話してきたように「わからないまま進んでしまった経験」や「教え方との相性」、「間違いを恐れる気持ち」など、心理的・環境的な要因が深く関係しています。
つまり、「嫌い」と感じるのは心の反応であり、根本を理解すれば克服は誰にでも可能です。
ここでは、数学嫌いを生む5つの根本原因を掘り下げていきます。
「わからないまま進む」ことが数学嫌いを深める最大の原因
改めてになりますが、数学は知識を積み重ねていく教科です。
ひとつの単元が次の内容と密接につながっており、途中で理解が抜け落ちると、その後の内容も理解できなくなります。
たとえば「分数の計算」や「関数の考え方」「二次方程式」などでつまずくと、その影響は高校内容にまで及びます。
多くの学生さんが「もう今さら聞けない」と感じ、わからない部分を放置したまま進めてしまいます。
その結果、内容がどんどん抽象的になり、「自分はもうダメだ」と感じるようになるのです。
しかし本当の原因は“能力”ではなく、“理解の穴”にあります。
克服の第一歩は、勇気をもって一度立ち止まり、“わかるところ”まで戻ることです。
理解の穴をひとつずつ埋めていけば、苦手意識は自然に薄れていきます。
教え方と理解のズレが“苦手意識”を生む構造
「授業を聞いてもピンとこない」「ノートを写しても意味がわからない」――それは、あなたの理解力が低いからではありません。
単に、教え方とあなたの理解のスタイルが合っていないだけなのです。
たとえば、図で理解するのが得意な人にとって、言葉だけの説明はわかりづらいでしょう。
逆に、音で覚えるのが得意な人には、動画や口頭解説が効果的です。
この「説明のズレ」が続くと、学生さんは「自分が悪い」と感じてしまい、自信を失ってしまいます。
もし今までのやり方で理解できなかったなら、他の方法を試してみてください。
図で考える、動画で学ぶ、先生や友人に別の言い方で聞く――方法を変えるだけで理解の早さが変わります。
間違いを恐れる気持ちが考える力を奪ってしまう
数学では「正解がひとつ」だからこそ、間違うことを恐れてしまう人が多いと上述しました。
「間違った=自分はできない」と思い込むと、挑戦する意欲まで奪われてしまいます。
しかし、本当の学びは間違いの中にあるのです。
たとえばスポーツ選手も、失敗をデータとして分析し、改善を重ねて上達しています。
数学も同じで、どこでつまずいたかを見つけることが、理解を深める最大のチャンスです。
間違いを恐れず、「なぜ間違えたのか?」を考えること、その姿勢が、考える力を鍛え、確かな理解を生み出します。
成功体験の少なさが「数学=苦手」の悪循環をつくる
「どれだけ頑張ってもできない」と感じている学生さんの多くは、成功体験の数が少ないだけです。
数学は正答率が低く、小さな成長が見えにくい科目です。
そのため、「解けた」喜びを感じる機会が少なく、やる気を保ちにくい傾向があります。
この悪循環を断ち切るには、ハードルを下げることが大切です。
なので、まずは基礎問題から始め、「できた!」という体験を積み重ねましょう。
1問解けた、昨日より理解が進んだ――それだけで十分な成長です。
小さな成功を積み重ねることが、次の挑戦への自信につながります。
「嫌い」と「苦手」を同じだと思ってしまう思い込みの危険性
多くの人が「苦手=嫌い」と思い込んでいます。
しかし実際には、「わからない」「できない」という不安や焦りが“嫌い”という感情にすり替わっているだけの場合が多いのです。
たとえば、「運動は苦手だけど体を動かすのは好き」という人もいますよね。
同じように、「数学が苦手」でも、「考えるのは嫌いじゃない」という人も多いはずです。
この二つを区別することが、克服への第一歩です。
苦手は“スキルの問題”、嫌いは“感情の問題”です。
スキルは努力で伸ばせるし、感情は経験で変えられます。
苦手な数学を得意に変えるための思考の切り替え方
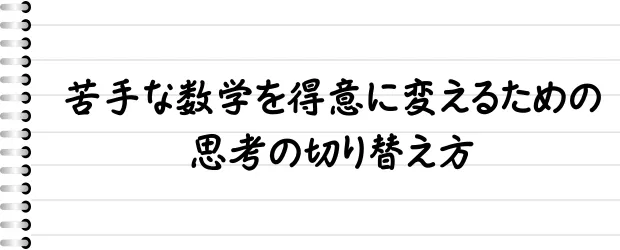
数学を「苦手」と感じる多くの中高生は、知識が足りないのではなく、考え方のクセが原因でつまずいています。
「間違ったら恥ずかしい」「頑張っても結果が出ない」――そんな気持ちは誰もが経験するものです。
しかし、少しだけ考え方を変えるだけで、数学との向き合い方は大きく変わります。
ここでは、“苦手”を“得意”に変えるための5つの思考の切り替え方を紹介します。
「できない自分」ではなく「成長途中の自分」と考える
数学でつまずくと、「自分は頭が悪い」「才能がない」と思い込んでしまう人が多いです。
しかし、実際にはそれは「理解途中」または「まだ学び方を知らないだけ」の状態にすぎません。
植物が芽を出すまでには時間がかかるように、成長には「見えない期間」があります。
数学の理解も同じで、「まだ伸びる途中」だという視点を持つことが大切です。
心理学ではこれを成長思考(グロースマインドセット)と呼びます。
「できない」ではなく「まだできていない」と考えるだけで、学びへの姿勢が前向きになります。
間違いは悪ではなく“理解を深めるチャンス”と捉える
数学において、「間違える」ことを極端に恐れる学生さんは少なくありません。
ですが、間違いは理解を深める最高のチャンスです。
間違えたということは、「どこでつまずいたのか」を具体的に発見できたということです。
正解だけを追い求めるよりも、誤った考え方を修正する過程のほうが、思考力や応用力を育てます。
間違いを「ダメな証拠」ではなく、「成長の記録」として受け止めましょう。
結果よりも「考える過程」を大切にする発想へ
学校ではどうしても「点数」や「正解数」が評価の中心になります。
そのため、「正解できなければ意味がない」と思い込む人が多いのですが、それは誤解です。
数学の真の価値は、「答えを出すまでの思考プロセス」にあります。
たとえ間違っていても、考えた過程を振り返ることができれば、それは確実に力になっています。
先生や保護者親御さんも、「点数」ではなく「考え方」を評価する姿勢を持つことが大切です。
一気に完璧を目指さず、小さな成功体験を積み重ねる
「全部できるようになりたい」と思うのは立派なことですが、いきなり完璧を目指すと挫折しやすくなります。
数学は成果が出るまでに時間がかかるため、「やっても無理」と諦めやすい教科でもあります。
ですが、大切なのは、小さな成功を積み重ねることです。
1問解けた、昨日よりも早く答えが出せた――そうした小さな達成を意識的に記録していくと、自信が芽生えます。
焦らず一歩ずつ進むことが、結果的に最短ルートになるのです。
「数学の苦手克服」は努力よりも“考え方のリセット”が鍵
多くの学生さんが「努力しても結果が出ない」と感じています。
しかし、努力を重ねても成果が出ないときは、努力量ではなく考え方を変えるべき時期です。
たとえば、間違いノートをつくる、わからない箇所をリスト化する、復習のタイミングを調整する――。
これらは根性ではなく「戦略的な努力」です。
ゲームでも、攻略法を変えれば同じステージを突破できるように、勉強も「やり方」を変えれば結果が変わります。
「頑張ること」よりも「考え直すこと」が、克服の鍵になるのです。
数学が苦手な人が陥りやすい勉強法とその改善策
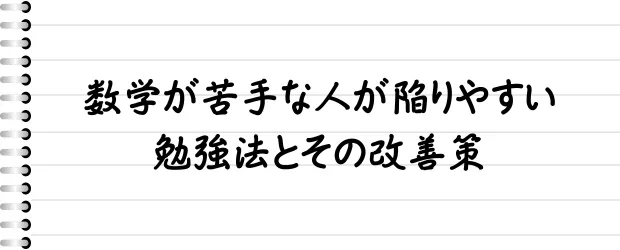
ここまで見てきたように、数学の苦手意識の多くは、「理解力の差」ではなく「勉強のやり方の違い」から生まれます。
つまり、方法を変えれば、誰でも確実に伸びていく教科です。
ここでは、数学が苦手な人が陥りやすい誤った勉強法を一つずつ見直しながら、「どう直せば成果につながるのか」を具体的に紹介します。
答えだけを覚える勉強は「数学ができない」状態を招く
多くの学生さんがやってしまいがちなのが、「答えを覚えるだけ」の勉強法です。
問題集を開いて、答えを見ながら丸写しし、「覚えた気分」で終わってしまうパターンです。
しかし、このやり方では一見理解できたように思えても、少し問題設定が変わるとすぐに手が止まってしまいます。
数学は「なぜそうなるか」を考える教科です。
答えを暗記しても、条件や数字が少し変わるだけで別の考え方が必要になります。
そのため、覚えるよりも「自分の言葉で説明できるか」を基準に理解を確認することが大切です。
たとえば、「なぜこの公式を使うのか」「この条件のときはどう考えるのか」を自分なりに説明できるようになると、本当の理解に近づきます。
解き方の暗記に頼りすぎると応用でつまずく理由
もう一つの落とし穴は、「解き方を覚えれば解ける」と思い込む暗記型勉強です。
たしかに、同じパターンの問題なら点は取れますが、入試や応用問題ではそれが通用しません。
応用力とは、「理解の深さ」と「思考の柔軟さ」の掛け算で生まれます。
暗記は手順の再現にすぎませんが、応用には「なぜこの手順が使えるのか」を理解している必要があります。
たとえば、同じ公式でも使う条件を間違えるとまったく意味がなくなります。
手順を覚えるよりも、背景や原理を理解し、「なぜこの方法を選んだのか」を常に意識することが、応用力を育てる第一歩です。
苦手分野を避けるほど“数学嫌い”が強くなる悪循環
苦手単元を避けてしまう――これも多くの学生さんが陥るパターンです。
わからない分野を後回しにすると、次の単元でさらに理解が難しくなり、結果的に数学全体が「苦手」に感じられてしまいます。
ですが、何度も言うように数学は積み上げ教科です。
土台が欠けたまま進めば、後の内容も崩れていきます。
たとえば、一次関数が苦手なままだと、二次関数やグラフ問題でも必ずつまずきます。
このような場合の解決策は実にシンプルです。
苦手単元こそ、やさしい問題から再スタートすることです。
最初は教科書の基本問題だけでも構いません。
グラフを描く、数値を代入してみるなど、「手を動かす学び」から始めることで、少しずつ理解の糸口が見つかります。
ノートをきれいにまとめることが目的化していないか?
「ノートがきれい=勉強できる」と勘違いしてしまう人も多いです。
たしかに、整理されたノートは気持ちがいいですが、見た目の美しさだけを目的にしてしまうと、学びの本質が抜け落ちます。
重要なのは、「どこで間違えたか」「どう考えたか」がわかるノートにすることです。
完璧にまとめるよりも、「自分の思考の跡」を残すほうが、後から復習するときに役立ちます。
たとえば、赤ペンで間違いの原因、青で要点、緑で再確認メモをつけるなど、色分けして「自分専用の復習ノート」を作ると良いでしょう。
正しい勉強法に変える3つのステップで「数学の苦手克服」を目指す
ここまで紹介した内容を踏まえ、数学ができるようになるための正しい学習ステップを整理します。
- 理解の確認:問題を解いたら、「なぜそうなるのか」を自分の言葉で説明する。
- 反復練習:間違えた問題は翌日と1週間後に再確認。時間を空けて定着を図る。
- 応用挑戦:1つの概念を複数の形で使ってみる。例題→応用→発展の順に取り組む。
この3ステップを意識すれば、「分かる → 使える → 定着する」という理想的な学習サイクルが完成します。
努力量よりも、「どんな順序で・どんな質の勉強をするか」が成果を決めるのです。
| 高校生のおすすめ学習塾3選 | |||
|---|---|---|---|
横浜予備校 |
WAM |
明光義塾 |
|
| 対象 | 高校生 | 中学生 高校生 |
中学生 高校生 |
| 授業料 (税込) |
50,160円~ (月額) |
9,200円~ (週1回) |
18,700円~ (週1回) |
| 入塾金 | 0円 | 16,500円~ | 11,000円 |
| 指導形式 | 学習塾 | 学習塾 (個別指導) |
学習塾 (個別指導) |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | |
「数学できない」を脱出する!わかる授業・問題集の選び方
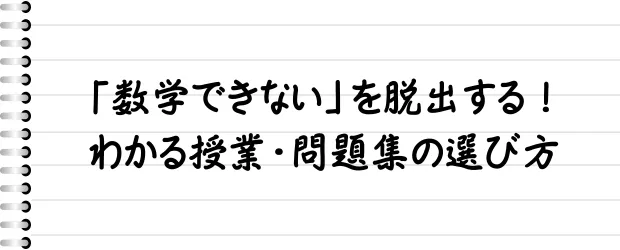
「数学が苦手…」と感じる生徒の多くは、実は“努力不足”ではなく、“学び方の選び方”でつまずいています。
授業の受け方や教材選びには、確かに正解があります。
自分に合った方法を見つけるだけで、これまでわからなかった内容がスッと理解できるようになることも珍しくありません。
ここでは、「わからない授業をどう乗り越えるか」「どんな問題集を選ぶと良いか」を具体的に紹介します。
行動のヒントを見つけながら、“わかる体験”を一つずつ積み上げていきましょう。
「わからない授業」をそのままにしないための聞き方の工夫
授業中、「なんとなくわかった気がするけど、本当は理解できていない…」という経験はありませんか?
この“わかったふり”が積み重なると、次第に数学が難しく感じられるようになり、やがて「もう無理」と諦めてしまう原因になります。
まず大切なのは、「質問が苦手」「何を聞けばいいかわからない」状態から抜け出すことです。
疑問が浮かんだら、途中式や考え方の流れを先生に聞くようにしましょう。
「この式はどうやって出てきたのか」「この考え方はいつ使えばいいのか」など、少しでも気になる点を紙にメモしておくのも効果的です。
また、授業中に質問できない場合は、授業後に友達同士で教え合ったり、自分で調べたりして理解を補いましょう。
先生に聞くタイミングをあらかじめ決めておく(授業後や休み時間など)ことで、質問へのハードルも下がります。
小さな疑問を一つずつ解消してこそ、本当の“わかる”が積み重なります。
“説明がわかりやすい先生”を見つける3つのポイント
同じ内容を教えていても、「先生によって理解度が変わる」と感じたことはありませんか?
それは、説明の仕方が自分に合っているかどうかで大きく変わるからです。
わかりやすい先生の特徴は、
- 生徒のペースに合わせて進めてくれる
- 具体例や図を多く使って説明する
- 途中式や考え方の理由を丁寧に説明してくれる
の3つです。
もし学校の授業だけで理解が難しい場合は、塾・個別指導・YouTube解説など、複数の「教え方」を試すのもおすすめです。
たとえば「説明→例題→質問タイム」という流れで授業を進める先生は、理解を深めやすいタイプです。
いろんな説明を比較することで、「自分に合う教え方」を見つけることができます。
先生選びも学びの一部と考え、柔軟に取り入れていきましょう。
数学が苦手な人ほど、問題集は“量より質”で選ぶべき理由
数学が苦手な人ほど、「たくさん解けばできるようになる」と思いがちですが、それは誤解です。
大切なのは、どんな問題を解くかとどんな解説を読むかです。
問題集を選ぶときは、「ページ数が多い」「分厚い」よりも、解説が丁寧で、例題と解き方がセットになっているものを選びましょう。
問題数が多すぎると途中で挫折しやすく、逆に「自分はやっぱりできない」と感じてしまうリスクがあります。
まずは、自分が「納得できる」問題を1冊やり切ることを目標にしましょう。
解説が見やすく、正解したときに「なるほど!」と思える教材を選ぶことで、“できる体験”が積み重なり、自信が生まれます。
わかる体験をくれる1冊が、何よりも価値のある教材です。
レベルに合わない教材選びが「数学ができない」を加速させる
「志望校のレベルに合わせて難しい問題集をやろう」と思って、途中で投げ出してしまった経験はありませんか?
これは多くの学生さんが陥る“頑張りすぎの落とし穴”です。
数学は基礎が積み重なって初めて理解が進む教科です。
だからこそ、自分の現状より少し易しいレベルから始めるのが正解です。
基礎を確実に固めてから応用に進むと、無理なく力がつきます。
途中でわからない問題があっても焦らず、一度スキップして後で戻るのも立派な学習戦略です。
一冊を最後までやりきる達成感が、次の意欲につながります。
解答を写すより“考え方の解説”が丁寧な問題集を選ぼう
最後にもう一つ重要なのが、「解答欄だけの問題集」よりも、「考え方の流れを丁寧に説明している問題集」を選ぶことです。
数学ができるようになるには、“答え”ではなく“発想の過程”を学ぶ必要があります。
途中の式や考え方の解説がしっかり書かれている教材なら、似た問題が出ても自力で解けるようになります。
図やイラストを交えた解説、ステップごとの説明がある教材は特におすすめです。
「どう考えれば良かったのか」を学ぶことで、理解が深まり、応用力も自然と身につきます。
“考え方”を学ぶことこそ、数学を得意に変える一番の近道です。
数学嫌いでも続けられる勉強習慣の作り方
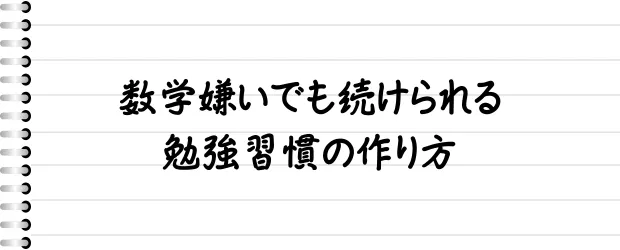
数学が苦手だと感じる人の多くは、「頑張っても続かない」「やる気が出ない」と悩んでいます。
しかし、数学克服のカギは“才能”ではなく、“続ける力”にあります。
どんなに小さな一歩でも、積み重ねることで確実に「わかる」感覚が増えていきます。
ここでは、数学嫌いでも無理なく続けられる勉強習慣をつくるためのコツを紹介します。
今日からでも始められる簡単な方法ばかりです。
短時間でもOK!“毎日少しずつ続ける”が数学克服の近道
数学の理解を深めるうえで最も効果的なのは、「毎日少しずつ」勉強を続けることです。
長時間一気に勉強しても、翌日には内容を忘れてしまうことが多いですが、短時間でも毎日触れることで、知識が自然と定着します。
特に苦手な人ほど、最初は“量より継続”を意識しましょう。
1日5分でも構いません。
「1問だけ解く」「公式を1つ書いて確認する」などの小さな行動から始めればOKです。
また、継続を視覚化するとモチベーションが上がります。
たとえば、
- カレンダーに「勉強できた日」にチェックをつける
- 習慣化アプリで連続日数を記録する
といった方法です。
完璧を目指すのではなく、「昨日より少し進めた自分」を褒めましょう。
勉強のハードルを下げる「5分ルール」の活用法
勉強が続かない最大の理由は、「始めるまでが面倒」という心理的ハードルの高さです。
そこでおすすめなのが、「5分だけやる」ことを目標にする5分ルールです。
「問題集を開くだけ」「教科書の例題を読むだけ」といった小さな行動を設定すれば、始めるハードルがぐっと下がります。
人間は、一度行動を始めると脳が「このまま続けよう」と働くため、結果的に10分、20分と集中できることも多いのです。
また、タイマーを5分にセットして始めるのも効果的です。
時間を区切ることで、「短時間ならできそう」という安心感が生まれます。
ポイントは「完璧にやる」よりも「まず始める」ことです。
行動のハードルを低くすることで、自然に学習習慣が定着していきます。
やる気が出ない日は“まずノートを開く”だけでいい
ですが、誰にでも「今日はやる気が出ない」「疲れて勉強したくない」という日があります。
そんな日は、無理に頑張らなくても大丈夫です。
むしろ、「ノートを開く」「机に座る」だけでも十分です。
“ノートを開く”という行為自体が、「勉強モードへのスイッチ」として働きます。
不思議なことに、ノートを眺めているうちに「昨日の続きだけ確認しよう」と自然に手が動くこともあります。
もしそのまま何もできなくても、「勉強の姿勢をとった」こと自体に意味があります。
大切なのは、勉強ゼロの日を作らないことです。
「今日は開いただけでもOK」と自分を認めることが、継続力を育てる秘訣です。
やる気は行動の“後から”ついてくるものだと覚えておきましょう。
目標を「テストで○点」ではなく「昨日より理解を深める」に変える
数学を続けるうえで大切なのは、目標設定の仕方です。
「テストで90点とる」などの“結果目標”だけだと、思うように点が取れなかったときにモチベーションが下がりがちです。
そこでおすすめなのが、「昨日より理解を深める」という“成長目標”に変えることです。
たとえば、
- 「昨日わからなかった問題をもう一度解いてみる」
- 「新しい公式を自分の言葉で説明できるようにする」
といった小さな目標です。
このような行動型の目標なら、達成感を毎日感じられます。
成績は一朝一夕で上がらなくても、理解の積み重ねが自信につながり、結果的に点数も上がっていきます。
“他人ではなく昨日の自分”と比べることが、継続のエネルギーになります。
苦手意識を軽くする“ごほうび学習法”で習慣化する
勉強を続けるためには、「頑張った自分を褒める仕組み」をつくることも大切です。
たとえば、
- 「5日連続で勉強できたら好きなスイーツを食べる」
- 「1章終わったら好きな動画を観る」
など、自分への“ごほうびルール”を設定しましょう。
脳は「報酬」を感じると、「またやろう」と思うようになります。
ごほうびはモチベーション維持の強い味方です。
また、家族や友人に「今日は10分頑張った」と報告して褒めてもらうのも効果的です。
褒められることで「次も頑張ろう」と思えるようになります。
苦手を克服するには、努力を苦痛にせず、前向きに続ける工夫が大切です。
“ごほうび”を味方につければ、数学への苦手意識は自然に薄れていくでしょう。
中学生と高校生では違う?ステージ別の数学克服アプローチ
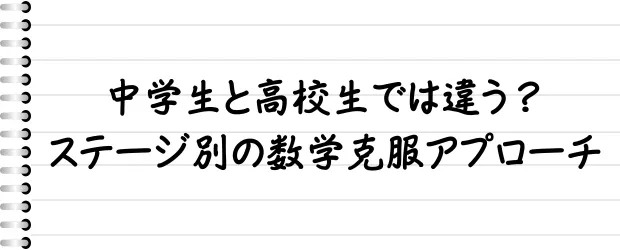
数学の苦手を克服するには、「学年ごとに求められる力が違う」ことを知ることが大切です。
中学生と高校生では、学ぶ内容だけでなく、思考の深さや求められる理解の形も変わります。
だからこそ、自分のステージに合った学び方を選ぶことが、無理なく続ける第一歩です。
ここでは、中学生と高校生それぞれに合った克服アプローチを紹介し、自分にぴったりの方法を見つけるヒントをお伝えします。
中学生の数学苦手は“基礎のつまずき”を取り戻すことが鍵
中学数学の最大の特徴は、「すべてが基礎の積み重ね」であることです。
計算、公式、グラフ、文章題――どれも高校数学の土台になります。
ここでつまずいたまま進んでしまうと、「高校に入ってから急に数学がわからなくなった」と感じる原因になります。
たとえば、方程式の意味を理解していないまま関数に進むと、グラフの読み取りや式の変形が難しく感じてしまいます。
計算ミスや文章題の読解不足も、基礎理解の甘さから起こることが多いのです。
そのため、中学生のうちに意識したいのは、「基礎を丁寧に取り戻すこと」です。
おすすめの方法は、
- 教科書の例題を繰り返し解く
- 解き方を自分の言葉で説明してみる
- 重要ポイントをノートにまとめ直す
といったシンプルな復習です。
高校生は“公式の理解”よりも“論理のつながり”を意識しよう
高校数学に入ると、覚える公式の数が一気に増えます。
そのため、「覚えるだけの勉強」に頼ってしまいがちですが、これが“応用が効かない”最大の原因です。
高校数学で大切なのは、「なぜこの公式が成り立つのか」「どの条件で使えるのか」という論理のつながりを理解することです。
たとえば、二次方程式の解の公式を覚えるだけではなく、「平方完成の考え方から導かれている」と理解すれば、問題の出方が変わっても応用できます。
おすすめの勉強法は、公式集や参考書で成り立ちを確認したり、解説動画で理論を復習したりすることです。
問題を解くときも、「なぜこの方法を使うのか」を自分に問いかける習慣をつけましょう。
中学数学の復習が“高校での数学できない”を防ぐステップになる
「高校数学が難しい」と感じる多くの原因は、中学内容の理解不足にあります。
高校の数学は、中学で学ぶ方程式・関数・図形などをベースに発展していくため、前の学年の穴を埋めることが重要です。
もし「高校からやり直したい」と感じているなら、いきなり難しい問題に挑戦するのではなく、中学の内容を一度振り返りましょう。
特に、文字式の操作や関数の基礎を見直すだけでも、問題の理解が格段にスムーズになります。
効果的な復習方法としては、
- 教科書の基本問題をもう一度解く
- チェックリストを作って苦手単元を整理する
- YouTubeなどで基礎動画を見て理解を補う
といった方法が挙げられます。
中高共通!授業の聞き方を変えるだけで理解が深まる理由
「授業をちゃんと聞いているのに理解できない…」という人は多いですが、その原因の多くは“聞き方”にあります。
ノートを取るだけの受け身姿勢では、知識が定着しづらいのです。
授業中に意識したいのは、
- わからない部分をその場でメモする
- 先生の例えや考え方に注目する
- 「なぜそうなるのか」を心の中で考えながら聞く
といった“能動的な聞き方”です。
授業後に5分だけ見直して、「今日の授業で理解できなかった部分」を確認するだけでも、理解度が大きく変わります。
特に、「わかったふり」をやめて、疑問を残さない姿勢が成績アップの近道です。
ステージごとの目標設定で無理なく数学を得意科目へ
最後に大切なのが、「今の自分に合った目標設定」です。
中学生と高校生では、重点を置くべきポイントが異なります。
- 中学生は「計算力・基礎力の定着」
- 高校生は「応用力・論理力の強化」
と目的を分けて考えると、自分の課題が明確になります。
無理に高い目標を立てる必要はありません。
「文章題を自力で説明できるようになる」「単元ごとの公式の成り立ちを自分の言葉で話せるようにする」といった小さな達成目標を積み重ねましょう。
チェックリストを使った進捗管理や、達成ごとに小さな“ごほうび”を設定するのもおすすめです。
友達と一緒に進めるとモチベーションが続きやすくなります。
| 高校生のおすすめオンライン塾・家庭教師3選 | |||
|---|---|---|---|
ウィズスタディ |
WITH-ie |
WAM |
|
| 対象 | 中学生 高校生 |
高校生 | 中学生 高校生 |
| 授業料 (税込) |
9,800円~ (1科目) |
22,000円~ (1科目) |
7,600円~ (週1回) |
| 入会金 | 27,500円~ | 38,500円 | 16,500円~ |
| 指導形式 | 学習塾 (オンライン) |
学習塾 (オンライン) |
学習塾 (オンライン) |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | |
数学を好きになるために今日からできる小さな一歩
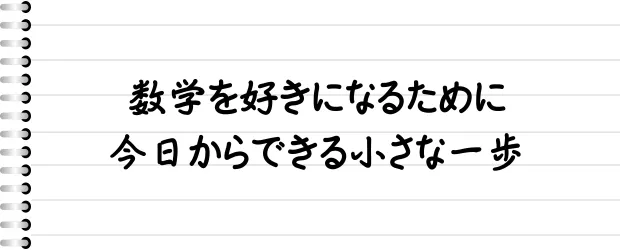
数学を「苦手」「嫌い」と感じている人でも、今日からできるほんの少しの工夫で、その気持ちは少しずつ変えられます。
いきなり完璧を目指す必要はありません。
むしろ、「ちょっとやってみよう」「少しだけ頑張ろう」という前向きな気持ちを持つことが、好きになるための第一歩です。
ここでは、毎日の生活や勉強の中で簡単に実践できる“数学と仲良くなる小さな行動”を紹介します。
「わからない」を放置せず、まず“質問する勇気”を持つ
数学が苦手になる一番の原因は、「わからない」をそのままにしてしまうことです。
1つの疑問を放置すると、その上に新しい内容が積み重なり、どんどん理解が追いつかなくなります。
だからこそ、“質問する勇気”が大切です。
先生に聞くのが恥ずかしいときは、友達や家族、ネット上の勉強解説などでも構いません。
「ここがわからない」と自分の言葉で説明するだけでも、頭の中が整理され、理解が深まります。
ノートの端に「質問メモ」を作っておくと、あとで先生に聞きやすくなります。
最初の一歩を踏み出すのは少し勇気がいりますが、「質問できた!」という行動自体が成長の証です。
質問することこそ、数学の苦手意識をなくす第一歩です。
1日1問でもOK!小さな“できた”を積み重ねる習慣
勉強を続けるうえで大切なのは「量」ではなく「継続」です。
1日たった1問でも、「自分で解けた!」「昨日よりわかるようになった!」という小さな達成感を感じることが、やる気の源になります。
大切なのは「やってみた」「ちょっと進んだ」という感覚です。
スマホやノートに“今日できたこと”を記録してみると、後から見返したときに自信が生まれます。
この“できた記録”が増えるほど、苦手意識は小さくなり、次の挑戦が楽しく感じられるようになります。
「少しずつでも続ける」ことが、数学を好きになるための近道です。
好きな科目や日常の中に“数学の面白さ”を見つける
また、数学は教科書の中だけの話ではありません。
買い物での割引計算、ゲームの確率、アートの中の対称性など、私たちの身近な生活の中にたくさん隠れています。
たとえば、理科のグラフや社会の統計、美術のデザインなどにも数学の考え方が生きています。
「これって数学の考え方だ!」と気づく瞬間があると、数字や公式が一気に身近に感じられます。
自分の“好き”と数学をつなげることで、学ぶ意味が見えてくるでしょう。
日常の中にある「数学の面白さ」を見つけることが、好きになるきっかけになります。
苦手な単元ほど“ゲーム感覚”で挑戦してみよう
どうしても苦手な分野は、「ゲーム感覚」で取り組むと気持ちが楽になります。
「10分で何問解けるか」「友達とどちらが早いか」など、ちょっとしたチャレンジを取り入れてみましょう。
得点表を作ったり、タイムを記録したりするのもおすすめです。
最近では、計算練習や図形パズルなどを楽しめる無料アプリもたくさんあります。
勉強を「作業」ではなく「遊び」に変えることで、自然と集中力が高まり、苦手意識が薄れていきます。
「遊びながら学ぶ」ことが、数学をポジティブに変えるコツです。
結果よりも「昨日より進歩した自分」に目を向ける
テストの点数や他人との比較ばかりに目を向けると、自信をなくしやすくなります。
しかし、「昨日できなかった問題が今日はできた」「先生の説明が少し理解できた」など、小さな進歩に気づくことができれば、学びがもっと楽しくなります。
ノートの余白に「できるようになったこと」を書いたり、成長グラフを作ったりすると、自分の努力が“見える形”になります。
その積み重ねこそが、数学を嫌いから好きに変える原動力です。
他人ではなく“昨日の自分”と比べることです。
「成長の実感」が、数学を好きになるための最大のエネルギーです。
このように、数学を好きになることは“才能”ではなく、“小さな行動の積み重ね”です。
今日の一歩が、明日の「できた!」につながります。
あなたのペースで、少しずつ前へ進んでいきましょう。
まとめ
数学が苦手だと感じる理由は、単なる能力差ではありません。
多くの場合、計算ミスや理解の穴・間違った勉強法・苦手の放置・「文系だからできない」といった思い込み、他人との比較による自己否定、そして教科書や授業の説明との相性やテスト評価へのプレッシャーなど、誰にでも起こりうる「環境」や「心のクセ」によって生まれます。
しかし、本当に大切なのは「自分にはできない」と決めつけず、小さな一歩から行動を始めることです。
どんなに苦手でも、1日1問の成功体験や「昨日より少しできた」成長の記録、質問する勇気、「できるようになりたい」という前向きな気持ちの積み重ねにより、徐々に苦手意識は和らいでいきます。
勉強法を見直し、答えの暗記ではなく「考え方」「なぜそうなるか」を理解する学びにしていきましょう。
基礎の復習・自分に合った問題集や授業スタイルの選択・短時間でも継続してみる工夫やごほうび習慣を活用することで、「できない」が「できる」に自然と変わります。
中学生・高校生それぞれの段階に合わせた目標設定とアプローチを意識すれば、自分に合った克服法が必ず見つかります。
数学は「努力=量」ではなく、「努力=正しい方向と継続」で上達する教科です。
苦手や嫌いは才能やセンスではなく、考え方や学び方を変えることで誰でも乗り越えられる壁です。
その気づきと小さな行動が、将来の自信につながります。
今の一歩が、明日の「できた!」をつくることを信じて、焦らず前に進んでいきましょう。

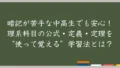
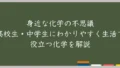

コメント