前回のページで度数分布表と度数分布表における代表的な値について解説してきましたが、度数分布表ではより深い情報を考えることができる万能な表になっています。
例えば、友だちとテストの点数を比べたり、スポーツの成績をまとめたりしたことはありますか?
そんなときに便利なのが、度数分布表の「相対度数」、「累積相対度数」などの値です。
これらの考え方を使うと、たくさんのデータをスッキリまとめて、いろいろな特徴を見つけることができます。
このページでは、
- 相対度数とは何か
- 相対度数の求め方と計算例
- 累積相対度数の意味と計算方法
- 身近な生活やニュースでの活用例
について、具体的に解説していきます。
まだ前回のページの内容が理解できていないという人は、前回のページを学習してからこのページの内容を勉強していきましょう。
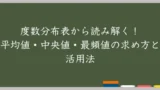
相対度数とは?基本の意味と考え方
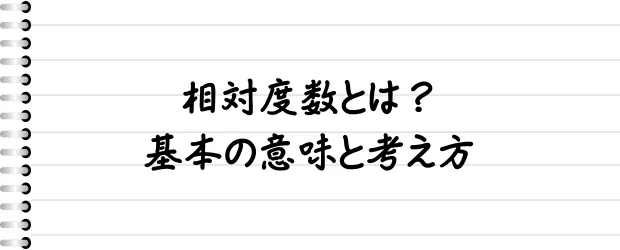
まずは相対度数の基本から見ていきましょう。
相対度数とは、全体に対して特定のグループや範囲が占める割合を表す数値です。
教科書的に言えば「度数(人数や回数)を全体の度数で割った値」です。
単位は「小数(0〜1)」または「百分率(%)」で表します。
たとえば、20人のクラスで
- 0〜19点の生徒が2人
- 20〜39点が4人
- 40〜59点が6人
- 60〜79点が5人
- 80〜100点が3人
というテスト結果があったとしましょう。
このとき、0〜19点の相対度数は
$2÷20=0.10$
つまり、10%です。
同様に、80〜100点の相対度数は
$3÷20=0.15$
つまり、15%になります。
なぜ相対度数が必要なのか?
では、なぜデータの集合を見ていくときに相対度数が必要になるのでしょうか?
それは、データの数の違いを認識しながらデータ同士の比較ができるからです。
単に「人数」だけを見ると、その集団が大きいのか小さいのか、他と比べて多いのか少ないのかがわかりにくい場合があります。
たとえば、クラスAで80点以上の生徒が3人、クラスBで4人だったとき、単純に「Bの方が多い」と言えますが、クラスAの人数が20人で、クラスBが40人だったらどうでしょう?
- クラスA → 3 ÷ 20 = 0.15(15%)
- クラスB → 4 ÷ 40 = 0.10(10%)
実はクラスAの方が高得点者の割合が高いことがわかります。
このように、相対度数は集団の規模の違いを補正して比較を可能にする重要な指標です。
相対度数の求め方|ステップごとの計算手順
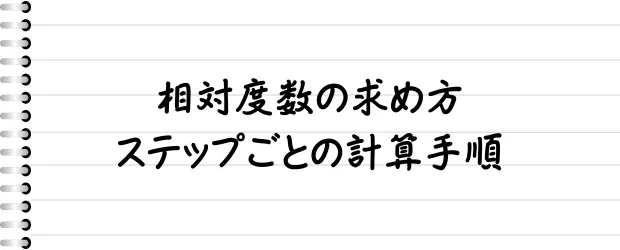
上記で見てきたように、相対度数の計算はシンプルですが、正しく求めるためには次の3ステップを押さえておきましょう。
- 全体の人数(度数の合計)を求める
すべての階級(範囲)の人数を足し合わせます。 - 各階級の人数を全体人数で割る
小数または百分率にします。 - 必要に応じてグラフ化する
棒グラフや円グラフにすると比較がわかりやすくなります。
この手順を踏まえて、実際の計算結果の例を見ていきましょう。
計算結果の例
| 点数範囲 | 人数(度数) | 相対度数 |
|---|---|---|
| 0〜19点 | 2人 | 0.10(10%) |
| 20〜39点 | 4人 | 0.20(20%) |
| 40〜59点 | 6人 | 0.30(30%) |
| 60〜79点 | 5人 | 0.25(25%) |
| 80〜100点 | 3人 | 0.15(15%) |
このように表にまとめると、各階級の割合がひと目でわかります。
身近な生活での相対度数の活用例
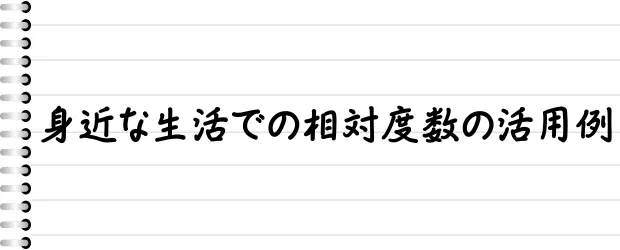
ここまで相対度数についての基礎知識を説明してきましたが、相対度数は数学の授業だけのものではなく、身近なところでたくさん使われています。
たとえば、下記のようなものが挙げられます。
- スポーツの成績分析
- バッターの打率(ヒット数 ÷ 打席数)はまさに相対度数です。
- サッカーでのシュート成功率も同様です。
- アンケート結果の分析
- 「はい」と答えた人の割合
- 「とても満足」と答えた割合
- 気象データ
- 雨の日の割合(雨の日数 ÷ 365)
- 台風の発生確率なども相対度数的な考え方です。
- 健康・医学分野
- 病気の発症率(患者数 ÷ 調査対象人数)
- 予防接種の接種率
このようにしてみると、今、学習している知識がそのまま将来の仕事の場面でも使えるものだということが分かります。
累積相対度数とは?意味と必要性
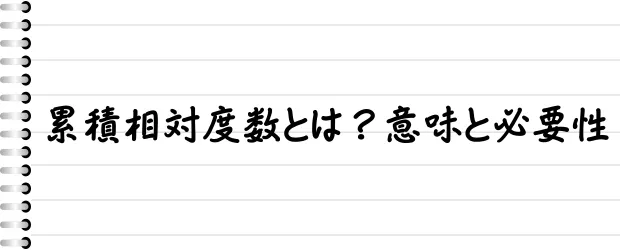
では、次に累積相対度数について見ていきます。
相対度数を理解したら、次に覚えておきたいのが累積相対度数です。
累積相対度数とは、相対度数を下から順に足していったものです。
つまり「この範囲以下の割合」がわかる指標です。
さきほどのテスト例をもとに、相対度数を累積してみましょう。
| 点数範囲 | 相対度数 | 累積相対度数 |
|---|---|---|
| 0〜19点 | 0.10 | 0.10 |
| 20〜39点 | 0.20 | 0.30 |
| 40〜59点 | 0.30 | 0.60 |
| 60〜79点 | 0.25 | 0.85 |
| 80〜100点 | 0.15 | 1.00 |
最後の階級では必ず1.00(100%)になります。
累積相対度数の活用例
累積相対度数は場合によっては求める必要がないこともありますが、どういったときに累積相対度数が使えるのかはしっかりと押さえておきましょう。
- 「60点未満の生徒は全体の何%か」→ 累積相対度数で簡単にわかる
- 「80点以上の生徒は何%か」→ 1.00から60〜79点までの累積相対度数を引く
累積相対度数は、学力分布の分析や顧客データのランク分け、在庫や売上の累積割合の把握など、幅広い分野で利用されます。
累積相対度数の求め方を徹底解説
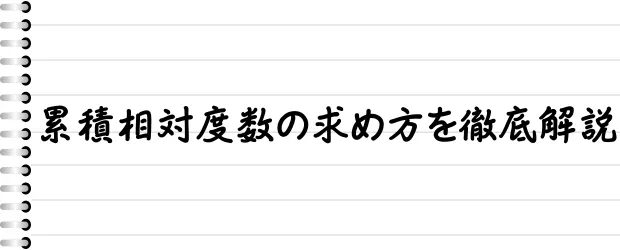
ここまでで、累積相対度数の基礎知識を説明してきました。
改めてになりますが、累積相対度数は、相対度数を下の階級から順番に足し合わせたものです。
ここで、累積相対度数の具体的な計算手順を例題を交えて見ていきましょう。
計算手順(3ステップ)
- 階級ごとの相対度数を求める
まず前半部分で説明した方法で相対度数を求めます。 - 下の階級から順に足す
最初の階級の累積相対度数は、そのまま相対度数と同じ。
次の階級は、直前の累積相対度数に相対度数を足していきます。 - 最終階級は必ず1.00(100%)になる
計算チェックの目安になります。
例題で計算してみよう
あるクラス30人の体力テスト(50m走)のタイムを分析します。
| タイム(秒) | 人数 | 相対度数 | 累積相対度数 |
|---|---|---|---|
| 6.0〜6.4 | 3人 | 0.10 | 0.10 |
| 6.5〜6.9 | 5人 | 0.1667 | 0.2667 |
| 7.0〜7.4 | 8人 | 0.2667 | 0.5334 |
| 7.5〜7.9 | 9人 | 0.3000 | 0.8334 |
| 8.0〜8.4 | 5人 | 0.1667 | 1.0001 ≈ 1.00 |
※ 累積相対度数の小数第4位以降は四捨五入してもOK。
この表を見ると、
- 「7.4秒以下で走れる人は全体の約53%」
- 「8.0秒以上かかる人は全体の約17%」
といった情報がすぐにわかります。
グラフで表す累積相対度数
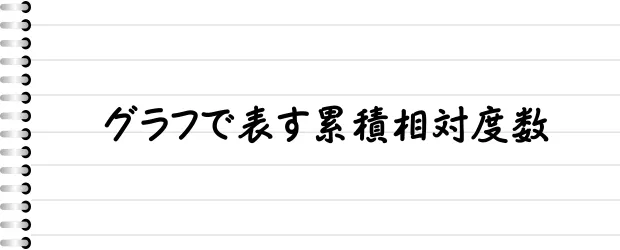
累積相対度数は数値で見ただけでもデータの割合をイメージしやすい数ですが、累積相対度数をグラフにすると、データの傾向がより直感的に理解できます。
代表的なのは累積折れ線グラフです。
累積折れ線グラフの特徴
- 横軸:階級の上限値(点数やタイムなど)
- 縦軸:累積相対度数(0〜1または0〜100%)
- 右肩上がりの曲線(または直線的な階段状)になる
- 最後は必ず1.0(100%)に到達
このグラフを使うと、「全体の○%がこの範囲以下」という読み取りがしやすくなります。
また、データの分布形(正規分布に近いのか、偏りがあるのか)をざっくり把握できます。
累積相対度数の応用分野
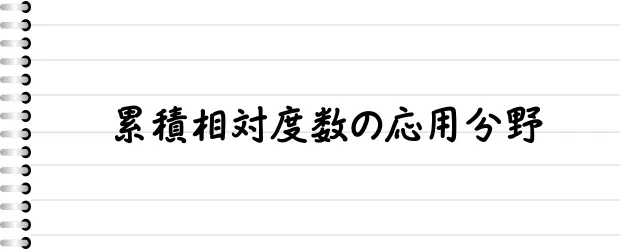
ここまでで説明してきた累積相対度数も、もちろん社会で活かせる知識であります。
その例もいくつか紹介しておきましょう。
- 学力テストの成績分布分析
受験の合格ライン判定、模試の偏差値算出など。 - 経済・ビジネス分析
- 売上上位商品の割合(パレート分析)
- 顧客の購買分布
- 品質管理
- 工場の不良品率
- 累積で見て何%の製品が基準を満たすか
- マーケティング
- アクセス数やCVR(コンバージョン率)の分布
- SNSの投稿反応率分析
統計的確率と相対度数・累積相対度数の関係
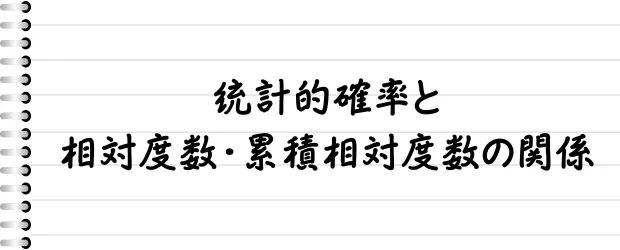
ここまでで相対度数と累積相対度数の説明をしてきました。
この知識だけでも十分にデータの分析は可能ですが、ここからは別の視点の統計的確率から相対度数や累積相対度数について見ていきたいと思います。
統計的確率とは
まずは「統計的確率」という言葉を説明しておきます。
統計的確率は、実際の観測や実験から得られた割合です。
たとえばサイコロを100回振って、1が出た回数が18回だった場合、統計的確率は18 ÷ 100 = 0.18(18%)となります。
この統計的確率と相対度数、累積相対度数との関連は下記ようになります。
関係性のポイント
- 相対度数 ≈ 統計的確率
大量の試行を行うと、相対度数は理論上の確率に近づく。 - 累積相対度数 ≈ 「〜以下」の確率
例:50点以下の確率、8秒以内で走れる確率など。
このことをしっかりと意識できるようになると、大量のデータを分析する際に、自分は今どういったことを分析しようとしているのかを認識しながら進めていけるようになります。
実生活での例
また、統計的確率は実生活の中でも活かされています。
その代表例が下記のものです。
- 天気予報の「降水確率」
→ 過去のデータの相対度数から予測 - スポーツの勝率
→ 勝った試合数 ÷ 総試合数 - 健康診断での異常値率
→ 異常値の人数 ÷ 検査人数(相対度数)
→ 「異常値○○未満の人は全体の○%」=累積相対度数
正の数・負の数とのつながり
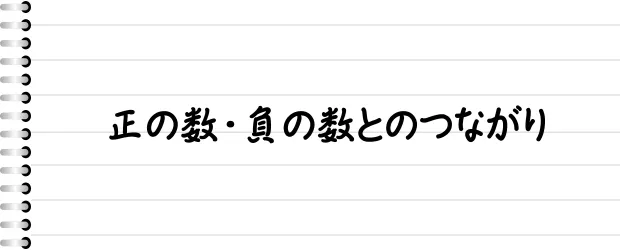
ここまでは、相対度数と累積相対度数の基本の知識と、確率的統計という周辺知識を学習してきました。
では、ここからの話ですが、これらのデータの分析の学習は他の学習単元とも結びつけていくことができます。
ここでは、「正の数負の数」というと中学1年生の始めで学習した内容との関連をお話していきます。
まだ正の数負の数の学習内容に不安がある人は先に下記のページを確認しておくことをおすすめします。

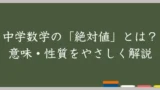
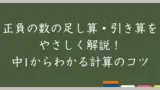
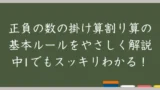
データの増減
今回学習を進めているデータの分析の内容と、正の数負の数の関連については、相対度数や累積相対度数の変化を「前回との差」で表すときに関連性が出てきます。
前回のデータとの差が
- 増えていれば正の数(+)
- 減っていれば負の数(−)
となります。
たとえばアンケートで「満足」と答えた割合が前回40%から今回55%になった場合、増加分は +15%(+0.15)です。
温度データの例
気温データでも相対度数は使えます。
たとえば1年間の最低気温が0℃未満の日の割合は、負の数の世界の相対度数です。
累積相対度数を使えば「氷点下5℃以下の日が全体の何%か」も求められます。
相対度数・累積相対度数でよくある間違いと注意点
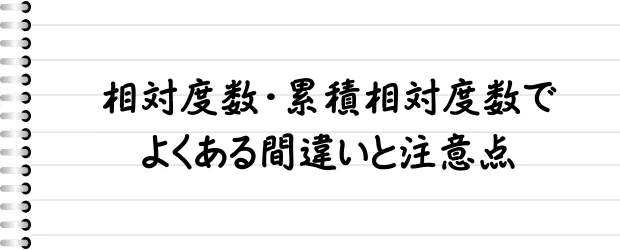
ここまでは学習の内容と他の単元への応用について解説してきました。
ここからは、相対度数や累積相対度数の学習で間違えてしまう点について紹介しておきます。
統計の学習でつまずくポイントは意外と似ています。
ここではよくある間違いを挙げ、間違いを防ぐためのチェック方法をまとめます。
①分母を間違える
相対度数は 「階級の度数 ÷ 全体の度数」 です。
たまに階級幅や別の数値を分母にしてしまうケースがあります。
→チェック方法:全ての相対度数を足して1.00(または100%)になるか確認。
②累積相対度数の足し方を間違える
累積相対度数は下の階級から順に足します。
途中の階級を飛ばしたり、逆方向に足すと誤った結果に。
→チェック方法:累積相対度数は必ず右肩上がり、最後が1.00になる。
③小数の丸め方
0.3333や0.1667などの小数は途中で丸めすぎると誤差が大きくなります。
→チェック方法:計算は少数第4位以上保持し、最後の表示だけ四捨五入。
実践的な応用例
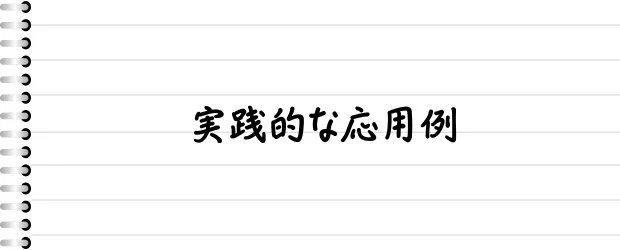
では、ここまでの学習内容をもとに、実践的な例を紹介していきます。
1.模擬試験の合格ライン判定
学生さんに一番身近なのは、模試などの合格ラインの判定です。
模試結果を度数分布表にまとめ、累積相対度数を用いると「全体の上位○%に入っているか」が一目でわかります。
たとえば上位30%以内が合格なら、累積相対度数が0.70になる得点を境に判定可能です。
2.スポーツデータの分析
たとえば、バスケットボールの選手シュート成功率を階級分けし、累積相対度数を求めると「上位20%の成功率は何%以上か」を導き出せます。
これは選手評価や戦術立案に直結します。
3.商品売上のパレート分析
売上データを相対度数化し、累積相対度数を算出すると「全売上の80%を占める上位商品群」が特定可能です。
これを活かして、マーケティングや在庫戦略で重要です。
練習問題
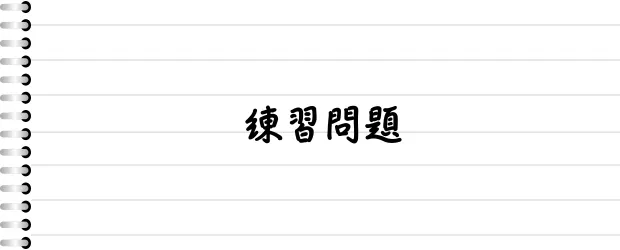
では、ここまでの知識を活かして、実際に計算してみましょう。
問題
あるイベントで、来場者の年齢層を調査しました。
| 年齢層 | 人数 |
|---|---|
| 10〜19歳 | 15人 |
| 20〜29歳 | 25人 |
| 30〜39歳 | 30人 |
| 40〜49歳 | 20人 |
| 50〜59歳 | 10人 |
- 相対度数を求めなさい。
- 累積相対度数を求めなさい。
- 「30代以下の来場者の割合」は何%か。
解答・解説
全体の人数=15+25+30+20+10=100人
① 相対度数
- 10〜19歳:15 ÷ 100 = 0.15
- 20〜29歳:25 ÷ 100 = 0.25
- 30〜39歳:30 ÷ 100 = 0.30
- 40〜49歳:20 ÷ 100 = 0.20
- 50〜59歳:10 ÷ 100 = 0.10
② 累積相対度数
- 10〜19歳:0.15
- 20〜29歳:0.15 + 0.25 = 0.40
- 30〜39歳:0.40 + 0.30 = 0.70
- 40〜49歳:0.70 + 0.20 = 0.90
- 50〜59歳:0.90 + 0.10 = 1.00
③ 30代以下の割合
累積相対度数で30〜39歳まで = 0.70 → 70%
まとめ
このページでは、「相対度数」と「累積相対度数」、そしてそれらと「統計的確率」の関係について学びました。
相対度数は「全体の中での割合」を示し、累積相対度数は「積み重ねた割合」を示します。
さらに、実際のデータをもとにした相対度数は、確率を考える手がかりにもなります。
データを整理し、わかりやすくまとめる力は、学校の勉強だけでなく、将来の生活や仕事でもとても大切です。
ぜひ、自分の身の回りのことにも統計の考え方を使ってみてください。
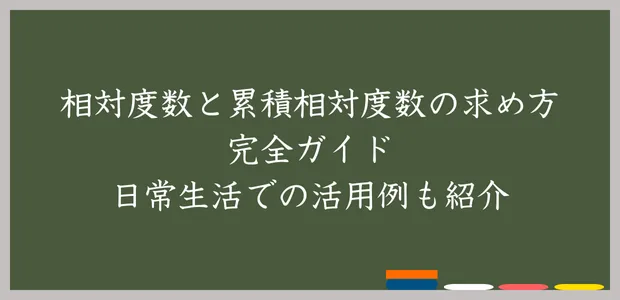







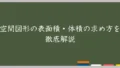
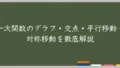

コメント