正負の数は中学数学の基礎で、数直線を使ってその意味や符号の役割を理解することが重要です。
このページでは、「正負の数とは何か」から始まり、乗法の符号ルールや除法の書き換え方法、さらに符号を使いこなすコツやよくある間違いの対策まで、 中学1年生がつまずきやすいポイントを丁寧に解説します。
符号のしくみをしっかり押さえて正確な計算力を身につけましょう。
| 中学生のおすすめ学習塾3選 | |||
|---|---|---|---|
横浜予備校 |
WAM |
明光義塾 |
|
| 対象 | 中学生 | 中学生 高校生 |
中学生 高校生 |
| 授業料 (税込) |
29,700円~ (月額) |
7,600円~ (週1回) |
15,400円~ (週1回) |
| 入塾金 | 0円 | 16,500円~ | 11,000円 |
| 指導形式 | 学習塾 | 学習塾 (個別指導) |
学習塾 (個別指導) |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | |
正負の数とは?基本の確認と符号の意味
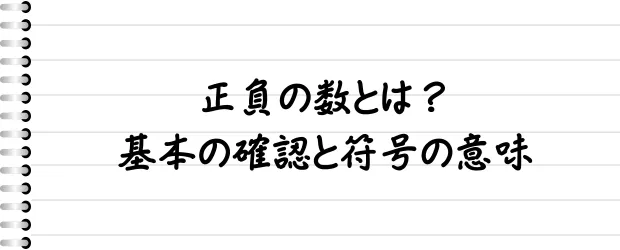
正負の数を理解することは、中学数学の「数と計算」を学ぶうえで最初の重要なステップです。
ここまで学んできた自然数や整数の考え方をさらに広げ、0より大きい数・小さい数を幅広く扱えるようになることで、温度や高さ、収支など、身のまわりの現象をより正確に表現できるようになります。
ここでは、正の数と負の数の意味、符号が示す役割、そして0との違いを数直線とともに丁寧に確認していきます。
正の数と負の数の基本的な意味とは?
まず「正の数」と「負の数」が何を示しているのかを整理しましょう。
正の数とは、0より大きい数のことです。
ふつうは「+」の符号を省略して書くため、+5は単に5と表します。
正の数は、量が増える方向・上がる方向・プラスの効果など、何かが「上向き」であることを示す場面で使われることが多く、身近な例としては次のようなものがあります。
- 気温:気温が 10℃ 上がる → +10℃
- 銀行口座:1,000円の収入 → +1000円
- 高さ:海抜 500m → +500m
一方で負の数とは、0より小さい数です。
書くときには必ず「−」を付け、−3のように表します。
負の数は、減る方向・下がる方向・マイナスの影響などを示す場面で活躍します。
- 気温:気温が −5℃ → 気温が0℃より5℃低い
- 収支:2,000円の支出 → −2000円
- 高さ:海面下 30m → −30m
このように、正負の数は整数だけでなく、小数や分数にも存在します。
たとえば、+2.5、−1.8、+$\frac{3}{4}$、−$\frac{1}{2}$といったように、正負の概念はすべての数に適用できます。
これにより、0より大きいか小さいかという情報を細かく表現できるようになります。
符号の役割と数の大きさの関係
ここで、正負の数に付く符号「+」「−」の役割について確認します。
多くの人が最初に間違えやすい点は、符号が「大きさ」を示しているわけではないということです。
符号は「向き」や「状態」を示す記号であり、数そのものの大きさ(=絶対値)とは別物です。
数直線で見る符号と大きさの違い
数直線上では、0を基準(原点)として右が正、左が負です。
ここで重要なのが絶対値の考え方です。
絶対値とは「0からの距離」を表し、符号は関係ありません。
- +3 の絶対値 → 3
- −3 の絶対値 → 3
つまり、同じ絶対値でも符号が異なると意味はまったく逆になります。
たとえば気温で考えると、
- +5℃ → 0℃より5℃高い
- −5℃ → 0℃より5℃低い
このように、符号は「方向」を示し、大きさは絶対値が担うという役割分担があるのです。
ゼロとの違いと数直線での表し方
「0」の扱いについても確認します。
0は正の数でも負の数でもない特別な数です。
正負を分ける境界であり、どちらにも属しません。
数直線では、0は中央に位置し、正の数と負の数は左右に対称に並びます。
数直線上の配置を見ることで、正負の数の関係が一目で理解できます。
特に正負の学習では、数直線を使って視覚的に理解することが非常に効果的です。
「0を境に右と左に広がり、向きが異なる」という感覚をつかむことで、正負の数の計算や符号ルールがスムーズに理解できるようになります。
正負の数の乗法のルールと計算のしかた
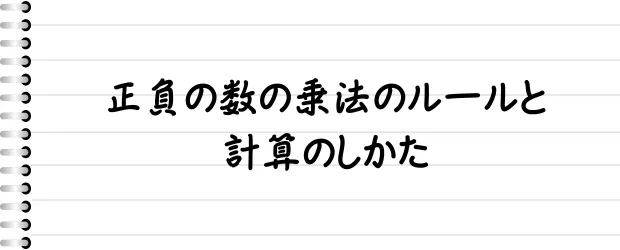
ここまでで、正負の数の意味や符号の役割を理解し、数直線を使ったイメージもつかめてきたはずです。
ここでは、正負の数の「かけ算(乗法)」に注目し、符号の組み合わせによって結果の符号がどのように決まるのかを詳しく学んでいきます。
正負のかけ算は、中学数学でつまずきやすいポイントの一つですが、符号の意味と数直線のイメージを組み合わせれば、しっかり納得して理解できるようになります。
同符号のかけ算はなぜ正の数になるのか?
まずは「同符号」、つまり「正×正」と「負×負」のケースを見ていきましょう。
正の数同士のかけ算はふつうのかけ算と同じ
正の数同士のかけ算は、これまで学んできた自然数のかけ算とまったく同じ意味をもちます。
(+3)×(+4)=12
これは「3を4倍する」という操作であり、向きや方向を示す符号が両方とも正なので、結果も自然に正になります。
負の数同士のかけ算はなぜ正になるのか?
ここで多くの人が疑問を感じるのが、
「マイナス × マイナス = プラス」ってなぜ?
という点です。
これには数学的な理由と直感的な理由があります。
数学的な性質からの説明
数の世界では、次の性質が常に成り立つようにルールを作っています。
「同じ量だけ減らすことを繰り返すと、逆向きの増加になる」
例えば、次のような性質を考えるとわかりやすくなります。
(−3)×4=−12
これは「−3を4回足す(方向がマイナスへ4回)」という意味です。
では、
(−3)×(−4)
を考えると、「−3を−4回繰り返す」という解釈が必要になります。
「−4回」とは、「逆向きに4回」という意味になり、マイナス方向に進む操作を逆向きにするとプラス方向に進むという結果になります。
日常のイメージで理解する
身近な例で考えるともっと納得できます。
- 「借金(−)」を「やめる(−)」 → お金が増える(+)
- 「減らす(−)」という操作を「取り消す(−)」 → 結果は増える(+)
「マイナスをマイナスする」と、プラスの効果になるわけです。
異符号のかけ算はなぜ負の数になるのか?
次に「正×負」、「負×正」の異符号のかけ算を見ていきます。
符号の向きが逆だから結果はマイナス
正と負の数をかけると、結果は負の数になります。
例:
(+4)×(−3)=−12
(−5)×(+2)=−10
理由は「方向が逆だから」です。
- 正の数 → プラス方向の量
- 負の数 → マイナス方向の量
プラス方向の量をマイナス方向へ伸ばすと、結果はマイナスになります。
数直線で考えると直感的にわかる
たとえば、3×(−4)を考えると、「3を4回プラス方向へ」ではなく「3を4回マイナス方向へ」進めると考えられます。
つまり、マイナス方向に大きく進むため、結果は負になります。
符号の組み合わせは「負が奇数個なら負」
正負のかけ算は、基本的に次のルールで判定できます。
- 負の数が1つ → 結果は負(異符号)
- 負の数が2つ → 結果は正(同符号)
つまり、
- 負が奇数個 → 結果は負
- 負が偶数個 → 結果は正
というルールが成り立ちます。
乗法の計算で気をつけたい符号の決まり
ここまで見てきたことを踏まえて、正負のかけ算でミスを防ぐための考え方と計算手順を整理します。
まず「符号」だけを決める
かけ算では、いきなり数字部分を計算するのではなく、最初に符号を決める癖をつけるのが大切です。
- 同符号 → 結果はプラス
- 異符号 → 結果はマイナス
このルールを先に決めてしまえば、計算ミスが大幅に減ります。
数字の部分は絶対値として計算する
符号を決めたら、次に絶対値だけを使って計算します。
例:
(−7)×(+3)
手順:
- 負と正の組み合わせ → 結果は負
- 絶対値:7×3=21
- 答え →−21
複数の数をかけるときのポイント
3つ以上の数をかける場合は「負の数の個数」を数えるのが効果的です。
例:
(−2)×(+3)×(−4)×(−5)
- 負の数は 3 つ → 奇数個 → 結果は負
- 絶対値:2×3×4×5=120
- 答え →−120
このように、正負の数のかけ算は符号の意味を理解すると一気に計算がスムーズになります。
符号と絶対値を分けて考えることで、より正確に乗法を扱えるようになります。
| 中学生のおすすめオンライン塾・家庭教師3選 | |||
|---|---|---|---|
ウィズスタディ |
家庭教師の銀河 |
WAM |
|
| 対象 | 中学生 高校生 |
中学生 | 中学生 高校生 |
| 授業料 (税込) |
9,800円~ (1科目) |
2,750円~ (1コマ) |
7,600円~ (週1回) |
| 入会金 | 27,500円~ | 22,000円 | 16,500円~ |
| 指導形式 | 学習塾 (オンライン) |
家庭教師 | 学習塾 (オンライン) |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | |
正負の数の除法は乗法に書きかえて考えよう
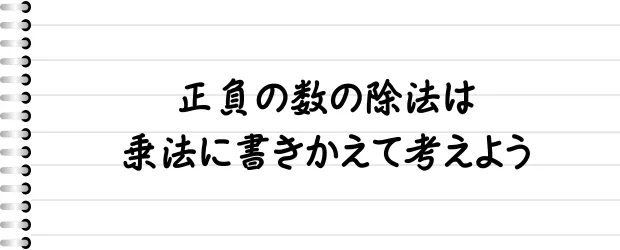
正負の数の計算には「加法・減法」と「乗法・除法」がありますが、中でも除法は得意・苦手が大きく分かれる単元です。
しかし、除法を「特別な新しい計算」として覚える必要はありません。
実は、割り算は「逆数をかける」計算に書きかえることで、すでに学んだ乗法のルールをそのまま使えるのです。
ここでは、割り算を乗法に直す理由、除法の符号の決まり、そして逆数を使った計算方法を丁寧に解説します。
ここまでに学習した「符号の決め方」がそのまま活用できるため、除法はむしろ簡単な単元になります。
割り算を掛け算に直す理由と基本ルール
割り算の基本的な考え方として、数学ではつぎのような関係が成り立つようにルールを決めています。
$a÷b=a×\frac{1}{b}$
この式は「割り算とは、割る数の逆数をかけること」という意味を表しています。
正負の数でもこのルールはまったく同じ
たとえば、
−6÷2
という計算は、割り算を掛け算に直すと、
−6×$\frac{1}{2}$
と書けます。
この形に直すことで、「符号の決め方は乗法と同じ」「あとは普通に数を掛ければよい」というシンプルな手順に変わります。
割り算を掛け算に直すメリット
- 符号のルールを覚え直さなくてよい
→乗法で学んだ「同符号なら正、異符号なら負」をそのまま使える。 - 分数計算と相性が良い
→中学数学では分数の計算が増えるため、逆数の操作を身につけると後の学習が楽になる。 - 文章問題でも強力に使える
→速さ・割合・比など、多くの単元で割り算→掛け算への書き換えが役立つ。
除法の符号のルールは乗法と同じ
除法を乗法に直せば、答えの符号は乗法と同じルールで決まります。
同符号のケース(答えは正)
(+10)÷(+2)=+5
(−10)÷(−2)=+5
割る数・割られる数がどちらも正、またはどちらも負のとき、符号がそろっているため答えは正になります。
異符号のケース(答えは負)
(+10)÷(−2)=−5
(−10)÷(+2)=−5
符号が異なると答えはマイナスです。
これは乗法の「正×負=負」「負×正=負」とまったく同じ考え方です。
手順は「まず符号、次に数字」
計算ミスの大半は符号を忘れることです。
そこで、次の順に必ず計算します。
- 符号を決める(負の数が奇数個ならマイナス、偶数個ならプラス)
- 数字(絶対値)を計算する
除法の式でも、たとえば
(−12)÷(−3)
の場合、
- 負の数は2個 → 偶数 → 答えはプラス
- 絶対値:12÷3=4
つまり、答えは+4になります。
逆数の考え方と除法の計算手順
ここまでの内容を踏まえると、除法は次の3ステップで解けます。
①割り算を逆数を使った掛け算に書きかえる
例:
−6÷2=−6×$\frac{1}{2}$
②乗法の符号ルールで符号を決める
負の数が1つ → 答えの符号は マイナス
③絶対値同士で数を計算する
6×$\frac{1}{2}$
=3
したがって答えは「−3」
となります。
分数を含む除法の例
−$\frac{3}{4}÷\frac{1}{2}$
①掛け算に直す
−$\frac{3}{4}×2$
②符号を決める
負の数1つ → 答えはマイナス
③数を計算
$\frac{3}{4}×2$
=$\frac{3}{2}$
よって答えは「−$\frac{3}{2}$」
となります。
正負の加法・減法と、乗法・除法では符号の決まりが異なるため、混同しないよう注意が必要です。
乗法と除法では、「まず符号、次に数字」という統一手順で処理することが非常に重要です。
この考え方を定着させることで、正負の数の計算全体が大幅に安定し、今後の計算単元でも大きく役立ちます。
符号のルールを使いこなす!正負の数の乗除問題の解き方
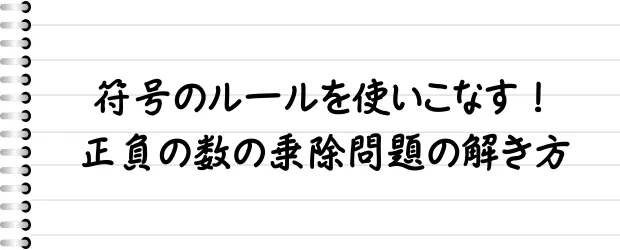
ここまでで、正負の数の乗法と除法における「符号の決まり」や「逆数を使った書き換え方」を学んできました。
ここでは、それらを実際の問題で使いこなすための解き方のコツをまとめます。
乗除の計算でつまずく原因のほとんどは、符号の判断をあいまいにしたまま数の計算に進んでしまうことです。
符号さえ正しく扱えれば、乗除問題は驚くほどミスが減り、計算のスピードも正確さも大きく向上します。
ここでは、符号を素早く正確に判定する方法、問題の解き進め方、間違えやすいポイントとその対処法を丁寧に整理していきます。
符号の組み合わせで答えの符号を素早く判断するコツ
正負の数の乗法・除法では、まず「符号がどうなるかを最初に判定する」ことが最も重要です。
数の計算はその後で構いません。
まず覚える基本の4パターン(最重要)
- 正×正=正
- 負×負=正
- 正×負=負
- 負×正=負
除法の場合も同じです。
符号が同じなら「正」、違えば「負」です。
これが基本ルールです。
複数の数の乗除では「負の数の個数」に注目
たとえば、つぎのような問題を考えてみます。
(−3)×4×(−2)×(−5)
符号だけ見ると、負の数は3つあります。
- 負の数が偶数個 → 答えは正
- 負の数が奇数個 → 答えは負
この例では負が3つ(奇数)なので、答えはマイナスです。
この判断を最初にしてしまうことで、計算途中で迷ったり、後から符号を付け忘れたりするミスを防げます。
数の計算は後回しでOK
符号が決まってから絶対値の計算(符号を取った数字)に進みます。
この順番を徹底するとミスは激減します。
実際の乗除問題で符号ルールを適用するステップ
乗除問題では、つぎの4ステップを意識しましょう。
①数と符号を正しく読み取る
式を見た瞬間に「どの数が負? いくつある?」をまず確認します。
記号に慣れていない人は、式を一度書き直すのも効果的です。
②割り算は掛け算に直す(逆数をかける)
割り算がある場合は必ず、
$a÷b=a×\frac{1}{b}$
に書き換えます。
例:
−6÷(−2)=−6×(−\frac{1}{2})
こうすることで「乗法の符号ルール」をそのまま使えるようになります。
③符号を決める
負の数がいくつあるか数えるだけで、答えの符号が決まります。
④数字(絶対値)だけを計算する
最後に、符号を除いた数字だけを計算します。
この順番を守るだけで、正確な答えにたどりつけます。
符号のルールを間違えやすいケースとその対処法
乗除の符号はシンプルですが、テストやスピード計算になると意外と間違いが起こります。
ここでは代表的なミスとその防止策をまとめます。
負×負で「負」だと思い込んでしまうミス
「マイナスは悪いイメージだから、どうしても結果もマイナスに感じてしまう」という感覚的な誤解が多いパターンです。
対処法は、負×負=正は基本4パターンとして暗記し、練習で慣れるようにしましょう。
慣れると自動的に判断できるようになります。
割り算で符号の扱いが混乱する
とくに、
(−6)÷(−2)
などの問題で「どっちの符号を見ればいいの?」と迷うケースがあります。
対処法は、割り算を掛け算に直す習慣をつけることです。
その瞬間、乗法のルールがそのまま使えるようになります。
計算途中で符号を忘れる
途中式のどこかで符号を書き忘れると、最後の答えが正反対になることがあります。
対処法は、まず符号だけ決めて式の先頭に書いておくことです。
また、途中式でも、符号は必ず明記するようにしましょう。
意識として持っておいてもらいたいのが、数の計算と符号の判断を絶対に同時にやらないということです。
間違えたときは「どの段階でズレたか」を振り返る
符号ミスの克服には「どのタイミングで間違えたか」を確認するのが最も効果的です。
- 符号を読み違えた?
- 負の数の個数を数え忘れた?
- 割り算の書き換えができていなかった?
この反省を重ねることで、符号の扱いが自然と身体に定着します。
| 中学生のおすすめ学習塾3選 | |||
|---|---|---|---|
横浜予備校 |
WAM |
明光義塾 |
|
| 対象 | 中学生 | 中学生 高校生 |
中学生 高校生 |
| 授業料 (税込) |
29,700円~ (月額) |
7,600円~ (週1回) |
15,400円~ (週1回) |
| 入塾金 | 0円 | 16,500円~ | 11,000円 |
| 指導形式 | 学習塾 | 学習塾 (個別指導) |
学習塾 (個別指導) |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | |
正負の数の掛け算割り算でよくある間違いと対策
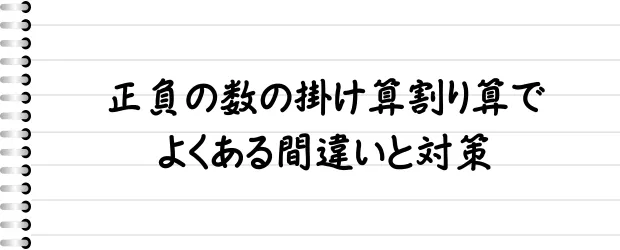
ここまでで、正負の数の掛け算・割り算の基本的な符号ルールは理解できたと思います。
しかし、実際の計算となると「符号をつけ忘れた」「正負が逆になった」といったミスが非常に起こりやすく、多くの中学生がつまずくポイントでもあります。
ここでは、特に間違いが多い場面や注意すべきポイントを具体的に整理し、どのように対策すればミスを大幅に減らせるのかを詳しく解説していきます。
ここで紹介する考え方や確認方法を習慣にすれば、複雑な計算問題でも落ち着いて正しい答えを導けるようになります。
符号の見落とし・逆転ミスを防ぐポイント
正負の計算ミスで最も多いのが、符号の見落としや勘違いによる誤答です。
特にマイナス記号「−」は、数字の左側に小さく書かれているため見逃しやすく、その結果として計算が大きくズレてしまいます。
このことを防ぐためにまず大切なのは、符号と数字は常にセットで読む習慣をつけることです。
たとえば「−4」とあったら、頭の中で「マイナス4」と確実に読んでから計算に進むようにします。
符号を切り離して数字だけを見てしまうと、後で「どっちだったっけ?」と混乱する原因になります。
また、符号の誤解で特に多いのが −(−4) の扱いです。
この場合、マイナスが2回続くので +4になる というルールを忘れやすく、つい「−4」のままで進めてしまうミスがよく見られます。
マイナスが2つ重なると必ずプラスになる、というポイントは繰り返し確認しましょう。
計算に入る前に、符号だけ先に書き出してチェックする方法も効果的です。
たとえば「−3×(−2)」なら、計算の前に「符号は:+」とノートに書くことで、符号ミスの大半が防げます。
特に複雑な式やカッコが多い式では、この「符号先取り法」が非常に役立ちます。
乗除の計算順序を間違えないためのコツ
掛け算と割り算が混ざると、「どれから手をつければいいのか?」と迷うことがあります。
計算の順序そのものを間違えると、正しく符号をつけても答えがズレてしまうため注意が必要です。
これを防ぐには、まず、割り算は掛け算に直して逆数をかけると、符号の考え方が統一できて分かりやすくなります。
例えば、6÷(−2)は6×(−$\frac{1}{2}$) に変換でき、掛け算だけで処理できます。
掛け算だけに統一することで、符号判断も「同符号なら+、異符号なら−」のルールだけに集中できます。
また、複数の乗除が並んでいるときには、符号だけ先に決めてしまう方法が非常に有効です。
「負の数が何個あるか」だけを数えて、
- 負の数の個数が偶数 → 答えはプラス
- 負の数の個数が奇数 → 答えはマイナス
と判断できます。
これによって、途中計算で符号が変わることに気を取られず、落ち着いて数の計算に専念できるようになります。
見直しのときも、計算式をもう一度なぞるのではなく、符号の順序・判断が正しいかだけを集中的にチェックすることで、ミスを素早く発見できます。
つまずきやすい符号ミスの具体例と修正方法
ここまで見てきた符号のミスについて、特に多い間違いの例と、それをどう直すべきかを紹介します。
自分がどのタイプのミスをしやすいのかを理解しておくと、対策がより効果的になります。
よくあるミス①:負×負を「負」としてしまう
例:
−3×(−5)を−15と書く
原因は、「負の数だから答えも負」という思い込みです。
対処法として、計算前に必ず符号だけ先に判断しておき、書き出すことが有効です。
「− × − → +」と書く癖をつければ、このミスは大幅に減ります。
よくあるミス②:割り算の符号を元のまま使ってしまう
例:
8÷(−4)を8÷4のつもりで計算してしまい、+2と答えてしまう
割り算は符号が見えづらく、符号の位置も掛け算より複雑なため見落としがちです。
必ず「÷相手の符号」を意識することが大切です。
また、÷(−4)を×(−$\frac{1}{4}$) に変えて計算する方法も効果的です。
よくあるミス③:符号の付け忘れ・書き間違い
数字だけ正しく計算できても、符号の付け方を間違えると答えは不正解になります。
符号を忘れやすい人は、答えを書いたあとに必ず「符号チェック」だけをもう一度行う習慣をつけることが重要です。
まとめ
正負の数の理解は、符号の意味と数直線のイメージから始まり、 乗法では同符号のかけ算が正、異符号が負となる規則を覚えることが鍵です。
また、除法は割り算を掛け算に直すことで、乗法のルールをそのまま使えます。
符号の判別を最優先にして、計算ミスを防ぐコツやミスの典型例とその直し方も学びました。
これらを習得すれば、数学の基礎計算力が格段に上がり、より複雑な問題にも対応できるようになります。
| 中学生のおすすめオンライン塾・家庭教師3選 | |||
|---|---|---|---|
ウィズスタディ |
家庭教師の銀河 |
WAM |
|
| 対象 | 中学生 高校生 |
中学生 | 中学生 高校生 |
| 授業料 (税込) |
9,800円~ (1科目) |
2,750円~ (1コマ) |
7,600円~ (週1回) |
| 入会金 | 27,500円~ | 22,000円 | 16,500円~ |
| 指導形式 | 学習塾 (オンライン) |
家庭教師 | 学習塾 (オンライン) |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | |
練習問題
問題1
次の計算をしなさい。
(1) −3 × (−4)
(2) 6 ÷ (−2)
(3) −5 × 2 × (−3)
(4) 12 ÷ (−3) ÷ (−2)
(5) −2 × (−1) × (−4)
問題2
ある学校で数字カードを使ったゲームをしています。
そのゲームは下記のとおりです。
ルール:2枚のカードを引いて掛け算をすると結果が得点になります。
カードには「+の数」と「−の数」が書かれており、Aさんは次のようにカードを引きました。
(1) 1回目: −3 と −2
(2) 2回目: −4 と +5
それぞれの計算結果(得点)を求めなさい。
解答
問題1
(1) −3 × (−4)
→ 符号:負×負=正
→ 12
(2) 6 ÷ (−2)
→ 符号:正÷負=負
→ −3
(3) −5 × 2 × (−3)
→ 負×正×負 → 負の数は2つ → 答えは正
→ 5 × 2 × 3 = 30
→ 30
(4) 12 ÷ (−3) ÷ (−2)
→ 負が2つ → 答えは正
→ 12 ÷ 3 ÷ 2 = 2
→ 2
(5) −2 × (−1) × (−4)
→ 負が3つ → 答えは負
→ 2 × 1 × 4 = 8
→ −8
問題2
(1) −3 と −2
→ 負×負=正
→ 6点
(2) −4 と +5
→ 負×正=負
→ −20点
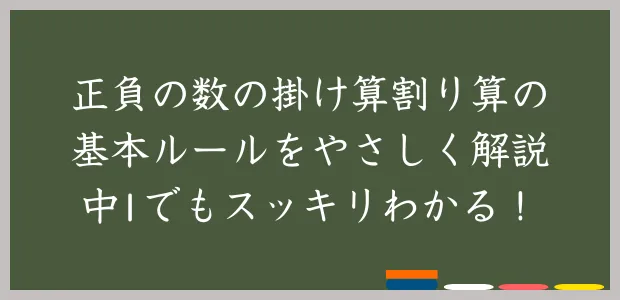
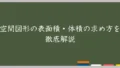
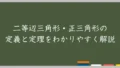
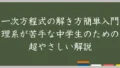
コメント