理系科目の学習において、どうしても避けて通れないものが公式や定理、定義の暗記です。
暗記が苦手で、仕方なく理系を選択した高校生も多少なりともいるとは思いますが、それでも理系科目にはどうしても覚えてから使えるようになる知識もないこともありません。
このページでは、暗記に苦手意識がある学生さんに向けて、理系科目で出てくる公式や定理、定義を効率的に覚えていく方法を紹介していきます。
- 暗記が苦手でも理系は乗り越えられる!
- 理系科目の公式・定義・定理は「使って理解する」ことで覚えやすくなる
- 公式や定義・定理は「意味と使いどころ」をセットで覚えよう
- 手を動かせば記憶が定着する:アウトプット型の勉強法を習慣に
- イメージ・図・語呂で覚える:暗記が苦手な人のための工夫
- 繰り返しとアウトプットで「忘れない知識」に変える
- 学びを“実行”に落とし込む:日々の学習にどう活かすか
- 授業中に「理解」と「記憶の種」を植える:インプットの質を変える
- 家庭学習での定着:演習と復習のバランスを取る
- 「忘れる前に復習する」:定着のための復習戦略
- 定期テストや模試での活用法:点数につなげるアウトプット
- 応用力を鍛える:受験勉強への発展的な取り組み
- まとめ
暗記が苦手でも理系は乗り越えられる!
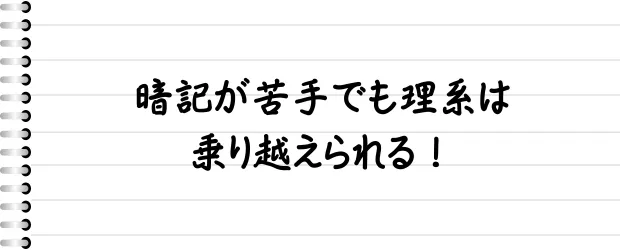
理系科目といえば、「公式」「定義」「定理」といった言葉が頻繁に登場します。
数学では複雑な公式や証明、物理では運動の法則やエネルギー保存の定理、化学では化学式やモルの概念、生物では細胞や酵素、進化の過程など――どれも高校で学ぶうえでは欠かせない重要な知識です。
その一方で、こうした知識の大半は暗記を避けて通れません。
暗記が得意な人にとっては問題ないかもしれませんが、「暗記がとにかく苦手……」というタイプの学生さんにとっては、理系科目の学習が大きな壁に感じられることもあるでしょう。
とはいえ、心配はいりません。
理系科目の勉強で重要なのは、単なる丸暗記ではなく、「理解しながら覚え、実際に使えるようになること」です。
これは暗記が得意でない人にとってこそ、効果的な学習方法になります。
まずは、理系の勉強で最も重要な考え方の一つ、「使って覚える」ことの意味から見ていきましょう。
理系科目の公式・定義・定理は「使って理解する」ことで覚えやすくなる
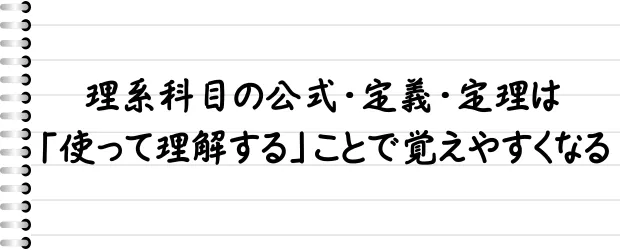
改めてになりますが、理系科目で暗記すべき内容が多いのは事実です。
しかし、その暗記を「ただ詰め込むだけ」で終わらせてしまうと、問題を解くときに応用が利かず、テストでもミスが増えてしまいます。
ここで重要になるのが、「理解」と「活用」をセットにして覚えるという考え方です。
「ただ覚える」ではなく「使って理解する」
公式や定義は、「意味を考えずに暗記しよう」とすればするほど、覚えにくく、忘れやすくなります。
たとえば、数学で学ぶ公式を覚えたとしても、それが「どうして成り立つのか」「どんな問題で使うのか」が分からなければ、テストで出題されたときに使いこなすことができません。
ここで1つ、よくある公式を例に考えてみましょう。
例:一次方程式の基本形
$ax+b=0$
この式は、多くの中学生が最初に習うものですが、実際に$x$の値を求めるためには、
- $b$を移項する(符号が変わる)
- $a$で割る(逆数をかける)
というステップを、「式の変形を使って解決する」という考え方に基づいて行っています。
この操作の意味を理解していると、似たような問題が出てきたときにも応用が効くようになります。
つまり、公式の使い方を実際に自分の手でやってみることが、記憶の定着につながるということなのです。
次は、理科の例でこの考え方をもう少し深掘りしてみましょう。
公式を「意味から理解する」と応用しやすくなる
たとえば、物理で習う「オームの法則」は、単純な公式のように見えますが、その背景には「電気の流れと抵抗の関係」があります。
例:オームの法則
$V=IR$
ここで、
- $V$は電圧(ボルト)
- $I$は電流(アンペア)
- $R$は抵抗(オーム)
この公式を覚えただけでは、どんな問題でも解けるわけではありません。
例えば、「電圧が大きくなると電流も大きくなる」「抵抗が大きくなると電流が流れにくくなる」といった現象とのつながりを理解しておくことで、公式が意味を持ち始めます。
つまり、「公式」や「定義」は、それ単体で覚えるのではなく、「現実でどう使われるのか」「どういう意味があるのか」と結びつけて理解することで、より忘れにくく、使いやすい知識になります。
次からは、こうした「意味の理解」を深めるために欠かせない「使いどころ」の意識についてお話しします。
公式や定義・定理は「意味と使いどころ」をセットで覚えよう
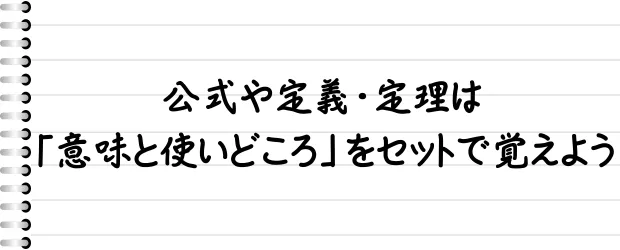
上記でも説明した通り、公式を覚えただけでは問題を解けるようにはなりません。
大切なのは、「どんなときにそれを使うのか」が分かるようになることです。
これによって、公式を「持っているだけ」から「使いこなせる」状態へと変えることができます。
公式の「意味」がわかれば忘れにくい
よくある理系のつまずきの1つに、「公式や定理の意味がわからず、丸暗記で済ませてしまう」というものがあります。
これを防ぐには、視覚的・具体的に意味を捉えることが効果的です。
例:三平方の定理(ピタゴラスの定理)
$c^2=a^2+b^2$
例えば、三平方の定理を例にしてみます。
これは直角三角形における斜辺と他の2辺の関係を示す公式です。
これをただ覚えるのではなく、実際に直角三角形を図に描いてみると、斜辺の長さが他の2辺から導かれる理由が視覚的に理解できます。
たとえば、$a=3$,$b=4$としたとき、
$c^2=3^2+4^2=9+16=25$
$c=5$
という結果になります。
これを「数字」「図」「意味」で確認することで、理解が深まり、忘れにくくなるのです。
「使いどころ」がわかれば、応用力がつく
しかし、たとえ公式を完璧に覚えていても、「どの場面でその公式を使えばいいのか」が分からなければ、問題を前にして手が止まってしまいます。
これは特に物理や化学で顕著です。
例:運動方程式($F = ma$)
次は物理の運動方程式を例に見ていきます。
この式は、力($F$)が質量($m$)と加速度($a$)の積で表されることを示しています。
公式そのものは単純ですが、これを「どんな問題で使うのか」が分かっていないと、記憶の中にあっても使えません。
- 物体に働く力が変わるとどうなるか?
- 摩擦力が加わったときは?
- 重力との関係は?
こうした「使いどころ」のイメージがあることで、公式を使う判断が正確になり、問題の解法がスムーズになります。
ここまでの内容をまとめると、理系科目の暗記を効率化するには、公式や定義をただ覚えるのではなく、
- 「意味」を理解する
- 「どの場面で使うか」を知る
この2点をセットで身につけることが重要です。
この後の説明では、そうした知識を定着させるための「実践的な勉強法」について詳しく紹介します。
手を動かせば記憶が定着する:アウトプット型の勉強法を習慣に
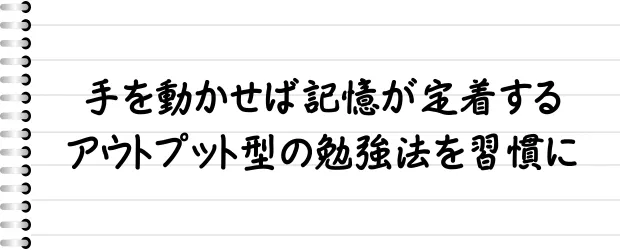
上述した通り、理系科目の公式や定義、定理は「意味」や「使い方」と一緒に覚えることが重要です。
ですが、「意味が分かっても、覚えきれない…」という声も多く聞かれます。
その悩みに対する解決策のひとつが、「手を動かす」アウトプット型の学習です。
つまり、頭の中だけで理解しようとするのではなく、実際に書いて、声に出して、使って覚えることです。
なぜ「手を動かす」と記憶に残るのか?
脳科学的にも、視覚・聴覚・運動(身体の動き)を連動させて記憶することで、定着率が高くなることが知られています。
理系科目の勉強では、
- 実際に式をノートに書く
- 図を描いて整理する
- 声に出して用語を覚える
- 問題を解いてフィードバックを受ける
といった作業がすべて「能動的な記憶」に繋がります。
たとえば、英語の単語を黙読するよりも、何度も書いたり声に出したりした方が覚えやすいのと同じで、理系の公式も書きながら覚える方が圧倒的に効率的です。
実際に手を動かして覚える学習方法を下記で紹介していきます。
実践①:公式ノートを自作する
方法の1つ目は公式ノートを作成することです。
教科書に載っている公式や定理をそのまま見るだけでは、なかなか記憶に残りません。
そこでおすすめなのが、「自分用の公式ノート」を作ることです。
- 左側に公式を記載
- 右側にその使い方や例題を記載
- 下部には図解やメモ、注意点などを追記
このように、自分の言葉で整理していくことで、ただの「受動的な暗記」から「能動的な理解」へと変わっていきます。
実践②:ミスした問題は必ず「書き直して」覚える
2つ目は解きなおしをしっかりと行っていくことです。
テストや演習で間違えた問題は、解きっぱなしにせず、必ず手を動かしてもう一度解き直すことが大切です。
特に、公式の適用ミスや定義の混同が原因のミスは、正しい使い方をその場で定着させるチャンスになります。
- なぜ間違えたかを分析
- 正しい手順をノートに再記述
- 似た問題を解いて確認
こうした「書いて覚えるプロセス」が、ミスを減らし、知識の再構築に役立ちます。
イメージ・図・語呂で覚える:暗記が苦手な人のための工夫
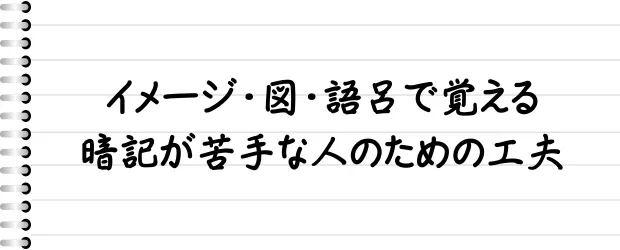
「手を動かす」ことに加えて、視覚的・感覚的な工夫を加えることで、より記憶しやすくなります。
特に、暗記が苦手な人にとっては、「公式や定義にストーリーや形を持たせる」ことが効果的です。
図にして覚えると、抽象が具体になる
数学や物理、化学などでは、抽象的な式や概念が多く登場します。
これらを「図」で視覚的に捉えることで、理解が飛躍的に深まります。
例:ベクトルの加法(数学)
この説明をイメージしやすくするのはベクトルの合成の定義が分かりやすいの説明します。
「ベクトルAB + ベクトルBC = ベクトルAC」という概念を言葉で覚えるのは難しいですが、図で三角形の形に描いてみると、一目で意味が理解できます。
視覚情報は記憶にも強く残りやすく、「図で覚えた内容」は時間が経っても思い出しやすいのが特徴です。
語呂合わせは「きっかけ」になる
また、暗記には「語呂合わせ」がかなり効果があります。
一見ふざけているように見える語呂合わせですが、暗記においては非常に強力な武器になります。
特に、物理や化学では単位や関係式が多く、語呂で「きっかけ」を作るだけで、スムーズに引き出せるようになります。
その例をいくつか紹介していきます。
例:電磁気の右手の法則
「電磁力は親の力(電流:中指、磁界:人差し指、力:親指)」
⇒中・人指し・親指の順で覚える語呂
例:炎色反応(化学)
「リアカーなきK村、動力借りようとするも貸してくれない、馬力でやろう
(Li:赤、Na:黄、K:紫、Cu:青緑、Ca:橙、Sr:紅、Ba:黄緑)」
語呂は暗記の補助として使い、意味理解とセットで運用すると非常に効果的です。
イメージ化で抽象を感覚に変える
さらに、化学の反応式や生物の代謝経路など、「工程が複雑で記号だらけ」の内容は、図やアニメーション的なイメージに変えることで理解しやすくなります。
たとえば、光合成の反応式を覚えるときには、「太陽のエネルギーが葉に吸収されて、二酸化炭素と水が合体してブドウ糖ができる」というストーリーを思い浮かべるだけで、機械的な暗記よりも記憶に残ります。
このように、図・語呂・イメージの3つをうまく使うことで、暗記に頼らず、感覚で覚える方法が可能になります。
繰り返しとアウトプットで「忘れない知識」に変える
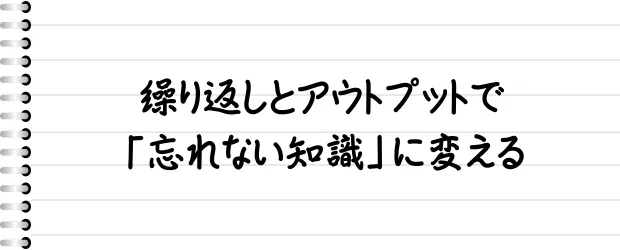
ここまで様々な暗記方法を紹介してきましたが、いくら意味を理解しても、覚えた内容を「思い出せなければ」テストでは使えません。
記憶の定着に不可欠なのが、反復とアウトプット(出力)です。
ここからは覚えた知識の効果的なアウトプットの方法を説明していきます。
「覚える」よりも「思い出す」ことが重要
心理学の研究では、「思い出す作業」そのものが記憶の強化につながることが証明されています。
(出典:Karpicke & Roediger, 2008)
つまり、何度もノートを読むよりも、一度自分で問題を解いたり、口頭で説明したりするほうが記憶に定着するのです。
では、この理論に則って、効果的な反復方法を下記で見ていきます。
具体的な反復法:3ステップ復習
効果的な反復方法は下記の3ステップ復習がおすすめです。
- 即時復習(勉強後10分以内に内容を整理)
- 1日後復習(翌日に同じ内容をざっくり思い出す)
- 1週間後復習(定着度をチェックして再整理)
このサイクルを意識するだけで、記憶の長期保持率は格段に上がります。
アウトプットの工夫:人に説明する/問題を解く
さらに、覚えた内容を確認するには
- 友達に説明する
- 自分に向けて話す(セルフトーク)
- 問題集を解く・赤シートで隠して復習する
といった方法が効果的です。
特に「人に説明する」ことは、自分が理解できていない部分を浮き彫りにする手段にもなり、記憶の再構築に最適です。
学びを“実行”に落とし込む:日々の学習にどう活かすか
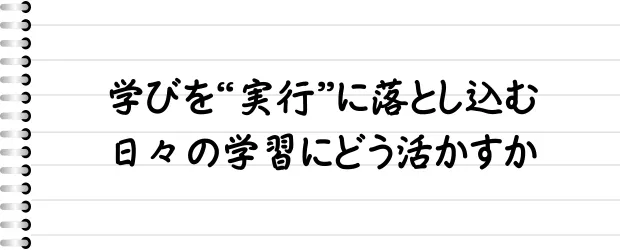
ここまで、理系科目の定義・定理・公式をしっかりと理解し、定着させるための「使って覚える」「意味を理解する」といった学習法を解説してきました。
しかし、これらの学習法を知識として理解するだけで終わらせず、実際の学習サイクルに取り入れてこそ、真の意味で効果が表れます。
この後は、普段の授業、日々の家庭学習、テスト勉強、そして受験勉強といったシーンごとに、具体的にどう取り入れるべきかを段階的に紹介していきます。
授業中に「理解」と「記憶の種」を植える:インプットの質を変える
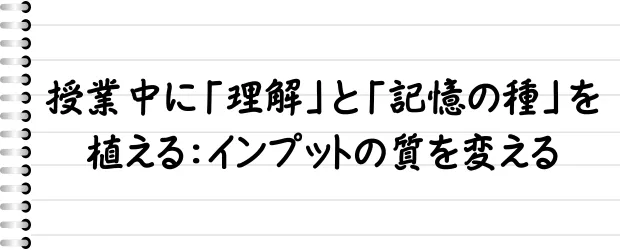
授業中は「公式の導出や意味」に注目しよう
理系科目の授業では、先生が板書した内容をノートに写すことに必死になりがちですが、重要なのはなぜその公式が成り立つのかという背景です。
特に理系科目では、公式や定義は必ずある理由があって導かれています。
その場で完璧に理解できなくても、「なぜこの式になるのか」という視点を持つだけで、学習の質が大きく変わります。
- 公式が出てきたときに、「どうしてこの形になるのか」と頭の中で問いかける
- 板書の横に、「使う場面」や「キーワード」などをメモしておく
- 定理の証明や意味に関して、自分なりにひと言で言い換えてみる
こうした習慣をつけることで、授業が単なる「写経」から「知識をつかむ時間」に変わっていきます。
家庭学習での定着:演習と復習のバランスを取る
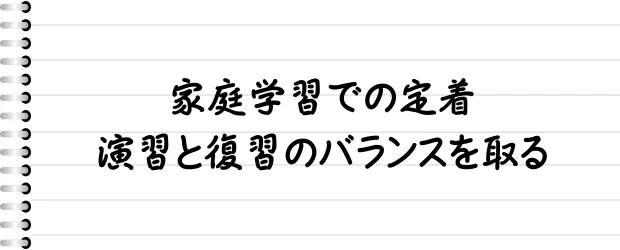
上記で授業中に完璧に理解できなかったはなぜこれが導かれるのか?という視点を持つ重要性をお話しましたが、そういった視点も含めて授業で得た知識の種を、自宅学習で定着させることが重要です。
ここでは、公式や定理を「身につける」段階に進めていきます。
練習問題で“使う練習”を必ずセットに
新しい公式を覚えたその日に、必ずその公式を使う問題をいくつか解くのがポイントです。
- 覚える → 解く → 間違える → 見直す → もう一度解く
このサイクルを回すことで、知識は初めて「使える知識」になります。
問題集を解く際には、「この公式を使うための問題を3問」など、意識的に目的をもって選ぶと効果的です。
自作の「まとめノート」で意味と使い方を整理
公式や定義をノートにまとめるときは、以下のような情報も一緒に書くと定着しやすくなります。
- 名前(定理・公式名)
- 式の形
- 使いどころ
- 覚え方(語呂や図)
- 例題1つ(簡単なもの)
このように「意味」「使いどころ」「練習問題」をセットでまとめておくと、あとから復習しやすくなります。
また、自作の公式ノートとセットで学習するとより効果的でしょう。
「忘れる前に復習する」:定着のための復習戦略
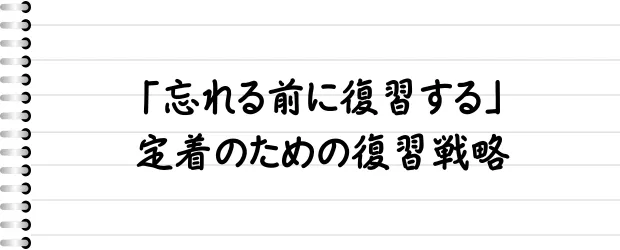
自宅での復習のやり方は上記のとおりですが、復習を行うタイミングも重要です。
せっかく時間をかけて覚えた知識も、復習しなければ驚くほど簡単に忘れてしまいます。
エビングハウスの忘却曲線にあるように、人間の記憶は短期間で急速に失われる性質があります。
復習は“戦略的”に行うと記憶に残りやすい
しっかりと覚えたことを定着させるには、下記のようなスケジュールで復習をすることをおすすめします。
おすすめの復習スケジュール
- 1日後:軽く見直して確認する(3〜5分でもOK)
- 3日後:問題演習で定着の確認
- 1週間後:間違えた問題をもう一度解く
- 1か月後:要点だけを再チェック
このように繰り返しのタイミングを分散させることで、記憶が長期的に定着しやすくなります。
「間違いノート」や「付箋メモ」で苦手を可視化
間違えた問題や理解があいまいだった公式は、付箋や別ノートに書き出して、目につく場所に貼るのも効果的です。
- 机の前
- スマホのロック画面
- トイレの壁 など
「何度も目にする」ことで自然と記憶に残っていく工夫をしましょう。
定期テストや模試での活用法:点数につなげるアウトプット
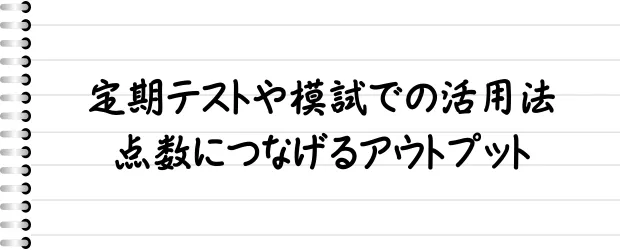
ここまでは復習の方法やスケジュールについてお話してきました。
ですが、理系科目の公式や定義は覚えて終了ではありません。
定期テストや模試では、知識を「覚えているか」ではなく「使えるか」が問われます。
なので、ここでは、試験で得点を取るための実践的な活用法を解説します。
試験前は「予想問題」と「間違えた問題」の見直しを重点に
勉強の最後に重要なのは、アウトプットの強化です。
以下のような演習を行いましょう。
- 過去問や予想問題を制限時間内で解いてみる
- 公式や定理を見ずに、自分で一から解法を組み立ててみる
- 間違えた問題だけを集めて、何度も解き直す
試験本番では、「この公式を使う」と判断する力と、実際に使いこなす力の両方が求められます。
アウトプット中心の復習は、その力を鍛える近道です。
解けた問題でも「なぜ使ったか」を振り返るクセを
さらに、正解できた問題も、「どうしてその公式を使ったのか」「他の方法でも解けたか」を考えるクセをつけておくと、応用力が高まります。
応用力を鍛える:受験勉強への発展的な取り組み
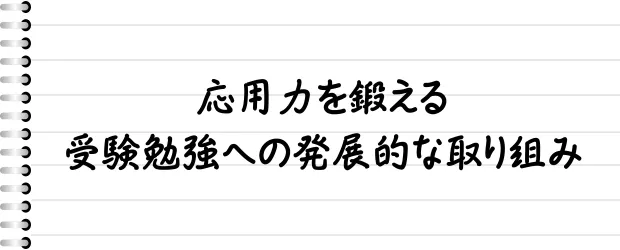
最後に少し応用的な部分ですが、受験では、「基本的な公式を知っている」だけではなく、複数の知識を組み合わせて使う力が求められます。
なので、受験勉強の際におすすめの取り組みを簡単ではありますが紹介しておきます。
応用問題では「複数の定理や概念がからむ」
特に高校入試や大学入試では、以下のような能力が試されます。
- 条件から使う公式を自分で選び取る
- 図形問題で図を描いてイメージする
- 単元をまたいだ複数の知識を統合する
こうした問題に対応するには、公式を丸暗記するだけでなく、意味と使いどころを深く理解しておくことが不可欠です。
自分で問題を作ってみると“理解の本質”に近づく
受験勉強中に余裕があるときは、「自分で問題を作ってみる」こともおすすめです。
例
- 「この公式を使う問題を1問作ってみよう」
- 「この定義を使わないと解けないようなひねった問題を考える」
問題を作るという作業は、公式や定義の核心を理解していないとできません。
これは、理解の最終チェックにもなります。
まとめ
ここまで、理系科目の定義・定理・公式を覚えるための具体的な学習法と、その実践方法について解説してきました。
最後にもう一度、理系の知識を効率よく、そして確実に身につけるための重要なポイントを振り返ります。
- 意味を理解する
└「なぜこの式になるのか」「どうしてこう定義するのか」に目を向ける - 使って覚える
└ 練習問題や例題で手を動かし、アウトプットで身につける - 視覚・語感で補助する
└ 図・グラフ・語呂・リズムで記憶を強化する - 復習と応用で記憶を定着させる
└ 復習スケジュールと、応用問題への挑戦を計画的に行う
この4つを意識して学習することで、理系科目の学習は「暗記が苦手」という悩みから解放され、「理解し、使える力」に変わっていきます。
理系を学ぶすべての学生にとって、「覚える」ことは目的ではなく、考え、活用するための手段です。
焦らず、段階的に、正しい方法で積み重ねていきましょう。
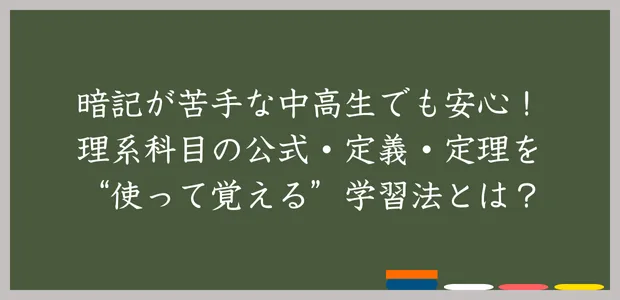









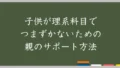
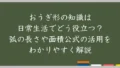
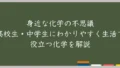
コメント