理系科目に限らず、学校で勉強するものについて、どうしても苦手な科目や分野が出てくることがあると思います。
苦手になる原因は人それぞれ違いますが、多くの人に共通している原因は、問題が解けなかったり、授業や教科書の内容が理解できないという点です。
これらの原因は学習方法の見直しや工夫で解決することができますが、どうしても回り道になってしまうと感じてしまうのは否めません。
なので、そもそも苦手にならないようにすることはできるのでしょうか?
このページでは、理系科目に絞って、理系科目を苦手にならないようにするためにできることや意識することについて説明していきます。
理系科目が苦手になる本当の理由とは?――「分からない」から「苦手」へ
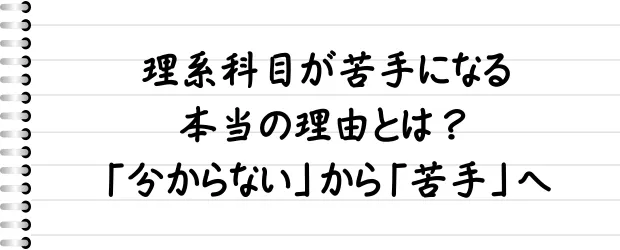
理系科目が苦手だと感じている人は少なくありません。
「計算が嫌い」「公式が覚えられない」「理屈っぽくて難しそう」……こうした声は、学校でもよく聞かれます。
ですが、多くの場合、その「苦手意識」は本人の能力不足ではなく、学び方や意識の持ち方の違いに由来しているのです。
たとえば、数学の文章題が苦手だと感じている人の多くは、問題の意味が理解できないまま、無理やり計算しようとしていることが原因です。
理科であれば、用語や知識の暗記だけに頼っていて、「なぜそうなるのか?」という本質的な理解ができていないケースが多く見られます。
苦手意識の裏には、「できなかった経験」や「分からなかった記憶」が積み重なっていることがほとんどです。
その経験が「自分は理系に向いていない」という思い込みにつながってしまいます。
しかし、それは本当に向いていないのではなく、向き合い方を知らないだけなのです。
このことを踏まえてここからは、理系科目が苦手にならないために必要な考え方と、日常生活に取り入れられる理系的思考法を紹介していきます。
知識ではなく、意識を変えるところから始めましょう。
理系科目は「特別なもの」じゃない――日常の「なぜ?」が学びのスタート
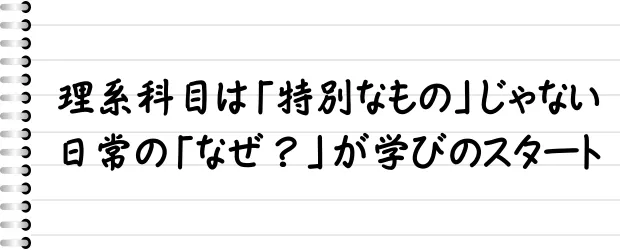
理系の勉強に苦手意識を持つ人ほど、「理系科目は特別な人だけができるもの」と感じている傾向があります。
ですが、本来理系科目の勉強内容というのは、私たちが日常の中で自然と使っている知識や考え方そのものです。
たとえば、以下のような出来事を考えてみましょう。
- 電車が時間通りに来るのは、どうやって制御されているのか?
- なぜコーラにメントスを入れると泡が噴き出すのか?
- 買い物で「1個あたりいくらか」を計算する時に、どんな計算をしているのか?
これらすべてに、理系的な考え方が使われています。
つまり、理系の知識は「教科書の中の話」ではなく、「私たちの生活の一部」なのです。
理系の第一歩は「なぜ?」と疑問を持つこと
理系科目の勉強内容が日常生活にあふれていることをイメージできたら、次に理系科目に強くなるための考え方をお伝えしていきます。
結論からお話すると、理系に強くなるための第一歩は、身近な現象に対して「なぜ?」と疑問を持つ習慣をつけることです。
たとえば、朝起きてカーテンを開けたら部屋が明るくなった――これは「光が反射する」「太陽光がガラスを通って入ってくる」など、物理の知識と結びついています。
雨が降ったあとに虹が見えた――これは「光の屈折と反射」「水滴の構造」「光の三原色」など、理科の分野そのものです。
一見ただの「現象」も、疑問をもって見直せば、それはすでに理系的な視点です。
そして、疑問を持ったらそのままにせず、調べてみる・誰かに聞いてみる・実験してみるというステップにつなげていくことが大切です。
調べること自体が苦手な場合は、まずは先生や家族に「なんでこうなるの?」と聞いてみましょう。
それだけでも、自分の興味の扉が開きます。
「理系=日常の中にある」を実感できるシーンとは?
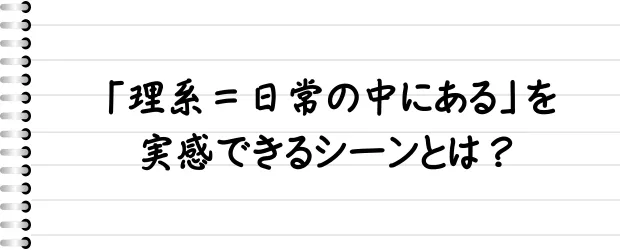
さらにここで、理系科目が得意な人たちが日常生活をどのように見ているのかを紹介していきます。
理系科目が得意な人たちは、「理系の力をどこで使っているか」に敏感です。
つまり、彼らは日常生活の中で理系的思考を自然と取り入れているのです。
では、私たちもどうすれば日常の中で理系の考え方を身につけることができるのでしょうか?
料理は立派な科学の実験
日常生活の理系的な思考を活用できる代表例は料理が挙げられます。
調味料を混ぜる、温度を調整する、加熱時間を測る――これらすべてに化学・物理・生物の知識が関わっています。
たとえば、揚げ物をする時に油の温度が高すぎると焦げてしまうのは、タンパク質の変性や油の発煙点に関係しています。
パンをふくらませるための酵母の働きは、生物の「発酵」の知識が必要です。
このように、料理は身近にできる科学実験です。
「なぜこの調味料で味が変わるのか」「どうして卵を泡立てるとふわふわになるのか」と考えながら調理するだけで、理科の見方が変わってきます。
買い物は日常の数学
また普段の買い物では数学の考え方を活かすことができます。
たとえば、スーパーで「100グラムあたりの価格がいくらか?」を計算したり、「ポイントを使った方が得か?」といった計算をしているとき、数学的思考を自然と使っていることになります。
また、友達とお金を割り勘にしたり、予算を立てて何が買えるかを考えるときも、比例・割合・四則計算などの知識が使われています。
このように、「計算」や「論理的な判断」は日常にあふれています。
つまり、理系を苦手にしないためには、「今、理系的なことをしているな」と自覚することが鍵なのです。
意識することで、勉強している内容と生活がつながり、「使える学び」になっていきます。
成功体験が苦手意識をなくす――理系に自信をつけるには?
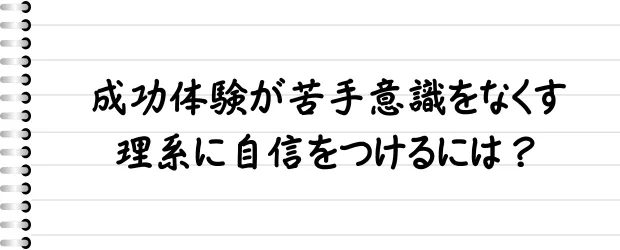
ここまでの説明で理系科目を日常生活で取り入れることが、理系科目を得意にしていく第一歩だということが分かりました。
第一歩を踏み出すためのこういった思考ができるようになるためには、少しでも理系科目に対する苦手意識がなくなっているとスムーズに導入することができるでしょう。
しかし、苦手意識をなくすのは簡単なことではありません。
その理由は、多くの人が「理系は苦手」と感じてしまうのは、「うまくできなかった経験」が強く残っているからです。
特に数学の問題で点数が取れなかったり、理科の実験でうまく結果が出なかったとき、その失敗が「自分には向いていない」という誤解につながってしまいます。
ですが、大切なのは完璧にやることではなく、小さな「できた!」を積み重ねることです。
小さな成功がやる気を生む
たとえば、昨日できなかった計算問題が今日は解けた。実験で予想通りの結果が出た。公式の意味がようやく理解できた――こうした体験を積むことで、少しずつ自信が生まれます。
勉強において最も重要なのは、「自分は成長している」という実感です。
それがないままテストに臨んでも、点数が取れずに自己肯定感を下げてしまうだけです。
だからこそ、日々の学習の中で「今日やった中で、何ができるようになったか?」を振り返るようにしましょう。
1問でも自力で解けたなら、それは立派な成果です。
分からないことはそのままにしない――「分からない」を解決する力を育てる
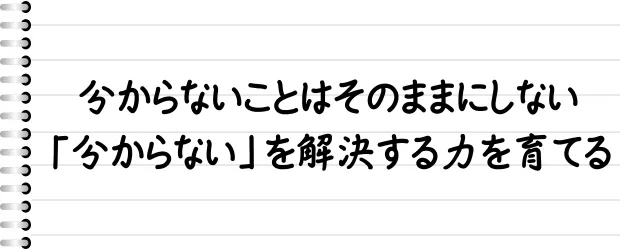
さらに、理系科目を苦手と感じてしまう最大の要因の一つは、「分からないことをそのままにしてしまうこと」です。
特に理系の内容は、積み上げ式になっているため、ひとつでも分からないポイントがあると、次の内容に進んだときにさらに分からなくなってしまいます。
たとえば、数学では「文字式の意味があやふやなまま、方程式に進んでしまう」といったケースが多く、理科では「物質の分類が理解できていないまま化学反応に入る」などが典型例です。
こうした状態が続くと、授業を聞いても「何を言っているのか分からない」と感じるようになり、勉強自体を避けるようになります。
これは、誰にでも起こり得ることです。
では、どうすれば「分からない」をそのままにせず、乗り越えることができるのでしょうか?
「分からない」はチャンスだと考えよう
「分からない」ことが出てきたとき、多くの人は「ダメだ、自分には向いていない」と思ってしまいがちです。
しかし、実はこれは成長のチャンスでもあります。
分からないことに出会ったということは、自分の理解の限界が見えたということです。
そして、それを乗り越えることで、確実に一歩前に進めるのです。
こういったときに重要なのは、「分からない」と感じた瞬間に立ち止まることです。
その場で理解しようとせずに、あとでまとめて調べたり、誰かに聞いたりして処理しようとすると、情報があいまいになったまま定着してしまいます。
すぐに質問する・調べる習慣をつける
たとえば、授業中に分からないことが出たら、その日のうちに解決することを目指しましょう。
方法は次のようなものがあります。
- ノートの余白に「?」マークをつけておいて、授業後に先生に聞く
- インターネットで調べてみる(※信頼できる情報源を選びましょう)
- 友達に説明してもらう(教える側にもメリットがあります)
- 図書室の参考書や教科書を読み直してみる
このように、「その日のうちに処理する」というサイクルをつくることで、わからないことをため込まず、継続的に理解を深めていくことができます。
信頼できる情報源を使うことも大切
分からないことを自分で調べて解決するのは、能動的に学習をしていることなので、自分の知識にしていくという意味では非常に効果的です。
その一方で、特にインターネットで調べる場合、情報の信頼性に注意が必要です。
間違った知識を覚えてしまうと、あとで修正するのに時間がかかってしまいます。
以下のような情報源は、比較的信頼性が高いとされています。
- 教育系YouTubeチャンネル
- 文部科学省や教育委員会が監修するサイト
- 中学・高校向けの参考書を出版している出版社の公式サイト
また、わからないことが複数ある場合は、「何がわからないのか」を具体的にすることも大切です。
たとえば「この公式の意味が分からない」「計算の途中で何をしているのか分からない」といった具合に、ポイントを言語化できるようになると、質問もしやすくなります。
一人で悩まない――仲間と学ぶことで理系はもっと楽しくなる
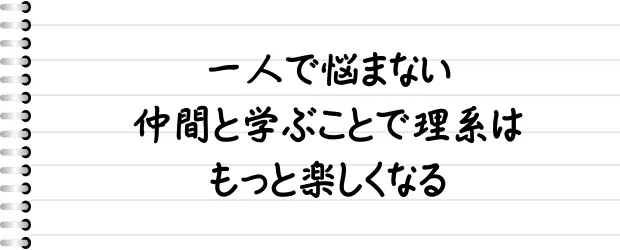
分からないことを自分で解決していく力も重要ですが、どうしても理系科目の勉強を一人で進めるのは、時に大きな壁にぶつかることもあります。
「分からない」「面倒だ」と感じたときに誰にも聞けず、ただただ苦手意識が積み重なってしまう……そんな状況に心当たりがある人も多いのではないでしょうか。
ですが、理系科目こそ仲間と一緒に学ぶことで楽しさが倍増する科目なのです。
友達と一緒に問題を解くことの意味
たとえば、同じ問題を2人で考えて、意見を出し合ってみると、自分では思いつかなかった視点に気づくことがあります。
また、間違えた問題を「なぜ間違えたのか」を一緒に検討することで、記憶に残りやすくなります。
実は、人に教えたり、教えられたりすることで理解はより深く定着するということが、さまざまな学習研究でも明らかになっています。
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0959475210001064
「一緒に学ぶ」ということは、勉強を楽しむだけでなく、理解を深めるためにも非常に効果的な方法なのです。
家族に説明してみるのも効果あり
また、友達以外にも、家族や兄弟に説明してみるのもおすすめです。
たとえば、「今日習ったことを5分で話してみる」といった形でアウトプットするだけでも、頭の中が整理されていきます。
もし話を聞いてくれる人がいない場合は、「自分に説明するつもりでノートにまとめる」だけでもOKです。
理解できた内容を言葉にして整理するプロセスは、記憶の定着に非常に効果的です。
興味のあることから理系に近づこう――動画・本・体験のススメ
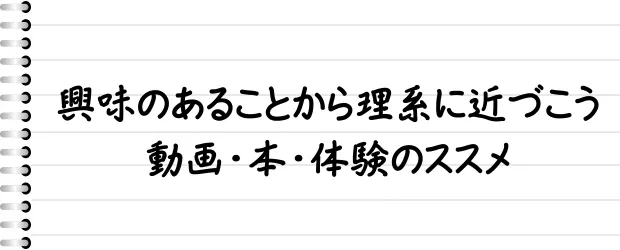
ここまでは苦手な理系科目の勉強方法をお伝えしてきました。
ですが、勉強方法が分かっても苦手な勉強をしていくのは大変であるというのもまた事実です。
そんな時は興味のある分野から勉強をしていくことをおすすめします。
「理系科目は苦手だけど、宇宙の話は好き」「人体の仕組みは面白いと思う」
そんな感覚を持っている人は、実は理系への入口にすでに立っているのです。
勉強=教科書の内容だけ、と思い込むと苦しくなってしまいますが、理系の世界には好奇心を刺激するテーマがたくさんあります。
楽しみながら学べる動画や本を活用しよう
今は、理系の知識を楽しくわかりやすく紹介してくれる動画や書籍がたくさんあります。
以下のようなコンテンツを活用すると、「理系=面白い!」という感覚が自然と育っていきます。
■ おすすめYouTubeチャンネル(一例)
- ヨビノリたくみ:難しい数学・物理の概念をわかりやすく説明
- サイエンスエンタメ系(くられ先生、バーチャル科学館など):化学や科学ネタを楽しく紹介
■ おすすめ書籍
- 『Newtonライトシリーズ』(ニュートンプレス)
- 『学研まんが NEW日本の歴史/科学のひみつ』
- 『頭のいい子が育つ!科学のふしぎな実験』
こうした教材は、興味を持てる内容から理系に接することで、「楽しい=得意につながる」経験を生むことができます。
体験から学ぶ「科学のリアル」
また、科学館や博物館、学校外での実験イベントなどもおすすめです。
「手で触れる」「実際に見てみる」という体験は、教科書の文字以上に記憶に残ります。
たとえば、国立科学博物館(東京・上野)では、定期的に中高生向けのワークショップが開かれており、身近なテーマを実験で体験できます。
公式サイト:https://www.kahaku.go.jp/
家でできる簡単な実験(空気砲、氷と塩でアイス作りなど)も、「やってみる」ことで理解が深まります。
理系の苦手克服には、「五感で学ぶ」アプローチが有効なのです。
苦手なままでも「理系的な力」は身につけられる?
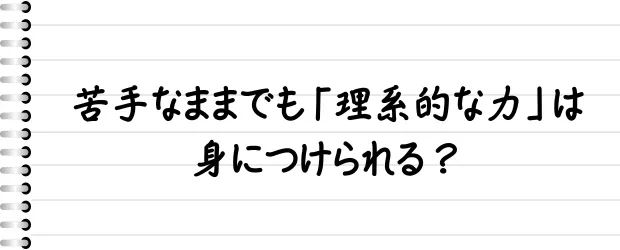
理系が苦手な人もここまでの説明で少しずつ得意になっていくことができそうだと思っていただいたと思います。
ですが、理系科目が苦手だと、「将来理系の仕事は無理だ」と早とちりしてしまう人も少なくありません。
しかし、現実には「理系が得意=理系の職業に向いている」とは限らず、逆もまた然りです。
たとえば、AIを活用したマーケティングや、ITを駆使した音楽制作、さらには心理学と統計の融合分野など、理系の知識を一部取り入れながらも「完全な理系」ではない職業が増えています。
つまり、理系的な思考力や論理的な整理の力だけでも大きな価値があるのです。
また、文系の職業であっても、数値分析やロジックの構築が求められる場面は多く、「理系的スキル」が活躍します。
理科や数学が苦手でも、「理系っぽい考え方」は意識すれば身につけられるという点は安心材料になるでしょう。
「できる人」との差をどう縮めるか?伸びる人の共通点
理系が苦手な中学生の多くは、「周囲の人はどうしてそんなにできるの?」と感じてしまうことがあります。
ここでは、理系が得意な人に共通する「伸びるための習慣」や考え方を紹介します。
①「わからない」を放置しない
理系が得意な人は、「わからない」を放置しません。
すぐに質問したり、教科書を見返したり、ネットや動画で調べたりと、自分で原因を突き止めようとします。
これを真似するだけでも、成績の向上に直結します。
②「なぜそうなるのか?」を常に考えている
理系分野に強い人ほど、公式をただ丸暗記せず、「なぜこの式が使えるのか?」と考える癖がついています。
暗記ではなく理解を深めることを重視し、公式の成り立ちに興味を持ちます。
③「できた!」の積み重ねを大切にしている
たとえ小さなことであっても、「できた」「理解できた」という感覚を積み重ねていくことで自信がつきます。
理系が苦手な人ほど、大きな成功を求めてしまいがちですが、「小さな成功体験」が何より大事なのです。
具体的な学習法:理系が苦手な人のためのステップ別対策
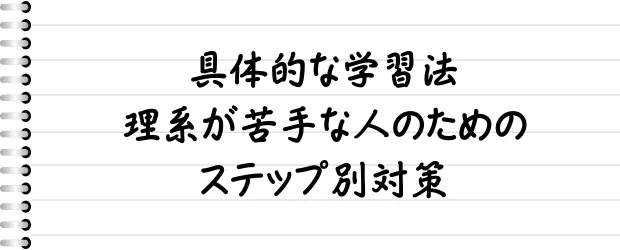
ここからは理系科目が苦手な人におすすめの学習方法を紹介していきます。
ここでは、理系科目が苦手な人に向けた、実際の学習法や取り組み方を3つのステップに分けてみていきましょう。
ステップ1:「なにが苦手か」を具体的に分ける
まず、「数学が苦手」「理科が嫌い」といった漠然とした感覚を整理しましょう。
たとえば、
- 計算が遅いのか?
- 問題文が理解できないのか?
- 単位や記号がごちゃごちゃで混乱するのか?
など、どの段階でつまずいているのかを自分なりに分析すると、次にやるべきことが見えてきます。
ステップ2:「基礎」だけに集中して反復練習
苦手意識のある人は、応用問題や複雑な内容に手を出す前に、基礎だけをしっかり身につけることに集中してください。
具体的には、
- 教科書の例題だけを何度も解く
- 同じ問題を3回以上繰り返す
- 説明できるようになるまで声に出す
といった方法が有効です。
基礎が固まれば、応用もスムーズに理解できるようになります。
ステップ3:「なぜそうなるか?」を説明してみる
「他人に説明できるか?」という視点は、学習の理解度を深めるうえで非常に重要です。
自分の言葉で友達や家族に説明してみたり、ノートに解き方を図解したりすることで、知識が自分のものになります。
家庭や先生ができるサポートとは?
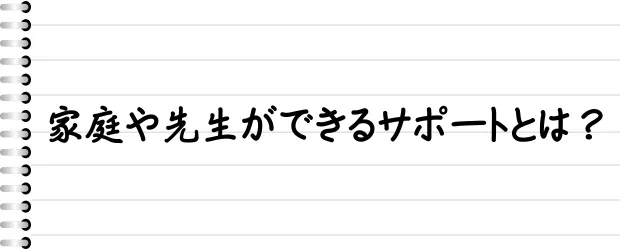
では、学生さんは勉強をコツコツ積み重ねていきますが、学生さんをサポートする家庭や学校ではどういったサポートができるのか見ていきます。
理系科目の苦手克服には、本人の努力だけでなく、まわりの大人の関わりも大きな意味を持ちます。
①「できたね」を積極的に伝える
理系科目に苦手意識を持つ生徒ほど、自信がなくなりがちです。
親御さんや先生が小さな成功を見逃さず、具体的に褒めることは、自己肯定感の育成につながります。
②日常にある理系的な話題を共有する
日常生活の中にも、理系の話題はたくさんあります。
- 料理中の計量(比の計算)
- 天気予報(気圧・湿度・気温)
- 買い物時の割引(パーセント)
こうした日常の例を通じて、「理系の考え方って身の回りにあるんだ」と実感できれば、興味もわいてきます。
③焦らず、継続的なサポートを
苦手意識の克服には時間がかかります。
焦らず、「少しずつでも前に進んでいる」という視点で継続的に見守ることが何より大切です。
結果を急がず、プロセスを重視しましょう。
まとめ
このページで改めて伝えたいのは、理系科目を苦手にしないためには、「理系は身近で楽しいもの」と意識することが何よりも大切だということです。
日常生活の中で「なぜ?」と疑問を持ち、調べたり考えたりする習慣をつけることで、理系科目への抵抗感は自然となくなっていきます。
小さな成功体験を積み重ね、自信を持って学び続けることで、理系の世界はどんどん広がっていきます。
難しいと感じたときは、周りの人と一緒に考えたり、身近な例に置き換えてみたりして、楽しみながら学んでいきましょう。
理系科目を「苦手」から「楽しい!」に変えることは、誰にでもできます。ぜひ、今日から身の回りの「なぜ?」に目を向けて、理系の世界を楽しんでみてください。
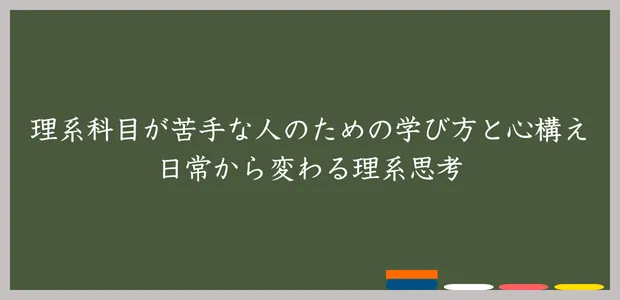









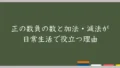
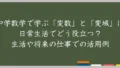
コメント