どのような人でも得意な科目、苦手な科目はあるかと思います。
実際に筆者は文系科目と理系科目それぞれで苦手な科目があり、文系科目は現代文が理系科目では特に物理が苦手な科目でした。(好きとできるは違うんだなぁと実感したのもこうした体験から感じました。)
学習を進めていくうえで、苦手科目があることは決して悪いことではありませんが、苦手科目の学習を継続することはこのページを作成しながら思い出すと、苦労した記憶が思い出されます。
なので、このページでは今、頑張って苦手科目、特に苦手な理系科目の学習と向き合っている学生さんに向けて、苦手科目を前向きに続けていくための向き合い方について説明していきたいと思います。
先に結論を述べておくと、理系科目が苦手でも、正しい向き合い方と自分に合った工夫を取り入れれば、誰でも前向きに学び続けることができます。苦手意識にとらわれず、1歩ずつ自分のペースで進んでいくことが大切です。
この内容に沿って解説していくので少しでも学習の参考にしてもらえればと思います。
なぜ理系科目が苦手になるのか?根本の原因を知ろう
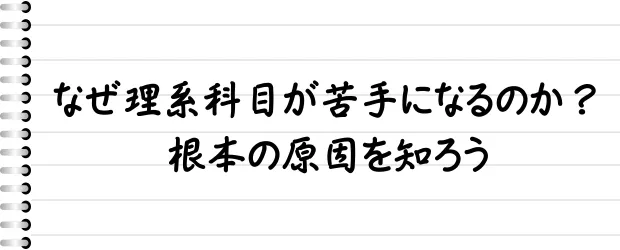
苦手な理系科目との向き合い方を考えていく前に、まずは、「理系教科ができない理由」を正しく理解することが大切です。
苦手意識の原因を知ることで、「自分は理系に向いていない」という誤解を解き、効果的なアプローチが見えてきます。
積み重ねの学問だから、1つつまずくとすべてが崩れる
最も理系科目が苦手になってしまう原因は、理系科目が「積み上げ型の構造」をしているからです。
たとえば数学であれば、計算の基礎(分数・文字式)ができていなければ方程式が解けませんし、方程式が分からなければ関数や図形の問題も理解できません。
物理も同じで、「力のつり合い」が分かっていなければ、運動方程式やエネルギー保存の単元にも進めません。
つまり、1つでも土台が欠けていると、次の単元がまるごと理解できなくなるのです。
その結果、「急に全く分からなくなった」「何を言っているかすら理解できない」と感じるようになります。
理系の勉強は、やり方を間違えると絶対に伸びない
もう1つの大きな壁は、「正しい勉強法を知らないまま学習している」ことです。
文系科目のように、「教科書を読んで覚える」だけでは、理系教科は伸びません。
なぜなら、理系は「理解→定着→演習→応用」というサイクルが不可欠だからです。
公式や法則を暗記するだけでは、応用問題や文章題には太刀打ちできません。
そのため、勉強しているのに点数が伸びない=やる気が下がる=さらにできなくなるという悪循環に陥ってしまうのです。
理系が全くできない人でも、必ず「伸びる瞬間」が来る
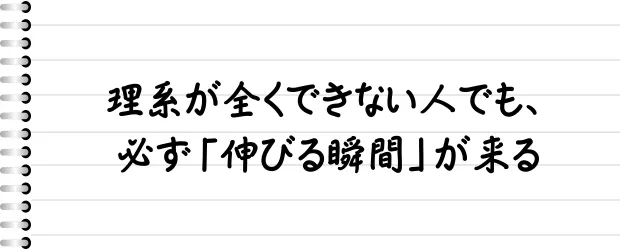
では、苦手になる原因が分かったとして、理系科目が全くできないと思っている人は、どう向き合っていけばよいのでしょうか?
結論からお話すると、「正しい学び方に切り替え、小さな成功体験を積み重ねること」です。
「今できない」は、単なる通過点にすぎない
少し難しい話をしますが、人間の脳は、新しいことを覚えるたびに神経ネットワーク(シナプス)を強化していきます。
最初はどんなに理解できなかったことも、繰り返し学び、解き、フィードバックを受けることで、確実に「できるようになる瞬間」がやってきます。
そのため、重要なのは「できない=才能がない」と思い込まないことです。
むしろ、「今はできない。でも、それは当然。これから学ぶからできるようになる」という考え方が、苦手な理系科目と上手く向き合っていく始めの第一歩になります。
「できた!」という成功体験が、次の一歩につながる
そして、多くの人が見落としがちなのが、苦手な教科こそ「小さな成功体験」が非常に重要だということです。
いきなり難しい問題に挑戦して挫折するよりも、「簡単な問題で確実に正解できる」ことを繰り返すほうが、はるかに自信につながります。
例えば、次のようなステップが効果的です。
- 教科書レベルの例題を解く
- 正解できたら「なぜそうなるのか」を自分で説明してみる
- 同じ形式の基本問題を複数解いて、パターンを覚える
このようにして「理解できた」「解けた」という感覚を積み重ねることで、「自分にも理系ができるかも」という前向きな気持ちが生まれてきます。
丸暗記ではなく「なぜ?」を重視すると理系は面白くなる
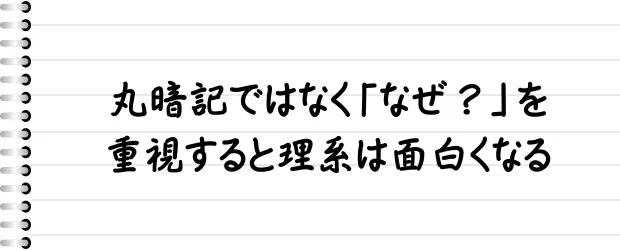
ここまでの説明を通して、苦手な理系科目との向き合い方の第一歩は見えてきたかと思います。
では、苦手なときの理系科目の学習方法としての第一歩はどういった学習がいいのでしょうか?
理系科目が苦手な学生さんは、覚えることが多くて嫌い――そう思っている方も多いと思います。
でもそこにこそ苦手と感じている学生さんの第一歩があり、理系科目の勉強は「暗記」ではなく、「理解」をするということが重要です。
「意味が分かる」と、記憶に定着しやすい
たとえば数学の公式も、ただ丸暗記するより、「なぜこの公式がこうなるのか」を図やグラフで理解した方が、忘れにくくなります。
- 二次関数の解の公式は、平方完成の意味が分かれば暗記せずに導ける
- 物理の運動方程式($F=ma$)は、「力の働き=加速度×質量」という因果関係を理解すれば自然と覚えられる
このように、「納得しながら学ぶこと」が、理系科目においては非常に効果的です。
疑問を大切にする姿勢が、理解力を伸ばす
結局は公式などは覚えていくことに意味があるのでは?と上記の説明で感じた方もいなくないと思います。
ですが、理解したうえで覚えることと、理解せずに暗記に一直線で進むのとでは、まるで違います。
そしてそのためにも、普段の学習から浮かんだ疑問にアンテナを張るようにしてください。
「なんでこの式になるの?」「なんでこうやって解くの?」と感じた疑問を、スルーせずにメモしておきましょう。
その疑問を調べたり、先生や友達に質問したりすることで、理解の深さが格段に増します。
わからないことを放置せず、ひとつずつ解消することが、「理系の地盤を固める作業」と言えるのです。
どうやって理系の苦手を克服する?「できない→できる」に変える5つの勉強法
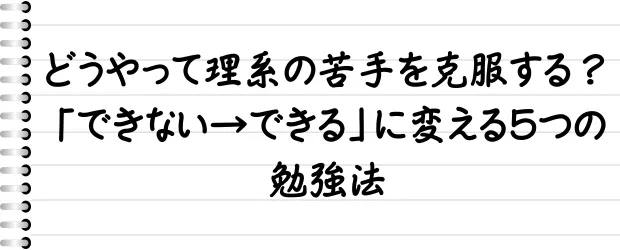
ここまでの説明では、「理系科目が苦手なのは才能の問題ではない」という前提をお伝えしました。
では次に、具体的にどうやって理系を克服していけばよいのか?ということを中心に実践的な学習法の説明に入っていきましょう。
①つまずいた単元まで一度戻る「さかのぼり学習」
まず最初にやるべきことは、「分からなくなった地点まで戻ること」です。
理系教科は前提知識の積み重ねで構成されているため、1つでも抜けていると、全体が理解できなくなります。
「高校の物理がまったく分からない」と感じたときは、中学の力の単元まで戻る。
「数学が壊滅的にできない」なら、小学校の算数から復習しても良いのです。
弧の学習方法のポイントは、「戻ることは恥ではない。最短で前に進むための戦略」という意識で行っていくことです。
焦らず、「理解できるところ」から再スタートすれば、驚くほどスムーズに知識がつながっていきます。
②「読む」より「解く」:手を動かす学習に変える
そして、理系科目の勉強で最も重要なのは、「手を動かすこと」です。
具体的にどういうことかというと、下記のような学習を行うようということです。
- 数学は問題を解いて初めて理解が深まる
- 物理は公式を使って計算してみて、初めて意味が分かる
- 化学も、反応式を書きながら覚えた方が記憶に残る
教科書を読んで「分かったつもり」になっても、実際に解けるとは限りません。
「1日30分でもいいから演習に取り組む」ことで、理解の質が大きく変わります。
補足:「アウトプット学習」は、記憶の定着率がインプットより約2倍高いという研究結果もあります(出典:Learning Pyramid – National Training Laboratories)
③「1冊を繰り返す」だけで基礎力は十分身につく
学習方法とは少し違いますが、参考書や問題集の取り組み方も触れていきます。
参考書や問題集を何冊も買い込む人がいますが、理系が苦手な人ほど、1冊に絞る方が効果的です。
なぜなら、複数の教材に手を出すと「解法がバラバラになって混乱する」リスクがあるからです。
まずは「基礎が丁寧に書かれていて、自分にも読めるレベルの本」を1冊選び、それを3〜5周繰り返すことを目指しましょう。
反復学習の中で、知識が定着し、問題パターンにも慣れることができます。
「理系に向いていない」と感じたときのメンタルマネジメント術
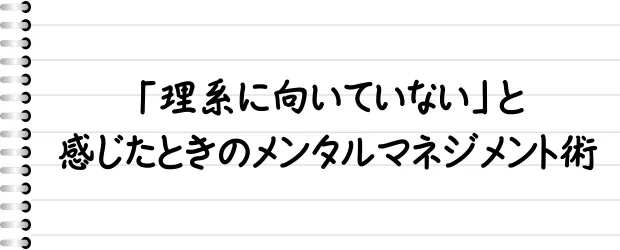
どんなに良い勉強法を知っても、心が折れてしまえば続きません。
ここでは、理系への苦手意識からくる「やる気の低下」や「自己否定感」を乗り越えるためのマインドセットを紹介します。
「センスがない」と思う前に、やり方を疑う
まず、「自分は理系に向いてない」と感じている人は、自分のセンスよりも学び方を向き合いましょう。
- 公式を意味もなく暗記している
- 教科書を読むだけで終わっている
- 1度間違えた問題を復習していない
これらは、全て「できない状態を生み出す典型的なやり方」です。
逆に言えば、やり方を少し変えるだけで、苦手はグッと克服しやすくなります。
「向いていない」と思い込むのではなく、「向いていないように見えるやり方をしていた」と捉え直すことが、メンタル面での大きな一歩になります。
比較ではなく、昨日の自分との勝負にする
また、成績や理解度を他人と比べると、やる気が削がれてしまうことがあります。
特に理系科目は「すぐに結果が出にくい」ので、他人との比較はモチベーションを下げる原因にしかなりません。
その代わり、「昨日より2問多く解けた」「1週間前よりグラフが読めるようになった」という自分との比較を意識してみましょう。
この取り組みの成功の鍵は「1日5%の前進」を積み重ねることです。
その積み重ねが、最終的には大きな成果につながります。
苦手科目別に対策!理系主要教科の学び方とコツ
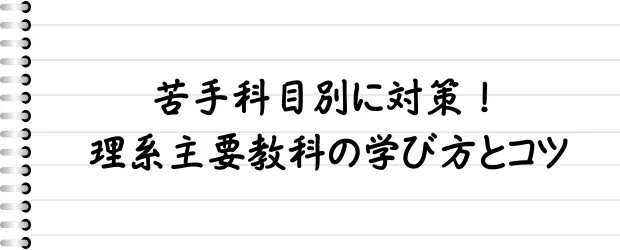
ここまでは「理系全体が苦手な人向けの勉強の進め方」を紹介しました。
ここからは、より具体的に、数学・物理・化学といった主要教科ごとの学習戦略を解説していきます。
数学:苦手克服のカギは「意味を理解すること」
まずは数学から見ていきます。
数学が苦手な人の多くが、「公式をただ覚える」学び方をしています。
しかし、本来の数学は論理の積み重ねで成り立つ科目です。
- なぜその公式になるのか?
- どんな場面で使うのか?
- 似たような問題との違いは何か?
このように「考えるクセ」をつけると、数学が急に意味のあるものに変わります。
たとえば、2次関数の最大・最小の求め方も、「平方完成はグラフの頂点を出す操作」と理解できれば、丸暗記の必要がなくなります。
数学は「パターン理解」が成績を左右するため、典型問題に何度も触れる反復練習が非常に有効です。
物理:イメージがすべて!図と式で理解する
次に物理です。
物理が苦手な人は、「公式の意味が全然わからない」と感じることが多いです。
これは、概念が抽象的で、生活とのつながりが見えにくいことが原因です。
この対策としては、「図を描いてイメージする」ことと「言葉で説明できるようにする」ことが非常に効果的です。
例は、斜面を滑る物体の問題では、必ず「力の向き」「分解の方向」「運動の方向」を図にしてから式にする。
また、公式を使う前に、「この式は何を表しているのか」を自問するクセをつける。
加えて、YouTubeなどで視覚的に学べる動画も活用価値が高く、難しい概念も直感的に理解しやすくなります。
化学:暗記+論理のハイブリッドがカギ
最後に化学です。
化学は、文系的な暗記要素と理系的な論理思考が融合した教科です。
苦手意識を持ってしまいやすい原因は、「知識が断片的になりやすい」ことにあります。
例えば、化学反応式や元素記号を丸暗記しても、それだけでは応用できません。
だからこそ、以下のような流れで学習を進めることが重要です。
- 単元ごとに「全体像」をざっくり把握する
- 基本用語や反応パターンを暗記する
- 問題を通じて「なぜそうなるのか」を確認する
特に、無機化学の暗記は「色・沈殿・反応条件」のセットで覚えると効率的です。
学校の成績やテストにとらわれすぎないでいい理由
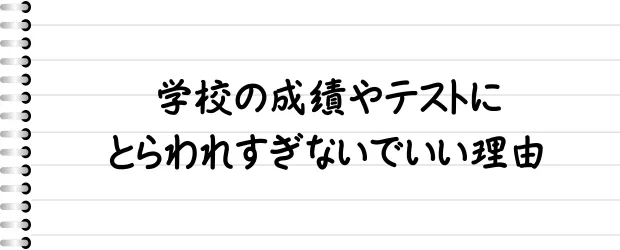
ここまでの学習法を実践しても、「すぐに成績が上がらない」「点数が伸びない」と感じることもあるかもしれません。
でも、それは当然のことです。
理系科目は「じわじわ伸びるタイプ」の教科だからです。
理解の遅れ=ポテンシャルの芽
何度もここではお話していますが、理系が苦手な人の多くは、「人より理解が遅い=才能がない」と誤解してしまいます。
ですが、時間がかかってでも一度理解できたことは、他人より深く記憶に残ります。
理系科目をしっかりと理解していく際に大事なのは、スピードより「深さ」です。
薄く早く理解する人は、すぐに忘れます。
遅くても丁寧に理解した人は、後になって大きな強みになります。
成績や模試の点数も、今は目安程度に考えてOKです。
「前より理解できている」と自分が実感できるかどうかを、一番の指標にしましょう。
理系的な考え方は、日常生活にも役立つ
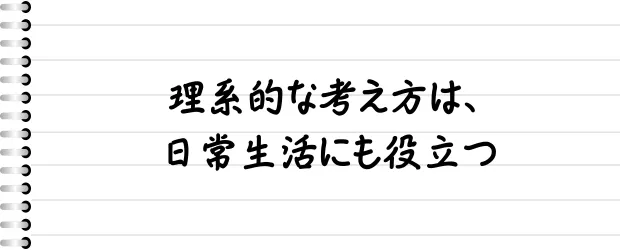
ここまでで、「理系教科はできるようになるし、向き合い方が大事」という話をしてきました。
でも実は、理系科目を学ぶ意義は「点数」や「進路」だけではありません。
論理的に考える力は一生モノ
数学・物理・化学などの理系科目を学ぶことで、物事を順序立てて考える力=論理的思考力が身につきます。
これは、日常生活にも非常に役立ちます。
- 複雑な手続きや説明を整理する
- ネットの情報を鵜呑みにせず、根拠を探す
- 問題が起きたとき、感情ではなく原因から考える
こうした「筋道立てて考える力」は、社会人になってからこそ求められるスキルです。
文系でも、理系的素養は必要な時代に
また、文系の学生さんも理系の知識が必要になってきた時代になりました。
現代はデータ社会・AI社会です。
文系であっても、「数的処理」「論理的読解」「簡単な統計」など、理系的な思考力は必須になりつつあります。
だからこそ、「理系は苦手だから全部シャットアウト」という姿勢ではなく、「理屈はわからなくても、考え方を知っておく」という意識が重要です。
進路選択と理系科目:必要なレベルだけでOK!
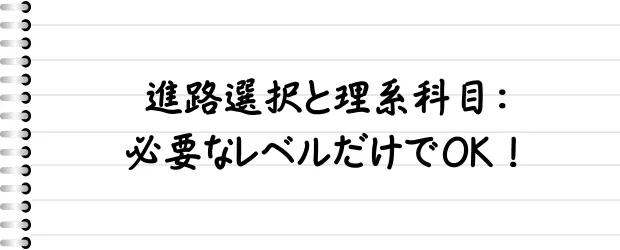
また、理系科目に苦手意識がある人の中には、「文系に進むから、理系は捨てていいですよね?」という質問をする人もいます。
たしかに、文系志望であれば理系科目の配点は低く、入試では重視されにくいこともあります。
ですが、上記でも紹介したように、文系でも最低限の理系的な基礎知識は、進学後・就職後に必須になることもあるのです。
文系大学でも使う理系知識の例
文系学生でも理系の知識を使うような例は、下記のような例です。
- 心理学 → 統計・数理処理が頻出
- 経済学 → 数学的なモデルやグラフ分析が基本
- 看護・福祉系 → 化学や生物の知識が必要
つまり、「自分の将来に必要な範囲で、理系科目を“使える程度”にしておく」ことが、人生の選択肢を広げてくれます。
まとめ
このページでは、理系科目が苦手な学生さんに向けて、苦手な科目との向き合い方について説明してきました。
理系科目が苦手でも、正しい向き合い方と自分に合った工夫を取り入れることで、誰でも前向きに学び続けることができます。
「できない」と思ったときこそ、「これからできるようになるチャンスだ」と前向きに考え、基本からコツコツと取り組んでいきましょう。
小さな成功体験を積み重ね、「なぜ?」を大切にして理解を深め、勉強を続けるための工夫を取り入れることで、理系科目の苦手意識は必ず克服できます。
理系科目の面白さや、身近な生活とのつながりにも目を向けてみてください。
あなたの努力は、必ず自分の力になります。理系科目が苦手でも、あきらめずに一歩ずつ進んでいきましょう。
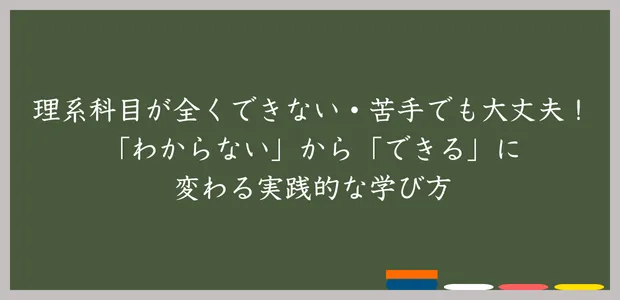








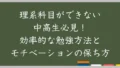
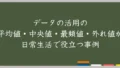

コメント