中学数学では様々な図形の学習をしていきますが、以前に空間図形の紹介をしました。
空間図形の学習はその特徴や構成要素を覚える以外に、算数でも学習したような面積や体積の計算ももちろん学習内容に入ってきます。
図形の問題で躓く学生さんの多くは、これらの計量が苦手で解けないというケースがありますが、それぞれどんな計算をしているのか?この計算の意味は何なのか?を考えながら数式を理解していけば、あまり難しいことを計算しているものではないということが分かります。
このページでは空間図形の表面積、体積の計算方法について学習していくので、まだ空間図形の特徴などの理解が深まっていない人は下記のページを見て理解したうえでこのページを読んでいきましょう。

空間図形とは?〜まずは立体図形の基本を理解しよう〜
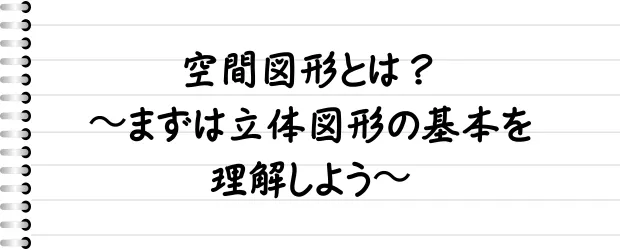
本題に入っていく前に、まずは空間図形とはどういうものだったかを復習していきましょう。
そもそも空間図形とは?
「空間図形」とは、立体的な形を持つ図形の総称です。
小学校で学んだ平面図形(三角形や正方形、円など)とは異なり、縦・横・高さの3つの方向を持つため、面積に加えて体積の概念が登場します。
空間図形には、以下のような種類があります。
- 三角柱
- 四角柱
- 円柱
- 三角錐
- 四角錐
- 円錐
これらの図形に共通して登場するのが、「底面積」「高さ」「母線」「側面積」などの用語です。
これらの用語は以前の上記のページで紹介しているので、何を指しているか分からない方はよく復習しておきましょう。
空間図形の計量とは? 〜面積・体積をどう求めるのか〜
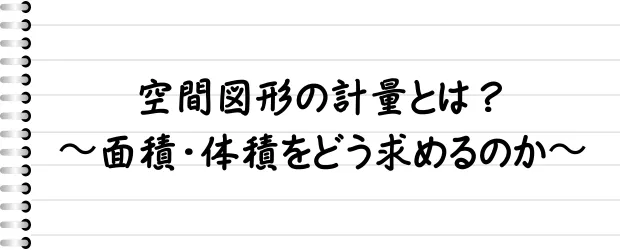
空間図形について振り返ったところで、早速、空間図形の計量について見ていきます。
計量ってどういう意味?
実際の計算問題を行っていく前に、そもそも空間図形における「計量」とは何なのか明確にしておきます。
空間図形の「計量」とは、図形の表面積や体積といった「量」を計算することを指します。
これは、単に公式を覚えて機械的に使うだけでなく、どの部分が底面か、どこが高さかを見極める力も問われます。
面積と体積の違いを理解しよう
計量について明確化したところで、次に面積と体積の違いもはっきりとさせておきましょう。
面積という言葉も体積という言葉もすでに算数の勉強の中で出てきている言葉ですが、改めて確認しておきます。
| 計量の種類 | 単位 | 内容 |
|---|---|---|
| 表面積 | cm²など | 図形の外側の面すべての面積の合計 |
| 体積 | cm³など | 図形が空間内に占める量(かさ) |
たとえば、「正方形の面積」を求める場合は $a×a$、一方「立方体の体積」は $a×a×a$ となり、次元(面積は2次元、体積は3次元)の違いが表れます。
空間図形の計算に必要な基本公式一覧
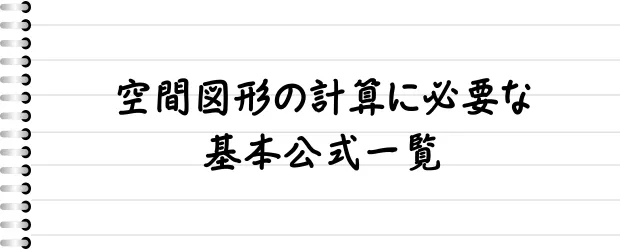
面積と体積の違い、それぞれの単位の違いを明確化したので、いよいよ空間図形の公式を確認していきます。
これから紹介するのは、空間図形の代表的な公式一覧です。
すぐに使えるように、図形ごとにまとめて整理しました。
◾️角柱の公式(三角柱・四角柱など)
- 表面積:底面積 × 2 + 側面積の合計
- 体積:底面積 × 高さ
◾️角錐の公式(三角錐・四角錐など)
- 表面積:底面積 + 側面三角形の合計面積
- 体積:$\frac{1}{3} × 底面積 × 高さ$
◾️円柱の公式
- 表面積:$2\pi r^2 + 2\pi rh$
- 体積:$\pi r^2h$
◾️円錐の公式
- 表面積:$\pi r^2 + \pi rl$($l$は母線)
- 体積:$\frac{1}{3}\pi r^2h$
※「$r$」は半径、「$h$」は高さ、「$l$」は母線の長さです。
それぞれ意味を理解しながら覚えていけるのが理想です。
三角柱・四角柱の表面積の求め方

上記で、空間図形の公式を紹介したので、それぞれの公式について詳しく見ていきたいと思います。
まずは三角柱を例に表面積の求め方を見ていきます。
ステップ①:底面の面積を求める
底面が直角三角形の場合
底面積=$\frac{1}{2} × 底辺 × 高さ$
例:底辺3cm、高さ4cmなら $\frac{1}{2}×3×4=6cm^2$になります。
ステップ②:側面の長方形をすべて求める
三角柱の側面は、三角形の3辺に対応する3つの長方形です。
たとえば、底面が3cm、4cm、5cmの三角形で、柱の高さが10cmの場合
- $3×10=30cm^2$
- $4×10=40cm^2$
- $5×10=50cm^2$
側面積の合計は$30+40+50=120cm^2$になります。
ステップ③:全体の表面積を求める
表面積=底面積×2 + 側面積
この例なら
$6×2+120=12+120=132cm^2$となります。
なぜ表面積は「底面積×2」なのか?
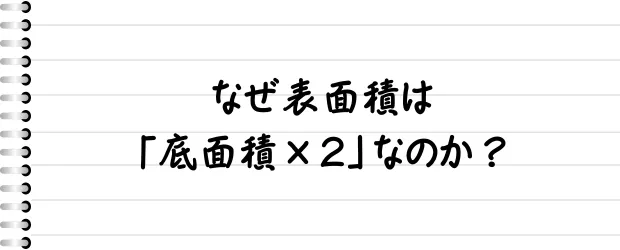
上記の例を見て、「なんで底面積は2倍しているのか?」と疑問に思った人はしっかりと数式の意味を考えようとしていて素晴らしいです。
上記の公式で底面積を2倍にする理由は、角柱や円柱のように上下に同じ底面が2つある図形は、底面積を2倍する必要があるからです。
三角柱・四角柱の体積の求め方
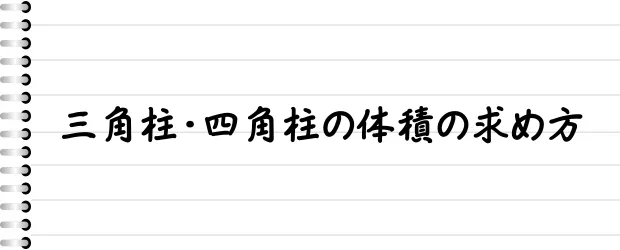
続いて同じく三角柱を例にして体積の求め方を見ていきます。
ステップ①:底面の面積を求める
先ほどと同じ設定で考えると
底面積=$\frac{1}{2} × 底辺 × 高さ$
例:底辺3cm、高さ4cmなら $\frac{1}{2}×3×4=6cm^2$になります。
ステップ②:体積を求める
体積は、
体積$=底面積 × 高さ$で求められるので、
$6×10=60cm^3$になります。
円柱の表面積の求め方
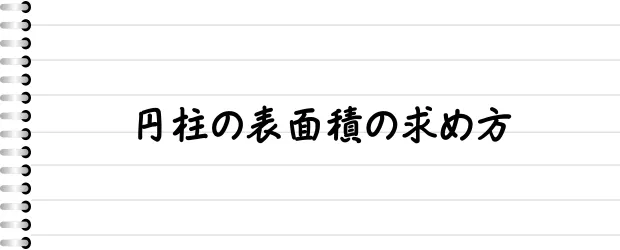
では次に、円柱の表面積の求め方を見ていきます。
計算のステップは三角柱や四角柱と変わりありませんが、円周率が入ってくるので、その処理は十分に気を付けるようにしましょう。
ステップ①:底面の面積を求める
円柱は底面が円なので、円の面積を求めます。
底面積=$\pi r^2$
例:半径4cmなら $\pi 4^2=16\pi cm^2$になります。
ステップ②:側面の長方形を求める
円柱の側面は、1つの大きな長方形です。
たとえば、底面の円は半径が4cm、柱の高さが10cmの場合、側面の長方形の横の長さは底面の円の円周になるので、
側面積は$10 × 2 × 4\pi =80\pi cm^2$になります。
ステップ③:全体の表面積を求める
表面積=底面積×2 + 側面積
この例なら
$2 × 16\pi + 80\pi =112\pi cm^2$となります。
円柱の体積の求め方
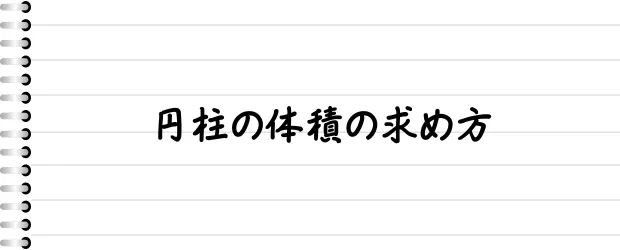
同様の流れで円柱の体積の求め方を見ていきます。
ステップ①:底面の面積を求める
先ほどと同じ設定で考えると
底面積=$\pi r^2$
例:半径4cmなら $\pi 4^2=16\pi cm^2$になります。
ステップ②:体積を求める
体積は、
体積$=底面積 × 高さ$で求められるので、
$16\pi × 10 =160\pi cm^3$になります。
三角錐・四角錐の表面積の求め方
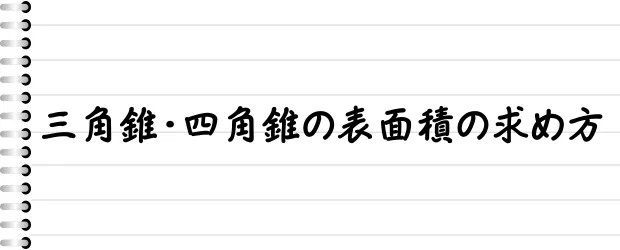
このペースで、三角錐・四角錐の表面積の求め方を見ていきます。
ステップ①:底面の面積を求める
ここでは四角錐を例に見ていきます。
底面が長方形の場合
底面積=$縦 × 横$
例:縦3cm、横4cmなら $3×4=12cm^2$になります。
ステップ②:側面の長方形をすべて求める
四角錐の側面は、長方形の4辺に対応する4つの三角形です。
今回だと、縦が3cm、横が4cmの長方形で、柱の高さが10cmの場合
- $\frac{1}{2}×3×10×2=30cm^2$
- $\frac{1}{2}×4×10×2=40cm^2$
側面積の合計は$30+40=70cm^2$になります。
上記の式で「×2」をしているのは、底面は長方形であるので、同じ形の側面の三角形が1組ずつあるからです。
ステップ③:全体の表面積を求める
表面積=底面積×2 + 側面積
この例なら
$12+70=82cm^2$となります。
三角錐・四角錐の体積の求め方
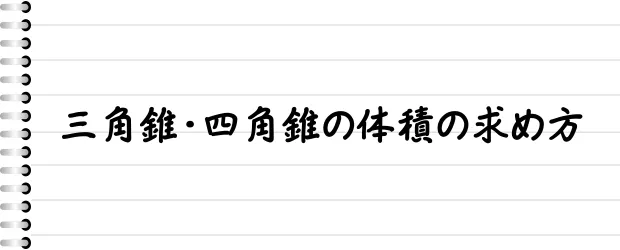
続いて同じく四角錐を例にして体積の求め方を見ていきます。
ステップ①:底面の面積を求める
先ほどと同じ設定で考えると
底面積=$縦 × 横$
例:縦3cm、横4cmなら $3×4=12cm^2$になります。
ステップ②:体積を求める
体積は、
体積$=\frac{1}{3}×底面積 × 高さ$で求められるので、
$\frac{1}{3}×12×10=40cm^3$になります。
円錐の表面積の求め方
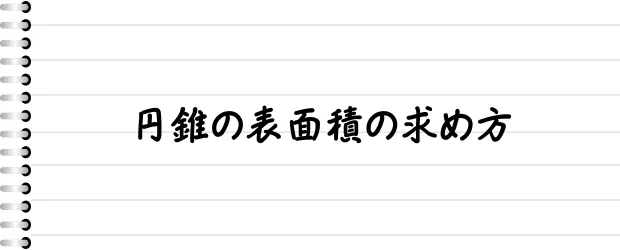
最後に円錐の表面積の求め方を見ていきます。
ステップ①:底面の面積を求める
円錐は底面が円なので、円の面積を求めます。
底面積=$\pi r^2$
例:半径5cmなら $\pi 5^2=25\pi cm^2$になります。
ステップ②:側面のおうぎ形を求める
円錐の側面は、1つのおうぎ形です。
たとえば、底面の円は半径が5cm、母線の長さが8cmの場合、
おうぎ形の面積$=\pi rl$となるので、
$\pi ×5 ×8=40\pi cm^2$となります。
ステップ③:全体の表面積を求める
表面積=底面積 + 側面積
この例なら
$25\pi + 40\pi =65\pi cm^2$となります。
円錐の体積の求め方
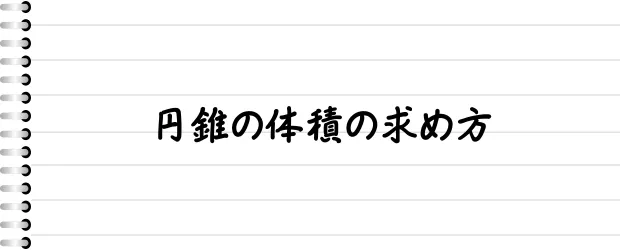
同様の流れで円錐の体積の求め方を見ていきます。
ステップ①:底面の面積を求める
先ほどと同じ設定で考えると
底面積=$\pi r^2$
例:半径5cmなら $\pi 5^2=25\pi cm^2$になります。
ステップ②:体積を求める
体積は、
体積$=\frac{1}{3}×底面積 × 高さ$で求められるので、
この円錐の高さを9cmとすると、
$\frac{1}{3}×25\pi × 9 =75\pi cm^3$になります。
計算ミスを防ぐ3つのチェックポイント
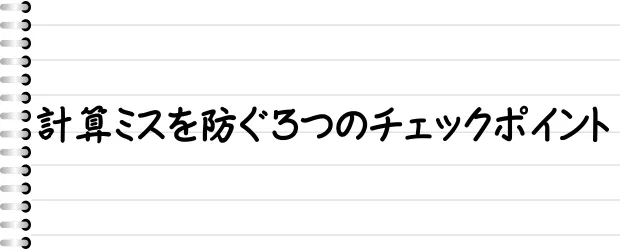
表面積や体積の実際の計算は、今見てきたとおりですが、実際に計算を見てみると少々複雑だと感じたり、計算自体に難しさを感じたりもしたかもしれません。
そういったときに最も注意したいのが「計算ミス」です。
ここでは、表面積と体積の計算をする際の計算ミスを防ぐポイントを紹介していきます。
①「高さ」と「母線」の違いを理解する
1つ目は、「高さ」と「母線」の違いを明確に理解しておきましょう。
円錐や角錐では「高さ」と「母線」が異なります。
体積は「高さ」を使い、表面積の側面(三角形)には「母線」を使います。
よくある誤りとしては、体積計算に母線を使ってしまうということがあるので、注意しましょう。
②単位の整合性を常にチェック
2つ目は単位の違いについてです。
面積はcm²、体積はcm³で求めていきます。
問題中でmmやmなどの単位が混じっている場合、すべて同じ単位に変換してから計算しましょう。
めったに出題されませんが、常に単位には意識を向けて問題を解き進めていきましょう。
③側面積の「枚数」を数え間違えない
3つ目は側面の数を間違えないようにするということです。
角柱や角錐では、側面がいくつあるかをしっかり確認しましょう。
- 三角柱 → 側面3枚
- 四角柱 → 側面4枚
- 四角錐 → 側面4枚(三角形)
空間図形の展開図を活用しよう
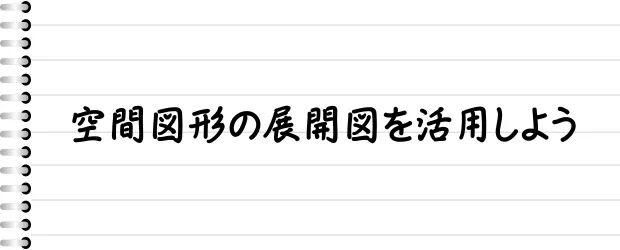
公式の解説では、計算を考える工程だけ紹介していきましたが、実際に計算する際はどういう図形なのかを考えながら計算を進めていくことになります。
特に、表面積の計算では慣れていないと、計算過程だけを考えて進めていくのは少々難しいと思います。
そこで、空間図形の学習で重要なスキルの1つが、展開図の理解と活用です。
展開図を描くことで、複雑な立体でも表面積の計算が簡単になります。
なぜ展開図が重要なのか?
表面積の計算を行っていくうえで、展開図が重要になる理由は下記のとおりです。
- 各面の形と数が一目で分かる
- 側面積の「見落とし」が減る
- 視覚的に図形構成を理解できる
特に視覚的な理解は計算ミスを減らしたら、側面の足し忘れを防止するという意味でもとても重要になります。
展開図の練習のコツ
実際に展開図を使って計算問題を解き進める際は、下記の手順で進めていくことをおすすめします。
- まず「底面の数と形」を確認
- 次に「側面が何枚あるか」を整理
- 側面を順番につなげるように描いていく
特に入試問題では、展開図を頭の中で思い浮かべる力が問われることが多いです。
入試によく出る空間図形の問題パターン
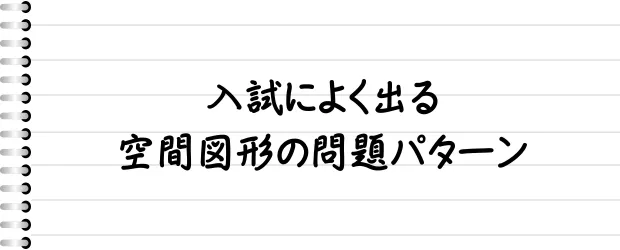
ここまでは空間図形の表面積と体積の計算を中心に解説してきました。
ここからは、入試の頻出問題を例を紹介していきます。
中学数学では、空間図形が高校入試の頻出テーマです。
以下のようなパターンで出題されることが多いため、対策も兼ねてみておきましょう。
①部分的な体積・表面積を求める問題
例:「容器に半分水を入れると何cm³か」
図形の体積を半分にするだけでなく、「水面の高さ」がどこまで上がるかを逆算する必要がある場合もあります。
②展開図の完成・正誤判定
例:「この展開図は、どの立体を組み立てられるか」
面の数や形のミスに注意しましょう。
角柱と角錐の違いを問われることもあります。
以上のような問題が出題されることが多いので、自分が実際に解こうとしたときに、しっかりと解法が分かるか確認しておくことをおすすめします。
実生活に役立つ!空間図形の具体例
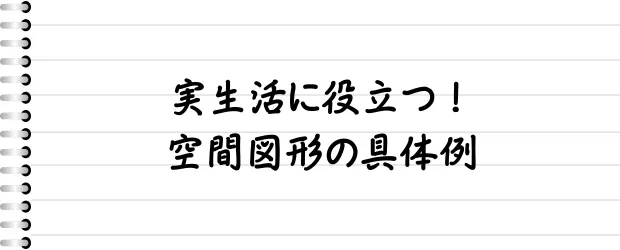
最後に空間図形の表面積や体積の学習が日常生活でどのように活かせるのかを紹介していきます。
数学の学びを「生活にどう使うの?」と思う方も多いでしょう。
実は空間図形は、日常や仕事の中で意外と使われています。
◾️例1:箱の表面積=包装紙の必要量
プレゼントの包装やダンボールのデザインは、すべて表面積の計算に基づいています。
◾️例2:水筒やタンクの体積=入る水の量
丸い水筒の容量表示は「円柱の体積計算」そのものです。
◾️例3:建築や製造業での設計図面
建築士や機械設計では、設計図を作成上腕、展開図や立体構造の理解が不可欠です。
ここで紹介している例はほんの一例ですが、私たちの身の回りのあるものはほとんどが空間図形なので、ご自身が普段利用しているものや建物なんかも注意深く見てみると、表面積や体積の計算ができるかもしれません。
まとめ
このページでは空間図形の表面積や体積の計算方法について解説していきました。
中学数学で初めて出てきた図形だからといって、苦手意識を持たずにしっかりと理解することをまずは心がけてみましょう。
解説の中でもお話しましたが、意外にも算数の知識をそのまま流用できる部分もありますし、これまで学習していき知識の組み合わせで問題が解けるようになっています。
なので、新しい分野の学習という認識ではなく、これまでの知識の組み合わせと復習をするという意識でまずはこの分野の学習を行ってみましょう。
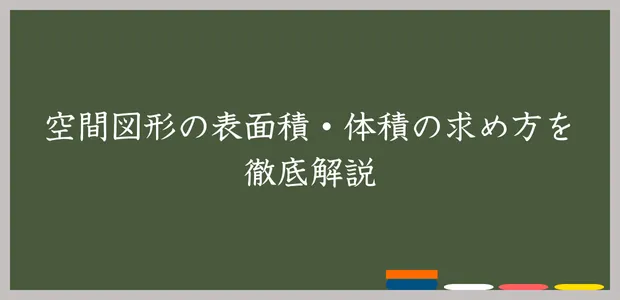







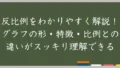
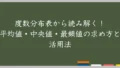

コメント