中学1年の数学で登場する比例の次に学習するのが「反比例」です。
比例との違いが少し分かりにくく、グラフや式をどう使えばいいのか迷う人も多い単元です。
反比例を理解するカギは、「一方が増えるともう一方が減る関係」と「かけ算の結果がいつも同じ」という2つの性質です。
このページでは、「反比例とは何か?」という基本から、比例との違い、式のつくり方、グラフの形、そして実際の問題への使い方までを、ていねいに解説します。
反比例の全体像をつかみ、数学の苦手をわかる!に変えていきましょう。
| 中学生のおすすめ学習塾3選 | |||
|---|---|---|---|
横浜予備校 |
WAM |
明光義塾 |
|
| 対象 | 中学生 | 中学生 高校生 |
中学生 高校生 |
| 授業料 (税込) |
29,700円~ (月額) |
7,600円~ (週1回) |
15,400円~ (週1回) |
| 入塾金 | 0円 | 16,500円~ | 11,000円 |
| 指導形式 | 学習塾 | 学習塾 (個別指導) |
学習塾 (個別指導) |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | |
反比例とは?中学生にもわかりやすく基本を解説
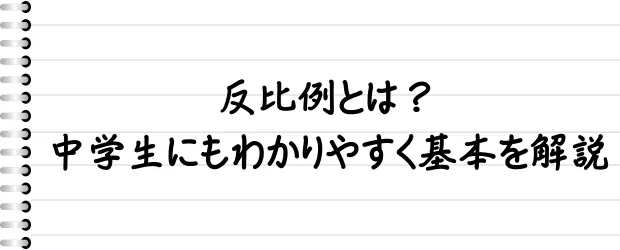
中学数学で学ぶ「比例」に続いて登場するのが、ここで扱う反比例です。
名前が似ているので最初は混乱しがちですが、比例と反比例は「変化の向き」がまったく異なる関係を表しています。
反比例を正しく理解できると、作業時間・速度と時間・密度・濃度など、身の回りの多くの現象がスッキリ説明できるようになります。
ここでは、まずは反比例のイメージをつかみ、比例との違いを整理し、最後に反比例を表す式$y=\frac{a}{x}$の意味をくわしく理解していきましょう。
反比例ってどんな関係?まずは意味をやさしく理解しよう
前回のページで比例の性質を学びましたが、ここで扱う反比例は、比例とは逆の変化をする関係です。
もっとも大切なイメージは、「一方の数が大きくなると、もう一方の数が小さくなる」というものです。
この逆向きの変化こそが反比例の大きな特徴です。
日常の例で考えてみましょう。
たとえば、ある作業をする人数が増えると、1人が担当する作業量は自然と減ります。
2人より4人、4人より8人のほうが、一人あたりの負担が小さくなるため、作業時間も短く終わります。
これは、人数が大きくなると、1人あたりの作業量(または作業時間)が小さくなる典型的な反比例の関係です。
また、一定の水の量を容器に入れるとき、容器の底面積が広ければ水の高さは低くなり、底面積が狭いと高さは大きくなります。
「底面積が大きいときは高さが小さい」という関係は、反比例のイメージそのものです。
さらに反比例には、もう1つ大切な考え方があります。
それは、「$x$と$y$をかけると、いつも同じ数になる」という性質です。
数学ではこれを
$x×y$=一定の数($a$)
と表します。
この「積が一定」という考えは、後で学ぶ反比例の式$y=\frac{a}{x}$に直接つながります。
まずは「大きいと小さいが入れ替わる関係」「かけ算すると一定」という2点を押さえておきましょう。
比例とのちがいを比べるとわかる!反比例の考え方
ここまでで反比例のイメージをつかんだところで、次は比例との違いをハッキリさせて理解を整理していきます。
比例は、「一方が大きくなると、もう一方も大きくなる関係」でした。
たとえば時給が同じなら、働く時間が2倍になれば給料も2倍になります。
これを式で表すと$y=ax$という形になります。
一方、反比例は、「一方が大きくなると、もう一方は小さくなる関係」です。
たとえば、同じ距離を移動するとき、速く走るほどかかる時間は短くなります。
距離を一定にして考えると、速度と時間はまさに反比例の関係です。
そして反比例には、比例にはない特徴があります。
それが、$x$と$y$をかけた値が常に同じになる(積が一定)という点です。
具体例を見るとわかりやすいでしょう。
- $x=2$, $y=6$ → $x×y=12$
- $x=3$, $y=4$ → $x×y=12$
どちらも積が12になっており、このように「かけ算で同じ値になる関係」であれば、その関係は反比例だと判断できます。
比例と反比例を表にまとめると次のようになります。
| 関係 | 変化の向き | 基本式 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 比例 | どちらも増える・どちらも減る | $y=ax$ | 割り算で一定の$a$が求まる |
| 反比例 | 一方が増えるともう一方が減る | $y=\frac{a}{x}$ | 積が一定の$a$になる |
まずはこの「変わり方の向き」と「積の一定性」をしっかり押さえておくことが、反比例の理解を大きく深めます。
反比例を数式で表すとどうなる?「y=a/x」の意味を知ろう
では、反比例を数学の式でどのように表すかを確認しましょう。
反比例の基本形は
$y=\frac{a}{x}$
です。
式に含まれている$a$は「定数」と呼ばれ、状況が変わっても変化しない数を意味します。
この式は、$x$と$y$が変化しても、$x×y=a$が常に成り立つということを表しています。
つまり、反比例では「$x$が変わると、$a$を一定に保つために$y$も変化する」という関係になっています。
たとえば$y=\frac{12}{x}$の場合を考えてみましょう。
いくつかの値を代入すると、反比例の特徴がよく見えます。
| $x$ | $y=\frac{12}{x}$ | $x×y$ |
|---|---|---|
| 1 | 12 | 12 |
| 2 | 6 | 12 |
| 3 | 4 | 12 |
| 4 | 3 | 12 |
| 6 | 2 | 12 |
| 12 | 1 | 12 |
どの組み合わせでも「かけると12」になっています。
このように、具体的な例を使うと$a$(定数) が「積として一定に保たれている値」であることが理解しやすくなります。
また、$a$が正の数の場合と負の数の場合では、グラフの位置が変わりますが、この段階では「$a$の値が変わると関係の形や大きさも変わる」というイメージだけ持っておけば十分です。
比例との違いをくらべてわかる!反比例の関係とは
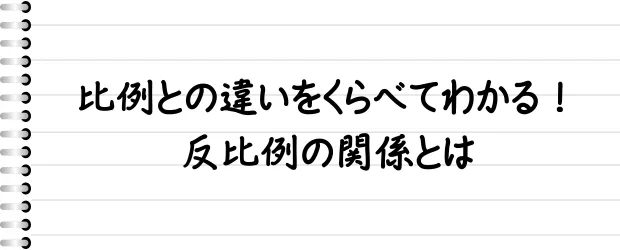
上記までは、反比例の基本的なイメージや式の意味について理解を深めました。
しかし、反比例をしっかり使いこなすためには、まず「比例と何がどう違うのか」を整理しておくことがとても重要です。
比例と反比例はセットで学ぶものですが、変化の向きやグラフの形がまったく異なります。
ここでは、まず比例の性質を復習し、そのうえで反比例との違いを表・例・グラフを使って直感的に理解できるように解説していきます。
比例の復習!どんな関係だったか思い出そう
最初に、反比例とくらべる基準となる比例について確認しておきましょう。
比例とは、「一方が大きくなると、もう一方も同じ割合で大きくなる関係」のことです。
この関係を表す式は$y=ax$です。
ここで$a$は比例定数と呼ばれ、「1増えたときにどれくらい増えるか」を表します。
単価・速さ・1あたりの量など、身の回りの多くの場面で登場します。
たとえば、野菜1個100円なら、
- 2個買えば200円
- 3個買えば300円
- 5個買えば500円
と、個数が2倍・3倍になれば、代金も同じように2倍・3倍になります。
これはまさに比例の性質がそのまま表れた例です。
また、「一定の速さで歩く」ときも比例の関係になります。
速さが変わらなければ、時間が2倍なら進む距離も2倍です。
表で考えてみると、$x$(時間)が増えるにつれて、$y$(距離)も同じ比で増えていくことがよくわかります。
さらにグラフで見ると、比例の関係は原点(0,0)を通る右上がりの直線になります。
直線であること、そして必ず原点を通るという特徴は、中学数学の中でも特に覚えておきたいポイントです。
比例と反比例のちがいをくらべてみよう
比例がしっかり思い出せたところで、次は反比例との違いを見ていきます。
反比例は、その名の通り比例とは「逆の変化」をする関係です。
比例が$x$が2倍 → $y$も2倍という関係であるのに対し、反比例は$x$が2倍 → $y$は$\frac{1}{2}$倍という動きをします。
つまり、
- 比例:増えると増える
- 反比例:増えると減る
というように、変化の向きが正反対です。
式で比べるとさらに分かりやすくなります。
| 関係 | 式の形 | 特徴 |
|---|---|---|
| 比例 | $y=ax$ | 割り算で一定の数($a$)が出る |
| 反比例 | $y=\frac{a}{x}$ | かけ算で一定の数($a$)が出る |
反比例の最大の特徴は、$x$と$y$をかけるといつも同じ数になる($x×y=a$)という点です。
たとえば、次のような対応を考えてみましょう。
- $x=2$, $y=4$ → 2×4=8
- $x=4$, $y=2$ → 4×2=8
どちらも積は8で変わりません。
このように「大きくなると小さくなる」「かけると同じ数になる」という関係が反比例です。
身近な例でも反比例はよく登場します。
- 同じ仕事をする時間と人数
→人数が増えるほど1人あたりの作業時間は少なくなる。 - 速度と時間(距離一定)
→速く走るほどかかる時間は短くなる。
比例は「一緒に増える関係」であるのに対し、反比例はまさに「シーソー」のように、一方が上がるともう一方が下がる関係だとイメージすると理解が深まります。
グラフで見ると一目でわかる!比例と反比例の関係
では、比例と反比例をグラフで比較してみましょう。
グラフは関係の違いを視覚的に理解するのに非常に有効です。
まず、比例のグラフはすでに学んだとおり、原点を通る右上がりの直線になります。
$x$が増えるほど$y$も増えるので、左下から右上へまっすぐ伸びる線になります。
一方、反比例のグラフはまったく違う形になります。
反比例のグラフは右下がりのカーブ(双曲線)になります。
原点は通らず、$x$が増えるほど$y$はゆっくりと小さくなっていく曲線です。
さらに、反比例の定数$a$によってグラフの位置が変わります。
- $a$が正のとき
→グラフは右上と左下に描かれる - $a$が負のとき
→グラフは左上と右下に描かれる
比例が「まっすぐ上へ伸びる線」であるのに対し、反比例は「なめらかに下がるカーブ」です。
この違いを見るだけでも、変化の方向が正反対であることがひと目でわかります。
比例と反比例を並べて考えることで、反比例の特徴である「増えると減る関係」「積が一定」「右下がりのカーブ」という3つのポイントをしっかり理解できるようになります。
| 中学生のおすすめオンライン塾・家庭教師3選 | |||
|---|---|---|---|
ウィズスタディ |
家庭教師の銀河 |
WAM |
|
| 対象 | 中学生 高校生 |
中学生 | 中学生 高校生 |
| 授業料 (税込) |
9,800円~ (1科目) |
2,750円~ (1コマ) |
7,600円~ (週1回) |
| 入会金 | 27,500円~ | 22,000円 | 16,500円~ |
| 指導形式 | 学習塾 (オンライン) |
家庭教師 | 学習塾 (オンライン) |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | |
反比例の式のつくり方と考え方を覚えよう
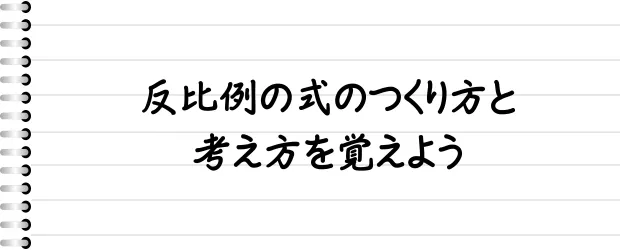
ここまでは、比例と反比例のちがいをくらべながら、反比例が「一方が増えるともう一方が減る」関係であることを学びました。
ここからは一歩進んで、反比例をより正確に扱うために必要な「式の意味」「比例定数aの役割」「式のつくり方」をまとめて理解していきましょう。
反比例は式の形が少し特殊に見えますが、その意味が分かれば計算やグラフの問題もぐっと扱いやすくなります。
実際に例を使ったり問題を解きながら、反比例の考え方を確実に身につけていきましょう。
反比例の式「y=a/x」ってどういう意味?
まずは、反比例の式$y=\frac{a}{x}$の意味をしっかりつかみましょう。
反比例とは、「$x$が大きくなると$y$は小さくなる関係」であり、さらに重要なのが$x×y$=一定の数(=$a$)になるという性質です。
この一定の数$a$を使うことで、反比例の関係を式としてまとめたものが
$y=\frac{a}{x}$
という形になります。
「割る」という形になっている理由は、$x$が大きくなるほど割られる数が増えるため、結果として$y$が小さくなるからです。
つまり、
- $x$を2倍にすると、$y$は$\frac{1}{2}$倍になる
- $x$を3倍にすると、$y$は$\frac{1}{3}$倍になる
という「逆向きの変化」が式にそのまま表れています。
たとえば、$a=12$の反比例の関係を見てみましょう。
| $x$ | $y$ | $x×y$ |
|---|---|---|
| 2 | 6 | 12 |
| 3 | 4 | 12 |
| 4 | 3 | 12 |
どの組でも$x×y=12$のまま変わりません。
このように「かけ算が一定になる」という考え方が、反比例の式を理解するうえでの最重要ポイントです。
比例が「掛けると一定」ではなく「割ると一定(=比例定数)」であることとも違い、反比例の特徴が数字の動きにしっかり現れています。
比例定数aのはたらきを知ろう!値が変わるとグラフはどうなる?
次に、反比例の式の中に出てくる比例定数aがどんな働きをしているのか見てみましょう。
この$a$は「変わらない数(定数)」であり、$x$と$y$をかけたときにできる値そのもの
を表しています。
つまり、$a$が変われば反比例の関係も大きく変わります。
$a$の値が大きいと、同じ$x$でも$y$が大きくなり、グラフはより「外側」に広がるイメージになります。
逆に$a$が小さいと、グラフは「内側」に寄り、$y$の値も全体的に小さくなります。
例として、$x=2$をそれぞれの式に当てはめて比べてみましょう。
- $y=\frac{6}{x}$ → $x=2$のとき$y=3$
- $y=\frac{12}{x}$ →$x=2$のとき$y=6$
同じ$x$でも、$a$が大きいと$y$も大きくなるのがよく分かります。
また、$a$が正のときと負のときでは、グラフが描かれる場所が変わるという特徴があります。
- $a>0$(正) …… 右上と左下にグラフが出る
- $a<0$(負) …… 左上と右下にグラフが出る
反比例のグラフは曲線(双曲線)ですが、この曲線の位置を決めているのが$a$の値です。
$a$は反比例の「広がり方」や「動きの強さ」を決めるスイッチのような役割だと考えると理解しやすくなります。
反比例の式をつくってみよう!問題を通して考え方を確認
ここまでで、反比例の式の意味や$a$の役割は理解できたはずです。
最後に、それらをもとに実際に反比例の式をつくる練習をしてみましょう。
反比例の式づくりの基本手順は次の3ステップです。
【反比例の式づくり 3ステップ】
- 「反比例する」と言われたら$y=\frac{a}{x}$の形で表すと決める
- 与えられた$x$と$y$の値を使って$a=x×y$を求める
- 求めた$a$を式に代入して完成させる
たとえば、次の問題を考えてみましょう。
例題
$x$と$y$が反比例して、$x=4$のとき$y=3$である。$y$を$x$の式で表しなさい。
解き方
反比例なので
→ $y=\frac{a}{x}$の形になる。
与えられた値から$a=4×3=12$となる。
したがって式は
$y=\frac{12}{x}$
これで完成です。
反比例の式を作れるようになると、次のような問題が簡単に解けるようになります。
- $x$の値が変わったときの$y$の値を求める
- 反比例のグラフを描く
- 表から反比例の関係を判断する
つまり、反比例の理解の中心となるのがこの「$a$」を使った式作りです。
反比例グラフの形と反比例の特徴をチェック!
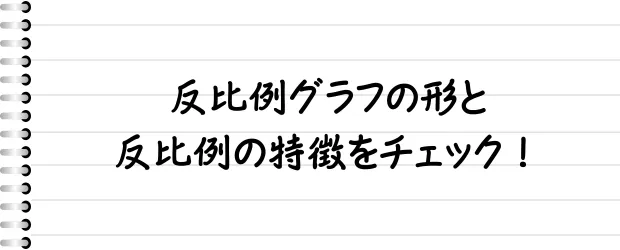
上記では、反比例の式が「$y=\frac{a}{x}$」と書けること、そして$x$が変わるときの$y$の変化のしかたを確認してきました。
ここからは、その式をグラフにするとどのような形になるのか、そして比例グラフとどう違うのかをしっかり理解していきます。
反比例の学習では、グラフの形をイメージできるかどうかがとても大切です。
ここでグラフの「見え方」や「動き」をしっかりつかんでおきましょう。
反比例のグラフはどんな形?基本のカタチを見てみよう
反比例の式$y=\frac{a}{x}$をグラフにすると、比例のような直線にはならず、なめらかなカーブになります。
このカーブは「双曲線」と呼ばれ、反比例ならではの特徴的な形です。
比例のグラフは必ず原点を通る直線でしたが、反比例のグラフは 原点を通らない 点が大きな違いです。
たとえば$a=12$の反比例$y=\frac{12}{x}$のとき、次のような表がつくれます。
| $x$ | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $y$ | 12 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
どの組み合わせでも$x×y=12$になり、積が常に一定です。
このグラフは「右に行くほど下がる」形になり、右上から左下へ向かうようにゆるやかにカーブします。
さらに、反比例グラフには次の性質があります。
- $a$が正のとき:右上と左下にグラフが現れる($x>0$なら$y>0$、$x<0$なら$y<0$)
- $a$が負のとき:左上と右下にグラフが現れる($x>0$なら$y<0$、$x<0$なら$y>0$)
また、カーブはどんどん$x$軸や$y$軸に近づきますが、決して触れません。
これは「漸近線」という考え方で、反比例グラフの大きな特徴の一つです。
xが大きくなるとyはどうなる?変化の様子をチェック!
反比例のもっとも重要な特徴は、$x$が増えると$y$は減るという「反対方向の変化」です。
たとえば$y=\frac{8}{x}$で考えてみましょう。
| $x$ | 1 | 2 | 4 | 8 |
|---|---|---|---|---|
| $y$ | 8 | 4 | 2 | 1 |
$x$が1 → 2 → 4 → 8 と 2倍、2倍…と増えていくと、$y$は8 → 4 → 2 → 1 と$\frac{1}{2}$、$\frac{1}{2}$…と小さくなっていきます。
つまり、
- $x$を2倍にすると$y$は$\frac{1}{2}$倍
- $x$が大きくなるほど$y$はどんどん小さくなる
という関係がいつでも成り立ちます。
グラフで見ると、右へ進むほど下がっていく
- $x$が1に近づくほど急に$y$が大きくなる
- $x$が大きいとカーブは緩やかになる
といった動きが読み取れます。
また、「人数が増えると一人あたりの分け前が少なくなる」というような日常の例に置きかえると、反比例の変化がイメージしやすくなります。
なお、$x$が負の方向へ行くと、$y$の符号も反対になり、グラフは別の象限に現れますが、カーブの形そのものは同じで、ちょうど左右反転・上下反転したような対称性があります。
比例のグラフと見くらべてわかる!反比例の特徴まとめ
ここで、比例と反比例の違いを整理しておくと理解が一気に深まります。
次の表を見てみましょう。
| 項目 | 比例 | 反比例 |
|---|---|---|
| 式 | $y=ax$ | $y=\frac{a}{x}$ |
| $x$と$y$の関係 | $x$が増えると$y$も増える | $x$が増えると$y$は減る |
| グラフの形 | 原点を通る直線 | 双曲線 |
| $x×y$ | 変わる | 一定 |
比例は「まっすぐ同じ方向に変わる関係」、反比例は「片方が増えるともう片方が減る関係」です。
グラフを見比べることで、「これは直線だから比例」「これはカーブで、原点を通らないから反比例」という判断もできるようになります。
反比例の特徴をしっかりつかんでおくと、式を見ただけ、あるいは数値の変化を見るだけで反比例かどうか判断できるようになり、問題を解く力がぐっと伸びます。
| 中学生のおすすめ学習塾3選 | |||
|---|---|---|---|
横浜予備校 |
WAM |
明光義塾 |
|
| 対象 | 中学生 | 中学生 高校生 |
中学生 高校生 |
| 授業料 (税込) |
29,700円~ (月額) |
7,600円~ (週1回) |
15,400円~ (週1回) |
| 入塾金 | 0円 | 16,500円~ | 11,000円 |
| 指導形式 | 学習塾 | 学習塾 (個別指導) |
学習塾 (個別指導) |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | |
反比例の考え方を使って問題を整理してみよう
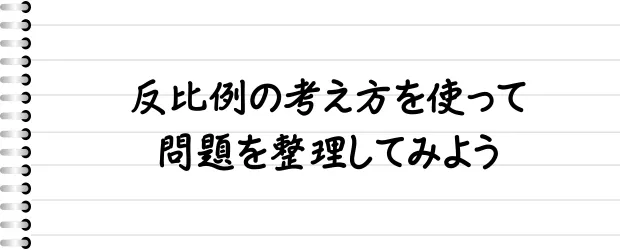
ここまでは、反比例のグラフや変化の特徴を学びました。
ここからは、実際の問題の中で「どのように反比例を見抜くのか」「文章を式にどう変えるのか」「どのように計算するのか」を整理していきます。
反比例は「掛け算の関係が一定」であることが本質です。
このポイントがつかめると、文章問題でも迷わず整理できるようになります。
反比例の問題ってどんなときに出てくる?見分け方のコツ
反比例の関係は「一方が大きくなると、もう一方が小さくなる」という特徴をもち、さらに$x×y$がいつも一定になります。
ここを比例と比べると違いがはっきりします。
- 比例:$x$が2倍 → $y$も2倍(同じ方向に変化)
- 反比例:$x$が2倍 → $y$は$\frac{1}{2}$倍(反対方向に変化)
反比例が使われる場面は、「全体の量が決まっている状況」で、一方を増やすともう一方を減らさなければ成り立たない場合です。
代表的な例として次のようなものがあります。
- 同じ仕事を分担する人数と作業にかかる時間
→人が増えれば時間は短くなる。 - 一定距離を進む速さと時間
→速く進むほど、かかる時間は短くなる。 - 一定の水量があるとき、底面積と水の高さ
→底面積が広くなると、水の高さは低くなる。
こうした「増えたら減る」現象を見つけられれば、反比例の可能性が高いと判断できます。
さらに見分けるコツとしては、
- 「かけたら同じ数になる」関係を探す
- 足し算・引き算ではなく掛け算で成り立つことを確認する
- 増加と減少がセットになっているか注目する
比例の考え方で「足し算・引き算」をしてしまうミスも多いので注意が必要です。
反比例はあくまで「掛け算の一定性」で判断することが大切です。
文章問題を式に変えて整理しよう!反比例を見抜くポイント
反比例の文章問題を解くには、問題文を読んで$y=\frac{a}{x}$の形を思い出せるかどうかが第一ステップです。
反比例とわかったら、まずこの式を書き、そのあとで$a$を求める作業をします。
たとえば、「$x=4$のとき$y=3$」という条件があれば、
$a=x×y=4×3=12$
となるので、
$y=\frac{12}{x}$
がその問題の基本式になります。
文章問題では次のような手順で式を整理するとスムーズに進みます。
- 条件を読み取る
→一方が増えるともう一方が減るか?
→全体の量が決まっているか?などをチェック。 - 反比例と判断したら$y=\frac{a}{x}$を書く
- 与えられた$x$・$y$を使って$a$を求める
- 求めた$a$を式に代入し、一般式をつくる
- 必要な値をこの式を使って計算する
文章問題の例としては、「人数と時間」「幅と高さ」「速さと時間」など、反比例の代表的な場面が多く登場します。
なかには、問題文に「反比例する」と書いていなくても、「$x$が増えると$y$が減る」、「$x×y$が一定になりそう」という情報から反比例を判断できる場合もあります。
比例の式($y=ax$)と混同しないように、問題文に書かれた変化の方向をていねいに読み取ることが重要です。
反比例の考え方で答えを導く!計算の流れをつかもう
最後に、反比例の式を使って具体的に値を求める方法を確認しましょう。
反比例の計算は、次の流れをしっかり押さえればとてもスムーズに解けます。
- 反比例の式$y=\frac{a}{x}$を書く
- 与えられた$x$・$y$を使って$a$を求める($a=x×y$)
- 求めた式を使って知りたい値を計算する
例題で見てみましょう。
例題
$x$と$y$が反比例し、$x=2$のとき$y=8$である。$x=4$のときの$y$を求めなさい。
まず、$a=2×8=16$なので、式は
$y=\frac{16}{x}$
求めたいのは$x=4$のときの$y$なので、
$y=16÷4=4$
となります。
確認として、2×8=16、4×4=16となり、どちらも積が一定なので反比例の条件を満たします。
反比例では、この「積の一定性」を使うと、式を作らなくても素早く計算できることがあります。
慣れてくると、
- 「$a=x×y$を最初に求める」
- 「あとは$x$が変わったら$y$を調整する」
というリズムで解けるようになります。
文章問題でも、反比例の考え方を使うと、条件を整理しながら落ち着いて解くことができます。
まとめ
反比例は、「一方が大きくなるともう一方が小さくなる」関係を表す重要な考え方です。
ポイントは3つでした。
- 「$x$と$y$をかけると一定の数になる($a=x×y$)」という性質。
- 式が「$y=\frac{a}{x}$」という形で表されること。
- グラフが原点を通らない右下がりのカーブ(双曲線)になること。
この3点を押さえておけば、反比例の文章問題も式も自信をもって解けるようになります。
比例との違いやグラフの形をイメージしながら、日常の中にも反比例の関係を探してみましょう。
数字の変化がもっと身近に感じられるはずです。
| 中学生のおすすめオンライン塾・家庭教師3選 | |||
|---|---|---|---|
ウィズスタディ |
家庭教師の銀河 |
WAM |
|
| 対象 | 中学生 高校生 |
中学生 | 中学生 高校生 |
| 授業料 (税込) |
9,800円~ (1科目) |
2,750円~ (1コマ) |
7,600円~ (週1回) |
| 入会金 | 27,500円~ | 22,000円 | 16,500円~ |
| 指導形式 | 学習塾 (オンライン) |
家庭教師 | 学習塾 (オンライン) |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | |
練習問題
問1
$x$と$y$が反比例し、$x=6$のとき$y=8$である。$x=12$のときの$y$を求めよ。
問2
$x$と$y$が反比例し、$y=5$のとき$x=4$である。$x=10$のときの$y$を求めよ。
問3
反比例の式が$y=\frac{18}{x}$で表されるとき、$x=3$のときの$y$を求めよ。
問4
$x$と$y$が反比例しており、$y=\frac{a}{x}$で表される。$x=7$のとき$y=6$であるとき、$a$の値を求めよ。
問5
$x$と$y$が反比例し、$x×y=48$である。$x=1.5$のときの$y$を求めよ。
問6
ある作業を数人で協力して行うことにした。この作業は、全員が同じ速さで作業をするものとする。$x$人で作業するとき、作業が終わるまでの時間$y$時間は反比例の関係になる。
(1)4人で作業したところ、終わるまでに6時間かかった。この作業について、反比例の式$y=\frac{a}{x}$を完成させよ。
(2)この作業を8人で行うとき、終わるまでの時間$y$を求めよ。
(3)逆に、作業を3時間で終わらせたいとするとき、必要な人数$x$を求めよ。
解答
問1
$a=6×8=48$
$y=\frac{48}{12}=4$
問2
$a=4×5=20$
$y=\frac{20}{10}=2$
問3
$y=\frac{18}{3}=6$
問4
$a=7×6=42$
問5
$y=\frac{48}{1.5}=32$
問6
(1)4人で6時間→ $a=4×6=24$
$y=\frac{24}{x}$
(2)$y=\frac{24}{8}=3$(時間)
(3)$x=\frac{24}{3}=8$(人)
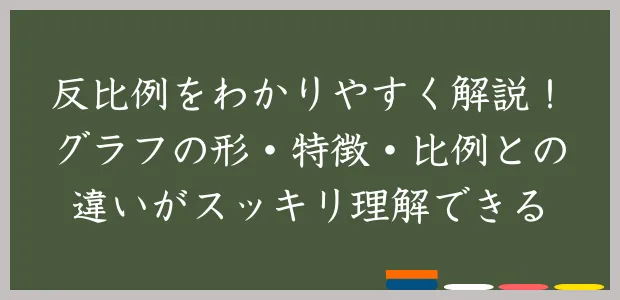

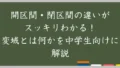
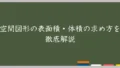
コメント