中学2年で学習する「平面図形」は、数学の中でも特に図形的な感覚を養うために大切な単元です。
小学校でも三角形や四角形といった基本的な図形を学んできましたが、中学ではそれをさらに発展させて、多角形全般についての性質や公式を体系的に学びます。
特に「多角形の内角の和」「多角形の外角の和」などは入試でも頻出であり、日常生活においても設計やデザイン、建築などの場面で役立つ知識です。
また、図形の学習では「なぜその公式になるのか」を理解することが重要です。
単に公式を暗記するだけではなく、三角形や四角形の基本性質から出発して、多角形に一般化していく流れを理解すると、数学的な思考力が養われます。
ここでは、まず多角形の基本的な性質を整理し、その後に「内角の和」「外角の和」の考え方と公式を順を追って解説していきます。
多角形の基礎知識
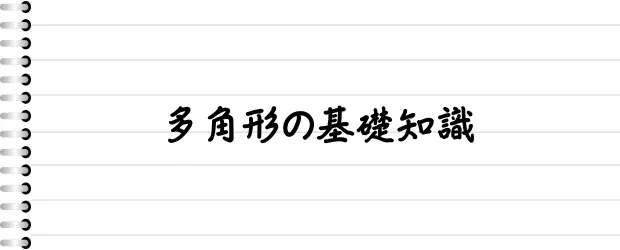
多角形とは、複数の直線をつなぎ合わせてできる閉じた図形のことです。
例えば三角形は最も基本的な多角形であり、4本の辺で囲まれた四角形も多角形の一種です。
辺の数によって次のように分類されます。
- 3本の辺 → 三角形
- 4本の辺 → 四角形
- 5本の辺 → 五角形
- 6本の辺 → 六角形
- $n$本の辺 → $n$角形(一般に「多角形」と呼ぶ)
多角形を学ぶうえで大切なポイントは、内角と外角という2つの角度です。
内角とは、多角形の内部にできる角のことです。
外角とは、その辺を延長したときに外側にできる角のことです。
中学数学では、この内角と外角の和や公式を理解することが第一歩になります。
多角形の内角の和を理解しよう
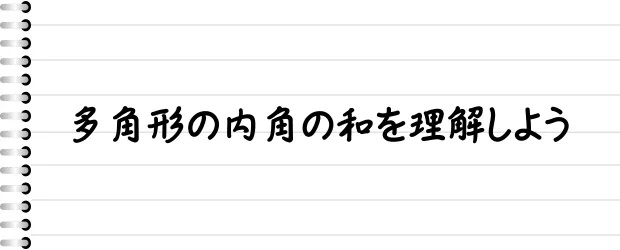
これらのことを踏まえて、まずは「多角形の内角の和」について学びましょう。
これはこれからの図形の学習の中でも大切なテーマであり、必ず押さえておくべき内容です。
三角形から考える内角の和
一番身近な三角形を例にすると、三角形の内角の和は必ず180°になります。
小学校でも学習しましたが、これが多角形の内角の和の基礎となります。
なぜ180°になるのかというと、次のように説明できます。
例えば三角形の一つの辺に平行な直線を引き、同位角や錯角の性質を使うと、残りの角度と一直線をつくることがわかります。
この性質を応用すると、三角形の3つの内角を合わせると180°になることが理解できます。
つまり、三角形が内角の和を求める出発点です。
四角形の内角の和
次に四角形を考えてみましょう。
四角形を対角線で分けると、2つの三角形に分けられます。
それぞれの三角形の内角の和は180°なので、合わせると360°になります。
つまり、四角形の内角の和は360°であることがわかります。
五角形・六角形の場合
同じように、五角形は対角線を引くと三角形が3つできます。
それぞれの三角形の内角の和は180°なので、180°×3=540°が五角形の内角の和になります。
同様に、六角形であれば三角形に分けると4つになるので、180°×4=720°です。
このように、多角形の内角の和は「三角形に分割する」ことで求められるのです。
多角形の内角の和の公式
上の考え方を一般化すると、$n$角形の内角の和は
($n$−2)×180°
という公式になります。
- 三角形 ($n$=3) → (3−2)×180°=180°
- 四角形 ($n$=4) → (4−2)×180°=360°
- 五角形 ($n$=5) → (5−2)×180°=540°
このように、公式を使えば簡単に求められます。
多角形の外角の和を理解しよう
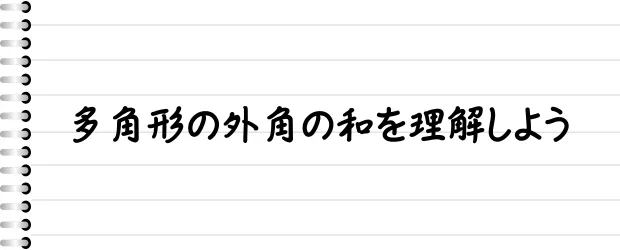
次に「外角の和」について学びましょう。
内角と並んで、多角形を学ぶうえで欠かせないテーマです。
三角形の外角の性質
三角形の1つの頂点で外角をつくると、その外角と隣り合う内角を足すと180°になります。
これは平行線の性質や角度の関係を使えば理解できます。
三角形の3つの外角を1つずつ考えると、実はその和は必ず360°になります。
四角形や五角形でも同じ?
ここで疑問が出るかもしれません。
「三角形では360°だったけど、四角形や五角形ではどうなの?」という点です。
実は答えはとてもシンプルで、どんな多角形でも外角の和は360°になります。
多角形の外角の和の公式
一般の$n$角形においても、外角を1つずつ取り出して合計すると必ず360°になります。
つまり、外角の和の公式は360°です。
これは非常に重要な性質で、入試問題や応用問題でもよく出題されます。
「多角形の外角の和は必ず360°」という事実を覚えるだけでなく、なぜそうなるのかを理解しておきましょう。
なぜ外角の和は360°になるのか
この理由は、多角形の各頂点で外角を順に回りながら歩いていくイメージをするとわかりやすいです。
外角を順番に回っていくと、最終的には一周して元の方向に戻ります。
そのときに回転した角度の合計はちょうど1周=360°になります。
つまり、外角の和が常に360°になるのは、「多角形を一周すると必ず360°回転するから」なのです。
多角形の内角の公式の活用法
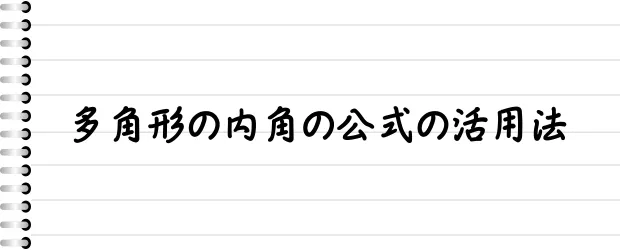
ここまでの説明では、多角形の基本性質と「内角の和」「外角の和」について整理しました。
ここからは、その知識を実際に問題に活用する方法や、さらに発展的な内容である「多角形の対角線の本数」について学んでいきましょう。
数学では「公式を覚えること」も大切ですが、それ以上に「公式をどう使うか」「どのように導き出せるか」を理解することが重要です。
ここからの学習で、皆さんがより自信を持って平面図形の問題に取り組めるようにしていきましょう。
まずは「多角形の内角の公式」を使った具体的な活用方法を確認します。
正多角形の1つの内角を求める
「正多角形」とは、すべての辺の長さと角度が等しい多角形のことです。
正三角形、正方形、正五角形などがその代表例です。
正多角形では、内角の和を辺の数で割ると、1つの内角の大きさが求められます。
例えば正六角形の場合、
内角の和=(6−2)×180°=720°
これを6で割ると、1つの内角=120°になります。
つまり、
正$n$角形の1つの内角=($n$−2)×180°÷$n$
という公式が成り立ちます。
応用問題例
問題
正八角形の1つの内角を求めよ。
解答
内角の和=(8−2)×180°=1080°
1つの内角=1080°÷8=135°
したがって、正八角形の1つの内角は135°となります。
このように「多角形の内角の公式」は、正多角形の内角を求める際に非常に役立ちます。
多角形の外角の公式の活用法
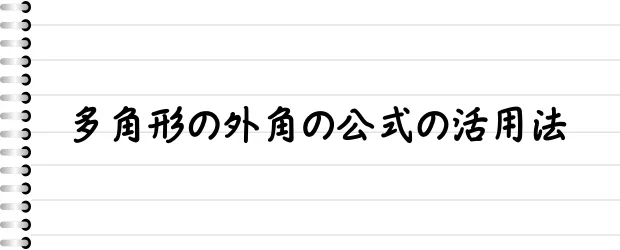
次に「多角形の外角の公式」の活用方法を見ていきましょう。
正多角形の1つの外角を求める
外角の和は360°であることを上記で学びました。
正多角形ではすべての外角が等しいため、外角の和360°を辺の数で割れば、1つの外角が求められます。
例えば正十角形なら、
1つの外角=360°÷10=36°
したがって、1つの内角は180°−36°=144°になります。
内角と外角の関係を使う
正多角形では「内角と外角の和=180°」という関係が必ず成り立ちます。
そのため、外角を先に求めれば内角が出せるし、内角を求めれば外角も簡単に求められます。
問題
正十二角形の1つの外角を求めよ。
解答
外角の和=360°
1つの外角=360°÷12=30°
よって、正十二角形の外角は30°となります。
外角を使った実用的な考え方
外角の考え方は、実際には「方向転換」にもつながります。
例えば、正六角形の頂点を順にたどるとき、進む方向を何度ずつ変えているかを考えると、それはまさに外角の大きさになります。
建築やデザイン、道路の交差点の設計などでも、外角の性質は役立っています。
多角形の対角線の本数を求める方法
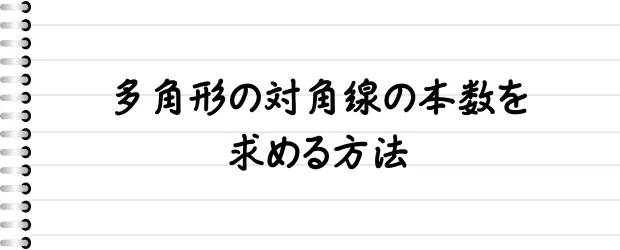
ここからは、新しいテーマ「多角形の対角線」について学んでいきます。
対角線とは?
対角線とは、多角形の頂点と頂点を結んだとき、辺にならない線分のことを指します。
例えば四角形では、隣り合っていない2つの頂点を結ぶ線が対角線です。
四角形・五角形の対角線の本数
四角形を例にすると、対角線は2本しかありません。
五角形の場合はどうでしょうか?五角形には頂点が5つあります。
それぞれの頂点から2本ずつ(隣り合う頂点を除いた)対角線を引けるので、合計5×2÷2=5本になります。
多角形の対角線の本数の公式
五角形の考え方を一般化すると、$n$角形の対角線の本数は次の公式で表されます。
$n(n−3)÷2$
- 四角形 ($n$=4) → 4×1÷2=2本
- 五角形 ($n$=5) → 5×2÷2=5本
- 六角形 ($n$=6) → 6×3÷2=9本
このように計算で求められるので、覚えておくと便利です。
なぜこの公式になるのか
公式の意味を理解することが大切です。
$n$角形では、1つの頂点から引ける対角線の本数は「($n$−3)本」です(自分自身と隣の2点は除くため)。
それを$n$個の頂点で数えると $n$($n$−3) 本になりますが、このままだと1つの対角線を2回ずつ数えてしまいます。
したがって2で割って、最終的に$n(n−3)÷2$となるのです。
応用問題
問題
八角形の対角線の本数を求めよ。
解答
公式$n(n−3)÷2$を使う。
8(8−3)÷2=8×5÷2=20本
よって、八角形の対角線は20本となります。
平面図形の知識をどう活かすか
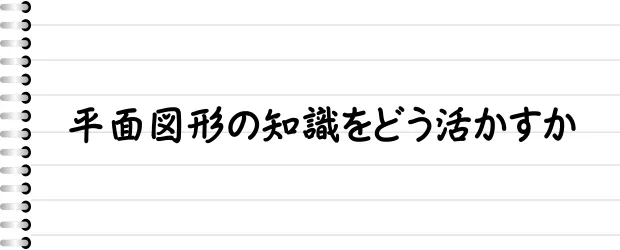
ここまでで「多角形の内角の公式」「多角形の外角の公式」「多角形の対角線の本数」を学びました。
これらは単なる数学の知識にとどまらず、実際の生活や仕事に応用できる知識です。
デザインや建築における応用
例えば建築では、多角形をモチーフにした建物や屋根の形を設計する際に、内角の大きさを正確に計算する必要があります。
また、インテリアデザインやタイルの模様などでも、正多角形の性質が活用されています。
プログラミングやグラフィックにおける応用
コンピュータで図形を描く際にも、多角形の内角や外角、対角線の数が関わってきます。
特に正多角形を描画するアルゴリズムでは「外角=360°÷$n$」という公式をそのまま使っています。
入試問題での出題傾向
中学数学の入試問題では、正多角形の内角や外角、対角線の本数を絡めた問題が頻出です。
単に公式を暗記するだけではなく、実際に図を書いて確かめる習慣をつけると、応用問題にも強くなります。
内角と外角を使った応用問題
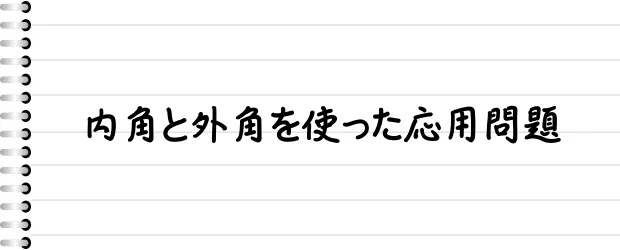
ここまでは、多角形に関する基本的な性質と公式を学びました。
ここからは、それらをどのように問題解決に生かすか、また日常生活や将来の学びにつなげるかについて考えていきましょう。
数学は「知識」と「活用」の両輪で理解が深まります。
知識として公式を覚えるだけではなく、問題を解きながら「なぜその公式が役立つのか」を実感することが、真の学力につながります。
まずは「多角形の内角の和」「多角形の外角の和」を実際の問題に応用してみましょう。
問題1:正多角形の角度を求める
問題
正十五角形の1つの内角の大きさを求めよ。
解答
内角の和=(15−2)×180°=13×180°=2340°
1つの内角=2340°÷15=156°
したがって、正十五角形の内角は156°です。
このように、公式を使うと多角形が何角形であってもすぐに求められることが分かります。
問題2:外角を利用した思考問題
問題
ある正多角形の1つの外角が24°である。この多角形は何角形か。
解答
外角の公式=360°÷$n$
24°=360°÷$n$
両辺を入れ替えると $n$=360°÷24=15
したがって、この多角形は正十五角形です。
外角を手がかりに多角形の辺の数を求める問題は入試でもよく出題されます。
問題3:内角と外角を組み合わせた問題
問題
正多角形の1つの内角が150°である。この正多角形の辺の数を求めよ。
解答
内角と外角の関係は「内角+外角=180°」
よって外角=180°−150°=30°
辺の数=360°÷30°=12
したがって、この正多角形は正十二角形です。
このように、内角と外角の両方の知識を活用すれば、問題を柔軟に解けるようになります。
対角線を使った応用問題
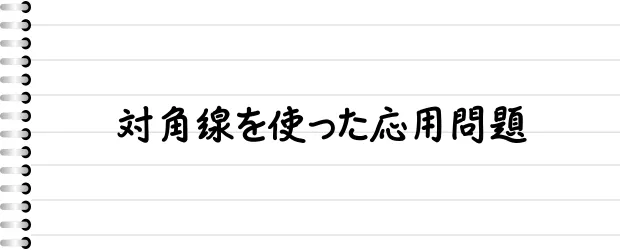
次に「多角形の対角線の本数」の公式を使った問題に挑戦してみましょう。
問題4:八角形の対角線の本数
問題
八角形の対角線の本数を求めよ。
解答
公式$n(n−3)÷2$を使う。
8(8−3)÷2=8×5÷2=20本
よって、八角形の対角線は20本となります。
平面図形と実生活のつながり
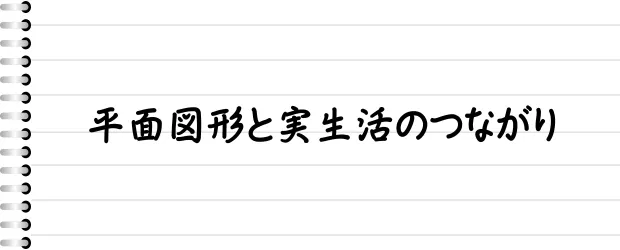
ここまで扱った内容は「試験対策のための数学」にとどまらず、実際に生活の中で役立っています。
建築・設計の分野
建物の形や屋根のデザインでは、多角形の性質がそのまま利用されています。
特に正多角形は安定した構造を持つため、ドームやタイル模様などによく用いられます。
設計者は「内角の和」や「外角の大きさ」を正確に理解していなければ、美しく安全な構造を作ることはできません。
アート・デザインの分野
グラフィックデザインや美術の世界でも、多角形のバランスは重要です。
例えば正五角形や正六角形を組み合わせた模様は、人の目に美しい対称性を感じさせます。
これもまた「多角形の内角の公式」「多角形の外角の公式」の知識が背景にあるのです。
情報技術・プログラミング
コンピュータで多角形を描画するとき、プログラムは実際に外角や対角線の計算を行っています。
正$n$角形を描くアルゴリズムでは、回転角度(外角)が必ず360°÷$n$であることを利用します。
このように、私たちが目にするアニメーションやゲームの背景にも、数学の知識が活かされています。
学習を定着させる工夫
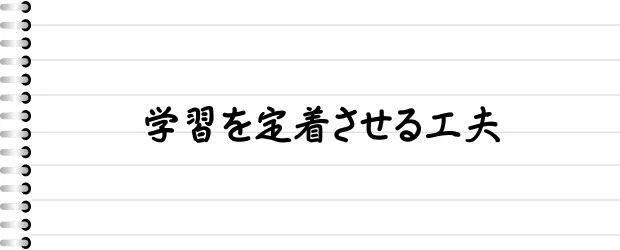
最後に、平面図形の学習をより効果的に進めるための方法を整理しましょう。
図を書いて確認する
公式を覚えるだけでなく、必ず図を書いて確認する習慣をつけましょう。
「対角線の本数」も図に線を引いて数えれば、公式の意味が納得できます。
基本問題を繰り返す
難しい応用問題に取り組む前に、基本的な公式を使った計算問題を繰り返すことが重要です。
例えば「正$n$角形の1つの内角を求める」問題をさまざまな$n$で解いてみると、計算がスムーズになります。
実生活に結びつけて考える
学んだ内容を実生活に関連づけると、理解が一層深まります。
例えば「正六角形の内角は120°」という知識を、ハチの巣の構造やタイルの模様と関連づけて考えると、数学が身近に感じられるでしょう。
まとめ
中学2年で学習する「平面図形」は、単なる公式の暗記にとどまらず、図形の性質を理解し、論理的に考える力を養う大切な分野です。
このページでは、多角形の内角の和や外角の和、公式の導き方や意味、そして対角線の本数を求める方法について、基礎から応用までを体系的に解説しました。
三角形を基本に分割して考える方法から始まり、一般化された公式(n−2)×180°の意味をしっかり確認しました。
さらに、具体例を通して公式の使い方を整理し、日常生活や実際の場面でどのように活かせるかまで解説しました。
また、「多角形の外角の和」と「外角の公式」について学びました。
特に重要なのは、どんな多角形でも外角の和が必ず360°になるという性質です。
このシンプルで強力な法則は、規則正しい多角形の学習や応用問題に直結します。
また、正多角形における1つの外角や内角の大きさを求める方法も扱い、受験や実生活の設計にも応用できる考え方を整理しました。
さらに「多角形の対角線の本数」をテーマにしました。
具体的な図を思い浮かべながら数える作業から始め、一般化された公式$n(n−3)÷2$の導き方と意味を学びました。
さらに、正多角形の対角線の持つ対称性や、建築・デザインにおける応用例も取り上げ、学習内容をより実感的に理解できる構成としました。
これらを理解すれば、中学数学の平面図形の基礎は確実に固まります。
学んだ内容を活かしながら、図形の持つ美しさや不思議さを楽しんで学習を続けていきましょう。
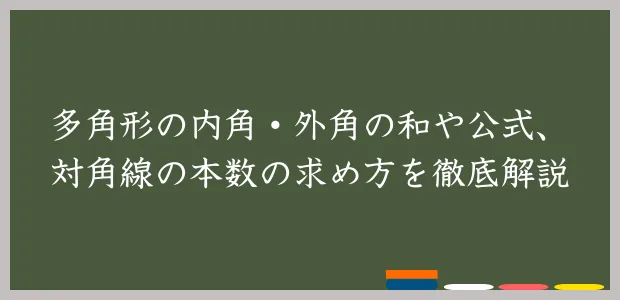







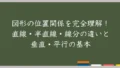

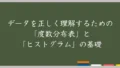
コメント