理系科目が苦手な中学生でも安心!
中学1年「一次方程式」の超やさしい解説ページです。
定義から解き方の3ステップ、小数・分数処理、文章題コツまで、例題たっぷりで天秤イメージを使ってスッキリ理解できる構成で説明しています。
つまずき注意点も網羅し、テスト対策に最適です。
| 中学生のおすすめ学習塾3選 | |||
|---|---|---|---|
横浜予備校 |
WAM |
明光義塾 |
|
| 対象 | 中学生 | 中学生 高校生 |
中学生 高校生 |
| 授業料 (税込) |
29,700円~ (月額) |
7,600円~ (週1回) |
15,400円~ (週1回) |
| 入塾金 | 0円 | 16,500円~ | 11,000円 |
| 指導形式 | 学習塾 | 学習塾 (個別指導) |
学習塾 (個別指導) |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | |
一次方程式とは
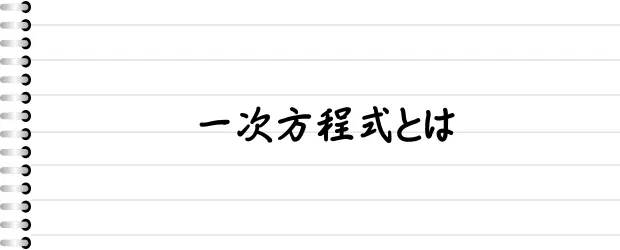
一次方程式は一次式を用いて「未知数$x$の値を求める問題」であることが自然に理解しやすくなります。
ここでは、一次方程式の定義から、解の意味、そして実際にどのような仕組みで解いていくのかを、初学者にもわかるように丁寧に説明していきます。
数学が苦手な中学生でも「なるほど、こういうことだったのか」と思えるように、できるだけ日常のイメージに結びつけて解説します。
一次方程式の定義
一次方程式とは、未知数$x$の最高次数が1の形で表された方程式のことです。
一般的には
$ax+b=0(a≠0)$
という形で表されます。
ここでいう「次数が1」というのは、$x$が1回だけ登場するという意味で、$x²$や$x³$のように2回・3回重なって出てくる形ではないということです。
中学生にとって「$x$」は「わからない数」を表す記号です。
これは小学校で扱った「□+3=7」の□の部分が$x$に置き換わっただけですから、必要以上に構える必要はありません。
同じ考え方の延長上にあります。
たとえば次のような式は一次方程式の典型例です。
$2x+5=11$
この方程式は、$x$の値を知りたいという問いを表しています。
$x=3$を代入すると
左辺:2×3+5=11
右辺:11
となり、左右が等しくなるため、$x=3$はこの方程式の正しい答えであることが確かめられます。
このように、一次方程式は必ず「解が1つに決まる」という特徴があります。
一次方程式の解とは
一次方程式の解とは、方程式の左辺と右辺を等しくする$x$の値のことです。
もっと平たく言えば、「$x$の正体を見つける」という作業です。
例えば、
$x−4=2$
という一次方程式を考えてみましょう。
この方程式を満たす$x$は$x=6$です。
代入して確認すると、
左辺:6-4=2
右辺:2
となり、本当に左右が一致することがわかります。
数学ではこの確認作業も重要なステップです。
中学1年の範囲では基本的に解が1つだけ存在しますが、次のように例外的な形もあります。
- $0x=5$ …… どんな$x$を入れても0にはならない → 解なし(不能)
- $0x=0$ …… どんな$x$でも OK → 無数の解(不定)
ただし、学習の中心は「1つの解を求める」形です。
ここでは、その仕組みを理解することを目的とします。
等式の性質で解く仕組み
一次方程式が解ける理由は、数学の基本ルールである等式の性質に基づいています。
等式の性質とは、
- 左右が等しいなら、両辺に同じ数を足しても引いてもよい
- 両辺に同じ数を掛けても、ゼロでない数で割ってもよい
という決まりのことです。
式で書くと次のようになります。
$A=B$なら
- $A+c=B+c$
- $A−c=B−c$
- $A×c=B×c$
- $A÷c=B÷c(c≠0)$
これは「天秤がつり合っているなら、両側に同じ操作をしてもつり合いは崩れない」というイメージで理解できます。
具体例を見てみましょう。
$2x+3=7$
この式は、両辺に「−3」をすると
$2x=4$
になります。
さらに両辺を2で割れば
$x=2$
という答えが得られます。
ここで行っている操作はすべて等式の性質に従ったものです。
また、中学数学ではよく「移項」というテクニックを使いますが、これは等式の性質を簡単に書くための省略表現です。
左辺の+3を右辺へ移すと−3に変わる、というルールは、両辺に−3をしているのと全く同じ意味です。
これらの性質を理解すると、どんな一次方程式でも「天秤のバランスを保ちながら$x$を一人にする」という流れで解けるようになります。
後の学習で扱う分数を含んだ方程式や応用問題でも、この考え方が軸となっていきます。
一次方程式を解く時に注意すること
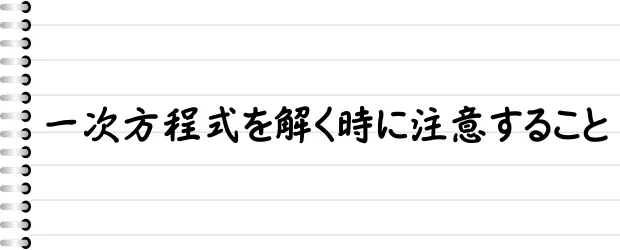
上記で、一次方程式が「等式の性質」を使って$x$を求める問題であることを学びました。
しかし、実際に計算していくと、多くの中学生が同じような場所でつまずきます。
特に、移項の符号、負の係数、両辺操作のルールなどは、少しでも曖昧なまま進めると計算ミスが連発します。
ここでは、一次方程式を正確に解くために絶対に押さえておきたい注意点を、例とともに詳しく解説します。
ミスが起きやすい原因を知っておくことで、計算への不安も大きく減り、スムーズに問題が解けるようになります。
移項するときの符号間違いに注意
一次方程式の計算で最も多いミスが「移項の符号を逆にするのを忘れる」ことです。
移項とは、方程式の項を反対側へ移動させる操作で、右へ移すときは符号を逆、左へ移すときも符号を逆にするというルールがあります。
たとえば、
$2x+5=11$
この式で、左側の+5を右へ移すときは
$2x=11−5$
のように符号を変える必要があります。
しかし、ここで「+5をそのまま右へ移して11+5としてしまう」というミスが非常に多く起こります。
この場合、$x=8$という誤った答えになってしまい、正しい計算と大きくズレてしまいます。
移項では特に 負の項の扱い が間違いやすいです。
例えば、$−3x$を反対側へ移すときは$+3x$になります。
この変化を忘れたり、逆に書いてしまうとその後の計算がすべて狂います。
ミスを防ぐコツとして有効なのが天秤のイメージです。
方程式は「左右がつり合っている状態」なので、片側から重さ(=項)を移動させるときは、その重りの向きを逆にしてバランスを取っていると考えるとよいでしょう。
例として、次の問題を見てみます。
$3x−4=x+2$
両辺の$x$の項を左へ、数字を右へ移すと、
左に$3x$と$-x$ → $2x$
右に2と+4 → 6
したがって、
$2x=6$
→$x=3$
となります。
移項を正しく行えば、あとは簡単な計算で答えまでたどり着けます。
数を移すたびに「符号は変えたか」を確認する習慣をつけましょう。
負の係数の処理を忘れずに
一次方程式を解いていると、移項の結果、$x$の係数が負になることがあります。
たとえば
$−3x=6$
のような式です。
負の係数のまま計算を進めると、符号の変化が多くなり混乱しやすくなります。
そのため、両辺に−1をかけて係数を正にする方法がおすすめです。
この例では、
両辺 ×(−1) をすると
$3x=−6$
になります。
ここまでくれば、あとは両辺÷3で$x=-2$と簡単に求められます。
特に中学1年の範囲では、移項後に「$−2x$」「$−5x$」などの負の係数がよく登場します。
負の数を扱う回数が増えるほどミスも増えるため、負の係数が出たらすぐに×(−1)で正にするというルールを徹底すると、途中式の見通しが一気によくなります。
両辺に同じ数をかけ割るルール厳守
一次方程式は「等式の性質」に基づいて解くため、両辺に同じ数をまとめて操作することが鉄則です。
特に、最後のステップで$x$の係数を1にするために必ず「両辺を同じ数で割る」操作が入ります。
たとえば、
$2x=10$
両辺を2で割って
$x=5$
となります。
ここで左辺だけを2で割ったり、右側だけを操作したりすると、当然ながら式の意味が変わってしまいます。
また、重要な注意点として0では割れないというルールがあります。
0で割ると計算が成立しないため、必ず係数が0でないことを確認してから割る習慣をつけましょう。
さらに、分数の入った方程式では「分母を一気に消すために両辺に最小公倍数をかける」という操作が必要になります。
この内容は後述しますが、基本ルールは同じで、「両辺に等しい操作をする」ことが大前提です。
| 中学生のおすすめオンライン塾・家庭教師3選 | |||
|---|---|---|---|
ウィズスタディ |
家庭教師の銀河 |
WAM |
|
| 対象 | 中学生 高校生 |
中学生 | 中学生 高校生 |
| 授業料 (税込) |
9,800円~ (1科目) |
2,750円~ (1コマ) |
7,600円~ (週1回) |
| 入会金 | 27,500円~ | 22,000円 | 16,500円~ |
| 指導形式 | 学習塾 (オンライン) |
家庭教師 | 学習塾 (オンライン) |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | |
一次方程式の簡単な解き方
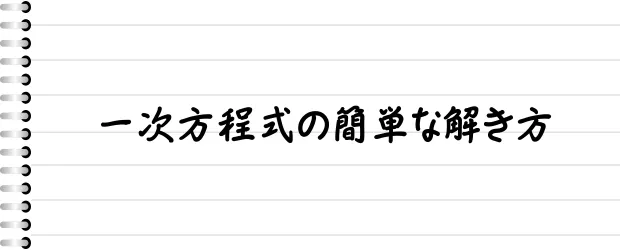
ここまでは、一次方程式を解くときの注意点や、移項・符号処理などで間違えやすいポイントを確認しました。
ここからは、実際に一次方程式をどのような手順で解いていけばよいのかを、3つのステップに分けて整理していきます。
手順をはっきりと決めておくと、どんな一次方程式に出会っても落ち着いて同じ流れで解けるようになり、ミスも大幅に減ります。
中学1年で身につけるこの流れは、高校数学に進んだあともずっと使う重要な基礎力となるため、この段階でしっかり固めておきましょう。
ステップ1:xの項を左に集める
一次方程式の解法の最初のステップは、$x$のついた項(文字の項)をすべて左辺に集めることです。
右辺に文字の項がある場合は左へ移項し、数字の項は後で右辺へ移します。
移項するときは「符号を逆にする」ことが絶対ルールです。
例として、次の式を見てみましょう。
$3x+2=x+7$
右辺の$x$を左へ移項すると、
$3x−x+2=7$
となり、左辺に$x$の項だけがそろいます。
この結果、
$2x+2=7$
の形に整理できます。
もう一つ例を見ましょう。
$5x−4=2x+1$
右辺の$2x$を左へ移すと
$5x−2x−4=1$
となり、
$3x−4=1$
と整理できます。
移項ミスを防ぐコツとして、「天秤のバランスをイメージする」という方法があります。
方程式は左右がつり合っている状態ですので、右から左に項を動かすときは、同じ重さを反対側に移すために符号が変わる、というイメージを持つと混乱が減ります。
練習として、次の式を移項するとどうなるか考えてみましょう。
$4x+5=7x−3$
右の$7x$を左へ移すと
$−3x+5=−3$
となります。
ここまでできれば、この後の計算が非常に進めやすくなります。
ステップ2:両辺を整理して計算
ステップ1で文字の項が左に集まったら、次は方程式全体を「$ax=b$」の形に近づけるために、両辺を整理して計算します。
必要であれば括弧をはずし、数字の項を右へ移項して、できるだけシンプルな形にしていきます。
先ほどの例
$2x+2=7$
の続きでは、左辺の+2を右へ移項して
$2x=7−2$
となり、
$2x=5$
という形になります。
これで「$ax=b$」が完成です。
もう少し複雑な例として、
$8x−3=5x+12$
を見てみましょう。
右辺の$5x$を左へ移項すると、
$8x−5x−3=12$
となり、
$3x−3=12$
となります。
ここで−3を右へ移せば、
$3x=12+3$
となり、
$3x=15$
まで整理できます。
このステップでは特に符号ミスが起こりやすいため、行ごとに「左と右は正しく対応しているか」を声に出して確認するとミスが減ります。
ここまでくれば次のステップで解が簡単に求まります。
ステップ3:xを単独にする最終操作
最後のステップでは、左辺の$x$の係数を1にして、「$x=$数値」の形にします。
係数が正の場合は、係数で割ればすぐに$x$が求まりますが、係数が負のときは先に×(−1) をして正の係数にしてから割ると計算が分かりやすくなります。
例として、
$2x=5$
では両辺を2で割り、
$x=\frac{5}{2}$
が答えです。
別の例として、
$3x=15$
では、
$x=5$
となります。
最後に元の式に代入して
3(5)=15
と確認すると安心です。
負の係数が登場する例も見てみましょう。
$−4x=8$
まず両辺に×(−1)をして
$4x=−8$
次に両辺÷4をして
$x=−2$
となります。
確認すると
−4(−2)=8
なので正しいことが分かります。
分数・小数を含む一次方程式の解き方
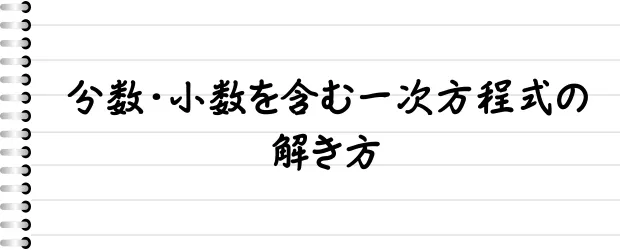
上記では、一次方程式の基本的な解き方や移項のルールを確認しました。
ここでは、その応用として「分数」や「小数」が含まれた一次方程式をどのように処理するかを学んでいきます。
これらが混ざると一気に難しく感じますが、実は最初の手順で整数にそろえるだけで一気に簡単になるのがポイントです。
特に中学生がつまずきやすい内容なので、例題を使いながら順番に確認しましょう。
小数を含む場合の手順:整数に変える
小数が入った一次方程式を解くときは、まず小数を完全に消すこと(整数化)が最重要ステップです。
これを行うだけで計算が劇的に見やすくなり、移項や係数処理のミスが大きく減ります。
小数を消すときは、次のように進めます。
手順
- 最も桁数の多い小数を確認する(例:0.05 → 小数第2位)。
- その桁数に合わせて、両辺に10、100、1000などをかける。
- 小数が消えて整数式になったら、通常の方程式と全く同じ手順で解く。
例題1
$0.3x+0.2=0.8$
最も細かい小数は第1位なので両辺×10。
→ $3x+2=8$
→ $3x=6$
→ $x=2$
代入して確認すると、0.3×2+0.2=0.8で正しい。
例題2
$0.05x−0.1=0.25$
最も細かいのは第2位 → 両辺×100
→ $5x−10=25$
→ $5x=35$
→ $x=7$
小数部分の桁数を読み間違えて×10だけにしてしまうミスが非常に多いので、「一番長い小数に合わせて×10・100・1000を決める」を習慣にすると確実です。
注意点
- 整数化後に負の係数が出ても、そのまま通常処理でOK。必要なら(−1)倍で整える。
- $0.001x$など第3位以上の問題も練習すると確実性が上がる。
分数を含む場合の手順:最小公倍数をかける
分数が含まれる一次方程式では、分母をすべて消すことから始めます。
そのために使うのが「最小公倍数」です。
分数を消すことで計算が一気に単純化するため、解くスピードと正確さが大幅に向上します。
手順
- 式に出てくる分母すべての最小公倍数を求める。
- 求めた最小公倍数を式全体(両辺のすべての項)にかける。
- 分数が完全に消えるので、通常の一次方程式として解く。
例題1
$\frac{x}{2}+\frac{1}{4}=\frac{3}{4}$
分母:2, 4 → 最小公倍数:4
両辺 ×4
→ $2x+1=3$
→ $2x=2$
→ $x=1$
例題2
$\frac{2}{3}x −\frac{x}{4}=\frac{1}{6}$
分母:3,4,6 →最小公倍数:12
両辺 ×12
→ $8x−3x=2$
→ $5x=2$
→ $x=\frac{2}{5}$
最小公倍数が苦手な場合は、
- 倍数を順番に書き出す
- 大きい方から探す
などの方法で十分対処できます。
注意点
- 分数のあるかっこ($\frac{2x+1}{3}$など)を処理するときは、分配法則でまとめてかける。
- 整数項(例:+2など)にも忘れず最小公倍数をかけるのが絶対ルール。
実践例で確認:小数と分数が混在したら
小数と分数が同時に出てくると、一気に難しいと感じる人が多いです。
しかし、実は手順はとてもシンプルで、
- 小数を整数化する(小数処理)
- 分数を消す(最小公倍数処理)
この順番で確実に行えば、どんな問題でも必ず解けるようになります。
例題
$0.2x+\frac{x}{3}=1.5$
①小数を消す:第1位 → 両辺 ×10
→ $2x+\frac{10}{3}x=15$
②分数を消す:分母3 → ×3
→ $6x+10x=45$
→ $16x=45$
→ $x=\frac{45}{16}$
代入しても正しいことが確認できます。
小数と分数の混在は学校テストでも頻出で、「それぞれの手順を2回使う」だけで勝手に整理される問題です。
焦らずステップを守ることが最大のコツです。
| 中学生のおすすめ学習塾3選 | |||
|---|---|---|---|
横浜予備校 |
WAM |
明光義塾 |
|
| 対象 | 中学生 | 中学生 高校生 |
中学生 高校生 |
| 授業料 (税込) |
29,700円~ (月額) |
7,600円~ (週1回) |
15,400円~ (週1回) |
| 入塾金 | 0円 | 16,500円~ | 11,000円 |
| 指導形式 | 学習塾 | 学習塾 (個別指導) |
学習塾 (個別指導) |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | |
文章題で一次方程式を使うコツ
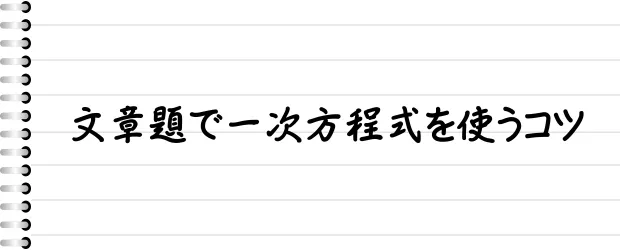
上記では、一次方程式の計算手順や、小数・分数の処理方法を確認しました。
しかし実際のテストでは、計算問題よりも「文章題で方程式を立てる」部分でつまずく中学生がとても多いのが現実です。
文章題は言葉で書かれているため、どこを式にすればよいのかが分かりにくく、数字だけを追ってしまって誤読するケースがよく見られます。
ここでは、文章題を読む最初の段階から方程式を立て、解き、そして答えを確認するところまでの流れを、例題を使いながら丁寧に解説します。
文章題の読み方とxの置き方
文章題を解くときの最も大切な第一歩は、「問題文を正しく読み取ること」です。
まずは ゆっくり2~3回読みながら、重要な数字や求められている量に線を引くことから始めましょう。
特に理系が苦手な中学生は、「誰が」「何を」「いくつ」関わっているのかを、メモとして簡単に整理すると混乱を防げます。
文章題で方程式を立てるときは、求めたいものを$x$に設定するのが鉄則です。
これを最初に決めておくと、後の式作りがスムーズになります。
また、$x$の意味を「$x$個」「$x$円」「$x$時間」などのように単位までセットで書くと、間違った式を作る確率が大幅に減ります。
例題1
「りんご3個とバナナ3個で450円。りんご1個120円のとき、バナナ1個の値段は?」
求めるのは「バナナの単価」なので、まず「$x=$バナナ1個の値段」と置いた方が自然です。
式は
$120×3+3x=450$
→ $360+3x=450$
→ $3x=90$
→ $x=30$(円)
等しい関係を見つけて方程式を立てる
$x$を置いたら、つぎはどの部分が等しい関係になっているのかを探す作業に入ります。
文章題は、必ずどこかに「=で結べる関係」があり、それを式に変換することで方程式が完成します。
文章題でよくある等式パターンは次の 3 種類です。
1. 合計の関係
$A+B=$全体
2. 差の関係
$A−B=$差
3. 速さの関係
距離=速さ×時間
表を作ることで「どこが等しいか」が見つけやすくなります。
特に数量・単価・合計の3つを整理する表は、多くの文章題に対応できる万能ツールです。
例題(距離の関係)
「A君が歩いた距離=B君が自転車で進んだ距離」
Aの距離:$3(t+2)$
Bの距離:$5t$
よって
$3(t+2)=5t$
応用例(残金が等しい)
「Aさんは1000円で本を2冊買い、Bさんは500円で本を1冊買った。残ったお金が同じ。」
本の値段を$x$とすると
$1000-2x=500-x$
が自然に立てられる。
等しい関係は必ず存在するので、キーワード(合計・同じ・残った・差・速さ・距離)を目印に探しましょう。
立てた方程式を解いて答えを確認
方程式が立ったら、ここまでに学んだ手順(移項 → 係数処理 → $x$を単独)で解きます。
しかし、文章題では 解いたあとに必ず答えを元の文に戻して確認すること が重要です。
確認の鉄則
- 求めた$x$を必ず元の文章に戻す
- 単位が合っているか(円?個?時間?)
- 問題の条件を満たしているか
特に「$x=$−3個」などの 明らかに不自然な値 が出た場合は立式ミスの可能性が高いため、式から見直しましょう。
まとめ
このページで一次方程式の基礎(定義・解・等式の性質)を固め、移項符号・負係数・両辺操作の注意点を学びました。
基本3ステップでシンプル解法をマスターし、小数(×10/100で整数化)・分数(最小公倍数で消去)の手順を追加しました。
文章題は表作成と$x$置きで等式を立て、確認習慣で完璧にしています。
練習問題を繰り返せば、少しずつ苦手が克服できます。
次は連立方程式へつながる基盤が完成します。
毎日の3問で自信を積みましょう。
| 中学生のおすすめオンライン塾・家庭教師3選 | |||
|---|---|---|---|
ウィズスタディ |
家庭教師の銀河 |
WAM |
|
| 対象 | 中学生 高校生 |
中学生 | 中学生 高校生 |
| 授業料 (税込) |
9,800円~ (1科目) |
2,750円~ (1コマ) |
7,600円~ (週1回) |
| 入会金 | 27,500円~ | 22,000円 | 16,500円~ |
| 指導形式 | 学習塾 (オンライン) |
家庭教師 | 学習塾 (オンライン) |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | |
練習問題
問1
ある品物を$x$個買うと400円になります。1個あたりの値段を一次方程式を立てて求めなさい。
問2
兄の年齢は弟の年齢より5歳多い。弟の年齢を$x$歳とすると、兄の年齢を$x$を使って表しなさい。
また、2人の年齢の合計が25歳のとき、弟の年齢を求めなさい。
問3
速さ4km/hで歩くAさんと、速さ10km/hの自転車で進むBさんがいます。AさんがBさんより2時間早く出発し、同時に目的地についたとします。Bさんが走った時間を$x$時間として、等しい関係の式を作りなさい。
問4
あるノートを2冊買い、消しゴムをy個買うと500円 でした。ノート1冊は120円 のとき、ノート2冊と消しゴム y個の合計金額を表す式を作り、消しゴム1個の値段を求めなさい。
問5
ある文房具店で、ノート1 冊:120 円、ペン1 本:y円とします。ノート3冊とペン$x$本を買ったところ、合計540円でした。
(1)求める量を$x$として、$x$の意味を書きなさい。
(2)ノートとペンの合計が540円になるという等しい関係の一次方程式を作りなさい。
(3)ペン1本の値段が60円のとき、問題(2)の式に代入して$x$を求めなさい。また、求めた$x$が正しいかどうか合計金額で確認しなさい。
解答
問1
1個あたりの値段を$p$円と置くと、$px=400$
よって、$p=\frac{400}{x}$
問2
兄の年齢は$x+5$(歳)。
合計が$x+(x+5)=25$
よって、
$2x=20$
$x=10$(歳)
問3
Aの距離=$4(x+2)$
Bの距離=$10x$
進んだ距離は等しいので、
$4(x+2)=10x$
よって、
$6x=8$
$x=\frac{4}{3}$(1時間20分)
問4
ノート2冊の金額:120×2=240円。
消しゴム 1 個の価格を$e$円とすると
$240+ey=500$
よって、
$e=\frac{260}{y}$
問5
(1)$x$は ペンの本数(本)
(2)$360+yx=540$
(3)$360+60x=540$
$60x=180$
$x=3$
ノート360円、ペン60×3=180 円、合計360+180=540 円 → 問題の条件と一致。よって$x=3$本(正しい)
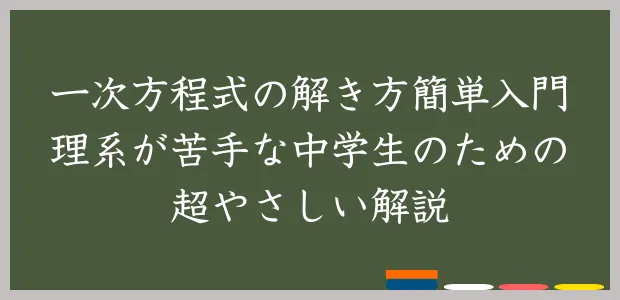
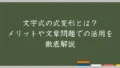
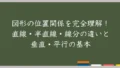

コメント