このページでは、一次式とは?という基本的な定義と特徴から始まり、$x$の一次式、具体例を使ったわかりやすい説明、さらに一次式と一次方程式の違い、一次式の計算方法:加法・減法・乗法・除法の基礎、そして一次式のよくある問題と解き方のポイントまで、中学1年生が理解しやすいように段階的に解説しています。
文字の指数の意味、計算ルール、問題の解き方の流れを具体例と共に丁寧に示し、理系科目が苦手な学生さんでも安心して学べる内容です。
| 中学生のおすすめ学習塾3選 | |||
|---|---|---|---|
横浜予備校 |
WAM |
明光義塾 |
|
| 対象 | 中学生 | 中学生 高校生 |
中学生 高校生 |
| 授業料 (税込) |
29,700円~ (月額) |
7,600円~ (週1回) |
15,400円~ (週1回) |
| 入塾金 | 0円 | 16,500円~ | 11,000円 |
| 指導形式 | 学習塾 | 学習塾 (個別指導) |
学習塾 (個別指導) |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | |
一次式とは?基本的な定義と特徴
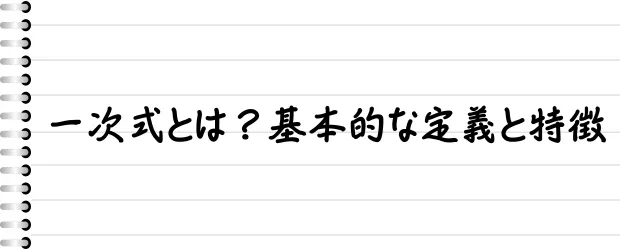
一次式は、中学数学のなかでも特に重要な基礎となる内容で、方程式・関数・文章題など後の単元すべてに関わってきます。
ここでは、一次式の定義、次数や項の意味、そして二次式など似ている式との違いを丁寧に整理します。
ここを正しく押さえることで、式の計算や整理がスムーズになり、後の学習がぐっと楽になります。
一次式の基本的な定義とは何か
一次式とは、「文字(変数)の指数がすべて1である文字式」を指します。
これはとてもシンプルな条件で、中学1年生でも確実に理解できるように作られています。
例えば、$2x+3$,$−5y+7$,$x−8$といった式は、いずれも文字の指数が1であり、数を掛けたり二乗したりしていないため、一次式の代表例です。
また、一次式は一般に$ax+b(a≠0)$の形で表されます。
$a$や$b$は数で、分数や負の数でも問題ありません。
例えば$−x+2$, $\frac{3}{4}x−5$ なども一次式に含まれます。
「指数が1である」という条件さえ守られていればよいのがポイントです。
さらに、多変数でも一次式は存在します。
例えば$2x+3y−5$のように、$x$と$y$といった複数の文字を含む場合も、それぞれの指数が1であれば一次式として扱われます。
この定義は、後に学ぶ一次関数や連立方程式の土台になり、数学における「基盤」のような役割を果たします。
一次式の次数と項の意味を理解しよう
上記の内容では一次式の基本的な形を確認しました。
ここからは、一次式をより正確に理解するために、「次数」「項」「係数」といった数学の重要な用語を整理します。
次数とは、その式の中で最も高い文字の指数のことを指します。
一次式では必ず最大指数が1なので、次数は1になります。
例えば、$2x+3$の場合、文字$x$の指数は1なので次数は 1、$3x+2x−x$のように同類項が複数あっても、$x$の指数が1であることに変わりありません。
次に、式を構成する部分である項について確認しましょう。
項とは「+」や「−」で区切られた一つひとつのかたまりです。
- 文字項(例:$2x$)
- 定数項(例:3)
などに分かれ、文字項の$x$の前に付く数が「係数」です。
係数が1の場合は$x$と省略して書くのが一般的です。
また、計算を簡単にするために「同類項」をまとめる場面が多くあります。
同じ文字を含む項同士は、足したり引いたりして整理できます。
例:$3x+2x−x=4x$
さらに、次数の見分け方は「各項の文字の指数を確認する」だけなので、複数の文字が出てきても戸惑わずに判断できます。
例えば、$xy$は$x$と$y$を1回ずつ掛けているので次数は2、$2x−3y+1$はどの項も指数1なので一次式です。
この次数や項の考え方は、二次式や三次式に進む際にもそのまま活かされる基本概念です。
一次式と似ている式(多項式・二次式など)の違い
ここまでで一次式の仕組みを理解しましたが、似ている式と比較することで、よりはっきり違いを意識できます。
一次式は多項式の一種ですが、「最高次数が1」という点が最大の特徴です。
例えば、
- $x²+2x+1$ … 最高次数が2 → 二次式
- $x³−x$ … 最高次数が3 → 三次式
といったように、最高次数が1以外の式は一次式ではありません。
また、文字が分母にある$\frac{1}{x}$のような式は、指数が−1となるため一次式ではなく「有理式」に分類されます。
この違いが分からずに「文字が1つあるから一次式」と誤解してしまう中学生も多いため、指数の値に注目することが重要です。
さらに、
- $xy$ … 2つ文字が掛け算 → 次数2(一次式ではない)
- $x+y²$ … $y²$が2次 → 二次式
のように、複数の変数が出てくる場合でも「指数の合計」で次数を判断します。
一次式は線形(linear)と呼ばれ、グラフにすると直線になるのが大きな特徴です。
一方、二次式は放物線を描くなど形が大きく異なるため、視覚的にも違いが分かりやすくなります。
xの一次式とは?具体例を使ったわかりやすい説明
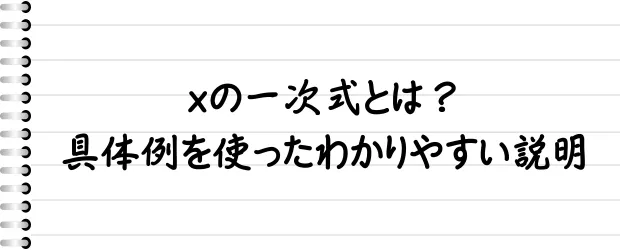
ここまでは一次式全体の基本的な仕組みを学びました。
ここでは、特に中学数学で最も登場する$x$を使った一次式 に焦点を当て、定義・一般形・具体例・間違いやすいポイントを順番に整理していきます。
$x$の一次式を正しく理解できると、一次方程式や一次関数の学習がスムーズになり、数学の基礎力がぐっと高まります。
xの一次式の定義と一般形
$x$の一次式とは、「文字$x$の指数が1である式」のことを指します。
中学数学では$x$を未知の量として扱いますが、その指数が2になったり、分母に入ったりしてはいけません。
指数が必ず1、これが一次式を見分ける最重要ポイントです。
$x$の一次式は、一般に次の形で表されます。
$ax+b$(ただし$a≠0$)
ここで
- $a$ … 係数($x$の前にある数字)
- $b$ … 定数項(文字を含まない数字)
と呼ばれます。
例えば$x+3$という式は、係数が1のため表には書かれていませんが、本来は$1x+3$と同じ意味です。
また、$b$が0の場合は$ax$のみであっても一次式になります。
代表的な$x$の一次式としては$2x+3$、$−5x$、$x−8$などが挙げられます。
いずれも「$x$の指数が1」「数字を掛け合わせていない」「加法と減法でつながっている」という共通の特徴があります。
xの一次式の簡単な具体例
ここでは、$x$の一次式をさらに直感的に理解できるように、いくつか具体例を見ていきましょう。
例1
$3x+4$
- 係数($x$の前の数):3
- 定数項:4
- 指数:すべて 1 → 一次式
例2
$x−7$
- 係数:1(省略)
- 定数項:−7
- 指数:1 → 一次式
例3
$−2x+5$
- 係数:−2
- 定数項:5
- 指数:1 → 一次式
これらの式はどれも「$x$の一次式」の条件を満たしています。
逆に、次のような式は一次式ではありません。
- 5(数字だけ → 定数式)
- $x²+3$(指数 2 → 二次式)
- $\frac{1}{x}+2$(指数 −1 → 有理式)
このように、一次式かどうかの判断には「$x$の指数を確認する」「文字がどの位置にあるかを見る」ことがとても大切です。
よくある間違いと正しい見分け方
ここからは、中学生が特につまずきやすい「一次式の見分け方」を整理していきます。
一次式を理解するときのポイントは、指数・分母・文字の数の3つに注目することです。
間違いやすい例1:指数が2以上の式
例
$x²+3x$
これは最高次数が2なので二次式です。
文字が$x$だからといって一次式にはなりません。
間違いやすい例2:負の指数(分母に文字)
例
$\frac{1}{x}+2$
これは$x⁻¹$を含むため一次式ではなく、有理式に分類されます。
間違いやすい例3:文字同士の掛け算
例
$xy$
$x$と$y$を掛け算しているので、指数の合計が2になり一次式ではありません。
正しい見分け方のポイント
一次式かどうかを判断するには、次の順番でチェックすると非常に分かりやすくなります。
- $x$の指数が1になっているか
→ 2以上・0・負の指数なら一次式ではない - 分母に$x$がないか
→ 分母に$x$があると指数が負になる - 文字が掛け算されていないか
→ $xy$などは次数が2になる - $x$の前の係数は何でもOK(分数・マイナスも許容)
→ $−3x$、$\frac{1}{2}x$も一次式に含まれる
特に「指数を確認する」という習慣がつくと、一次式だけでなく二次式や三次式の分類も簡単にできるようになります。
これは数学の後の単元でも何度も必要になる重要なスキルです。
| 中学生のおすすめオンライン塾・家庭教師3選 | |||
|---|---|---|---|
ウィズスタディ |
家庭教師の銀河 |
WAM |
|
| 対象 | 中学生 高校生 |
中学生 | 中学生 高校生 |
| 授業料 (税込) |
9,800円~ (1科目) |
2,750円~ (1コマ) |
7,600円~ (週1回) |
| 入会金 | 27,500円~ | 22,000円 | 16,500円~ |
| 指導形式 | 学習塾 (オンライン) |
家庭教師 | 学習塾 (オンライン) |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | |
一次式と一次方程式の違いをやさしく理解しよう
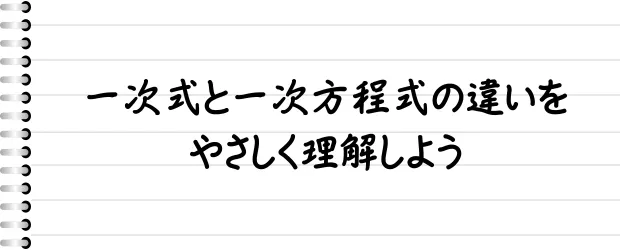
上記では「$x$の一次式」の形や特徴を学びました。
ここからは、一次式とよくセットで扱われる一次方程式との違いを整理していきます。
どちらも似た形をしているため、中学生が特に混同しやすいポイントですが、「式」と「方程式」は役割が大きく異なります。
この違いをしっかり押さえると、方程式の学習がスムーズになるだけでなく、文章題を解くときにも迷わず式を立てられるようになります。
一次式と一次方程式の基本的な違い
まずは、一次式と一次方程式の意味を明確に分けて理解しましょう。
一次式とは?
一次式とは、文字を含む式のうち、文字の指数が1である式のことです。
例
- $2x+3$
- $−3x+5$
- $x−8$
これらはいずれも「式」であり、左側と右側に値が分かれておらず、=(イコール)は含まれません。
一次式の役割は、数量の関係や計算の途中で出てくる「形」を表すことです。
たとえば文章題の中で「代金の合計を$x$を使って表す」など、状況を式として表現するときに使われます。
一次方程式とは?
一次方程式とは、一次式を使って成り立つ等式(=のある式)のことです。
例
- $2x+3=11$
- $x−5=7$
- $3x+2=5x−4$
一般形は次のように書けます。
- $ax+b=c$
- $ax+b=0(a≠0)$
ここでの役割は「$x$の値はいくつなら、この等式が成り立つか」を調べることです。
つまり、一次式が「材料」だとすれば、一次方程式は「その材料を使った問題そのもの」と考えると理解しやすくなります。
等号「=」の有無で見分けるポイント
中学生が最も混乱しやすいのは、見た目が似ている式と方程式の区別です。
しかし実は、最初に見るべきポイントは1つだけです。
まず「=」があるかどうかをチェック!
- =がない → 単なる式(一次式など)
- =がある → 方程式
この確認だけで、ほとんどの場合区別できます。
どんな方程式が「一次方程式」?
次の2つを確認します。
- = がある(→ 方程式である)
- 左辺・右辺の$x$の最高次数が1(→ 一次方程式)
この2点を満たせば一次方程式と判断できます。
混同しやすい例を丁寧に比較
- $2x+3$(一次式)
- $2x+3=0$(一次方程式)
前者は「計算して形を変えることはできても、$x$を求める問題ではない」です。
後者は「$x$が−$\frac{3}{2}$のときに成り立つ」という 具体的な解が出る問題です。
同様に、
- $x+5$(一次式)
- $x+5=12$(一次方程式)
後者は解が$x=7$と明確に決まります。
具体例で比較:式と方程式の使い分け
ここでは、一次式と一次方程式の実際の使われ方を具体例で比較してみましょう。
一次式の使い方:値を計算する「道具」
例
$2x+3$
この式に$x=4$を代入すると、2×4+3=11のように、$x$に好きな数を入れて値を求めるための形です。
一次式は、文章題の「代金の合計」「距離」「個数」などを式で表すときによく使われます。
この段階では「$x$の値を求める」ことが目的ではありません。
一次方程式の使い方:xの値を求める「問題」
例
$2x+3=11$
これは「どんな$x$なら左と右が同じ値になる?」という問題です。
簡単に解くと、
$2x=8$
$x=4$
となり、解は$x=4$と分かります。
同様に、
$2(x+3)=x+8$
のような式も、展開・移項・割り算などを使うことで$x$の値が求められます。
並べて比較すると理解しやすい
| 種類 | 例 | 目的 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 一次式 | $2x+3$ | $x$を入れて値を出したり、関係を表したりする | = がない、単なる「式」 |
| 一次方程式 | $2x+3=11$ | $x$の値(解)を求める | = がある、左右が等しくなる$x$を探す |
このように、一次式は「形」、一次方程式は「問題」。この違いを理解しておくと、今後の学習でも迷わなくなります。
一次式の計算方法:加法・減法・乗法・除法の基礎
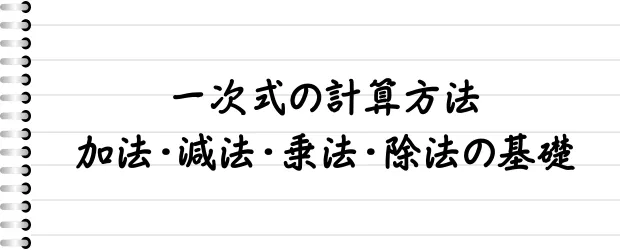
一次式を正しく計算できるようになることは、中学数学のあらゆる単元の土台になります。
特に、加法・減法・乗法・除法の計算は、方程式や関数の学習に進むうえで必ず必要となる力です。
ここでは、一次式の計算において最も基本となるルールを、例を交えながら丁寧に確認します。
上記で学んだ「項」「係数」といった基礎知識を活用しつつ、実際の計算でどのように扱うかを整理していきましょう。
一次式の加法・減法の基本ルール
一次式の加法・減法では、「同じ文字を含む項どうしをまとめる」ことが最も重要です。
これは「同類項をまとめる」と呼ばれ、計算の基本中の基本になります。
たとえば、次の式を見てみましょう。
例
$2x+3x$
これは$x$がついた項どうしなので、係数どうしを足して$(2+3)x=5x$となります。
また、数字だけの項である「定数項」も別でまとめます。
例
4+(−5)=−1
このように、文字の部分と数字の部分を分けて考えるのがポイントです。
減法では、引く式の符号を変えて足し算として扱うとミスが減ります。
例えば、
$(2x+4)−(3x−5)$
では、後ろのカッコ内の符号を変えて$2x+4+(−3x+5)$とすることで、
$2x−3x=−x$
4+5=9
したがって
$−x+9$
となります。
このとき、「項の符号は係数の一部である」という意識が大切です。
$−3x$の「−」は$x$にかかる符号であり、これを誤って無視すると計算ミスが起きます。
途中式を丁寧に書くことで、符号の間違いを防ぐことができます。
一次式の乗法:分配法則を使って計算
一次式の乗法では、分配法則が非常に重要になります。
分配法則とは、
$a(b+c)=ab+ac$
というルールで、次数の低い式でも高い式でも必ず使われる基本的な法則です。
例
$2(x+3)=2x+6$
このように、外側の2をカッコ内の両項に掛けることがポイントです。
また、係数同士を掛けることや、文字の係数に数字を掛ける操作も丁寧に扱います。
例えば、$−3(x−4)$の場合、まず符号に注目し、
$−3×x=−3x$
−3×(−4) = 12
となるため、
$−3x+12$
となります。
一つ注意したい点として、文字同士を掛けると一次式ではなくなります。
例
$x×x=x²$(これは二次式)
したがって、ここでは文字同士の掛け算は扱いません。
一次式を維持できる範囲での計算に限定し、係数や数値との掛け算を中心に学びます。
一次式の除法:簡単なポイントと注意点
除法では、式全体を同じ数で割る場合に「各項に割り算を分配する」形で考えるとわかりやすくなります。
例
$6x÷2=3x$
これは係数6を2で割り、$3x$となります。
複数の項がある場合も同様です。
$4x+8$
を2で割るときは、それぞれの項に割り算を分けて
$4x÷2=2x$
8÷2=4
となるので、
$2x+4$
が答えです。
ただし、注意すべき点がいくつかあります。
- 文字で割る計算(例:$x÷x$)は一次式ではなくなるため、ここでは扱わない。
- 除数が0のときは計算できない。(0で割ることは数学的に定義されていない)
- 式全体を割る場合、すべての項に割り算を適用する必要がある。
除法は加法・乗法ほど目立つ操作ではありませんが、方程式を解く際などに頻繁に登場する重要な考え方です。
分配や符号の扱いを丁寧に確認しておくことで、後の学習が格段にスムーズになります。
| 中学生のおすすめ学習塾3選 | |||
|---|---|---|---|
横浜予備校 |
WAM |
明光義塾 |
|
| 対象 | 中学生 | 中学生 高校生 |
中学生 高校生 |
| 授業料 (税込) |
29,700円~ (月額) |
7,600円~ (週1回) |
15,400円~ (週1回) |
| 入塾金 | 0円 | 16,500円~ | 11,000円 |
| 指導形式 | 学習塾 | 学習塾 (個別指導) |
学習塾 (個別指導) |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | |
一次式のよくある問題と解き方のポイント
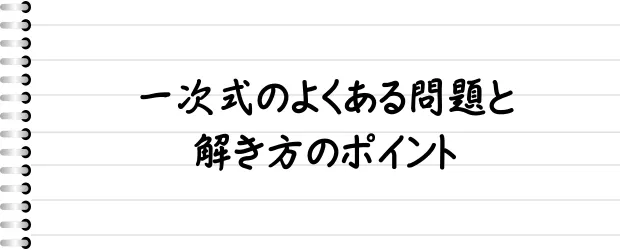
一次式の計算ができるようになったら、次のステップは文章題で式を立てて解く力を身につけることです。
文章題では、状況を正しく数式に翻訳することが最も大切で、ここでつまずく学生さんが多くいます。
ここでは、文章題でよく出てくる一次式の問題パターンを整理し、解くときに意識すべきポイントや具体的なステップを丁寧に解説していきます。
ここまでで学んだ計算ルールを使いながら、実際の問題でどのように活用できるかを理解していきましょう。
文章題でよく出る一次式の問題例
一次式を使った文章題は、中学数学の中でも頻出のジャンルであり、さまざまなテーマで出題されます。
特に多いのは次のようなパターンです。
①道のり・速さ・時間の関係を扱う問題
「道のり=速さ×時間」の公式に基づき、距離を$x$km としたり、速さを$x$km/h として式を立てるタイプの問題です。
例:家から学校までの道のりを$x$km とし、歩く速さやかかる時間をもとに式を立てる。
②代金や個数計算の問題
ケーキ1個の値段を$x$円とし、購入した個数や支払金額から等式を作る問題です。
中学の文章題で最も頻出の形式で、数量と単価の関係を式にする練習に適しています。
③比較・過不足を扱う問題
「兄は弟より5個多い」「合計は20個になる」など、数量の差や和を式に落とし込むタイプです。
文中の「差」「合わせて」「より多い」などの表現がそのまま一次式になります。
④年齢・貯金・分配の問題
年齢の差が一定であることを利用して式を作る問題、または貯金の増減・物の分配を式にする問題もよく出ます。
「増える」「減る」「等しく分ける」といった表現が式に結びつきます。
これらの文章題に共通するのは、状況を文字で表し、条件を一次式に変換して考える点です。
文章題が苦手な人は「式を作る段階」でつまずきやすいため、まずはどの数量を x と置くかをはっきり決めることから始めるとよいでしょう。
問題を解くときに意識するべき3つのポイント
文章題を解くときには、次の3つのポイントを常に意識することが重要です。
ポイント1:問題文を丁寧に読み、求める量を明確にする
文章題では、「何を求める問題なのか」をしっかり把握する必要があります。
ここを曖昧なまま進めると、式を作る段階で間違いが起きやすくなります。
また、未知数としてどの数量を$x$に置くかを最初にはっきり決めることで、問題全体の整理がしやすくなります。
ポイント2:関係する数量を正確に式にする
文章中の条件を丁寧に読み取り、それらを一次式の形にします。
「等しい」「つりあう」「合わせて」「残りは」などのキーワードは式の形を表すヒントになります。
数量の関係が複雑に見えても、表にしたりメモを書きながら整理すると理解しやすくなります。
ポイント3:方程式を解くときの手順を守る
式を立てたら、次は計算です。
移項するときの符号の扱いや、分配法則、項の整理など、上記で学んだルールを正しく適用しましょう。
最後に得られた$x$の値が文章題の文脈で正しいかどうか、単位が必要かどうかも忘れずに確認します。
式の立て方と解き方のステップ解説
文章題を解くときの基本的な流れは次の通りです。
ステップ1:未知の量を文字で表す
問題の中で不明な数量を$x$として定義します。
例:「ケーキ1個の値段を$x$円とする」
ステップ2:文章中の条件を数式に変換する
数量×単価のように、文章の内容をそのまま数式に置き換えます。
例:ケーキ3個の代金 → $3x$円
ステップ3:条件から方程式を作る
「支払ったお金 − 商品代 = おつり」など、左右が釣り合う形を作ります。
ステップ4:一次方程式を解く
左右の項を整理し、移項や割り算を使って$x$の値を求めます。
ステップ5:文脈に合うか確認する
求めた解が問題文に合っているか、単位は必要かなどを確認し、答えとしてまとめます。
この流れを意識することで、文章題に対する苦手意識が大幅に減り、一次式の理解がより確かなものになります。
まとめ
改めてになりますが、一次式とは、文字の指数が1の式のことで、数学の土台となる重要な概念です。
中学生にとって押さえておきたいのは、文字の前の係数や定数項の役割、そして同類項の計算ルールです。
特に、一次方程式との違いを理解し、「=」の有無で区別できることを覚えましょう。
また、一次式の加減乗除の計算は、方程式や関数を学ぶ上で必須の基礎力となります。
文章題では、問題文から未知の量を文字で表し、適切な一次式や方程式に変換して解いていく手順を確実に身につけることが成功のカギです。
このページを通じて、数学の根幹を理解し、次のステップに自信を持って進んでください。
| 中学生のおすすめオンライン塾・家庭教師3選 | |||
|---|---|---|---|
ウィズスタディ |
家庭教師の銀河 |
WAM |
|
| 対象 | 中学生 高校生 |
中学生 | 中学生 高校生 |
| 授業料 (税込) |
9,800円~ (1科目) |
2,750円~ (1コマ) |
7,600円~ (週1回) |
| 入会金 | 27,500円~ | 22,000円 | 16,500円~ |
| 指導形式 | 学習塾 (オンライン) |
家庭教師 | 学習塾 (オンライン) |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | |
練習問題
【問題1】
家から学校までの距離を$x$km とします。徒歩で毎時4km で歩くと、学校に着くまで30分かかりました。
次の式のうち、距離を表す式として正しいものを選びなさい。
- $x=4×0.5$
- $x=4+0.5$
- $x=4−0.5$
【問題2】
ノート1冊の値段を$x$円とします。ノートを5冊買って1,000円支払ったところ、おつりは200円でした。
この状況を表す方程式として正しいものを書きなさい。
【問題3】
兄は弟よりも$x$個多くアメを持っています。弟が8個のアメを持っているとき、兄のアメの個数を一次式で表しなさい。
【問題4】
1,000円を3人で分けるとき、AさんはBさんより$x$円多く、CさんはBさんより200円少なくなるとします。
3人の合計が1,000円になることを表す方程式を作りなさい。
【問題5】
今、兄の年齢を$x$歳とします。弟は兄より4歳年下です。5年後の兄と弟の年齢の和を表す式を作りなさい。
【問題6】
ある花屋で、花を1本$x$円で買えるとします。あなたは花を6本買い、1,000 円を支払いました。すると、店員さんから160円のおつりをもらいました。
(1) この状況を表す方程式を立てなさい。
(2) 方程式を解いて、花1本の値段$x$を求めなさい。
(3) 文脈に合うかどうかを確認して、文章として答えをまとめなさい。
解答
問題1
1:$x=4×0.5$
問題2
$5x+200=1000$
または
$5x=800$
問題3
$x+8$
または
$8+x$
問題4
Bさんの金額を$b$円とすると、
Aさん:$b+x$円
Bさん:$b$円
Cさん:$b-200$円
よって、
$(b+x)+b+(b-200)=1000$
$3b+x-200=1000$
問題5
弟の年齢は、$x-4$歳となります。
5年後のそれぞれの年齢は、
兄:$x+5$
弟:$X-4+5=x+1$
よって、
$2x+6$
問題6
- $6x+160=1000$
- $6x=840$
$x=140$ - 140円の花を6本買うと、840円。1,000円で支払うとおつりは、160円。
よって、花1本の値段は 140 円。
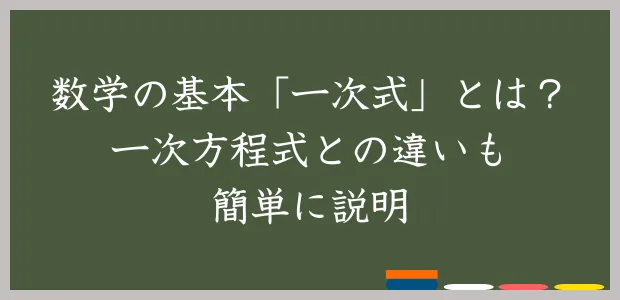
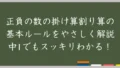
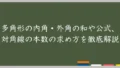

コメント