前回のページでは、単項式の乗法・除法の計算の解説と指数法則の復習を行っていきました。
中学2年ではここまでの知識が身につくと、ここからどんどん計算のハードルが高くなっていきます。
とはいっても安心してください。
一気にレベルが上がるわけではなく、段階的に少しずつ上がっていくので、ここからの学習内容を丁寧に理解しながら進めていくことができれば、特につまずくことなく学習を進めていくことができます。
早速このページでは、ここまで学習してきた指数法則と文字式の計算の知識を駆使して、多項式と単項式の計算を行っていきます。
新しい学習内容だと思うかもしれませんが、実際の計算処理は今までの知識を使って十分に進められるので、計算処理を理解しながらも、復習をするつもりで行っていきましょう。
まだ、指数法則や単項式の計算に慣れていない学生さんは、下記のページを振り返ってからこのページの学習を進めていきましょう。
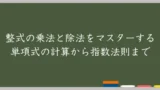
中学2年の数学で重要な「整式の計算」
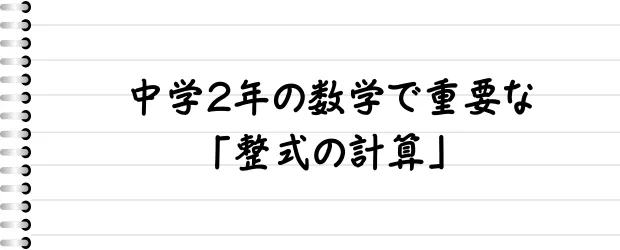
中学2年生の数学では、文字式の計算が本格的になっていきます。
その中でも特に重要なのが「整式の計算」です。
整式とは、単項式や多項式と呼ばれる文字式をまとめた呼び方です。
例えば次のような式があります。
- 単項式:$3x$,$-5a^2b$, $\frac{1}{2}xy$
- 多項式:$x^2+3x$,$a^2-5a+7$,$x^2y-3xy+4y$
中1の段階では、まだ「文字式の表し方」や「簡単な計算」しか扱いませんでした。
しかし中学2年になると、乗法・除法・展開といった計算が本格的に出てきます。
そして、これらの「単項式と多項式の計算」は、分配法則や指数法則を正しく理解していればスムーズに解けます。
逆にここでつまずいてしまうと、この後に学ぶ因数分解・平方根・関数にも影響が出てしまうため、とても重要な単元です。
このページでは、次の流れで詳しく解説していきます。
- 分配法則の復習
- 単項式×多項式の計算(展開)
- 文字が2つ以上ある場合の計算
- 多項式÷単項式の計算(除法)
- よくあるミスと対策
さらに、途中で例題を交えながら、実際の計算の手順をイメージできるようにしています。
「ただ公式を覚える」だけではなく、なぜそうなるのかを理解しながら読み進めてみましょう。
分配法則の復習
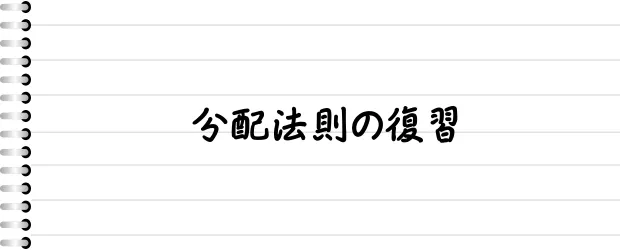
まずは基礎となる分配法則を復習しましょう。
分配法則とは、掛け算をそれぞれの項に分けて行えるという法則です。
例えば次の計算を考えます。
$2×(3+5)$
普通はかっこの中を先に計算して、
$2×8=16$
と求められます。
しかし、分配法則を使うと次のようにも計算できます。
$(2×3)+(2×5)=6+10=16$
つまり、
$a×(b+c)=ab+ac$
という形で表せるのです。
この考え方は文字式の計算にもそのまま使えます。
単項式×多項式の計算(展開)
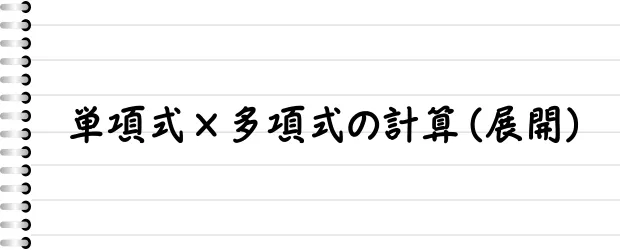
分配法則の考え方を説明したので次に、中学2年で最初に学ぶ「整式の展開」を見ていきましょう。
これは、単項式と多項式をかける計算です。
例題1
次の式の計算をしなさい。
$2x×(x+3)$
この場合、単項式 $2x$をかっこの中のそれぞれの項にかけます。
$2x×(x+3)$
$=2x×x+2x×3$
$=2x^2+6x$
この計算におけるポイントは「かっこの中の項すべてに掛ける」ということです。
例題2
次の式の計算をしなさい。
$−3a×(2a−5)$
上記の式の計算では、符号に注意しながら計算します。
$−3a×(2a−5)$
$=−3a×2a+(−3a)×(−5)$
$=-6a^2+15a$
特にマイナスの掛け算は符号を間違えやすいので、1つ1つ丁寧に確認しましょう。
文字が2つ以上ある場合の計算
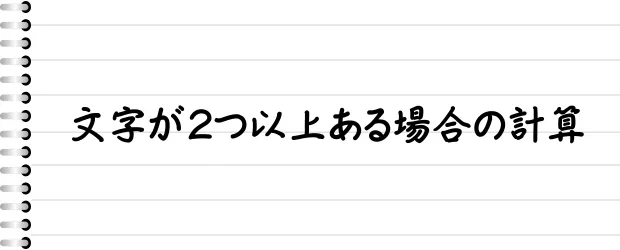
ここまでの計算は文字が1種類の場合の計算を見てきました。
次は、文字が複数出てくる場合です。
一見ややこしく見えますが、実際にはやり方は同じです。
例題1
次の式の計算をしなさい。
$2xy×(x+y)$
文字が複数になっても計算方法は変わらず、1つずつかけ算をしていきます。
$=2xy×x+2xy×y$
$=2x^2y+2xy^2$
ここで大切なのは、同じ文字は指数でまとめるということです。
例題2
次の式の計算をしなさい。
$−x×(3x−4y+1)$
上記の式は、かっこの中に3つ項がありますが、同じように1つずつかけます。
$−x×(3x−4y+1)$
$=−x×3x+(−x)×(−4y)+(−x)×1$
$=-3x^2+4xy-x$
項が多くても、「1つずつ計算する」というルールを守れば大丈夫です。
よくある間違いポイント
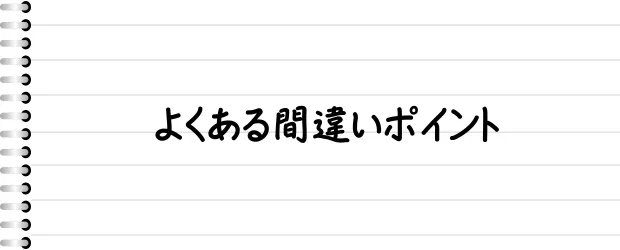
ここまでの計算を振り返り、単項式と多項式の計算で、特に中学生がよく間違えるのは次の3つです。
- かっこの中の項すべてにかけない
例:$2x(x+3)$を$2x^2+3$としてしまう。
→ 正しくは$2x^2+6x$です。 - 符号を間違える
例:$-3a(2a-5)$を$-6a^2-15a$としてしまう。
→ 正しくは$-6a^2+15a$です。 - 文字の指数をまとめ忘れる
例:$2xy・x$を$2x^1y$のままにしてしまう。
→ 正しくは$2x^2y$です。
このような間違いをしないためにも計算のルールや符号についてはしっかりと注意しましょう。
多項式を単項式で割るときの考え方
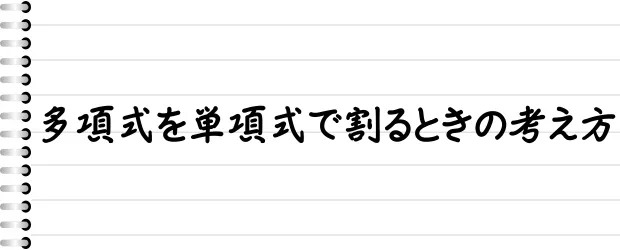
ここまでの説明では、単項式×多項式の計算(展開)を学びました。
次に重要になるのが、多項式÷単項式の計算です。
一見すると難しそうに見えますが、実は「分配法則を逆に使う」と考えると理解しやすいです。
例えば、次の式を考えてみましょう。
$(6x^2+12x)÷3x$
このとき、多項式のそれぞれの項を「$3x$」で割ります。
$(6x^2+12x)÷3x$
$=6x^2÷3x+12x÷3x$
$=2x+4$
となります。
つまり、かけ算のときは「すべての項にかける」、割り算のときは「すべての項で割る」というルールなのです。
例題で確認:多項式÷単項式
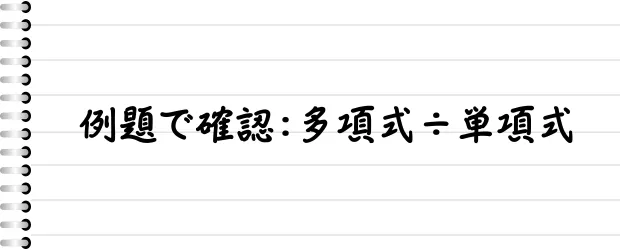
ここから実際に例題を解きながら、計算の流れを確認していきます。
例題1
次の式の計算をしなさい。
$(8x^3+12x^2)÷4x$
それぞれの項を$4x$で割ります。
$(8x^3+12x^2)÷4x$
$=8x^3÷4x+12x^2÷4x$
$=2x^2+3x$
例題2
次の式の計算をしなさい。
$(9a^2b−6ab^2)÷3ab$
同じようにそれぞれ割ります。
$(9a^2b−6ab^2)÷3ab$
$=9a^2b÷3ab−6ab^2÷3ab$
$=3a-2b$
このように、指数の引き算をきちんと使うとシンプルに計算できます。
複雑な文字式の除法
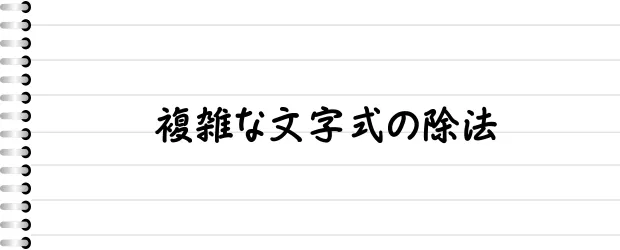
分配法則の計算と同じように、除法でも文字が複数の式が出てきます。
文字が2つ以上ある場合は、少し複雑に思うかもしれません。
ですが基本は「共通の文字を消して指数を引く」だけです。
例題3
次の式の計算をしなさい。
$(12x^2y−6xy^2+3x)÷3x$
それぞれの項を$3x$で割ると、
$(12x^2y−6xy^2+3x)÷3x$
$=12x^2y÷3x−6xy^2÷3x+3x÷3x$
$=4xy-2y^2+1$
例題4
次の式の計算をしなさい。
$(15a^3b^2−9a^2b^3+6ab)÷3ab$
この式も$3ab$をそれぞれの項に分けます。
$(15a^3b^2−9a^2b^3+6ab)÷3ab$
$=15a^3b^2÷3ab−9a^2b^3÷3ab+6ab÷3ab$
$=5a^2b-3ab^2+2$
よくあるミスと注意点
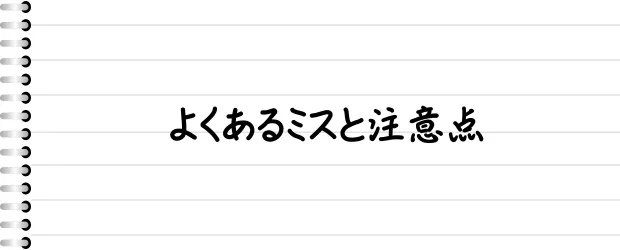
多項式÷単項式の計算では、次のようなミスをしやすいです。
どのようなミスがあるのか見ていきましょう。
- 1つの項だけ割って、他の項を忘れる
例:$(6x^2+12x)÷3x$を$2x^2+12x$としてしまう。
→ 全ての項に割り算をしなければいけません。 - 指数法則を間違える
例:$x^2 ÷ x = x^2$としてしまう。
→ 正しくは$x^{2-1} = x$です。 - 符号の処理を間違える
例:$(-9a^2b) ÷ (3ab) = -3ab$と答えてしまう。
→ 正しくは$-3a$です。
このように、ちょっとした計算の確認不足でミスが起きます。
常に「1項ずつ確実に計算する」ことを意識しましょう。
応用問題にチャレンジ
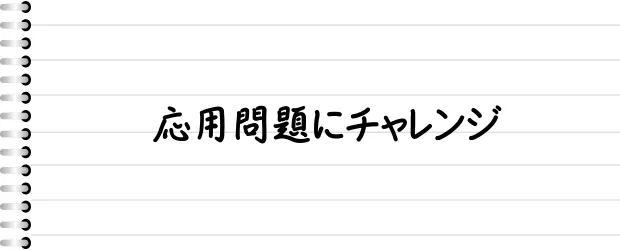
基礎の理解ができたら、少し応用的な問題にも挑戦してみましょう。
応用例題1
次の式の計算をしなさい。
$(10x^4y^2−5x^3y+15x^2y^3)÷5x^2y$
このような複雑な式でも焦らず1つずつ割ると、
$(10x^4y^2−5x^3y+15x^2y^3)÷5x^2y$
$=10x^4y^2÷5x^2y−5x^3y÷5x^2y+15x^2y^3÷5x^2y$
$=2x^2y-x+3y^2$
応用例題2
次の式の計算をしなさい。
$(−18a^3b^2+12a^2b^3−6ab^4)÷(−6ab^2)$
この問題も同様に1つずつ割ります。
$(−18a^3b^2+12a^2b^3−6ab^4)÷(−6ab^2)$
$=−18a^3b^2÷(−6ab^2)+12a^2b^3÷(−6ab^2)−6ab^4÷(−6ab^2)$
$=3a^2-2ab+b^2$
符号の計算を丁寧に行えば、きれいに答えが出ます。
計算を速く正確にするコツ
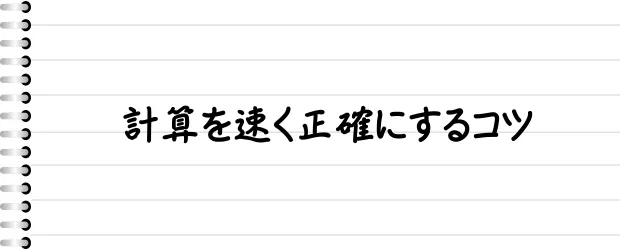
上記で見てきた応用問題のように複雑な単項式と多項式の乗除法を速く正確に解くためには、次の3つのポイントが大切です。
- 分配法則を意識する
「かけ算はすべてにかける」「わり算はすべてにわる」ことを習慣化する。 - 指数法則を確実に使う
$x^m ÷ x^n = x^{m-n}$を常に意識する。 - 符号の処理を最後まで確認する
「マイナス×マイナス=プラス」「マイナス÷プラス=マイナス」を忘れない。
これらを意識するだけで、計算ミスを大幅に減らすことができます。
実践的な応用問題に取り組む
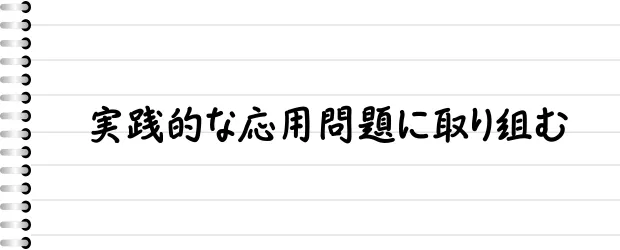
ここまでで「乗法(かけ算)」、「除法(わり算)」を学びました。
ここからはそれらを組み合わせたり、文章題の中で活用したりする問題を通して理解を深めていきます。
応用問題1:乗除の混合
次の式の計算をしなさい。
$(12x^2y−6xy^2)÷3x×2y$
解説
まずは除法を先に行います。
$(12x^2y−6xy^2)÷3x×2y$
$=(12x^2y÷3x−6xy^2÷3x)×2y$
$=(4xy-2y^2)×2y$
$=8xy^2-4y^3$
応用問題2:符号が混ざる場合
$(−15a^2b+9ab^2−3a)÷(−3a)$
この問題はそれぞれの項を$-3a$で割ります。
$(−15a^2b+9ab^2−3a)÷(−3a)$
$=−15a^2b÷(−3a)+9ab^2÷(−3a)−3a÷(−3a)$
$=5ab-3b^2+1$
符号に注意すればミスなく解けます。
応用問題3:文章題
「ある長方形の縦を$x+3$、横を$2x$とする。この長方形の面積を式で表しなさい。」
面積は「縦×横」です。
$(x+3)×(2x)$
$=2x^2+6x$
多項式×単項式の形が自然に出てきます。
応用問題4:逆の文章題
「長方形の面積が$12x^2+18x$で、横の長さが$6x$のとき、縦の長さを求めよ。」
面積 ÷ 横 = 縦 なので、
$12x^2+18x÷6x$
$=12x^2÷6x+18x÷6x$
$=2x+3$
縦の長さは$2x+3$となります。
よくある質問(Q&A形式)
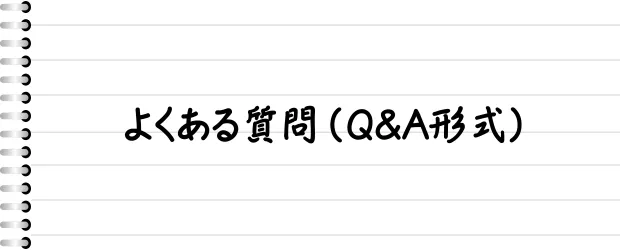
最後にこの単元の学習でよくある質問をQ&A形式で紹介していきます。
Q1. 割り算のとき、分母に文字が残る場合はどうすればいいですか?
Q2. 符号を間違えやすいのですが、コツはありますか?
まとめ
このページでは、多項式と単項式の計算について、展開を伴う計算方法について解説してきました。
整式の展開の計算は、どちらも「分配法則」をもとに考えることができます。
- 展開(乗法):単項式×多項式→1つずつかける
- 展開(除法):多項式÷単項式→1つずつわる
このように、どちらも「項ごとに丁寧に計算する」ことが大切です。
また、文字をかける・わるときには、指数のルールにも気をつけましょう。
展開や除法の計算に慣れておくと、この先の中学3年の数学で出てくる因数分解や関数の学習にもつながります。
計算のコツをつかんで、しっかり得意分野にしておきましょう。
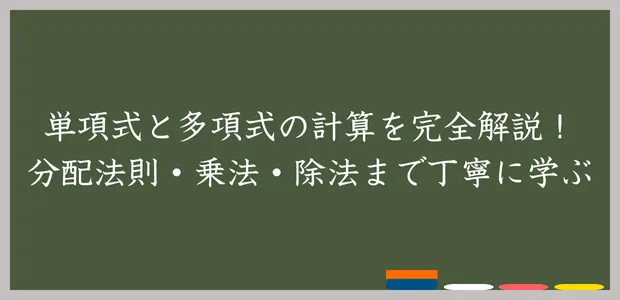








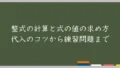

コメント