数学の学習を進める中で、多くの中学生がつまずきやすいテーマのひとつが「整式の計算」です。
特に「整式の足し算や引き算(加法・減法)」では、文字式のルールをしっかり理解していないと、符号の間違いや同類項のまとめ方で迷ってしまうことが多いです。
算数では数の計算が中心でしたが、中学校に入ってからは文字を使った「文字式」の計算が増えました。
そして中学2年生になると、「整式」という新しい言葉が登場し、本格的に文字式の計算を扱うことになります。
整式という言葉を聞いたときに、「何となく難しそう」と感じる人もいるかもしれません。
ですが、実際にはこれまでに学んだ計算の知識を活用することができ、基本ルールさえ理解すれば決して難しい分野ではありません。
このページでは、整式を構成する「項」についての理解から始めて、整式の加法・減法について、順を追ってわかりやすく解説していきます。
整式とは?その定義と基本的な考え方
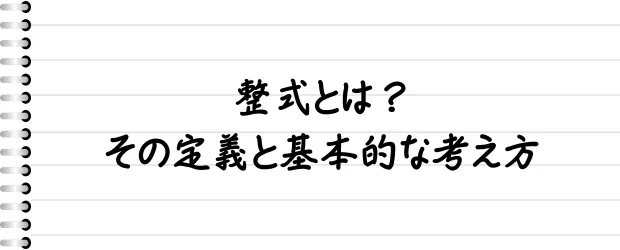
まず最初に、「整式」という言葉の意味を確認しておきましょう。
整式とは、数や文字を使った式のうち、足し算や引き算でつながっているものをいいます。
つまり、複数の「かたまり(項)」が+(プラス)や−(マイナス)で並んでいる形を整式と呼びます。
ここで注意したいのは、掛け算やべき乗(累乗)は整式の中に含まれていてもかまわないという点です。
例えば$x^2+3x+1$は整式です。
ただし、以下のような場合は整式とは呼びません。
- 文字が分母にあるもの(例:$\frac{1}{x}+2$)
- 文字の指数が負の数のもの(例:$x^{-2}+4$→指数が負の数の場合は文字が分母に来るため)
- 文字の指数が小数のもの(例:$x^{0.5}+3x$)
これらは中学数学で扱う「整式」からは外れるため、計算方法も異なります。
まとめると、整式は文字や数のきれいなまとまりとイメージすると理解しやすいでしょう。
整式の具体例とそうでない例
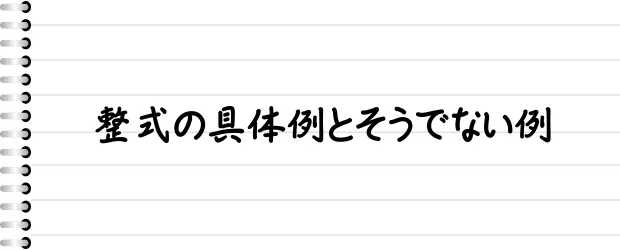
整式に当てはまるものと当てはまらないものの条件を見てきたので、具体例を見て整式に当てはまるもの、当てはまらないものを比較してみましょう。
- 整式の例
- $3x+2$
- $-5xy+2x-7$
- $x^2+3x+1$
- 整式ではない例
- $\frac{1}{x}+2$(文字が分母にあるため)
- $x^{-2}+4$(指数が負)
- $x^{0.5}+3$(指数が小数)
このように、整式であるかどうかは「分母に文字がないか」「指数が自然数かどうか」に注目すれば判断できます。
中学数学の整式は「指数が自然数(0を含む)」に限定されるため、安心して足し算・引き算のルールを練習していきましょう。
整式をつくる要素:「項」とは?
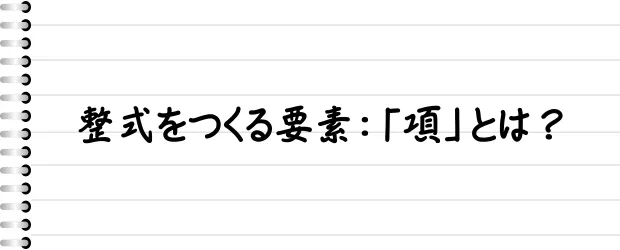
ここまでで、整式になるものとそうでないものの比較を行ってきました。
その知識を踏まえて、次からは「項」について見ていきます。
整式を理解するうえで欠かせないのが「項」という考え方です。
整式を+や−で区切ってみると、それぞれのまとまりが出てきます。
これを「項」と呼びます。
例えば、$3x+2y-5$という整式では、
- $3x$
- $2y$
- $-5$
の3つが「項」となります。
単項式とは?
項と整式についての理解を深めるために、もう少し知識をステップアップしていきます。
整式は項の数によってさらに「単項式」と「多項式」という2つの種類に分けることができます。
「単項式」とは、数や文字が掛け算だけでつながっている式のことです。
例を挙げると
- $3x$
- $-2xy$
- $x^2y$
- $5$(数だけの式も単項式)
単項式は「項がひとつだけの整式」と考えるとわかりやすいです。
多項式とは?
続いて「多項式」です。
「多項式」とは、単項式が2つ以上あって、それらが足し算や引き算でつながっている式です。
たとえば
- $2x+3$
- $x^2-44x+7$
これらは複数の単項式が+や−でつながっているため「多項式」と呼びます。
整式という大きな分類の中に、単項式と多項式があると理解しておきましょう。
定数項とは?
上記で見てきた単項式には、数だけの場合でも単項式に分類されることが分かりました。
ここで、整式の中には、文字を含まない「数だけの部分」が含まれることがあるということがわかります。
これをこれからは「定数項」と呼びます。
たとえば
- $3x+5$では「5」が定数項
- $x^2-4x+2$では「2」が定数項
定数項は文字の値に左右されない部分で、いつも一定です。
計算するときには見落とさないように注意しましょう。
整式の計算で重要な「同類項」とは?
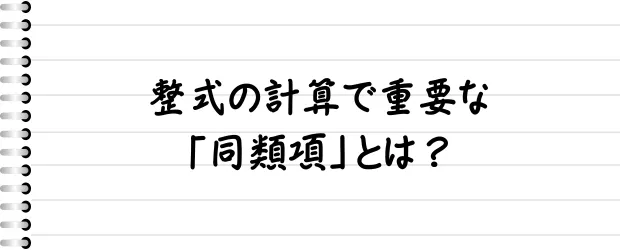
整式の基本事項の確認を終えたところで、早速整式の計算方法を見ていきます。
整式の足し算・引き算を正しく計算するために、まず理解すべき概念が「同類項」です。
同類項とは、文字の種類と次数(文字の指数)が同じ項同士のことを指します。
例えば次のペアを見てみましょう。
- $2x$と$5x$ → 同類項(文字も次数も同じ)
- $-3xy$と$7xy$ → 同類項
- $x^2$と$-x^2$ → 同類項
一方で次のものは同類項ではありません。
- $x$と$x^2$(次数が違う)
- $xy$と$x^2y$(次数が違う)
- $2x$と$3y$(文字が違う)
以上のことから、ポイントは「文字の組み合わせ」と「文字の指数」が完全に一致しているかどうかです。
同類項はまとめて一つにすることができます。
逆に言えば、同類項でないものはまとめることができません。
ここを押さえておくと、加法や減法の計算がとてもスムーズになります。
整式の加法(足し算)
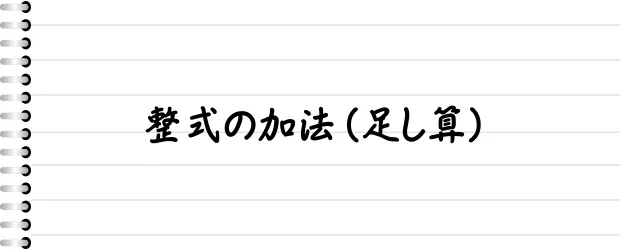
整式の計算における基本的なルールは上記のとおりです。
上記のルールに則って、整式の加法から見ていきます。
整式の加法は、同類項をまとめることが基本です。
計算のルール
整式の計算のルールは下記のとおりです。
- 同類項を見つける。
- 同類項同士の「係数(数の部分)」だけを足す。
- 文字の部分は変えずに残す。
例題1
次の整式の計算をしなさい。
$3x+2x$
上記の式は同類項なので係数を足します。
$(3+2)x=5x$
例題2
次の整式の計算をしなさい。
$x^2+2x+3+4x+5$
この式も同類項を整理すると
- $x^2$(1つしかない)
- $2x$と$4x$は同類項
- 3と5は定数項どうし
計算すると
$x^2+(2+4)x+(3+5)=x^2+6x+8$
例題3(複数文字のパターン)
次の整式の計算をしなさい。
$2xy+3x+5+4xy-2x+1$
これも同じく同類項を探します。
- $2xy$と$4xy$ → $(2+4)xy=6xy$
- $3x$と$-2x$ → $(3-2)x=x$
- 5と1 → 6
よって、まとめると
$6xy+x+6$
整式の減法(引き算)
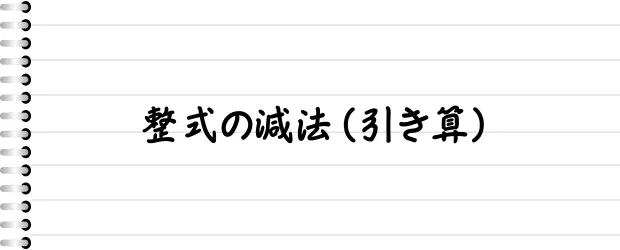
続いて整式の引き算も見ていきます。
整式の減法も加法と同じように同類項をまとめます。
ただし、大きな違いは符号の扱いに注意が必要なことです。
減法の基本ルール
- かっこがある場合は、かっこの前の符号に注目する。
- 「−(マイナス)」がかっこの前にあるときは、中の符号をすべて逆にする。
- その後、加法と同じように同類項をまとめる。
例題1
次の整式の計算をしなさい。
$5x-3x$
これは同類項なので係数を引きます。
$(5-3)x=2x$
例題2(かっこを含むパターン)
次の整式の計算をしなさい。
$(3x+5)-(2x+4)$
この問題は、かっこの前に「−」があるので、かっこの中の符号をすべて逆にします。
$3x+5-2x-4$
ここで同類項をまとめます。
$(3x-2x)+(5-4)=x+1$
例題3(複数文字のパターン)
次の整式の計算をしなさい。
$(2xy+3x+5)-(4xy+2x+1)$
この問題ではまず符号を変えます。
$2xy+3x+5-4xy-2x-1$
続いて同類項をまとめます。
- $2xy-4xy=-2xy$
- $3x-2x=x$
- 5-1=4
よって、
$-2xy+x+4$
減法でつまずきやすいポイント
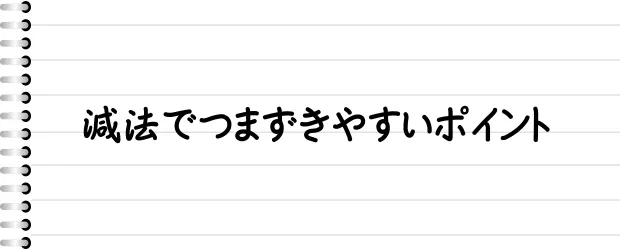
ここまでで、整式の加法と減法について見てきました。
整式の計算のおいて、減法では、符号のミスが最も多いです。
特に次のようなケースに注意しましょう。
- かっこの外にマイナスがあるとき
例:$-(x+3)$
→ $-x-3$に変わる - かっこの外が二重マイナスのとき
例:$-(-x+4)$
→ $x-4$になる
このような注意点でミスをしないためにも、マイナスを「かっこごと分配」する感覚を持てば間違いを防げます。
加法・減法の応用問題
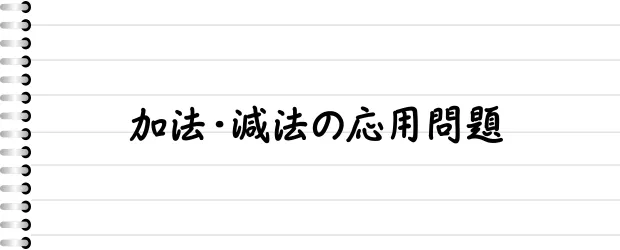
整式の計算の基本が分かったところで、少し難易度を上げた問題も見ておきましょう。
整式の加法・減法は、今後の数学学習で必ず必要になる基礎です。
様々な問題で定着させましょう。
問題1
次の整式の計算をしなさい。
$(x^2+3x+5)+(2x^2-4x+1)$
同類項をまとめると
$(1+2)x^2+(3-4)x+(5+1)=3x^2-x+6$
問題2
次の整式の計算をしなさい。
$(4x+7)-(2x+3)$
符号を変えてから計算すると
$4x+7-2x-3=(4-2)x+(7-3)=2x+4$
問題3
次の整式の計算をしなさい。
$(3a+2b-5)-(a-4b+2)$
まず符号を変えます。
$3a+2b-5-a+4b-2$
そして同類項をまとめていきます。
$(3a-a)+(2b+4b)+(-5-2)=2a+6b-7$
整式の加法・減法でつまずきやすい原因
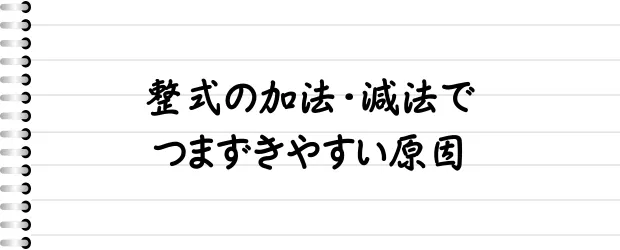
整式の計算は項が増えてくれば、その分だけミスも起きやすくなります。
ですが、その原因以外にも、中学生が整式の計算でつまずく理由には、いくつか共通点があります。
代表的なものを整理してみましょう。
- 同類項を正しく見つけられない
- $x^2$と$x$を同じと考えてしまう。
- $3ab$と$3a^2b$を同類項だと勘違いする。
- 符号の処理ミス
- 「$-(x+2)$」を「$-x+2$」にしてしまう。
- 引き算のとき、かっこの中の符号をすべて変え忘れる。
- かっこの扱いに慣れていない
- $(3x+5)-(2x+4)$を$3x+5-2x+4$としてしまう。
これらはどれも「ルールの理解不足」というよりも「計算の習慣」が身についていないことが原因です。
このようなミスは、意識して練習することで克服できます。
符号の扱いを克服するコツ
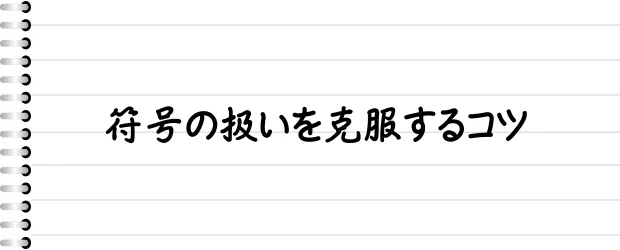
上記で紹介したミスの中で、整式の減法で一番多いミスは符号です。
ここでは具体的なコツを紹介します。
コツ1:かっこの前を「−1」と考える
$-(x+3)$は「-1をかける」と考えると間違えません。
コツ2:二重マイナスはプラスになる
$-(-x+4)$は「−を分配」すると$x-4$
二重マイナスの処理を徹底すればスムーズに計算できます。
コツ3:計算の途中で整理する
大きな式は、かっこを外した時点でまず「符号の処理だけ」を済ませ、次に「同類項をまとめる」と段階を分けると安心です。
効率的に学習するための工夫
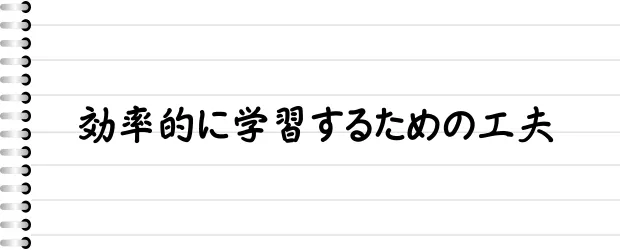
整式の学習内容を一通り解説したところで、学習の工夫の仕方をお話していきます。
ただ問題を解くだけでなく、以下の工夫を取り入れると学習効果が高まります。
工夫1:同類項に色をつける
計算するときに「同類項どうし」に色をつけるとミスが減ります。
例
$3x+2y-5+4x-3y+7$
$x$ の項に青、$y$ の項に赤、定数に緑をつける。
最後に同じ色どうしをまとめる。
こうすることで、計算練習を行う際にミスを格段に減らすことができます。
工夫2:符号を丸で囲む
マイナスを忘れやすい人は、符号ごと項を囲んで「ひとまとまり」と意識すると安心です。
工夫3:声に出して読む
「プラス3エックス、マイナス2エックス」と声に出しながら計算すると、符号を見落とすミスが減ります。
練習用ミニテスト
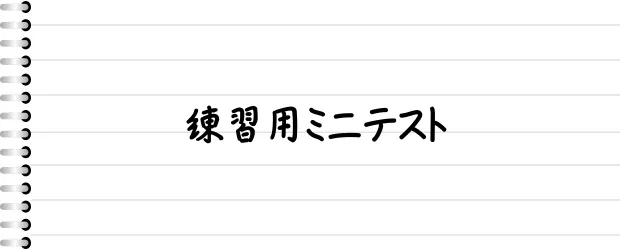
最後に、自分の理解度を確認するために、以下の練習問題に挑戦してみましょう。
- $(2x+3)-(5x-7)$
- $(a+b)-(2a-3b)$
- $(x^2+4x+1)+(3x^2-x-5)$
- $(3p-2q)-(2p+5q-4)$
- $(x+y)-(y-x)+(2x-3y)$
答えは次の通りです。
2.$-a+4b$
3.$4x^2+3x-4$
4.$p-7q+4$
5.$4x-3y$
まとめ
このページでは整式の加法・減法について解説していきました。
整式の加法・減法は、これからの数学の学習を進めていくうえでもとても大切な基本です。
この単元で出てくる考え方は、他の単元にもたくさん登場します。
「同類項をまとめる」力は、方程式や因数分解など、今後の学習にも役立ちます。
ぜひこの分野の学習で整式の基本をしっかり身につけておきましょう。
そして、計算のルールを「知っている」だけでなく、「使いこなせる」ようになることを目指して、楽しく学んでいきましょう。
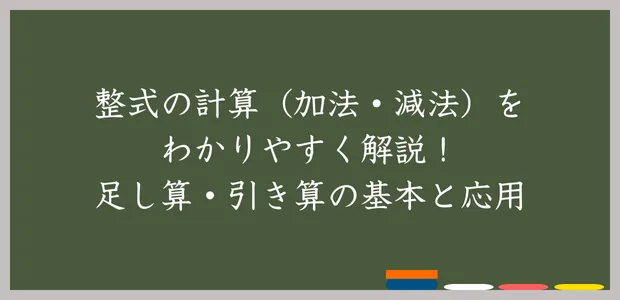








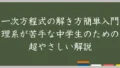

コメント