データの分析の分野では様々な用語やヒストグラムの特徴を学んできましたが、中学1年のデータ分析の範囲では最後にもう1つ「度数折れ線」というものを学んでいきます。
度数折れ線はヒストグラムを使って、以前学習した代表値(平均値、中央値、最頻値)を求めていくことができるとても
便利なものになります。
データの分析の学習範囲は、数学においては珍しく覚えることが多く、少し苦労している学生さんもいるかもしれませんが、中学1年の範囲はここまでなので、最後にもうひと踏ん張りしていきましょう。
もし、このページで出てくる代表値(平均値、中央値、最頻値)やヒストグラムについて、まだ理解が十分でない場合は、下記のページに戻って、理解を深めたうえで、このページの学習内容に挑戦してみましょう。
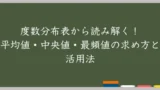
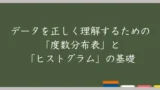
度数折れ線とは?データを線でつなぎ、分布の特徴をつかむ
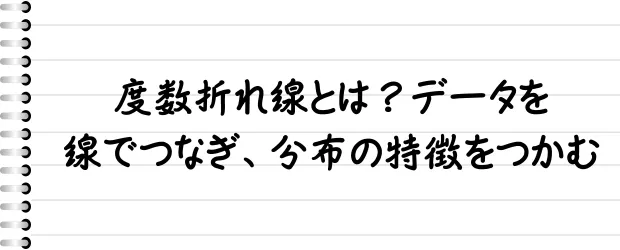
では、早速本題に入っていきます。
数学の「データの分析」分野では、データを整理・可視化して読み解く力が求められます。
特に度数折れ線は、ヒストグラムと同じ情報を持ちながら、線で結ぶことでデータ全体の形や傾向をより直感的に理解できる便利なグラフです。
例えば、どの点数帯に人数が集中しているのか、全体の分布が左右どちらに偏っているのかが、線の高さや傾きから分かります。
さらに、平均値・中央値・最頻値などの代表値を予測する手掛かりにもなります。
しかし、この度数折れ線を正しく描くためには、まず土台となる度数分布表が必要です。
ここからは、その度数分布表の作成方法から丁寧に見ていきましょう。
度数分布表とは?度数折れ線を描くための基礎
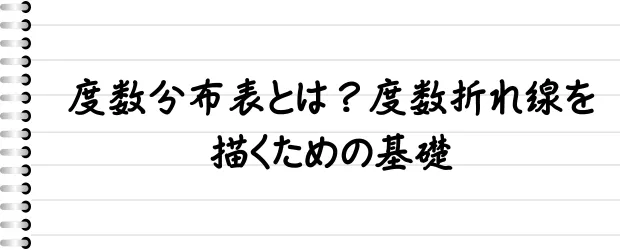
データが大量にあると、そのままでは全体の傾向を把握しづらいものです。
そこで、一定の幅で区切り(階級)を設定し、それぞれに何個データが入っているか(度数)を数えることで、データを整理するのが度数分布表です。
この表は、単に度数折れ線を描くための準備だけでなく、データ分析の第一歩としても重要です。
どんな分野のデータでも、まずは度数分布表で全体像を把握するのが基本と言えます。
度数分布表を理解するための基本用語
度数分布表の作成や活用には、いくつかの用語の意味を知っておく必要があります。
- 階級
データを区切った区間のこと。例:テストの点数なら「50〜59点」など。 - 階級値
階級の中央の値。度数折れ線を描く際、横軸に使います。
計算式:階級値 = (階級の下限 + 上限) ÷ 2 - 度数
その階級に含まれるデータの個数(人数や回数など)。
これらの用語を押さえておくことで、度数分布表の作り方もスムーズになります。
度数分布表の作成例
では、実際に例を使って度数分布表を作ってみましょう。
次の表は、40人のクラスの数学テスト(100点満点)の結果を階級別に整理したものです。
| 点数の範囲(階級) | 人数(度数) |
|---|---|
| 20〜29点 | 2人 |
| 30〜39点 | 3人 |
| 40〜49点 | 5人 |
| 50〜59点 | 10人 |
| 60〜69点 | 9人 |
| 70〜79点 | 6人 |
| 80〜89点 | 3人 |
| 90〜99点 | 2人 |
この表を見るだけでも、おおよそ50〜59点の階級に最も多くの人が集まっていることが分かります。
しかし、度数折れ線にすると、この傾向がさらに分かりやすくなります。
度数折れ線を描く前に準備すること
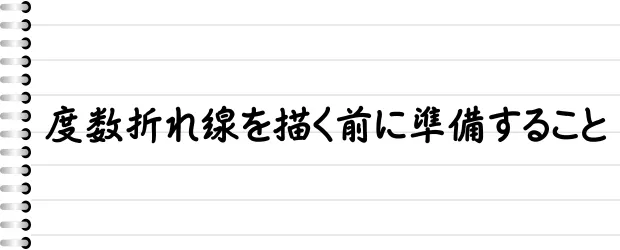
度数折れ線は、階級値と度数の対応を線で結んだグラフですが、そのためにはまず階級値を計算しなければなりません。
階級値を計算することで、グラフの横軸が整い、正しい位置に点を打つことができます。
階級値の計算例
先ほどの度数分布表をもとに、階級値を計算してみます。
- 20〜29点 → (20 + 29) ÷ 2 = 24.5
- 30〜39点 → (30 + 39) ÷ 2 = 34.5
- 40〜49点 → (40 + 49) ÷ 2 = 44.5
- 50〜59点 → (50 + 59) ÷ 2 = 54.5
- 60〜69点 → (60 + 69) ÷ 2 = 64.5
- 70〜79点 → (70 + 79) ÷ 2 = 74.5
- 80〜89点 → (80 + 89) ÷ 2 = 84.5
- 90〜99点 → (90 + 99) ÷ 2 = 94.5
このように計算した階級値を、度数と一緒にまとめた表を作っておくと、作図がスムーズになります。
階級値と度数のまとめ表
先ほどの階級値の値と度数を表にまとめると下記のようなひょうになります。
| 階級値(中央の値) | 度数(人数) |
|---|---|
| 24.5 | 2 |
| 34.5 | 3 |
| 44.5 | 5 |
| 54.5 | 10 |
| 64.5 | 9 |
| 74.5 | 6 |
| 84.5 | 3 |
| 94.5 | 2 |
この表は、度数折れ線を描く際に直接使える情報です。
次のステップでは、これをもとに実際の作図方法を見ていきましょう。
度数折れ線の描き方とポイント
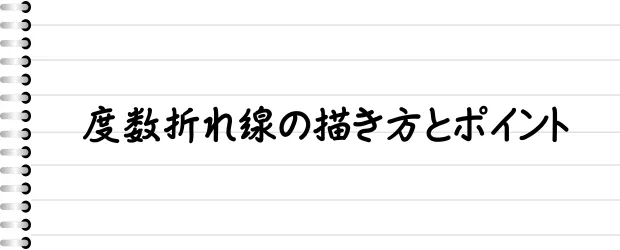
度数折れ線は、データの分布を視覚的に把握するためのグラフで、次の4つのステップで描くことができます。
正しい順番で作業すれば、誰でもきれいで正確なグラフを作れるようになります。
ここから度数折れ線の作成手順を見ていきます。
ステップ1:座標軸を用意する
まず、方眼紙で横軸(階級値)と縦軸(度数)を設定します。
横軸には、先ほど計算した階級値(例:24.5, 34.5, 44.5…)を並べ、縦軸には人数(度数)を取ります。
縦軸の目盛りは、最大の度数(例では10人)を少し上回る値まで取ると見やすくなります。
ステップ2:度数に対応する点を打つ
次に、各階級値に対応する度数の位置に点を打ちます。
例:階級値 54.5 に度数 10 → 横軸54.5の位置から縦に10の高さのところに点を打ちます。
ステップ3:点を線で結ぶ
すべての階級値の点を、順番に直線で結びます。
こうすることで、データの分布が「山の形」「右上がり」「右下がり」などの形として見えてきます。
ステップ4:両端を0まで下ろす
最後にグラフの両端を0まで下ろします。
多くの場合、度数折れ線はグラフの両端を度数0まで下ろします。
これは、データがその範囲外では存在しないことを視覚的に示すためです。
例えば、20未満や100を超える点数は存在しない場合、端の点から下に0まで線を引きます。
度数折れ線の読み取り方
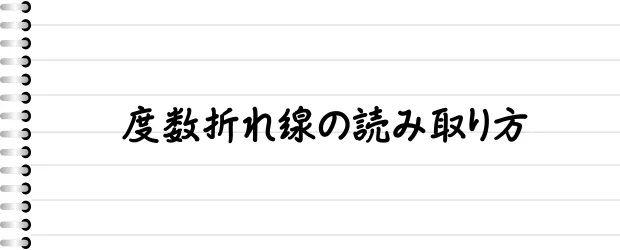
度数折れ線を描いたら、それをもとにデータの特徴を読み取ります。
ここからは、読み取りの代表的な観点を紹介します。
1.最頻値
度数折れ線の山の頂点の位置が、そのデータの最頻値を表します。
例のグラフでは、階級値54.5(50〜59点)が最も高く、最頻値にあたります。
2.分布の形
線の形が左右対称なら正規分布に近く、片方に伸びていれば「右(左)に偏っている」と判断できます。
例えば、低い点数帯に山があり右に尾を引く形は「右に偏った分布」です。
3.データのばらつき
山が鋭ければデータが集中しており、なだらかであればデータが広く分布していると分かります。
教育やマーケティングの分野では、この形から「学力差」や「顧客の購入価格の幅」を判断することがあります。
ヒストグラムとの違いと使い分け
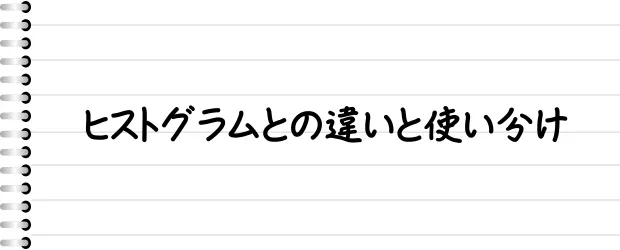
ここまでの学習を振り返ると、データの分析の分野では度数折れ線のほかにグラフをもう1つ学習しました。
それは、ヒストグラムです。
ヒストグラムは各階級の度数を棒で表すため、度数の絶対値が分かりやすく、数量の比較に強いという特徴があります。
一方、度数折れ線は線で結んでいるため、全体の傾向の把握や複数の分布の比較に向いています。
両方を組み合わせるとさらに見やすい
実際にこれらを使い分けてグラフ化することもありますが、場合によっては組み合わせて使うとよりデータの分析が効率的に進むことがあります。
つまり、実務や学習では、ヒストグラムと度数折れ線を重ねて描くこともあります。
棒の高さと線の形を同時に見ることで、正確さと傾向把握の両方が可能になります。
複数の度数折れ線を比較する
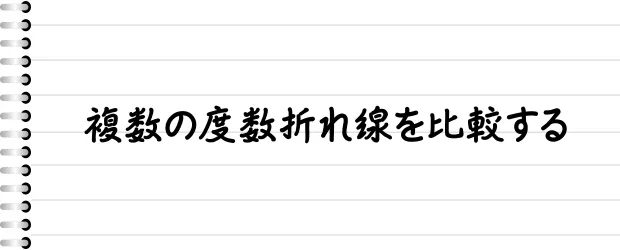
ここまでは、1つのデータ群について、1つの度数折れ線を使った分析の手順を説明してきました。
ですが、実際にデータの分析を行う際は、データ群は1つとは限りません。
そういった際に度数折れ線は、複数のグループのデータを比較するときにも便利です。
例えば、同じテストを別のクラスでも実施した場合、それぞれの度数折れ線を同じグラフ上に描くことで、どちらのクラスが全体的に高得点か、得点分布が広いかを一目で比較できます。
これをそろえないと、正しい比較ができません。
実例:学力テストの2クラス比較
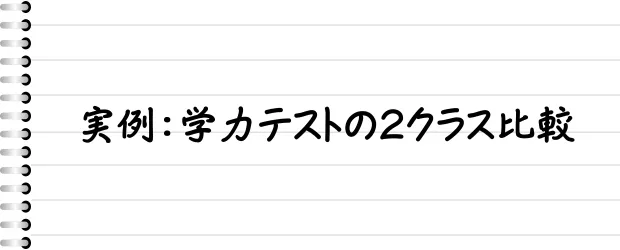
では、2つのデータ群を比較する例を見ていきます。
下記のような2つのクラスのテストの点数データがある場合を想定します。
| 点数範囲 | クラスAの度数 | クラスBの度数 |
|---|---|---|
| 40〜49点 | 5 | 8 |
| 50〜59点 | 10 | 12 |
| 60〜69点 | 9 | 6 |
| 70〜79点 | 6 | 3 |
このデータで2本の度数折れ線を描くと、クラスAは中央の60点台にピークがあり、クラスBは50点台にピークがあることがわかります。
このように、度数折れ線は単に1つのデータの形を示すだけでなく、複数の分布を比較する分析ツールとしても役立ちます。
度数折れ線を活用した応用的な分析
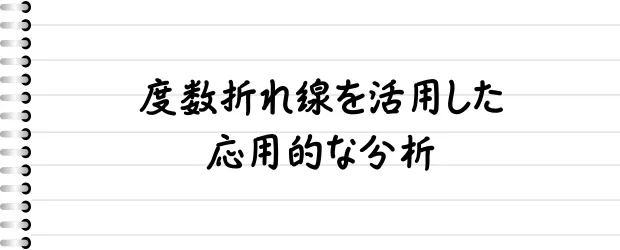
ここまでで学んだ基本の作成手順と読み取り方を踏まえると、度数折れ線はより実践的な場面で大きな力を発揮します。
これらの知識を活かして、ここからは、応用的な活用方法や、注意すべき点を具体例とともに紹介します。
平均値・中央値との組み合わせ
まずはデータの分析でおなじみの代表値との関連を見ていきます。
度数折れ線は形を見るだけでなく、代表値を計算して一緒に解釈することで、より深い分析が可能になります。
- 平均値:全データの合計をデータ数で割った値。山の位置が平均に近ければ左右対称の分布に近いことが分かります。
- 中央値:データを小さい順に並べて真ん中に来る値。度数折れ線で累積度数を利用すれば求めやすくなります。
- 最頻値:先ほど解説した通り、度数折れ線の山の頂点が該当します。
これらを組み合わせることで、「平均値よりも最頻値が高い=右に偏った分布」など、より詳細な特徴を把握できます。
累積度数折れ線(オージーブ曲線)
次に少し発展的な内容の累積度数折れ線についても触れておきます。
度数折れ線には派生形として累積度数折れ線というものがあります。
これは、階級の左端または右端までの度数を累計し、その累積値を折れ線で表したグラフです。
累積度数折れ線を使うと、「全体の何%が60点以上か」などの割合を素早く読み取ることができます。
例えば、顧客の購買額データで累積度数折れ線を作れば、「上位20%の顧客が売上の80%を占める」といったパレート分析にも応用可能です。
複数年度の比較で変化を把握
また、先ほどは複数のデータの比較にも度数折れ線は有効だということをお話しました。
これは、同時に2つのデータが存在する必要はなく、例えば、去年やおととしのデータと比較する際にも用いることができます。
例を挙げると、同じテストを3年連続で実施し、毎年の度数折れ線を1つのグラフに重ねれば、「年々平均点が上昇している」「分布がなだらかになり学力差が縮小している」など、改善や課題を客観的に把握できます。
誤った読み取りを防ぐためのコツ
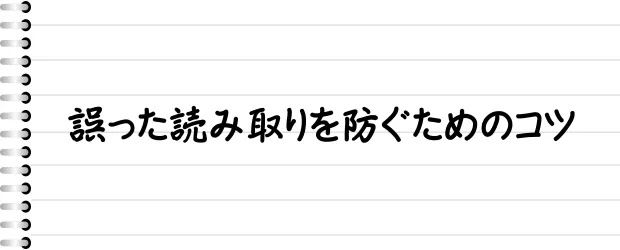
度数折れ線については、ここまで見てきたようにデータを比較する際にとても有効だということが分かりましたが、度数折れ線を作成し、しっかりとデータを分析する際に注意も必要です。
どういった注意が必要かというと、度数折れ線は視覚的に分かりやすい反面、作り方や解釈を誤ると、間違った結論につながります。
ここではそれらを福ぐための注意点を3つにまとめます。
1.階級幅を変えない
1つ目は階級幅を変えないということです。
階級幅がバラバラだと、度数の比較が正確にできません。
必ず全階級の幅を同じにします。
2.度数ではなく相対度数で比較する
2つ目は単純な度数で比較しない場合があるということです。
別の集団を比較する際には、人数が異なることがあります。
その場合、単純な度数ではなく、全体に対する割合(相対度数)で比較することが重要です。
3.外れ値に注意する
3つ目は外れ値と呼ばれるデータに注意するということです。
一部の極端な値(外れ値)が分布を歪ませることがあります。
必要に応じて外れ値を除外して分析するか、外れ値があることを明示して解釈します。
日常生活・ビジネスでの活用事例
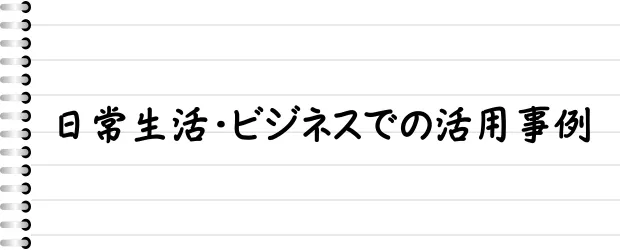
最後にここまで見てきた度数折れ線を実際に社会に出てから使い可能性がある仕事を紹介しておきます。
今、学習していることが、自分の将来にも活かされるということを知っているだけでもモチベーションは違ってくると思うので、参考まで見ておきましょう。
教育分野
学校のテスト結果分析で、学年全体やクラス別の学力傾向を把握するために利用されます。
補習対象者や学力上位者の分布を視覚的に確認でき、指導方針の立案に役立ちます。
マーケティング分野
商品購入金額や購買頻度を度数折れ線で可視化すれば、顧客層の中心や購買パターンが見えてきます。
累積度数折れ線を併用すれば、重点的にアプローチすべき顧客群も特定できます。
製造業
製品の品質検査で、寸法や重量の測定結果を度数折れ線にすると、規格内の製品が多いかどうか、品質が安定しているかを確認できます。
健康・医療分野
健康診断の結果(血圧、体重、BMIなど)を集計して度数折れ線を描くことで、対象集団の健康状態の傾向を把握し、生活習慣改善の施策立案に活用できます。
まとめ
今回は、「度数折れ線」について度数分布表と絡めて解説していきました。
表にまとめることで見えてこなかった「データの形」がグラフで一目で分かるようになりました。
また、改めてになりますが、度数折れ線はそのグラフから代表値(最頻値・中央値・平均値)のおおよその位置を読み取ることもできます。
データを読み解く力は、勉強だけでなく日常生活でも役立つものです。
グラフを読み、データの背景を考えられる力を少しずつ育てていきましょう。
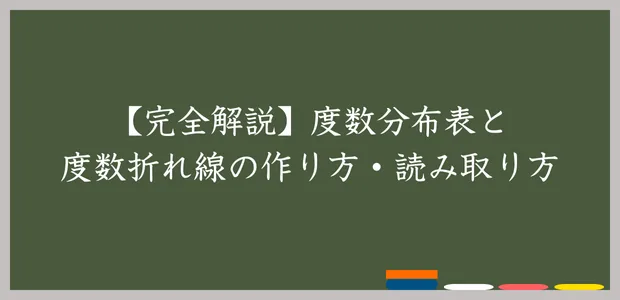










コメント